辞書の中の単語たち
ここでは辞書の中にひっそりと棲息する地味な単語にスポットを当て,彼らにまつわるおもしろそうなエピソードを「つれづれなるままに」述べてみたいと思います。辞書については次の略称を用います。
| COB2 | Collins COBUILD English Dictionary 2nd edition (1995) |
|---|
| OALD5 | Oxford Advanced Learner's Dictionary 5th edition (1995) |
|---|
| COD10 | The Concise Oxford Dictionary 10th edition (1999) |
|---|
| RHWCD | Random House Webster's College Dictionary 2nd editon (1997) |
|---|
| CIDE | Cambridge Internatinal Dictionary of English (1995) |
|---|
1. bob (その1)《「魚釣りの浮き」と「断髪」の関係は?》
Bob は Robert の愛称です。では小文字のbobはどういう意味でしょうか。実はこれも結構いろんな意味があって,たいていの英和辞典では3つくらいの見出しを載せています。例えば「ジーニアス英和」1998)や「グローバル英和」(1994)では,
bob1 上下に動く(こと),おじぎ
bob2 断髪(にする),(魚釣りの)浮き,
bob3 シリング
となっています。これを見て不思議に思われることはありませんか。「おじぎ」が「上下に動く」のbob1に入っているのは納得しますが,それでは「(魚釣りの)浮き」がどうして「断髪する」のbob2に入っているのでしょうか。「(魚釣りの)浮き」は水面に上下運動をしながらプカプカ浮いているものですから,bob1に入れるのが普通ではないでしょうか。そこで英英辞典ではどのような分け方をしているのかを調べてみました。すると次のようになりました。
① bob1, bob2 と分けずに1つにまとめて記述している →COB2
② bob1に「動詞」,bob2に「名詞」を記述している →LDOCE3
③ bob1に「上下運動」の(動)(名)を,bob2に「短髪」の(動)(名)を記述し,「魚釣りの浮き」については言及しない →OALD5,COD10
④ bob1に「上下運動」,bob2に「短髪」を記述するが,「魚釣りの浮き」はbob2に入れている(上記の英和辞典はこれに従っています) →RHWCD,Random House Unabridged Dictionary 2nd Ed.
⑤ bob1に「上下運動」, bob2に「短髪」を記述し,「魚釣りの浮き」はbob1に入れる →Collins English Dictionary Millennium ed.(1998)
COD10によるとbob1,bob3の語源は不明,bob2の語源は「房,かたまり」という意味だそうです。「浮き」も見方によれば「かたまり」と見えないこともないですが,私は⑤の分け方が妥当だと思います。
2. bob (その2) 《断髪とおかっぱ》
女性のヘア・スタイルについては全く知らなかったのですが,講談社大図典View(1984)のP.1334には様々なヘア・スタイルの写真が載っています。その中で「ショート・ボブ」として
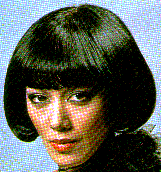 右の写真が,そして「ロング・ボブ」として
右の写真が,そして「ロング・ボブ」として
 左の写真があります。これから判断すると,「ボブ」は日本の「おかっぱ」に近く,マッシュルーム型のヘア・スタイルのようです。ところが「グローバル英和」のbobの項に載せられている挿絵はこのいずれの形とも異なり,極端に短いボーイッシュなヘアカットになっています。いったいどれが正しい「ボブ」なのでしょうか。そこで何でもありのインターネットで調べてみました。すると,なんと1263にも及ぶ様々なボブ・ヘアスタイルを集めたThe Bob Haircut Worship Pageというホームページがあるではないですか!タイトルから見てちょっとフェチっぽい感じもしますが,それはそれとして,ここでもやはり基本は「おかっぱ」です。やはり英和辞典では特殊なものではなく「基本的一般的」なものを載せるべきでしょうね。
左の写真があります。これから判断すると,「ボブ」は日本の「おかっぱ」に近く,マッシュルーム型のヘア・スタイルのようです。ところが「グローバル英和」のbobの項に載せられている挿絵はこのいずれの形とも異なり,極端に短いボーイッシュなヘアカットになっています。いったいどれが正しい「ボブ」なのでしょうか。そこで何でもありのインターネットで調べてみました。すると,なんと1263にも及ぶ様々なボブ・ヘアスタイルを集めたThe Bob Haircut Worship Pageというホームページがあるではないですか!タイトルから見てちょっとフェチっぽい感じもしますが,それはそれとして,ここでもやはり基本は「おかっぱ」です。やはり英和辞典では特殊なものではなく「基本的一般的」なものを載せるべきでしょうね。
3. bitch 《雌犬とcurse word》
あるアメリカ人(女性)に「男性を侮辱する表現は何か」と問うと"ass hole"という。それじゃ,「女性を侮辱するのは?」とさらに問うと,笑いながら「bitch よ」といった。ほとんどの英和辞典では
① 雌犬
② [けなして]みだらな女,ばいた,あま;不快なもの.
③ 不平
と記しています。しかし,「現代の使用頻度順を原則」(ジーニアス英和)に並べているにしては①雌犬を一番にもってくることは首を傾げざるを得ません。日常の生活では当然②がはるかに多く使われているのではないかと想像するからです。巨大な The Bank of English コーパスに基づいて作られた COB2 は頻度を特に重視していますが,その語義順は
① 女性に対するののしり言葉
② やっかいなこと(もの)
③ 不平を言う
④ 雌犬
となっています。辞書つくりでは徹底した頻度の検証が大切です。(学習英和辞典における頻度の大切さについては「雑誌掲載記事」コーナーの「学習英和辞典では頻度も考慮すべき」もお読みください)
ところで「ウエブスター第3版」を編集するとき,「俗語,軽蔑的な語,卑語,教養のない人がよく用いる語」などが非常に不足していることに編集長が気づき,編集長自らその用例集めにいそしんだとウエブスター大辞典物語には書かれています。この辞典は天才的な編集長フィリップ・ゴーブが「記述的立場」(辞書の役目は,言葉はかく使うべしという『規範』を示すのではなく,現実に使われている実態をありのまま『記述』すべきであるという立場)を明確に打ち出したものでした。こうした態度は今ではあたりまえのことですが,当時のアメリカ人は「ウエブスター」に「規範」を求めていました。わからない語に出会うと,「じゃ,ウエブスターに聞いてみよう」となるのでした。そして皮肉にもこの第3版は「教養のない人がよく用いる」とされていた「ain't」をとりあげたことから徹底した批判を浴びることになるのです。この過程が実におもしろいので「ウエブスター大辞典物語」をお読みになることをおすすめします。
4. bikini 《男性用のビキニ?》
bikini は女性用の水着です。男性には楽しいことですが,年々覆い隠す面積が小さくなっています(^^ゞ 「ビキニ」と聞けば水着以外には何を思い浮かべますか。そうです,あの「ビキニ環礁」です。1946~58年にかけて米国はここで原爆実験を行い,1954年にはわが国の第五福竜丸の乗組員が致死量に近い放射能を浴びました。水着の「ビキニ」はその衝撃度をこのビキニ環礁で行われた「原爆」に例えて命名されたのです。といってもそこには原爆に対する非難や反省の気持ちは全くなく,ただ「原爆くらい衝撃度がある」といういささか不適当で能天気な例えにすぎません。
ところで,このビキニを男性も着るというとどう感じますか。わたしは見たくもありません。RHWCD には「2. a very brief, close-fitting bathing suit for men.」とあります。もっとも男性は胸のほうはしないと思いますけど(^_^;) たぶん水泳競技などで水の抵抗を極力少なくするために小さくした男性用水着でしょうね。NTC's American English Learner's Dictionary(1998)にも同じような記述があります。ただし,イギリス系の辞典には載っていないのでイギリスではそう言わないようです。
5. biannual 《1年に1回,それとも2年に1回?》
2000年は20世紀か21世紀か---こんな話が1999年終わりによく聞かれましたね。「2001年宇宙の旅」という映画もあるように一応2000年はまだ20世紀とされますが,"The period 1900-1999 is the twentieth century." という例文を載せて,2000年は21世紀の方に分類している英英辞典(Longman Dictionary of English Language And Culture)もあります!
[補注]
実はこの文を書いた時点で,私は2001年が当然正しいと思っていました。つまり,上記のLDELAC の記述を誤りと考えていたのです。ところが,そうではないことが判明しました。この「新世紀の始まりは00年か01年か」という論争はなんと17世紀以来延々と行われてきた論争だったのです。S・J・グールドの「干し草のなかの恐竜 上」(早川書房・渡辺政隆訳,2000年)によれば,00年派は一般大衆,すなわちポップカルチャーに属する人が多く,一方01年派は理屈っぽい学者たちのハイカルチャーに属する人が多いそうです。20世紀には圧倒的にハイカルチャーの勝利だったのですが,21世紀はどちらかといえばポップカルチャー派に軍配が上がりそうだと書いてあります。どうやらこの論争は簡単には決着が着かないようです(2003.01.13 記)。
ところで,biannual という単語があります。見ておわかりのようにこれは「bi + annual」 の合成語のようですが,
この 「bi-」を「年に2回」とととらえるか「2年ごとに」とみるかで全く意味が異なります。実に不便なものですが,使用している英語国民も二つの意味としてとられているのです。RHWCDには,
1. occurring twice a year; semiannual.
2. occurring every two years; biennial.
とあります。違いは「文脈で判断せよ」というのですが,それでもこれは混乱のもとです。そこでMerriam Webster's Dictionary of Synonyms には「2 との区別がつきにくいので,1 の意味ではSEMIANNUALを,2 の意味ではBIENNIALを使う傾向がある」と書いてあります。もっとも, LDOCE3,OALD5 などイギリス系辞典は「年2回」という意味しか挙げていないので混乱はないのかも知れません。
ここに面白い辞書があります。Harper Dictionary of Contemporary Usage (Harper & Row, 1975) これはIssac Asimov, S.I.Hayakawaなど136人のそうそうたる人々を語法パネラーとして様々な表現についてそれを許容するか否か問い,その答えを%で示したものです。その中に 「bimonthly は『2ヶ月に1回』という意味と『月2回』という意味があるが,あなたはどちらに意味にも用いるか」という問いに対して,9% がYes, 91% がNoと答えています。bimonthlyを「2ヶ月に1回」, semimontly を「月2回」に使うという人や,紛らわしいのでevery two months, once a monthを用いるという人など様々ですが,いずれにしても混同を避けるためにbimonthlyを二重の意味で用いることには反対しています。
6. bloomers 《ウーマンリブとブルーマ》
「ブルーマ」と言えば,体育の時間によく女生徒が身に付けていたものです。あのまぶしい姿は今はもう見かけませんね。そもそも「ブルーマ」は1850年頃アメリカの社会運動家 Ameria Bloomer 夫人がサイクリングなど活動する女性の「合理的な衣類」として推奨(発明ではありません)したために,彼女の名がつけられました。固有名詞の普通名詞化の一例です。わざわざbloomersと複数形にしているところなど芸が細かいですね(^.^)
このbloomersはスカートの下にはく「したばき(knickers)」の意味もあります。ただし,bloomerと単数形で書くと「開花する植物」,またイギリスでは「大ドジ」という意味になります。
7. blue-eyed 《青い目は魅力的か?》
白人社会(というより日本人の中でも)における「金髪碧眼願望」については英語教師もの申す「あなたはブロンドがお好き?」にも書きましたのでご一読ください。
さて,「青い目の」はblue-eyedといいます。この語自体は無色ですが,イギリスでは a blue-eye boy となると「軽蔑的な意味」が加わります。COB2からの用例です。
He was the media's darling, the Government's blue-eyed boy.
(あいつはマスコミの愛人,政府の寵児だ)
ようするに体制にべったりな人間ということです。米国では fair-haired boy ともいいます。ソウルは黒人の音楽ですが,それが白人によって演奏されるのが blue-eyed soul です。
8. boarding house reach《「下宿式手伸ばし」とは?》
boarding house が「賄(まかな)い付きの下宿」ですね。私が大学生のころは,今のような「ワンルーム・マンション」などはなく,まだあちこちにこのboarding houseがありました。大阪の住吉で下宿していたときの大家さんは70を過ぎたおばあちゃん。しかし作ってくれる料理はなかなかハイカラでとってもおいしかった。「すがさーん」という声がするので行ってみると,近所で饅頭をもらったから半分ごっこして食べようなどということがしょちゅうありました。
この語には「(寄宿学校の)寄宿舎」という訳語を当てている英和辞典もありますが,注意したいのはboarding houseは「私立」であるということです。どの英英辞典にもprivateであることが明記されています。
ところで "boadinghouse reach" という言葉をご存知ですか。reachには「着く」の他に「手を伸ばして取る(こと)」という大事な意味があります。out of [beyond] my reach は「私の手の届かないところに」という意味です。このreachとboardinghouseを組み合わせたのが"boardinghouse reach"です。本来食卓には自分のテリトリーがあります。もし調味料などが相手のテリトリーにある場合は"Would you pass me the salt?"といって相手にとってもらうのがマナーです。しかしboarding houseの住人はたいていはマナーなどそっちのけの若者たち。「欲しいものがあれば勝手に手を伸ばして取る」--これが "boardinghouse reach"です。
9. quaint 《新しい意味の発見》
昨今は,「古い」という言葉にはともするとマイナスなイメージが伴いがちですね。「古くさい」「古びた」「古ぼけた」等々のように。逆に「古くて良い」という言葉がなかなか見当たりません。「古風な」くらいでしょうか。
だからこの quaint を日本語で表すには「古くて珍しく魅力的な」というふうにいくつも形容詞を重ねないとだめなようです。もともと quaint はこのようにいい意味だったのですが,英米でも今では,「古くさい」「時代遅れの」という意味も付加されるようになってきました。例えば,a quaint anachronism「古くさい時代錯誤」(Time誌)という具合です。
ところでこの単語についてたいていの英和は「風変わりでおもしろい」とか「古風で趣のある」といた説明をしています。しかしわたしは次のような用例を眺めているうちに,そこにもう一つの感情があることに気づきました。
a quaint little town in Virginia (バージニアの昔風の小さな町)
a quaint country pub (田舎の昔風の大衆酒場)
a quaint and picturesque paved streets (古風で絵のような石畳の通り)
こうした表現を用いている人の脳裏には「今はもう見られなくなった,昔子供のころはよく見かけた」というような「郷愁」が感じられるのです。「昔なつかしい」という表現がぴったりしますね。英和辞典の訳語がすべてではありません。コーパスなどを使って用例をじっと見ていると新しい発見があります。
10. quack 《ガチョウとガマ油》
quack はご存知のように「アヒル・ガチョウの鳴き声」であのかまびすしいガーガーという鳴き声の擬声語です。私たちは「口うるさく話す」ことを「ペチャクチャしゃべる」とか「ピーチクパーチクしゃべる」とか言いますが,英語でも chirp (さえずる)や quack を用いて,
Stop your chirping and quack! (ペチャクチャおしゃべるするのは止めないか)
といったりします。
最近の子供は人が話していてもその目の前で平気でおしゃべりをします。悪気がないのですが,全く周囲への配慮がないんですよね。大学などでもかなりひどいところもあるのではないでしょうか。
さて,話は変わってガマ油の話です。筑波山麓のガマが鏡に映った自らの醜さに思わず流した脂汗から取り出したというガマ油。何にでも効く万能の膏薬。こうした薬は何も日本だけではありません。西洋にも古くからありました。人呼んで,"quacksalver"。日本語にすると「ペチャクチャ軟膏」。自家製秘伝の軟膏の効能をかまびすしく吹聴するニセ医者が結構いたわけです。だいたい何にでも効く "cure-all" というのは毒にも薬にもならないもの。ともあれ「イワシの頭も信心から」というプラシーボ効果もありますから,昔はそれでよかったのかもしれません。
この"quacksalver"が縮まって"quack"。つまり quack には「ヤブ医者」という意味もあるのです。そうした人の行なう医療行為が quack cures です。もっとも,この「ヤブ医者」の語源については「小さな謎である」と『英米単語の歴史辞典』(クレイグM.カーバー,1996,柏書房)はしています。ただ本書によれば,現在では「ほとんどの語源学者」はこのquackを「アヒルの擬声語に由来する」と考えているとのことです。つまり「自分の軟膏の効用をアヒルの鳴き声のようにかまびすしく自慢する人」を指したようです。
11. quadruped 《4本足と2本足》
痔や腰痛に悩まされている方も多いと思います。私も対処療法でなんとかやっていますが,いつ爆発するかもしれない状況です。多分近い将来抜本的な手術が必要になるでしょう(^_^;)
ところで「痔」や「腰痛」は,我々人類が二足歩行を始めたときから定められていた宿命であるという話を聞いたことがあります。4つ足動物には「痔」や「腰痛」はありません。牛がボラギノールを手放せないとか,馬がぎっくり腰で歩けないといった話は耳にしません。ヒトは上体を上げて二本足で立ったために腰に無理な重力がかかるようになったのです。
quadru は「4」,ped は「足」,つまりこの "quadruped" は「4つ足動物」ということです。人は biped です。それでは centipede は? そう,「百足(ムカデ)」ですね。
100周年記念とか,紀元2000年など「きりのいい数字」に対して私たちは何か特別な感情を抱きますが,これはあまり意味がないと思われます。そもそもどうして2000が「きりがいい」と私たちは感じるのでしょうか。それは10進法に慣れているからです。ではどうして10進法なのか。どうしてコンピュータのような2進法や8進法でなくて10進法なのか。それは私たちの指が「たまたま」10本だったからです。もし人類が両手合わせて8本の指に進化していたらどうでしょう。こう考えると2000という数字をありがたがる必要はないですね。
12. qualm 《第1次資料の大切さ》
これは [クォーム] と読みます。500万語コーパスで数語くらいの頻度ですから結構地味な単語です。CIDEは
an uncomfortable feeling of doubt about whether you are doing the right thing.
という意味であると説明しています。つまり「今自分のやっていることが果たしてこれでいいのだろうかという一抹の不安」ということですね。よっぽど能天気な自信家でないかぎり,「これでいいのだろうか」という不安とともに我々は進んでいるといっても過言ではありません。どんなに注意しても起こることは起こるのだとすれば,我々としては「たとえ最悪の事態が生じたとしても被害を最小限に」ということを心がける以外に手はありません。
私はパソコンの個人データは外付けの別のハードディスクにバックアップしていますが,これとてCドライブのハードディスクが一瞬にして「飛んで」しまった経験から学んだことです(^^ゞ。
ところこの qualm ですが,コーパスの用例では without a qualm の形で用いることが多いようです。qualm が「不安」とすれば,without a qualm は「不安なしで→安心して」となるように思えます。事実ジーニアス(1998)にもそう書いているのですが,それでは
Did she see her husband as capable of murder? She had used the word without a qualm.
(彼女には夫に人殺しができるとわかっていたのだろうか。彼女は「安心して」その語を用いていた---COB2の用例)
はおかしな訳になってしまいます。COB2 は実際に使われている表現を極力加工せずにそのままもってくる主義ですのでちょっとわかりにくい用例ですが,ここで使われている最初の文の主語である She と2番目の文の主語の She とは別人だと思われます。「murder(人殺し)」という本来使うのがはばかられる言葉を「ためらいもなく,怖がることなく」用いたというのです。私はここでは「安心して」ではなくて「平然として」が適切であると思います。実際に用いられている第一次資料に当たると面白いものが見えてきます。
13. quantum 《量子と大躍進》
「Quantum(カンタム)」と言えばパソコン通なら有名なハードディスク・メーカーをすぐに思い浮かべることでしょう。この語は元来「量子」という意味で,語源は16世紀半ばに quntity の意味で用いられていたことに始まるとNODEは説明しています。もっとも物理学の用語としては20世紀の始めに用いられるようになりました。他におもしろい意味として「突然の大進歩」というのがあります。進化の過程をみてもわかりますが,物事の進歩や発展というものは直線的なものではなく,ある時点で爆発的に進歩することが多いようです。
英語の進歩もよくアナログ時計に例えられます。時計の分針の動き方には二種類あって,じわじわと少しずつ動くものと,60秒がくるまでじっと動かずにいて60秒になったとたんサッと1分進むものがあります。英語の進歩というものは後者のようだというのです。つまり,いくらやってもなかなか進歩が形になってあらわれないのに,やがてそのうちいつの間にかレベルアップしている自分に気づくというのです。
そうした「躍進」をさらに明確にする言葉として"quantum leap"というのがあります。まさしく「大躍進」ということなのですが,LDOCE3には AmE ((米語)) というレーベルがつけられています。ただイギリスでも使われている例が見られますので「((主に米))」とすべきでしょう。(英語の単語を見ていますと今や米語から英語への流入は激しいものがあります)
また,quantum theory は「量子論」ということです。英和辞典には [the ~] という注記をつけているものが多いようですが,実際の英語に当たってみますと
according to quantum theory
のように無冠詞で用いる例が大変多いのです。英和辞典ではこうした点もよく資料に当たって記述してほしいものです。
14. quark 《ジョイスと素粒子》
これはかなり有名な話ですのでご存知の方も多いと思いますが,現在知られている最も基本的な素粒子
である "quark" の名前は実はジェームズ・ジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」から採られたものです。
米国の物理学者マレー・ゲルマンがhadronという重い粒子が3個の要素から成り立っているという理論を立てたとき,彼はこの要素を臨時に "quork" と名づけました。この語自体には全く意味がありません。その後彼はジェームズ・ジョイスの奇作『フィネガンズ・ウェイク』の第12章はじめに "three quarks" という表現が出てくることを発見し,これは面白いと考えて quork を quark に変名したということです。
命名に凝るというのも第一発見者の特権かもしれません。それにしても理論物理学とアイルランドの奇才ジェームズ・ジョイスの組み合わせはなかなかおもしろいものですね。日本の科学者も何かを発見したら「万葉集」あたりから引用してみたらいかがでしょう。
15. quarrel 《けんかにもいろいろある》
アメリカでホームステイをしたとき,13歳の娘が父と口論する場面に出くわしました。といっても怒鳴りあいをしていたわけではありません。父の意見に娘が「どうして?」としつこく食いさがっていくのです。私なら「もういい加減にしろ!」と怒鳴っているところですが,この父親は根気強く「それはね・・・」と応対していました。見かねた母親が,"Don't argue."というと娘は心外だという顔をして「別に argue なんかしてないわ」といいました。argue は「議論する」という意味がありますが,「口論する,屁理屈をいう」といったマイナスな意味もあるのです。
「口論する」と言えば quarrel ですが,それでは argue とどう違うのでしょうか。Longman Dictionary of Common Errors 2nd ed. (1996)には「quarrel はつまらないことで感情的にいつまでも口論すること。argue は感情的にならずに議論する意味」とあります。そして,
Sometimes we quarrel about which programme to watch.
(ときどき私たちはどの番組を見るかで言い合いになる)
は不自然な文であり,quarrelをargueに変えるように指示しています。これは意外に思われるかもしれません。なるほど小さな子どものチャンネル争いならば怒鳴りあいや取っ組み合いになることもあるかもしれませんが,大人の間では普通は理屈で相手を納得させようとするものです。ちなみに,
I don't quarrel with that idea.
というと「その考えに反対というわけではない」という意味です。
16. bilingal 《「2ヶ国語ペラペラ」だけではない》
最近「バイリンガル」という語をよく目に入ります。言語学者グロータース神父の本(『それでもやっぱり日本人になりたい』)の中にも,幼い頃父親が彼をオランダ語とフランス語のバイリンガルにさせるため引越しをするという話がでてきます。
この bilingal という語は確かに「二か国語がうまく話せる(人)」という意味があります。しかし,もう一つ大切な意味があることをご存知でしょうか。それは「二か国語使用の」という意味です。これは「二か国語を話せる」と同義ではありません。むしろ bilingalism (二言語主義)の形容詞形と考えるべきものです。つまり,国内で一つの言語を強要するのではなく,二つの言語の使用を保証しようとする態度を示しているわけです。英和辞典では bilingalism については,ただ「二言語使用」としか書いていないものが多いのですが,これには次のような「重い」背景があるのです。
カナダの起源は、フランス植民地(今日のケベック州)であるが、そこでは、イギリスに併合されて後も、フランス語の使用が認められていた。この慣行は、現在のカナダ連邦の起点になった「一八六七年憲法」でも確認されている。第二次大戦後は、「二言語・二文化主義に関する王立委員会」が設置されて、二言語主義に関する真剣な検討が行われた。その結果、一九六九年には「公用語法」が制定されて、連邦議会、連邦政府の諸機関、王立の諸機関では、英仏二言語の使用が保障された。八二年のカナダ憲法でも、英仏二言語が公用語であることが確認されている。それにもかかわらず、ケベック州は、七四年に「公用語法」、七七年に「フランス語憲章」を制定して、フランス語だけが公用語であることを宣言している。また、西部の諸州では、ケベック州に対する反発が強まっており、二言語主義は困難な状況に立たされている。(『現代用語の基礎知識』1999年版より)
私はナイアガラの滝を見るために合衆国側からカナダ領へ越境したことがありますが,カナダ領に入ったとたんすべての交通標識がフランスとと英語の両語併記に変わったことに驚いたことがあります。一つの国の中で二つの言語を保証するということはたいへんな費用と労力がいります。それでも敢えてそれを保証しなければならないことがあるわけです。これはマイノリティの立場に立った態度の尊重とも重なってきます。
17. breathalyser 《固有名詞の普通名詞化》
「ホッチキス(Hotchkiss)」と言ってもなかなか相手に通じなかった経験をお持ちの方もおられるでしょう。もちろん英語では stapler が一般的。広辞苑によれば
ホッチキス【Hotchkiss】
(アメリカの兵器発明家ホッチキスBenjamin Berkeley H. 1826~1885の名に因る)
①機関銃の一種。ガス圧を利用した空冷式のもの。
②紙綴器の一種。「コ」の字形の綴じ針を挿入し内側へ折り曲げることで,紙などを綴り合わせる具。綴込器。ステープラー。ホチキス。(広辞苑第五版)
機関銃の弾と同じ発想からという話も有名ですね。このように固有名詞が普通名詞化することがよくあります。例えば傷口を「バンドエイド」で貼ると言っても,実際は「バンドエイド」ではなく「カットバン」などという商品名かもしません。しかし,我々はその種のものはみな「バンドエイド」と呼んでいます。
この breathalyser はもともと「酒気検知器」の商品名です。警察が,酒酔い運転の疑いのあるドライバーの息(breath)からアルコール分を分析(alnayse)するときに用いる機械です。イギリスではこれが普通名詞化してしまっています。なお,アメリカでは drunkometer といいます。
18. obscene 《Hな意味だけではない》
obsceneというと「卑猥な」という意味を思い浮かべます。例えば深夜に女性宅へ電話していきなり卑猥な言葉を浴びせる輩がいますが,これは obscene phone calls (いたずら電話)といいます。こうした行為は実に暗く人間として誠に哀れな感じがしますが,それはそれとして,このobsceneは他にもう一つの意味があるのです。次の英文をごらんください。
He spends obscene amounts of money on food. He should know millions are starving in the world.
「いやらしい額のお金」ではありません。「道徳的に許しがたい額のお金」という意味です。obsceneはもともと「不吉な,忌まわしい」という意味のラテン語obscaenusに由来します。
19. oblique 《遠まわしの》
oblique line は「斜線」のことです。oblique は「斜めの,はすかいの」という
意味です。ただ,実際の使用例では英和辞典では普通第2の語義にもってきている
「[通例限定] 遠回しの, 間接的な(not straight)←ジーニアス英和」
の意味が結構多いようです。例えばBNC samplerのコーパスで oblique を検索すると
次の10件(1と7は同じ表現が2度出現)が得られました。
1. oblique ways(2) 「婉曲的なやり方」
2. eity oblique seven seven eight 「80,/,7,7,8」
3. oblique crediting 「不正な信用貸し」
4. oblique kilo 「/キロ」
5. oblique angles 「斜角」
6. oblique autobiography 「それとなく述べられた自伝」
7. oblique reference(2) 「暗に~についていうこと」
8. oblique line 「斜線」
|
「斜線」という意味は2,4,8の3例,「遠まわしの」は1,6,7の重複を入れて5例,「不正な」は3の1例となっています。この oblique という語は他のコーパスでも,
make an oblique reference to~ (暗に~について言う)
という表現で結構使われています。
Home Pageへ
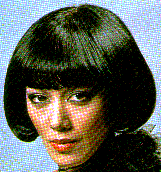 右の写真が,そして「ロング・ボブ」として
右の写真が,そして「ロング・ボブ」として
 左の写真があります。これから判断すると,「ボブ」は日本の「おかっぱ」に近く,マッシュルーム型のヘア・スタイルのようです。ところが「グローバル英和」のbobの項に載せられている挿絵はこのいずれの形とも異なり,極端に短いボーイッシュなヘアカットになっています。いったいどれが正しい「ボブ」なのでしょうか。そこで何でもありのインターネットで調べてみました。すると,なんと1263にも及ぶ様々なボブ・ヘアスタイルを集めたThe Bob Haircut Worship Pageというホームページがあるではないですか!タイトルから見てちょっとフェチっぽい感じもしますが,それはそれとして,ここでもやはり基本は「おかっぱ」です。やはり英和辞典では特殊なものではなく「基本的一般的」なものを載せるべきでしょうね。
左の写真があります。これから判断すると,「ボブ」は日本の「おかっぱ」に近く,マッシュルーム型のヘア・スタイルのようです。ところが「グローバル英和」のbobの項に載せられている挿絵はこのいずれの形とも異なり,極端に短いボーイッシュなヘアカットになっています。いったいどれが正しい「ボブ」なのでしょうか。そこで何でもありのインターネットで調べてみました。すると,なんと1263にも及ぶ様々なボブ・ヘアスタイルを集めたThe Bob Haircut Worship Pageというホームページがあるではないですか!タイトルから見てちょっとフェチっぽい感じもしますが,それはそれとして,ここでもやはり基本は「おかっぱ」です。やはり英和辞典では特殊なものではなく「基本的一般的」なものを載せるべきでしょうね。