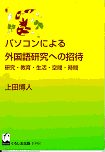 【インパクト指数】7.3
【インパクト指数】7.3
私がこれまで読んでおもしろかったと思われた本を以下の紹介します。すべて私の独断と偏見によってかかれておりますが,何かのご参考になればと存じます。評価も私個人の判断であり,客観的なものではありません。
【インパクト指数】
この数字は,その本を100頁に換算した場合,私が面白いと感じた頁がどのくらいあるかを示しています。数字が大きいほどインパクトがあります。
計算方法は(私が面白いと感じた頁)÷(総頁数÷100)です。
(山口謠司著、集英社インターナショナル,2016年2月29日第1刷発行,総頁数522頁,ISBN978-4-7976-7261-9 C0095
【インパクト指数】13.8
【本文から】
|
■日本語が英語になる可能性は実際にありえた! 明治の教育システムを作る中心にいたのは森有礼(ありのり),大木喬任(たかとう)(1832~1899),外山正一(1848~1900)の三人であった。(略) 実質的に高等教育における英語の重要性を前面に押し出したのは,森有礼であった。森は,日本語を排して英語を日本の公用語にしようということを唱えた人物でもある。今から思えば,不可能にも思われるが,当時の人口は約3千万人,唯一の大学である東京大学の学生数は千人である。そしてここに入学する学生たちは,遅くとも十四歳頃から英語を習っている頭脳も優秀な学生たちだった。大学南校や帝国大学での授業がすべて英語でなされていたという事情も,このようなことを考えれば,不思議でもないことであった。(略) 日本語を捨て去って,母国語を英語にするということを,もし,彼らが決めていたとしたら…ということも,必ずしも不可能ではなかったのである。(P.50) ■明治の初めにはまだ「日本語」という言葉はなかった (明治18年頃の)人はみな,日本語を話,日本語で手紙や戯作を書いていた。しかし,「仮名文」や「漢文 はあっても「国語」はまだだれも知らなかった。外国から来た人は,日本人が話す言葉を「JAPANESE」と呼んだが,日本人は,「日本語」という言葉を知らなかったのである。(P.90) 高橋義孝は『森鴎外(←「おうがい」の「おう」の字が正しい漢字が変換されないので,ここではやむなくこの字を用いる)』で,漱石と鴎外の文章を例に挙げ,その差について見事に記している。 (略)そして鴎外の「日本語」はあとに残らず,漱石の気安い文体があとに残ることになった。?外の文章を拒否したのは,おそらく日本人の心性そのものではなかったであろうか。 漱石の文体は,ほとんど,万年が望む言文一致体であった。当時より現代まで,漱石の文体は古びることなく,人々の心を掴んでいるのである。 |
【私のコメント】
522頁の大作であるが,実におもしろかった。「上田万年」の名は「かずとし」と読む。しかし,本人自身はドイツ留学中でも「Mannen」と書いていた。
幕末から明治にかけての「日本語」は,「日常会話」と「書き言葉」があまりにも乖離していた。さすがに候文は消えていったが,漢文訓読調はなかなか捨て去られることはなかった。本書の冒頭には,万年が司会を務める「臨時仮名遣調査会」ではすでに教科書には「新しい仮名遣い」を使うことに決まりかけていたのに,軍服をきて山形有朋の権威をバックにした森鴎外によってくつがえされ,「旧仮名遣い」にもどってしまう場面が描写されている。本書には,「国語」に関係する様々な人々の人間関係も語られており,非常に興味深いものがある。「日本語」に関心を持つ人々には,買って損のない書籍である。
(田澤耕著、中公新書2251,2014年1月25日発行,総頁数264頁,ISBN978-4-12-102251-6
【インパクト指数】9.5
【本文から】
|
■「辞書屋」とは? 私は辞書を作る者は、「学者」というよりも「職人」に近いと思う。したがって、「辞書職人」とする選択肢もあった。しかし、lexicographerの仕事には「作る」以外に、もう一つの側面がある。それは、「辞書を売る」ことである。(略)辞書を作る者には「商人」としての才覚も求められるのである。偏屈な「職人」であると同時に、如才ない「商人」でもあらねばならぬ。最上の選択とは言えないかもしれないが、わたしはこの職に「辞書屋」の語を当てた。(p.iii) ■主婦が書いたもっともすぐれた西西辞典 スペイン語の専門家に「もっとも優れた西西辞典は?」と尋ねたら、十人中十人がマリア・モリネールの『スペイン語用法辞典』Dicionario de Uso del Espanolと答えるだろう。スペイン語の最高権威たる「スペイン王立言語アカデミー」の辞書を差し置いてナンバーワンに挙げられるこの辞書を「書いた」のは一人の主婦であった。(p.206)
|
【私のコメント】
辞書作りは根気のいる仕事であり、かつ、自らの言語への感性が問われる仕事でもある。今は亡き大野晋は「辞書を作っていると、あっ、このまま死ぬのかなと思う瞬間がある。編集者の一人や二人が死ななければまともな辞書とはいえない」といった趣旨の発言をしたことがある。本書は、OED、ヘブライ語大辞典、カタルーニャ語辞典、言海、ウェブスター辞典、和英語林集成、西日辞典、スペイン語用法辞典等に携わった歴史的人物について語られている。筆者自身が、銀行マンから辞書学に進んでいったおもしろい経歴の人である。専門のカタルーニャ語については特に力が入っている。カタルーニャは、いわばスペインの「スコットランド」と言うべき、独自の歴史と文化と言語を持つ「国」なのだ。
(佐々木健一,文藝春秋,2014年2月10日第1刷,総頁数329頁,ISBN978-4-16-390015-5 C0095
【インパクト指数】9.1
【本文から】
|
■「新明解三版」による「恋愛」の定義 れんあい【恋愛】特定の異性に特別の愛情をいだいて、二人だけで一緒にいたい、出来るなら合体したいという気持ちを持ちながら、それが、常にはかなえられないで、ひどく心を苦しめる・(まれにかなえられて歓喜する)状態。(p.17) ■謎の「1月9日」 じてん【時点】「1月9日の時点では、その事実は判明していなかった。(「新明解国語辞典」第4版)(p.57) ■「名義貸し」の悪習 辞書界では、「監修」や「共著」と名前が出ていながら、単なる”名義貸し”であることがまかり通っていた。当時、「金田一京助」の名を掲げる国語辞典は、三省堂の『明国』『三国』以外にも、小学館の『新選国語辞典』などがあった。世間の辞書に対する絶対的な「金田一京助ブランド」が存在する限り、会社としては名前を落とすことはできなかった。(p.311)
|
【私のコメント】
高校生の時、小さな安っぽい英語の問題集に英語界では有名な先生の名が監修者として出ていた。担任の先生が、「あっ、これはな、名前だけ貸しとるんや」と言った。そのときは、自分が書いてないのにそんなことするのかなと思っていたが、実は事実だった。出版社は売るために「ブランド」を重視する。でも、名前を貸す「有名人」の方にも責任(または良心の呵責)はないのだろうか。この本を読むと、これまでの「辞書の金田一」って、いったい何だったのだと思う。特におもしろかったのは、金田一春彦がポロッともらした情報で、出版社にうっとうしく権利の要求をしてくる見坊と山田に対して、結果的に会社側が彼らの仲を裂く形で動いたということだ。この二人の辞書観の違い、性格の近い、それぞれの思惑の違いも錯綜して、二人は1972年1月9日「新明解国語辞典」完成の打ち上げ会を境に決別する。爾来、二人は他界するまで直接口をきくことはなかった。ノンフィクションであるが故に、また辞書界に足を踏み入れているが故に、フィクションである三浦しをんの「舟を編む」よりも私はおもしろかった。
(阿辻哲次,文春新書702,2009年6月20日第1刷 ISBN978-4-16-660702-0 C0295
【インパクト指数】11.7
【本文から】
|
■世代によって「しんにゅう」派と「しんにょう」派に分かれる 小学校のときに「しんにゅう」と習って以来,最近までずっとそう呼んできた。おそらく私のみならず,私より年上の方はもちろん,それほど年が離れていない世代には,「しんにゅう」と呼ぶ方が多いのではないだろうか。(略)昭和40年代以後に刊行されている国語の教科書では「しんにょう」となっているそうで,わが家の子どもたちは二人とも,なんの疑問もなく「しんにょう」といっている。(p.34) ■コザトヘンは「天と地をつなぐ階段」 コザトヘンのついた漢字は甲骨文字にもいくつかあるが,そこではコザトにあたる部分があきらかに階段の形をかたどった象形文字として描かれている(略)。古代人の認識では天上の世界と地上のあいだには目に見えない階段がかかっていて,神はその階段を使って天と地上を行き来していたのである。コザトのもっとも古い形は,その階段をかたどった象形文字だった。 ■おならは「ピー」 おならのことを漢字では「屁」と書くが,その漢字は見てのとおり《尸》と《比》の組み合わせでできている。《尸》は(略)「人や動物のからだ」という意味を表している。一方,もう一つの構成要素である《比》は(略)「ヒ」という発音を表しているだけにすぎない。(略)《比》の中国語での発音は昔も今も,カタカナで書けば「ピー」となる音である。(p.176)
|
【私のコメント】
阿辻先生の本は,いずれをとっても参考になる。時に下ネタもあっておもしろい。本書は「猫や狐にケモノヘンがあって,馬や犬にはないのはなぜか?」「氏名に異体字が多いのはなぜか?」「しんにょうにはどうして一点と二点のものがあるのか?」「漢字はいつごろできたのか」「漢字はなぜ『漢字』というのか?」「一番新しい漢字は何か?」などの問いに筆者が答えるものである。買って損のない本。
(阿辻哲次,講談社現代新書1928,2008年2月10日第1刷 ISBN978-4-06-28792-6 C0280
【インパクト指数】17.3
【本文から】
|
◆日本では,長江下流域での発音を基礎とした呉音で漢字を読むのが主流であった。それが唐との交流がさかんになるにつれて,漢音がどんどんと流入するようになったのである。漢音が流入し,その学習が広まるにつれて,二種類の音読みが使われ,混乱が生じてきた。そこで漢字の読みを統一するために,桓武天皇が延暦11年(792)に漢音の使用を奨励する詔勅を出し,儒学を学ぶ学生に対し漢音の学習を義務づけた。こうして平安時代以降には漢音が正統的な音読みとされるようになった。(p.22) ◆漢音と呉音のほかにじつはもうひとつ,平安・鎌倉時代から江戸時代までの長い日中交流のなかでさまざまないきさつによって入ってきた漢字の音読みがあって,それを「唐音(とうおん)」と呼ぶ。(略)禅宗で使われる用語いは唐音で読む語彙が多くあって,禅宗の僧侶は,ほとんど唐音に囲まれて生活していたといってもいい過ぎではないほどだ。(略)禅宗では仏具のひとつである「鈴」(漢音レイ・呉音リュウ)を「リン」と呼ぶ。この「鈴」を「リン」と読む唐音がいまも「風鈴」に生きているので,じつはそれはだれでも知っている読みなのだが,ただそれが唐音であることが知られていないだけである。(p.26~29) ◆「のれん」はじつは中国で使われていた「暖簾」の唐音読み「ノンレン」が変化したものであった。もともと中国の商店で使われていた「暖簾」は,日本の「のれん」とは,形も用途もかなりことなったものだった。中国の「暖簾」は,厳寒期に外から冷たい風が建物内に入ってくるのを防ぐために,玄関や部屋の出入口にかけて地面まで垂らす厚い布,または綿入れカーテンのことで,だから「暖」という漢字が使われているのだ。(p.33) ◆もしだれかが書き取りのテストで「校」や「松」という漢字にある木ヘンをはねてバツをつけられたら,唐代の楷書の名手として知られ,中国書道史を代表する書家の一人として,昔もいまも書道関係者や芸術家が崇敬してやまない顔真卿(がんしんけい)(709~785)が,「校」や「松」を図のように(ハネて)書いているが,それはまちがいなのかと聞いてみればよい。(P.87)
|
【私のコメント】
本書には漢字に関する様々なエピソードが満載されていて楽しい。特に学校や塾で怖い先生が,生徒が木ヘンをハネて書いていたり,間違った筆順をすると減点をしたりするが,それについて筆者の指摘はきびしい。そもそも漢字を書く場合に,「ハネる」たり「トメる」することのルールや「正しい筆順」などというものはないのだ。それにはそもそおm「絶対的な基準」などはないのである。筆者は様々な資料を示して,その事実を教えてくれる。目からウロコの書物である。
(大野晋,朝日新聞社,1999年12月10日発行 ISBN4-02-258448-5-3 C0095
【インパクト指数】11.6
【本文から】
|
◆(一高の)入学試験の合格発表は親父が身にいってくれた。親父が帰ってきた。「どうだった」と出迎えると,「受かってた」という。「よかった!」と叫んで「何番だった?」ときくと,親父は一呼吸置いて答えた。「お前の後には誰もいないよ」。(p.56) ◆顔の浅黒い大きな男がすっと現れた。坐っていたわれわれを見下ろすその男(折口信夫)の眼の異様な鋭さ。かつて知らないその眼の色と光とは長く私の心にかかっていた。戦後かなり時がたって池田弥三郎氏が折口信夫の講義ノートを編集していて,中央公論社から出版した。その時「月報に何か折口に関する文章を」という電話があった。(略)「昭和二十年代に加藤守雄という方の折口信夫論を読みました。それによって,折口氏の眼の光の由来が分かったように思いました。そのことなら書けます」。池田氏はしばらく考えて「ではやめにしましょう」といった。加藤氏の本には折口氏のhomosexualityについてかなりの記述があった。池田氏は当然それを御存知のはずだった。(p.86) ◆チューリッヒの学会では社会学部門で「狭山事件」が扱われた。被告石川一雄氏の筆跡鑑定をした私にスピーチの依頼が来た。私は事件の全容は知らないが,唯一の物証とされる脅迫状は,被告人の当時の学力では到底書けない高度の言語技術が駆使されていることを話した。後で聞くとそこでチューリッヒアピールという反政府的声明が出されたという。ススムオーノはそれで反政府活動に加わっている人物としてマークされたのだろう。(p.92) ◆似た意味の言葉の差を見るためには,多くの使用例を集め用法の型を分析する。(略)言葉は我々は無自覚に反射的に使っているけれど,語例を多く集めて分析すれば,「意味」や「使い方」を抽出できることをこうして知らせた。(p.169)
|
【私のコメント】
私は尊敬する学者としては大野晋を,尊敬する作家としては住井すゑを挙げるのが常だった。今やお二人とも鬼籍に入られた。この本は大野氏の自伝ともいうべき本である。一高での発狂寸前の苦しみ,父との葛藤。すべてがありのまま書かれている。彼のベストセラー「日本語練習帳」(岩波新書)にも表れているが,用例を多く集めてそれらの中から類語の微妙な違いを発見する――これこそまさに,「コーパス言語学」の手法である。私はいつか,DNA解析の研究がすすめば,大野氏の夢見た「日本語のタミール由来」が証明されることになるだろうと確信している。あれほど嘲笑され,一部の人々から敵視された説が見直される日がきっとくる。なによりも,彼は誠実な人であった。これほど優れた学者を我々は失った。
(高島俊男,講談社学術文庫1291,1997年8月10日第1刷,2009年12月18日第16刷) ISBN4-06-159291-2 C0198
【インパクト指数】15.3
【本文から】
|
◆容易にひとに許さず,またひとからも親しまれなかった杜甫が,その生涯においてこれほど心を開きなつかしんだのは,李白と,のちに長安で知り合った狷介(けんかい)の学者鄭虔(ていけん),そしておそらく妻,だけであった。(P.18) ◆不幸なことに,李白の目的は詩人たることではなかった。むろん彼は詩人であり,みずからもわれこそ第一級の詩人なりと自負している。けれどもそれは,よき文学創作者こそよき官吏,よき政治家たりうる,という,李白の信念,同時に当時の通念をふんまえてのわれこそは第一級の詩人,なのであって,単なる詩人たることは,いかに一級であろうと超一級であろうと,断じて李白のめざすところではなかった。そこに李白の悲劇があったのである。(P.61) ◆全く信じられないようなことだが,杜甫は筋の通ったふつうの文章というものが書けない男だったのである。(略)杜甫は,おそろしくいびつな発達をした天才なのである。彼は詩という形をとらなければ何も言えなかった。言ったところで支離滅裂であった。(P.230)
|
【私のコメント】
本書はもともと1972年に評論社から出版された著者の最初の本である。著者の他の本もおもしろいが,この本はとりわけおもしろい。「詩人」としての李白や杜甫でなく,生涯求職活動をしながらも,その夢を十分には実現できなかった二人の天才「詩人」の実像が描かれている。同時代を生き,夢を果たせず,貧窮の中で詩を読んだ天才詩人。この二人が直交した驚くべき時期。二人の性格や実生活の様子がわかって実におもしろい。つまらぬ本100冊より,これ1冊。おすすめしたい。
(加藤徹,培風館,2010年9月10日初版発行) ISBN978-4-12-004148-8 C0095
【インパクト指数】18.3
【本文から】
|
◆日本語は膠着語である。日本語の漢文訓読では,語と語のあいだに,「たる」「の」「に」「・・・しからん」など形態素的な語を,膠のように付着する。漢文の原文とは大違いだ。そんな日本語でも,手話は孤立語的になる。日本語の「口話」で使う「てにをは」のような助詞も(略)手話では切り捨てざるをえない。(P.35) ◆江戸時代から現代に至るまで,日本人の中国観は二つに大別できる。一つは士人ルートの流れを汲む「漢文派」である。漢文古典や儒教的教養など,中国の士人文化への強い関心をもつ。もう一つは商人ルートと移民ルートの流れを汲む「唐話派」である。中国の俗文学や芸能など,同時代的なサブカルチャーに興味関心をもつ。(P.55) ◆よく「英語のアルファベットは26文字だけだが,漢字は約5万字もある」という俗説を聞く。が,この比較対象は,経済言語学的ア見地から見てフェアではない。5万に及び漢字はバラバラな記号ではない。その9割は意符(部首などの意味領域限定符号)と音符(漢字の右半分であることが多い)を組み合わせた形声文字である。意符の総数は約200にすぎない。音符もほぼ同数である。(P.83)
|
【私のコメント】
加藤徹氏の本には「はずれ」はない。いずれもが示唆に富み,新たな発見がある。我々には漢文と言えば,古くて現代とは関係のないもののように思えるが,そうではない。漢文は時にはサイエンティフィックであり,時には現代の日本そのものに深く関係している。中国人の奥さんを持ち,京劇から現代中国語まで幅広い学識を持つ著者だからこそ,書ける内容ばかりだ。常に高いインパクト指数を持ち続けるのも当然と言えよう。日本と中国――その長くて深い交流の歴史は,尖閣列島くらいで吹き飛ぶようなものではない。
(山口謠司,新潮新書345,2010年2月20日発行,2010年3月5日2刷) ISBN978-4-10-610349-0 C0281
【インパクト指数】20.4
【本文から】
|
◆「上代特殊仮名遣い」で書かれた『古事記」を読んでいると,驚くべきことに気がつく。なんと,「ん」と読む仮名が一度も出てこないのである。(略)また『万葉集」はどうかと思って探してみると,これにも「ん」がないではないか。はたして,日本語にはもともと「ん」はなかったのだろうか?(P.29) ◆「ん」という仮名がなかった時代,西大寺の僧は,舌内撥音と喉内撥音の「ン」を「イ」で表していたのである。(略)他にも様々な形で「ン」を表そうとする記号がつかわれては,定着することなく消えてしまっている。(P.52) ◆彼(=白井寛陰)の研究によって,「ん(ン)」と書かれるものは,上代日本語にはじつは「舌内撥音―n」「唇内撥音―m」,「喉内撥音―ng」の三種類の撥音があったことがようやく明らかにされたのである。(P.134) ◆現在のところ,「ン」という<カタカナ>が使われたもっとも古い写本は,(略)龍光院に所蔵される,康平元(1058)年の『法華経」だとされている。(略)「ン」という文字は,撥ねを示すための記号である「レ」が,<カタカナ>の「レ」と混同しないように区別されて作られた文字だと言われている。(P.156)
|
【私のコメント】
著者の奥さん(フランス人)は,著者が言葉に詰まって「ん――」というときの音を嫌うという。[m]を連ねて[hmmmmm]と発音するのならOKらしい。著者はこの「ん」に興味を持って,これがいつ頃使われだしたかを調べ始める。音としての「n, m, ng」は古くからあったようだが,記号としての「ン」は11世紀,「ん」は12世紀あたりから使われだしたようだ。インパクト指数20を越える本で,得るところが多い。第一,「ん」というタイトル一文字が奇抜でおもしろい。
(川合康三,岩波新書1228,2010年1月20日第1刷) ISBN978-4-00-431228-4 C0298
【インパクト指数】10.0
【本文から】
|
◆逆境からこそすぐれた文学が生まれるのだと説いたのが,北宋の欧陽脩(1007-1072)であった。(略)ところが稀有な例外があった。白楽天である。中国士人の一般的な価値観に基づくならば,官人として高位にのぼること,文人として名声を博すること,人として長寿を得ること,そのすべての幸福に彼は恵まれたのだ。(P.5) ◆仕官は栄達と富裕を与えてくれるものであり,隠逸は地位も金銭もないが,世俗の煩わしさや汚濁から解放される。どちらもほしいのが人の常だが,しかし本質的には相いれない。その両者を兼ね備えうるのが白楽天のいう「中隠」である。(略)「中隠」の「中」たるゆえんは,官でもあり隠でもある,あるいは官でもないし隠でもない,官と隠の中間,そこに位置することだ。何事も中間の状態,「ほどほどに」を好む白楽天らしい発想であった。(P.196)
|
【私のコメント】
李白も杜甫も恵まれた人生を送ったわけではない。とりわけ杜甫は貧苦にあえぐ大変な苦労人であった。中原中也や石川啄木などを思い浮かべると,そもそも詩人はハングリーの状況から生まれるものではないかという気がする。それくらい詩人は生活に苦労している。ところが官吏としては宰相の一歩手前まで上り詰め,詩人としてはすでに生前において遠く日本にまで知られる名声を博した男がいる。それが白居易(字は楽天,日本では通称白楽天)だ。また,運にも恵まれたし,友人にも恵まれた。境遇や性格に由来するのだろうが,詩人独特の刺々しさのないところが好まれた(そして,批判された)。
スティーブン・ピンカー著,幾島幸子・桜内篤子訳,NHKBOOKS 1132,2009年3月30日第1刷 ISBN978-4-091130-3 C1380
【インパクト指数】8.8
【本文から】
|
◆もし9・11が一つの事件だとみなされれば彼の受け取る保険金は35億ドル,もし二つの事件だとみなされればその倍の70億ドルとなるはずだった。裁判の争点はこの「事件」が何を意味するかに集中した。シルヴァースタイン側の弁護士は物理的な解釈(崩壊は二回起きた)から事件は二つだと主張し,保険会社側の弁護士は心理的な解釈(計画は一つ)から事件は一つだと主張した。そう,「単なる」意味論などではないのだ! (P.17)
|
【私のコメント】
◆ピンカーは大草原の小さな家のお父さん役をしていた故マイケル・ランドン似のカナダ人心理学者だ。「言語を生み出す本能」「心の仕組み」などもすでにNHKブックスから出ており,いずれも言語に関心のある人には必読の書だ。今回の本の冒頭に,9・11の話が出てくる。崩壊したツインタワーの持ち主は,ツインタワーを保険にかけていた。そこには「一つの出来事(event)に35億ドル支払う」とあった。当然持ち主は二つのビルが崩壊したのだから,70億ドルを要求したが,保険会社は「これはビンラディンらが計画した1つの出来事である」と出張した。つまり,9・11は史上最も「高価」な「意味論」の問題となったのである。
◆本書には「ののしり語ななぜ存在するのか」などの面白いテーマもある。そもそもF*ck you!は命令形としてはおかしい。それをいうならF*ck yourself!となるべきである。I f*ck you.の省略形という説もあるがそれも間違い。正しくは,May God damn you.に由来する別のののしり語"Damn you."の連想によるものらしい。本書は他にも随所に興味深い話が紹介されている。
笹原宏之,岩波新書(新赤版)991,2006年1月20日第1刷 ISBN4-00-430991-3
【インパクト指数】18.0
【本文から】
|
◆(漢字に)日本独特の字義が加えられたとき,それは「国訓」と呼ばれている。中国ではなまずを意味した「鮎」が「あゆ」と読まれるようになったもの,中国では朝焼けや夕焼けといった意味であった「霞」が「かすみ」を指すのも,国訓である。(p.15)
|
【私のコメント】
◆漢字ブームというが,私にとってはこれほどありがたいことはない。漢字にまつわる様々な良書が出版されているからだ。この本も,ほとんどのページがすべておもしろい。中でも,今出回っている「誤字」がどのように生じてきたかを様々な例をあげて示しているところが非常に面白い。例えばJIS漢字第二水準に,「妛」という奇妙な漢字がある。これはなんと「山」の下に「女」と書いて「あけび」と読ませる国字であったのだが,『国土行政区画総覧』を編集する際に切り貼りした「山」と「女」の間に「コピーの影線が写って」しまった。それを別の人が「妛」と取り違えてしまった証拠を著者は発見する。「妛」はなんと「幽霊語」であったのだ。
小駒勝美,新潮新書253,2008年3月20日発行,2008年5月10日5刷 ISBN978-4-10-610253-0 C0281
【インパクト指数】16.0
【本文から】
|
◆戦前の新聞の見出しや,商店の看板を見ると,横書きの文字は右から左へと書かれている。それで,戦前は右横書きだったのが,戦後になって左横書きに変わった,と考える人が多い。だが,戦前にも,横書きは左から右へ書いていたのである。(略)では,あの新聞の見出しや商店の看板は何なのか。実はあれは,縦書きなのである。どんなに横長でも,縦書きなのだ。日本語では縦書きで書く場合,右の行から左の行へと書き進めていくのだから,(略)「山本商店」の看板も(略)左から「店商本山」になる。(P.53)
|
【私のコメント】
◆掛け軸は壁に掛けるものだから縦長でもよい。だから「花鳥風月」もこの順で上から書く。しかし,欄間に掛けている額はどうしても横長になる。だから,縦書きで一文字ずつ右から左へ「改行」しながら書くことになる。すると「横書き」を右から書いているように見えるのだ。本書にはこのように「なるほど」とうなってしまうおもしろい事実がふんだんにある。久し振りの二桁のインパクト指数。「己」「已」「巳」の違いを知りたいと思いませんか?なぜ「大坂」でなく「大阪」と書くのか,また「々」はなんと読むのか知りたくありませんか?本書はそれに答えてくれます。
橋本治,ちくま文庫,2001年12月10日第1刷,2007年4月25日第13刷 ISBN4-480-03690-3 C0195
【インパクト指数】9.5
【本文から】
|
◆昔の女の人は,御簾の奥にいて,絶対に男に顔を見せないものでした。平安時代のお姫さまがそうでしたが,べつにこれは,平安時代に始まったことじゃありません。『古事記』の昔からそうで,身分の高い女の人なら,江戸時代になってもそうでした。「まともな女なら,絶対に人前に顔をさらして歩かない」という,イスラム原理主義のような常識が,長く日本を支配していたのです。だから「まぐあう」という言葉も生まれます。(略)「まぐあう」の漢字は,本当は「目合う」なんです。(略)「男と女の目と目が合ったら,これはもうセックスしたのと同じ」というのが,その昔の常識でした。(P.76-77)
|
【私のコメント】
◆私は定価680円の本書(文庫本)を古本屋で400円で購入した。期待していなかっただけに,いずれのページも目から鱗の体験ばかりだった。この本は私が購入した価格の10倍の値打ちがある。ものごとをわかりやすく説明するのは至難のわざであり,それができるのは一部頭のよい人たちなのだが,著者はその一人である。さすが「桃尻語訳枕草子」を書いただけはある。あれもこれもと,私が得た知識をお教えしたいが,それはぜひ本屋でこの本を買っていただきたい。お買い得の本である。
齋藤希史,NHKBOOKS 1077,2007年2月25日第1刷
【インパクト指数】8.8
【本文から】
|
◆1797年の倹約令に始まり,老中松平定信によって足かけ7年にわたって行われたのが寛政の改革と呼ばれる一連の政策です。そしてそのうちでも,寛政2年(1790)から行われた異学の禁が,素養としての漢文にとっては重要です。(略)朱子学を正統とし,それ以外の学派(略)を幕府の儒者が講じることを禁じました。(略)近代的な概念で言い換えれば,国定教科書を指定し,国立学校を設置し,国家統一試験を行った,ということになります。(略)あくまでも標準モデルを定めた,ということです。(略)解釈の標準が定まっていないと,訓読もまちまちになってしまいます。(略)やや極端な言い方ですが,異学の禁があればこそ,素読の声は全国津々浦々に響くことになったのです。(P.21-23)
|
【私のコメント】
◆本書は,これまでの漢文主体の議論を離れ,社会全体の漢文脈の中で,漢文そしてその読み下し文が日本社会に与えてきた影響を鳥瞰する。寛政の改革での「異学の禁」が漢文解釈(読み下し)の標準化を進め,それが国民の漢文学習を一挙に推し進めたという話は実におもしろかった。中国語である漢文でもなく,かといって日常の話し言葉でもない,あの不思議な魅力と活力に満ちた人工語「訓読文」がどのように生まれたのか,この本はわかりやすく説明してくれる。そしてその普及に大きな役割を果たしたのが頼山陽の「日本外史」や中村正直の「西国立志論」などの大ベストセラーだったのです。
【インパクト指数】4.5
【本文から】
|
◆延喜五(905)年,紀友則・貫之らは『古今集』の編纂を下命された。政界で没落し,菅原氏のように詩で名をなすことのなかった紀氏にようやくめぐってきた栄光である。仮名序結語の躍動するような文章は再生の機会をつかんだ者の喜びを伝えている。しかし,貫之の従兄で『古今集』筆頭選者であった友則は選集の途中に没し,完成の喜びをわかつことはできなかった。痛恨の思いはいっそう深かったであろう。貫之は友則の功績をひそかに,しかも公然と顕彰した。それが『古今集』仮名序の人麻呂である。(P.234)
|
【私のコメント】
◆私は紀州出身であるがゆえに,「紀氏」にはひときわ親近感を持つ。紀貫之がまるでわが先祖のような感覚を持つ。紀氏の祖先は,大和朝廷にあっては武人として「日本書紀」に登場する。称徳女帝に子はなく,天智天皇の子の施基(しき)皇子と紀諸人(もろひと)の娘・橡姫(とちひめ)の間に生まれた光仁が天皇として迎えられ,紀氏はおもいがけなく天皇家の外戚となり,大きな権力を持つようになる。しかしやがて藤原氏の策謀に敗れてしだいに没落していく。その紀氏が今度は和歌の道で頭角を現すようになったのだる。ただ,柿本人麻呂がそうであったように,朝廷での歌人の身分ははなはだ低い。
◆「古今集」の序文には,不思議な人麻呂の描写がある。述べていることが支離滅裂なのだ。人麻呂の官位も,作品も,活動した時代もてんででたらめなのだ。他の部分ではいたって緻密な紀貫之がそのような誤りをおかすわけがない。そこには意図的なものがあるに違いない。そもそもこの「古今集」はしゃれと物名が満載された「言語遊戯」の本ではないか。そして著者は,ここでいう「人麻呂」は貫之の従兄で不遇にも「古今集」完成前に逝去した,紀友則であるという結論に達する。まるで推理小説のようにおもしろい本である。余談ではあるが,著者の「ジョークとトリック」(講談社現代新書)は傑作である。
【インパクト指数】20.5
【本文から】
|
◆目的と手段の取り違え 「旦那様,旦那様,起きて下さいませ。睡眠薬を飲む時間です」――「健康のためなら死んでもいい」という人も多い。酒もダメ,タバコもダメ,美食もダメとなると「生きていることが健康に悪い」と思えてくる。船は港にいると安全だが,船が作られた目的は海に出ることだ。(P.80) ◆言葉は最初から理由があって決まっている訳ではない。「蝶」を「チョウ」という理由は一つもないのに,日本語では「チョウ」といわなければならない。自分一人が「テフ」が正しいといっても誰にも通じない。イエスペルセンという文法学者はエスペラントのような世界共通言語イドを作ったが,普及せず一人しか話せなかったという。どんなに正しくて完璧な言語を完成させても通じなければ意味がない。(P.104)
|
【私のコメント】
◆新書でインパクト指数20ということは,ほとんどすべてのページがおもしろいということだ。言語学というととかくこむずかしいように思えるが,この本は実にさまざまなエピソードを例にわかりやすく書かれている。筆者の博覧強記ぶりがわかる。この内容で700円とは!最近は新書ブームでくだらない本も増えているが,この本は言葉に関心のある人ない人に関わらず,勧めたい。
【インパクト指数】8.8
【本文から】
|
◆唐の詩人で「鬼才」と呼ばれた李賀(りが)(791-817)は,「夢天(むてん)という詩のなかで自らを月面上に立たせ,そこから地球を見下ろしました。 遥望斉州九点煙 遥かに望む 斉州九点の煙月世界に立って,はるか地球をながめた。大陸は小さな九つの雲煙の点にすぎず,海洋も丸いコップに注がれた青い水に見えた。(P.161)
|
【私のコメント】
◆アポロ11号のニール・アームストロング船長が月面から地球を眺める1000年以上も前に,すでに中国の詩人は想像の中で,「地球の出」を体験していたとは!
◆漢文は何も文系人間だけのものではない。本書は漢文を文学という狭い視野から解き放ち,理系的な問題も含めて,現代人が直面する様々な問題について中国の先達が答えようという画期的な試みである。これまでの受験漢文から脱皮し,一段高い所から漢文が果たしてきた役割を考えることができる本である。著者は広島大学の助教授だが,この人の本はおもしろい。
【インパクト指数】13.2
【本文から】
|
◆近代以前は,どの文明国も,三層構造の言語文化を持っていた。上流知識階級は高位言語たる純正文語を,中流実務階級は口語風にくずした変体文語を使った。下層階級は,文字の読み書きができぬ者が多かった。(略)封建時代の日本でも,言語文化は三層構造だった。上流知識階級である公家や寺家,学者は,純正漢文の読み書きができた。中流実務階級たる武家や百姓町人の上層は,日本語風にくずした変体漢文を交えた文体「候文」を常用した。下層階級,たとえば長屋に住んでいる「熊さん」「八っあん」は,無筆(文字の読み書きができないこと)が多かった。(P.13)
◆「漢文は,しょせんは外国語である」
|
【私のコメント】
インパクト指数の高さからもわかるように,この本からは得るものが多かった。本書は720円だが,5倍得した感じがする。しかも非常にわかりやすい。夏目漱石は「草枕」を書くにあたって,自分の語彙力を鍛えるために「楚辞」を読み込んだというが,ことほどさように漢文は日本の文化の根底をなすものである。幕末から明治にかけて,「人民」「憲法」「権利」「義務」などという西洋文化に関する新漢字が次々と作られた。現代中国語の「社会科学」に関する語彙の60~70%はそのときに日本で作られた日本漢字を逆輸入したものであるという。今,我われはこうしたことを忘れ,「コンピュータ」「IT]など外国語をそのまま日本語に持ち込んでいる。一方,中国では「電脳」という語彙を充てている。
【インパクト指数】評伝のため計測不能
【本文から】
|
◆けっきょく三上文法はどう評価されたのか,と言えば,「一介の高校数学教師の奇説」として,国語学界はまともに相手にしなかったのである。「一介の」という表現が三上文法を語る際に,枕詞のように使われた。(P.176)
◆私は,もし橋本文法でなく,山田文法が学校文法に採用されていたら,日本語と日本人にとってどんなに良かったかと思う。文法の質として雲泥の差があるのは,山田文法は橋本文法よりもはるかに日本語の発想に根ざしているからである。学校文法にならなかった理由を忖度すれば,それはきわめてあきらかだ。山田が富山中学を中退しているからである。山田は独力で,実力で小中学校教員検定試験に合格し,その後,一歩一歩,文法学者への道を進んで大成した第一級の学者である。しかし,いかに自分の頭で文法を編み出す実力をしめしても「学歴は中学中退」と目にしたら,もうそれで文部科学省のお役人は思考停止してしまうのである。(P.194) |
【私のコメント】
かつて「学歴」がないためにその実力が評価されず苦い思いをした先達の例は古今東西あまたある。レオン・フーコー,マイケル・ファラデー,野口英世・・・。しかし日本の現状はあまりにもひどい。私もかつてある本を出そうとしたら,ある出版社から「名前だけでもいいですから,大学の先生の共著という形にしてもらえませんか」と言われて,出版を断念したことがある。「一介の高校教師」では売れないからだそうだ。三上章も「就職に有利だから」ということで,ついには東洋大学から博士号をもらう。なぜだろう。それは学界には学歴というスケールなしで,その人の業績が本物であるかどうかを識別する力がないからではないか。筆者は日本の国語学界は三上を無視し続けたことに怒りをあらわにする。ただその矛先が,日本の国語学界の重鎮大野晋であることはつらい。私は彼が好きだからだ。著者はモントリオール大学で日本語を教える先生。三上章への思い入れは熱い。
【インパクト指数】7.6
【本文から】
◆江戸時代のこと,参勤交代で江戸詰めとなっていた大名は,朝から江戸城に出仕してさまざまな業務をや会合をこなしていた。それは現代サラリーマンと基本的には同じことで,昼時分になるともちろん昼食をとる。登城した大名たちは,昼食として藩邸から持参させた弁当を城内で食べたのだが,その時は広い座敷にすわった大名たちが,一人一人それぞれ周囲に屏風を立てさせ,ものを食べているところを他の大名たちから見られないようにしていたという。大名の弁当だから,もちろんそれはかなり高級な中身であったろうが,いかに豪華な弁当でも,まちがっても他人といっしょに食べようという性格のものではなかった。(p.10)
◆(平安時代の)女房たちにとっての食事とは,「とても恥ずかしいことではあるが,といって避けては通れない」というものだった。それはあたかも現代人にとってのセックスと同じような感覚でとらえられていた,といってもそれほど的外れではないだろう。それゆえに女房たちは,そんな「あさましくて恥ずかしい」行為である食事に関することがらをそのまま口にせず,婉曲的なことばを作りだして表現した。食事に関して数多くの女房言葉が生まれたことには,そのような背景がある。(p.12)
【私のコメント】
この本の帯には「はばかりながら読む漢字の文化史!」とある。平安時代の女房言葉の「~もじ(文字)」は婉曲用法であるが,私はなぜ食事に使う「しゃくし」が「しゃもじ」といいかえられなければならなかったのかがこれまでよく理解できなかった。しかし,食事がセックスと同じように恥ずかしく隠すべき作業であるとと当時は考えられていたという本書の説明で合点がいった。
本書によるとそもそも「家族団欒」(家族がわきあいあいと,その日にあったことなどを話ながら食事を楽しむ)などという習慣は主に戦後になって広まったことであり,かつては食事などというものは「こっそりと,黙って,なるべく早く」済ませるべき行為であったのだ。本書はこの他にもこれまで我々が知らなかった多くの事柄を教えてくれる。
【インパクト指数】14.6
【本文から】
◆言語の発達過程にある幼児が耳にする言葉は,多くの言い間違いや不完全な文を含んでおり,限りある言語データしか与えられない。それにもかかわらず,どうしてほとんど無限に近い文を発話したり解釈したりできるようになるのだろうか。これが,ギリシャ時代の哲学者,プラントンの考えた問題(「プラトンの問題」)であり,幼児に与えられる言語の刺激が貧困であるという事実を指して「刺激の貧困」とも呼ばれている。この問題は,今なお古くて新しい問題である。(P.44)
◆クリストファという一人のサヴァン(症候群患者)は,二十カ国語を使いこなす「言語天才」であり,著名な言語学者による詳細な研究とともに有名になった。(略)29歳のときの精神年齢は9歳と見積もられた。(略)クリストファの能力がユニークなのは,一般の人が思うような「特殊な能力」を身につけているからではない。幼児のときには,誰でもクリストファと同じように,この「言語モジュール」を浸かって,どんな言語でも獲得しているのだから。クリストファは,幼児の言語モジュールの能力を大人になっても失わなかったことがユニークなのである。(p.89)
◆私は,あらゆるチョムスキー批判を謙虚に受けとめたうえで,実証的に言語の脳研究を進めていきたいと考えている。言語の脳科学に「○○主義」は必要ない。実証的に否定されれば,現在の仮説を取り下げ,新しい仮説を作るだけであり,これがサイエンスの基本であろう。
【私のコメント】
インパクト指数2桁で久々のヒット。読む価値あり。たった900円でその何十倍ももとのとれる本。これは(現在のところ)チョムスキーのいう生成文法の立場に立つ著者が,言語について脳科学の面から論じたものである。もっとも,上記の最後の引用にあるように,著者は「○○主義」でなく,その仮説が実証できるかどうかだと言っている。実証性がなければチョムスキーの立場からも降りる覚悟である。科学者はこうであらねばならない。
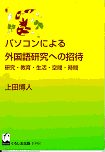 【インパクト指数】7.3
【インパクト指数】7.3
【本文から】
◆回りにいる外国語研究者には二つのタイプがある。仮に「経験派」と「理論派」と名づけることにしよう。経験派の人たちは,がんばってデータを集め,分類し,頻度を求め,言語現象の傾向をさぐる。言語構造のモデル化にはあまり興味を示さない。一方,理論派の人たちは,言語現象の頻度はあまり気にせず,その形式化・抽象化に熱意を燃やし,論点となるデータを自分の直観を頼りに作成する。(P.77)
◆私のような凡人には,やはりデータ中心にやっていくしか手がない。しかし,理論派の人たちの説明を理解したい。(P.79)
◆コンピュータが結論を出すことはけっしてない。データを分析し,結論に導くのはあくまでも人間である。(P.83)
◆私は授業では直訳を排除しない。むしろ,直訳をさせることで学生がスペイン語文の構造を正しく理解しているかがわかるのである。段階式に考えるとすれば,直訳でスペイン語の文法と語彙を扱うというのが第一段階,それを正常な論理,言語外知識,語用論的な常識,そして話者(発話者)への共感によってその意図や意味を理解するというのが第二段階,最後に適切な日本語表現(意訳)を目指すというのが第三段階である。(P.104)
【私のコメント】
著者はスペイン語を教える先生である。この本は170頁あまりのこぶりながら,その内容はコーパスをいかに利用するかということも含め,随所にたいへん興味深く示唆に富む言及がある。すべてが著者の経験に裏打ちされているものであるが故に,説得力がある。また,各章末に挙げられている参考文献からいもづる式に興味ある他の文献を入手することもできる。私は本書によって「文章を科学する」(前川守,1995,岩波書店)や「真贋の科学 計量文献学入門」(村上征勝,1994,朝倉書店)などの本と出会えた。コンピュータを語学研究に利用したいと考えておられる方には必読の書である。
 【インパクト指数】5.6
【インパクト指数】5.6
【本文から】
◆人間の子どもが,特に何かを教えるという努力なしに,みるみることばを習得していくのは驚異に値することがよくわかるのです。アメリカの資料によると,人間は6歳までに,平均して一日9語を習得するといわれています。この年代で,ほぼ二万語くらいを知っていることになるわけです。大人のもつ語彙数は,推定法がやっかいで簡単には断定できませんが,少なくとも何十万のオーダーに達します。
◆嘘とは,一口にいって,存在しない状況,事実と反する状況を言語的に構成することといえましょう。いってみれば,それはメタ言語への一歩なのです。このような働きが想像力と伴って,やがては文芸作品といった道が開けていくことを考えてください(嘘が悪になるかどうかは,存在しない状況の構成にあるのではなく,それを利用するという意図や目標がかかっていることを忘れないようにしたものです。また,幼稚な自己防衛としての否認は,まだ本当の嘘といえないことにも注意すべきでしょう)。
【私のコメント】
私は息子が3~4歳のとき,嘘を言ったということで家の外に放り出したことがある。こんな幼児の頃から嘘をつく習慣をつけさせてはいけないと思ったからだった。なきじゃくる息子を暗い庭に出してしばらく締め出してしまった。今,上のような文章に出くわして冷や汗が出る思いだ。幼児の嘘はある意味では,人見知りを覚えた赤ん坊と同じく望ましい発達を示しているわけだ。願わくは息子のtraumaになっていないことを祈る。
 【インパクト指数】10.7
【インパクト指数】10.7
【本文から】
◆親は,子供に話しかけるとき,文法的に正しい発話をする。ニューポートやラボーフの研究が示すところでは,文法的におかしいことばはほとんど使われない。(略)チョムスキーは "degenerate(変質している)"という語を使い,子供が触れる文はほとんど非文法的だと主張していたが,親ことばの文が大部分,文法的であるという研究結果は,チョムスキーに対する反論になる。
◆万国共通の手話というものは存在しない。むしろ,1つの手話言語内でも方言上の違いが著しい。たとえば,パリとリヨンの手話使用者は意思の疎通が難しい。また,驚くことに,アメリカ式手話とイギリス式手話ではコミュニケーションが不可能である。
◆生成意味論は言語学の舞台から消えた。しかし,1980年代に2つの新しい意味中心の文法が灰の中から蘇生した。それは,認知文法(ラネカー,ジョージ・レイコフ)と機能文法(ディク,コナリー)であり,これはともに生成意味論から創造的に発展したものである。
【私のコメント】
著者は駿河大学教授であり,日本についてもくわしい。難しい言語の問題を実にわかりやすく説明してくれる。チョムスキーは「あまりにも不完全な言語環境の中でかくも短期間に幼児が言語を獲得するのはなぜか」を考え,普遍文法にいきついた。しかし,本書では幼児のまわりの言語環境は本当に「不完全」なのか,幼児が言語を獲得する時間は本当に「短期間」なのかを一つ一つ検証している。心理言語学のみならず,言語に関心のある方にはお奨めの一冊である。
 【インパクト指数】3.3
【インパクト指数】3.3
【本文から】
◆ある日,例のクスクス笑いにがまんならなくなった私は,立ちあがって,みんなにむかって,何がそんなにおかしいのか,という怒りをぶつけました。しかし,かえってきたのは教室全体をゆるがすような大笑い。それは,そのとき私の口をついて出たことばが,「ミナサン,ミナサンハ,イッタイ,ナニガオカシイノデショウカ」という,完全な文章語だったからです。(P.23)
◆「宿直室」というのは,この「御真影」と「教育勅語」の謄本を奉安しておく場所であり,「宿直」教師の任務というのは,「御真影」と「教育勅語」を命をかけて守るものだったのです。(略)こういう「宿直」ということばの歴史性とまったくかかわらずして,『坊ちゃん』という小説が読めるでしょうか。(P.114)
【私のコメント】
東大教授の小森陽一氏が自らの言語形成過程を書いたのがこの本である。彼は父の仕事の関係で小学校時代をプラハのロシア語学校で学びます。そして中学校のときに帰国し,ニホンゴを第二言語として学ぶ。のちに北大の大学院を経て東大教授となるのだが,帰国してからのニホンゴとの悪戦苦闘がぶりが興味深く描かれている。自分のハンディを逆に学問の対象とした点はすごい。
 【インパクト指数】6.8
【インパクト指数】6.8
【本文から】
◆(ゴーブは)辞書の本質や歴史に関する知識がほとんどなく,辞書編纂に関わる論争をイデオロギー戦争に持って行こうとするような中傷者によってもっぱら自分の辞書の価値が判断されようとは夢にも思わなかった。(P.12)
◆はたして集められた引用はどの程度信頼でいるものなのか。また用法を代表するような引用であるか。百万枚,いや1千万枚の引用カードがあっても,必ずしも言語の実体を示しているわけではないということをゴーブは十分認識していた。引用カードは単に実際の使用例を示しているに過ぎないのである。(P.127)
◆ゴーブは創作された会話や大部分の詩,それに広告では言語が「純粋に機能している」とは思わなかった。こういった媒体では,ある特定の目的を達成するためによく言葉が「不自然に」用いられているとみなした。(同頁)
◆『ニューヨーク・タイムズ』は第三版は ain't の用法を「擁護した」と述べている。しかし第三版が意図したのは単に「記述する」ことでありこれは大きな違いであった。
【私のコメント】
あのでっかい「ウェブスター第三版」がこれほど厳しい試練にさらされてきたとは知らなかった。そして辞書編纂者のフィリップ・ゴーブが気の毒になった。彼がとった方針は「記述的」であることに徹するということ,つまり語の使用に関する価値判断は使用者にまかせ,辞書はあくまで言語の使用実態を示すという立場であり,これは現在ではあたりまえのことである。
しかし,ain't の例をとってみても編纂者と批判者には大きな誤解があり,騒ぎが大きくなった。「記述的」か「規範的」かという立場の違いの上に,大学の英語学科内部の言語学系教員と文学系教員の対立がからみ論争は泥沼化していく。
本書は言語に関心のある方には是非一読いただきたい本である。
 【インパクト指数】6.9
【インパクト指数】6.9
【本文から】
◆パースの格言は「事実はその事実以上におかしな仮説をもってしては,説明できない。さまざまな仮説がある場合には,一番おかしくないものを採るべきである」ということであった。(P.32)
◆ホームズ物語りにおいて,警察がしばしばとんでもない方向に進んでしまうのは,初期捜査の段階で,二,三の目立つ事実をうまく説明できそうな仮説を選びとってしまうと,それから先は,「些細な点」になど眼をつむってしまい,都合がよくないデータには蓋をしてしまうからである。
【私のコメント】
本書は「探偵としてのC・S・パース」と「記号論者としてのシャーロック・ホームズ」を対比しつつその類似点を探っていく。そして全体として記号論のわかりやすい入門書ともなっている。これから論文を書こうと思われている方々には「仮説をどう立てるべきか」という点でたいへんためになる記述も多い。巻末に付録として載っているシービオクと山口昌男氏との対談(1980)もおもしろい。
 【インパクト指数】3.4
【インパクト指数】3.4
【本文から】
◆「ことばを他の言語に貸してやれる言語というのは,何かの分野で力とか影響力とかをもつ人たちによって話されている言語だということなの」 (P.85)
◆「いちばん重要なのは何を言うかであって,それをどのように言うかではないの。10分もたてばあなただって,私が言ったことの意味は覚えていたとしても(略)私がどんなことばを使ったかなんてとっくに忘れているはずよ」(P.103)
◆「話すとき,私たちは一度にとてもたくさんのことをしているのよ。ふつうだったら一度にできないようないろいろなことをね。文の初めを言いながら,残りの部分を何というか計画を立てているの。はっきりしないような考えでもともかく考えたことを,文はこうあるべきだという規則に従って,文にするの。こういうことがぜんぶものすごい速さで行なわれているのよ。1秒につき約200音節!」(P.167)
【私のコメント】
本書を手にとるとすぐわかることだが,これは「ソフィーの世界」の言語学版である(^.^) 筆者自身も「ソフィーの世界」について2度も言及している。ただ形式を借りたと言うことであって中身は哲学ではなくこちらは言語学。
毎週金曜日にやってくる不思議な女子大生(言語学専攻)アンナによって「ぼく(オスカル)」は次第に言語学への関心を抱いていくという設定。わかりやすい言語学入門書となっている。
 【インパクト指数】3.9
【インパクト指数】3.9
【本文から】
◆まず私が,生成文法の一番の功績だと思うのは,文の「構造」のきちんとした一般的な表し方を考え出してくれたということです。(P.186)
◆最小主義ではXバー理論が「ウソ」だったと言われているわけではありませんが,もう使われなくなってしまっているんですから,そうなると,原理とパラメータの時代に,言語学の俊英たちがあれやこれやと深く頭を悩ました結果の議論は,一体何だったんだろう,ということになってしまわないでしょうか。(略)生成文法が新しい言語理論として認められたころの大切な部分は,今ではほとんどなくなってしまったとも言えるのではないでしょうか。(P.200~203)
【私のコメント】
私が生成文法を本格的に学ぶことになかなか踏み切れないでいるのは上記の後者の意見に関係があります。「あしたに学んだ理論がゆうべにはもはや破棄されてしまうのではないか」という不安があるからです。
私はかつて大変な時間とお金(本代が高かった!)をかけて当時データベース・ソフトの雄であった「dBASEⅢ」のマクロを用いてのプログラム作成法を独学し,雑誌「教育とマイコン」(学研)に原稿が載ったこともありました。ところが今では本屋のパソコン雑誌コーナーで,dBASEの d の字も見当たらない有様です。せっかく時間や労力をかけるにはそれを末永く役立てたいと思うのが人情ではないでしょうか。人生,限りがあるんですから。
 【インパクト指数】11.6
【インパクト指数】11.6
【本文から】
◆当時私の家ではライスカレーは作って食べていた。しかしこの名も知らない液体を舌に乗せたことはなかった。今日では誰でも知っているクリームシチューである。「山の手」ではこういうものを食べているのだ。(P.45)
◆そこには欠けているものがある。季節の循環を味わって生きるだけでは誤っているような気がする。人間はもっと理路整然としたものを求める心構えが要るのではないか。それがないと世界では生きて行けないのではないか。(P.71)
◆親父は急に私の前から逃げ出した。裸足で彼は逃げた。犬は逃げる相手を追うという。逃げることに怒り,反射的に私は追いかけ,近所の神社の庭で転んだ親父に腕力をふるった。手許にピストルがあったら,私は彼を撃っただろう。(P.223)
◆男が嫉妬すると社会的な仕組みを使って相手を傷つけ,殺そうとする。大事なのは事実・真実に対して誠意をもつことなのに。
【私のコメント】
狭山事件に関する本を読んでいたとき,石川一雄の日本語力から見て彼が犯人ではあり得ないと鑑定した国語学者がいた。それが大野晋氏だった。そこには真理のみを追求する学者の誠実さが感じられた。もし,石川一雄が犯人という結果が出ていても,彼はそれを事実として発表していただろう。
私は常日頃から人文学には科学的な手法が不可欠であることを痛感してきた。大野氏の研究にはそれがある。タミル語と古代日本語との関係を発表したとき,大野批判が巻き起こった。とりわけ文春の攻撃には学問上の論争というよりは常軌を逸したものがあった。この本にはそのいきさつも書かれている。彼がいうように「大事なのは事実に対して誠意をもつこと」である。
※2008年7月15日(火)の朝日新聞に大野晋氏が14日午前4時に心不全で亡くなったという記事が載っていた。「狭山事件」で脅迫状を鑑定し被告の無実を訴えるなど誠実な人であった。住井すゑをはじめ,尊敬する日本人が次々と鬼籍に入っていくのがさびしい。
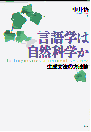 【インパクト指数】6.2
【インパクト指数】6.2
【本文から】
◆チョムスキーは,言語学(本書で言語学といえば,特にことわらないかぎり,生成文法理論に基づいた言語学のことを指す)は自然科学と同じ方法で研究すればよいのであり,自然科学と同じ方法で研究していれば文法の心的実在など問題にしなくてもよいのだと言っている。
◆ニュートン力学が全宇宙の法則であるように,GB理論(原理とパラメータの理論)は全言語の文法理論となり,自然科学でニュートン力学が占めている位置を言語学でも占めることになるだろう。
【私のコメント】
著者は基本的には生成文法の立場をとりながらも,言語を生物学と同じ手法でアプローチしようとするチョムスキーのやり方に疑問を感じてもいる。天文学者は太陽の中がどうなっているかを直接調べることはできない。太陽から発せられる光をもとに理論を組み立てるのである。人間の脳の中も直接見ることはできないが,ことばとして外に現れるものを材料として理論を組み立ててもいいはずである。大切なのは理論が現実を矛盾無く説明できるかであって,理論が現実に存在するのかということではない。まあ,チョムスキーはこういうのだが,著者と同様私も胸にストンと落ちる説明ではないと思う。
 【本文から】
【本文から】
◆「まことに残念ですが,それは違います。誤解なさっているようです。私はブロードムア刑事犯精神病院の院長をつとめるものです。マイナー博士は間違いなくここにおりますが,彼は入院患者であります。20年以上前からここに入院している,最も古い患者なのです。」
◆トレンチがいま提案している新しい冒険は,単に意味を示すだけでなく,意味の歴史を示すこと,つまりそれぞれの単語の一代記を記すことだった。そしてそのためにはあらゆる文献を読み,その単語のなんらかの歴史を示すあらゆる用例を引くことを意味した。
◆この計画に着手するには,一人の力では足りない,とトレンチは言った。英語のあらゆる文献を丹念に読み,ロンドンとニューヨークの新聞にくまなく目を通し,雑誌や定期刊行物のうち文学的なものを綿密に調べるためには,「多くの人びとの協力」が必要だ。そのためにはチームをつくらなければならない。何百人もの人びとで構成される巨大なチームをつくり,アマチュアの人たちに「篤志協力者として」無給で仕事をしてもらわなければならない,とトレンチは述べた。
【私のコメント】
OEDに多大な貢献をなした謎の篤志家マイヤー博士。実は彼はパラノイアによる殺人を犯し,精神病院にいたのだった。博士は妄想に悩まされながら,辞書編纂に携わっていることを心のよりどころとしていたのである。この本はOEDの誕生の秘話にまつわるゾクゾクするエピソードを,このマイヤー博士の生い立ちからその死までを中心に語られていく。完成までに70年もの歳月を要したOEDがどういった人々の苦労によってどのようにできたのか。日頃辞典の恩恵に浴している英語教師には是非読んでほしい一冊である。
 【本文から】
【本文から】
◆学問とはただ風が吹いてきてほこりが立ちのぼったとか,木の葉の吹きだまりができたというものではなく,また,やみくもに努力したらできましたとかいうものでもない。努力ももちろん入り用なのですけれども,努力の形づけの基礎になる傷やら基本的な願いやらがある。その傷が なんであったか,願いが何であったかを理解しないと学問が人間と結びついてこないでしょう。
◆(編者が)誰も死んでいない辞書は大体いい加減に作った字引きです。
【私のコメント】
本居は当時女々しいとされていた色恋沙汰(源氏物語)をなぜ敢えて自らの研究の中心に置いたのか。最初の「語学と文学の間」の章ではさながら推理小説のように意外な展開を見せ,わくわくして読み進んでいくだろう。言葉というものを通じて筆者は学問とは何かを問う。言語に関心がある人は必読の書である。
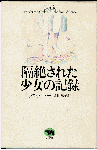
【本文から】
◆(野生児に関する)これらのケースの調査研究は,だいたいどれも大騒ぎのしすぎと方法論の欠如からだいなしになってしまい,子供たちの不幸を新しい知識の源へと変えることはできなかった。
◆「言葉を話す前の赤ちゃんを何人か離れ小島に置いたような場合,彼らの言語力がたちまち言語をつくり出す見込みはじゅうぶんにあるのです。おそらく最初の世代ではないでしょう。しかし言語誕生のあかつきには,わたしたちの知っているのと似たものができているはずです。もちろん実験はできません。子どもをそんな実験に使うわけにはいかないからです」(チョムスキー)
【私のコメント】
奇しくも現代版野生児として発見されたジーニ。本書は一人の人間としてよりも貴重な研究対象して翻弄される少女を描いたドキュメンタリーである。言語はどのようにして獲得されるのか,言語の研究はどうあるべきかなど様々な問題を提起する。とりわけ,人類初の言語は何であったかを知ろうとして二名の赤子を使って実験しようとしたエジプト王の話は衝撃的である。

【本文から】
◆ある言語を知っているというのは,心的言語を単語の列に,単語の列を心的言語に翻訳するすべを知っている,という意味になる。 言語を持たない人間も心的言語は持っている。赤ん坊や人間以外のさまざまな動物も,単純な形ではあれ心的言語を持っていると考えられる。
【私のコメント】
たとえチョムスキアンでなくても,この本を読むとつい納得してしまう。ここには例のXバー理論も変形も出てこない。
ピンカーは実に分かりやすい例を出して,チョムスキー理論を擁護する。自律言語学に賛同する人も反対する人もこの本は必読である。
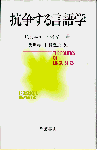 【本文から】
【本文から】
◆彼(チョムスキー)は世界でも最も支持者の多い学者であると同時に,最も敵の多い学者でもある。正確な数値は憶測の域を出ないが,ひとつだけはっきり していることがある。つまり,彼の思想は言語学を完全に変容させてしまったのである。言語研究者であればいかなる立場であれ,彼の考えを無視していやしく も言語研究をおこなうことなど許されないのである。
◆社会言語学が倫理に訴えたことが,1970年代に生成文法が衰退した原因のかなりの部分をしめることは疑いない。ここ5,6年のあいだに生成文法への関心 が徐々に回復してきたことと,アメリカの大学において権利と不平等への関心が薄らいでいることとのあいだに, たとえ弱い意味合いであれ,多少は相関関係があるという説は,たしかに考えられないことではない。
【私のコメント】
本書は過去2世紀にわたって繰り広げられてきたそれぞれの言語理論の抗争と盛衰の歴史である。とりわけチョムスキーの出現とその発展の過程は国防省からの多額
の援助を受けてきた事実などもからめておもしろい話となっている。本書によれば現在のアメリカの言語学者の1/3は生成文法家,1/3はアンチ生成文法家,そして残り1/3は
社会言語学や音声学などその種の問題には関係のない言語の側面に取り組んでいる学者であるという。特にアメリカの言語研究の流れを知るには本書の一読を薦めたい。
 【本文から】
【本文から】
◆明治四年の三月,文彦は大学南校をやめて箕作秋坪・奎吾の英学私塾三叉学舎に入った。ここでの教育法の軸になっているのが,例の洋書調所流の輪講だった。生徒が輪になって坐り,ひとりずつ順にテキストの一節を講釈する。他の生徒がその解釈に異論を出す。互いに自分の解釈を主張して闘い,最後に先生が誰の解釈が勝ちと判定して白星を付ける。敗者は黒星である。それを順に繰り返して一冊の原書を読み了える。白星に喜び,黒星にくやしがる。白星を取るために,字引がボロボロになるほど下調べをして教室に出る。
◆くわい-どく(名)[解読]数人集リテ,同ジ書ヲ読ミ合ヒ,意味ヲ解キ,疑ヲ論ズルコト。
【私のコメント】
かつて大野晋氏は,「『苑』とか『林』などという語のつく辞典は『言葉の苑や林の中を逍遥する』というような意味でたいていいいかんげんに作った辞典だ。『海』という語のつく辞典は真剣である。泳ぎつづけないと言葉の海の中で溺れてしまうからだ」という主旨のことを述べられていた。
この本は明治時代に日本初の本格的国語辞典「言海」を作り,66歳で改訂版「大言海」に着手,そして昭和3年82歳のとき,「さ」行のところまでたどりつきながら終に命尽きた男,大槻文彦の伝記である。幕末から明治への激動期に翻弄されながらも辞典への情熱を注ぎつづけた男の話である。
 【本文から】
【本文から】
◆植え込みの馬酔木の花を見ながら散歩していると,午前中読んだ本の中から whether/if のことがぼんやりと思い出されてきた。どこかひっかかるところがある。 whether と if が自由に交換できるのが原則であるとするならば,随分と例外の多い規則だ。あれだけ交換できない場合が多いのだから,それらの間に何か規則性があるに違いない。
【私のコメント】
本書はこれから学部を選ぼうとしている受験生や,文学をやるか言語学をやるか決めかねている英文・国文科の学生を対象として書かれている。筆者が経済学から言語学へと専攻を変更していったか,また言語学の中でもとりわけ理論言語学に関心を持つに至ったかがわかりやすく書かれ,語学教師にも参考になる。
 【本文から】
【本文から】
◆学者生活と司祭生活とが両立するかどうかということではなくて,むしろ学問のレベルが高くなればなるほど,神に向かっている度合いもそれだけ高くなる。真理とは神の別名である。こうしたテイヤールの考え方が,どんなに新しい方向づけを私にもたらしてくれたか,またそれが精神的にも宗教的にも,どんなに私を解放してくれたか,どれだけ繰り返して言っても言い過ぎることはない。
◆人間にとって欠くことのできない幸福の島は,人間の心の奥にある。その幸福の島を魂のなかに築いて,騒音や嫌悪のざわめきが入ってこないように,魂の扉を見張らねばならない。
【私のコメント】
私がグロータース神父の存在を知ったのは,彼の著書「誤訳」(三省堂)を読んでからである。「誤訳」ではここまで書いていいのかと思うほどするどい批判が当時新鮮に感じた。本書は前著の「わたしは日本人になりたい」の続編の形をとっているが,内容はグロータース氏の自伝的要素が強い。オランダ語とフランス語のバイリンガルとして育った彼が,中国語,日本語とつぎつぎとマスターしていく。日本の社会や文化に対して常にあたたかいまなざしを向けてきた。本書は「その他」に分類すべきものだろうが,言語学者としての彼に敬意を表して,このコーナーで紹介した。
Copyright (C) 1998 Hiroshi Suga All Rights Reserved.