【インパクト指数】 私が面白いと感じた頁÷(総頁数÷100)つまり,その本を100頁に換算した場合,私が面白いと感じた頁がどのくらいあるかを示しています。この数字が大きいほどインパクトがあります。
マット・リドレー著/太田直子他訳/本文421頁/2016年9月25日初版/早川書房/ISBN978-4-15-209637-1
(本文から)
|
◆進化はいたるところで起こっている 進化は私たちの周りのいたるところで起こっている、というのが本書の主張だ。自然界のみならず人間の世界がどのように変化するかを読み解くうえで、それが最善の見方となる。人間社会の制度や組織、所産、習慣における変化は、漸進的で否応がなく、避け難い。ある段階からから別の段階へと、一つのナラティブに沿って進む。飛躍はなく、じわじわと進展する。外から駆り立てられるのではなく、独自の自然発生的な勢いを持っている。ゴールも目的も頭にはない。おもに試行錯誤で起こる――いわば、自然淘汰の一バージョンだ。(P.11) ◆ルクレティウス的逸脱(スワープ) ルクレティウス(デモクリトスとエピクロスの思想を継承していた)は、予測可能な運動しかしない原子からなる世界のなかでは、どう見ても人間には備わっていると思われる自由意思という能力がなぜありうるのか説明できなかった。これを説明するために、彼はご都合主義的にこう示唆した。原子たちはときおり予想外に逸脱(スワープ)した振る舞いをするに違いない、なぜなら、そのようなことができるように神が原子を作られたから、と。ルクレティウス本人がこのように弱気になってしまったことは、「ルクレティウス的逸脱(スワープ)」として古くから知られている。(P.28) ◆管理しないほうがうまくいく 自由貿易のほうが指令統制政府よりも、経済的あるいは人道的に優れた記録を残していることに、もはや疑いの余地はほとんどない。(略)商業の核となる特徴であり、社会主義の計画と一線を画すところは、分権的であることだ。何枚の毛織物の上着、何台のノートパソコン、何杯のコーヒーに需要があるかを経済が知るのに、中央からの指揮は必要ない。それどころか、誰かがやろうとすると、悲惨な混乱が生まれる。つまり北朝鮮だ。(P.139) ◆ワイルド・ウェストは無法地帯ではなかった 開拓時代のアメリカ西部、いわゆるワイルド・ウェストにはまともな統治機関がなかったが、そこはけっして無法地帯ではなく、暴力の横行もなかったというのが真相である。(略)人々は独自の取り決めをして、それを使節執行官が執行し、違反者は幌馬車帯から追放されるなど、単純な方法で罰せられた。(略)政府による独占的支配がないなかで、複数の私設の法執行者が出現し、彼らのk放送が改良とイノベーションを推進し、それが自然淘汰によって繁栄したのである。(P.310)
|
【私のコメント】
これはむちゃくちゃ面白かった。ほぼすべてのページに「得るところ」がある。インパクト指数28.3は、他にないのではないか。同著者の『赤の女王』も面白かったが、これはそれ以上におもしろかった。文化、社会、その他人間が活動するところに「進化」ありというのが本書の主張だ。手放しで推薦する。
ユヴァル・ノア・ハラリ著/柴田裕之訳/256(上)+265(下)頁/2016年9月30日初版,2017年1月30日第11刷/河出書房新社書房/ISBN978-4-309-22671-2
(本文から)
|
◆7万年前に起きた「認知革命」がホモ・サピエンスの運命を変えた ほとんどの研究者は、(芸術・言語などの)これらの前例のない偉業は、サピエンスの認知的能力に起こった革命の産物だと考えている。(略)最も広く信じられている説によれば、たまたま遺伝子の突然変異が起こり、サピエンスの脳内の配線が変わり、それまでにない形で考えたり、まったく新しい種類の言語を使って、意思疎通をしたりすることが可能になったのだという。(P.35) ◆認知革命はサピエンスに「虚構を語る能力」を与えた 見たことも、触れたこともない、匂いを嗅いだこともない、ありとあらゆる種類の存在について話す能力があるのは、私たちの知るかぎりサピエンスだけだ。伝説や神話、神々、宗教は、認知革命に伴って初めて現れた。それまでも、「気をつけろ1ライオンだ!」と言える動物や人類種は多くた。だがホモ・サピエンスは認知革命のおかげで、「ライオンはわが部族の守護霊だ」という能力を獲得した。虚構、すなわち架空の事物について語るこの能力こそが、サピエンスの言語の特徴として異彩を放っている。(P.39) ◆虚構を語る能力が帝国の出現を可能にした ホモ・サピエンスはどうやって(略)何万もの住民から成る都市や、何億もの民を支配する帝国を最終的に築いたのだろう? その秘密はおそらく、虚構の登場にある。膨大な数の見知らぬ人どうしも、共通の神話を信じることによって、首尾良く協力できるのだ。(P43) ◆秩序は、大半の人々がそれを信じているときのみ保たれる キリスト教は、司教や聖職者の大半がキリストの存在を信じられなかったら、2000年も続かなかっただろう。アメリカの民主主義は、大統領と連ぴう議会議員の大半が人権の存在を信じられなかったら、250年も持続しなかっただろう。近代の経済体制は、投資家と銀行家の大半が資本主義の存在を信じられなかったら、一日も持たなかっただろう。(P.145)
|
【私のコメント】
宗教、社会、文化――これらはすべてホモ・サピエンスが頭の中に作り出した「虚構」だ。そして人々が「信じている」ことで成り立っている。そしてこうした「虚構」を語る能力は、ホモ・サピエンスが言語を獲得した、7万年前の「認知革命」に由来する。
(P)
これが本書の「肝」である。想像力こそがホモ・サピエンスをホモ・サピエンスたらしめており、我々が生きているこの社会は、すべて人類の頭が作り出した「虚構」だというのだ。頭をガーンと一発たたかれたかのような衝撃を受ける本である。これまでにない歴史の切り口と、その説得力には舌を巻いた。あまり、騒がれていたので敬遠していたのだが、得るところの多い本である。著者は40歳(2016年時点)のヘブライ大学の歴史学者。
ヴィクトール・E・フランクル/池田香代子訳/157頁/2002年11月5日第1刷,2016年3月10日第29刷/みすず書房/ISBN4-622-03970-2 C0011
(本文から)
|
◆暴力的で意地の悪い囚人がカポ(囚人の頭)に選ばれた カポーはよく殴った。親衛隊員でもあれほど殴りはしなかった。一般の被収容者のなかから,そのような適性のある者がカポーになり,はかばかしく「努力」しなければすぐさま解任された。(p.2) ◆いい人は帰ってこなかった 収容所暮らしが何年も続き(略)1ダースもの収容所で過ごしてきた被収容者はおおむね,生存競争のなかで良心を失い,暴力も仲間から物を盗むことも平気になってしまっていた。そういう者だけが命をつなぐことができたのだ。何千もの幸運な偶然によって,あるいはお望みなら神の奇跡によってと言ってもいいが,とにかく生きて帰ったわたしたちは,みなそのことを知っている。わたしたちはためらわずに言うことができる。いい人は帰ってこなかった,と。(p.5) ◆親衛隊員の人差し指のかすかな動きで生死が決められた 男は(略)右肘を左手でささえて右手をかかげ,人差し指をごく控え目にほんのわずか――こちらから見て,あるときは左に,またあるときは右に,しかしたいていは左に――動かした…。(略)夜になって,わたしたちは人差し指の動きの意味を知った。それは最初の淘汰だった!生か死の決定だったのだ。(略)およそ90パーセントにとっては死の宣告だった。(略)左にやられた者は,プラットホームかのスロープから直接,焼却炉のある建物まで歩いていった。(p.17) ◆労働で死ぬほど疲れていても夕陽に感動する心が残っていた ある夕べ,わたしたちが労働で死ぬほど疲れて(略)へたりこんでいたときに,突然,仲間がとびこんで(略)とにかく点呼場に出てこいと急き立てた。太陽が沈んでいくさまを見逃させまいという,ただそれだけのために。そしてわたしたちは,(略)この世のものとも思われない色合いでたえずさまざまに幻想的な形を変えていく雲をながめた。(略)わたしたちは数分間,言葉もなく心を奪われていたが,だれかが言った。「世界はどうしてこんなに美しいんだ!」(P.65)
|
【私のコメント】
ヴィクトール・E・フランクルの「夜と霧」はあまりにも有名だったが故に,長い間手に取ることなくそのままにしていた。買ってから何十年もたってやっと手に取って読んでみた。一気に読んでしまった。フランクルはフロイトに精神医学を学んだウィーン大学医学部神経科教授であったが,ユダヤ人であったがゆえに両親,妻とともにアウシュビッツに送られる。両親と妻は収容所で殺害される。奇跡的に生き延びたフランクルは精神科医の目で収容所の生活を描写する。人生で一度は読むべき本である。
加地伸行著/300頁/角川ソフィア文庫402/平成28年4月25日初版(1991年集英社文庫として刊行)/ISBN 978-4-04-400045-5 C0123
(本文から)
|
◆孔子は差別されていた儒の出身であった 死を扱う儒に対する畏怖と敬遠とがあったであろう。しかし,のちにそれは不幸にして逆転して,心の底では蔑視の感情となっていたのである。差別である。そうした儒の中から,優れた理論的指導者として登場したのが孔子であり,孔子は徹底的に小人(原儒)を否定し,君子(儒教徒,儒家)であろうとしたのである。『論語』中,対比的に君子をたたえ,小人を非難していることばが多いのはそのためである。(P.80) ◆孔子は異様な面体をした2.1メートルの巨漢だった (厄病神を追い払う役目の人がつける面(マスク)は)悪疫を追い払う呪力を持つ姿であるから,悪疫,悪霊のほうが恐れるほどこわい面体でなくてはならなかった。孔子の面相がそれに似ていたという。(P.54) (孔子は)身長,九尺六寸(約2.1メートル)であったと伝えられる。(略)伝説的ではあるが,孔子のゲタの長さは一尺四寸(約31.5センチメートル)であったという。(P.55) ◆仁の顔淵,知の子貢,勇の子路 (孔子は)はっきりと子貢に向かって言っている。「君子の道なるもの(として)三(箇条)あり。(しかし)我は(とても)能するなきなり。(けれどもお前たちはそれが出来ている。すなわち)仁者は憂えず,知者は惑わず,勇者は懼(おそれ)ず」と。孔子は,仁の顔淵,知の子貢そして勇の子路これら三人の弟子の才能や人がらに敬意を抱いていたのである。彼らは孔子のブレーンであった。(P.172)
|
【私のコメント】
「論語」はすばらしい。しかし,それだけでは,孔子の実際の生活はどのようなものだったのか,弟子を引き連れて何年も諸国を放浪するが,その間の資金はどうしていたのかは分からない。私はそこを知りたかった。そして,その問いに満足のゆく答えを与えてくれる本書に出会った。商才に長けた子貢が財政面を受け持ち,武闘派の子路がボディーガードし,そして徳のある顔淵が孔子の悩みを黙って聞いていたのである。孔子は自説を実践すべく,政治的地位を追い求めて諸国を巡った。だが,常に挫折,挫折の連続だった。一度は首相格まで昇りつめたこともあったが,すぐに排除されてしまった。学而第一の「人知らずしていきどおらず、亦君子ならずや」は,孔子の自身への戒めの言葉でもある。
孔子が死んだとき,魯国の国君哀公が形式的ながら孔子を称える弔辞を述べた。それを聞いた子貢は怒った。では,どうして,先生が生きていたときに宰相の地位に付けなかったのか。子貢は,葬儀の後,一門に向かって,「ああいう君主は,政治力がなく,魯で安らかに最期を全うできないだろう」と言い放った。(P.297)
加藤徹著/248頁/NHK出版新書347/2011年2月10日第1刷/ISBN978-4-14-088341-9 C0298
(本文から)
|
◆『論語』は二流の書物だった 『書経』など主要な経典は,孔子が校訂し再編集したテキストである(と伝統的儒教では信じられてきた)。だが『論語』は,孔子の死後に編纂された書物なので,孔子自身の筆は加わっていない。そのため,昔の儒教では『論語』は正規の経典と言うより,儒教を理解するための副読本のように位置づけられたのである。(p.23) ◆『論語』の後半の十篇は,後世の作? 『論語』にはもう一つ,不自然な点がある。前半と後半で,ガラリと叙述のトーンが変わることである。(略)前半は簡潔で生き生きとした言葉が多い。ところが後半は,ダラダラと教条的なお説教が増える。(p.53) ◆支配者が採るべき道は2つ 儒教の大義名分論からすれば,(江戸時代の)将軍がとるべき道は二つ。即座に政権を天皇に奉還するか,さもなくば,天命を受けてみずからが天子となるしかない。(p.291) ◆『論語』は妙薬にも毒にもなる 徳川家康や松平定信のように,『論語』を支配体制の強化道具として使うこともできる。吉田松陰や西郷隆盛のように,『論語』を体制転覆のエネルギーとする志士もいる。(略)昔の日本人は,『論語』の危険さを自覚していた。(p.241)
|
【私のコメント】
加藤徹の本はいずれもおもしろい。特に本書は,すべてのページが示唆に富む。読書でおもしろいと思った箇所は,カード化する習慣にしているが,本書はすべてにマークが入り,結局は,本書一冊を丸ごとカードにするような羽目になった。インパクト指数が42.7なんて,信じられず,なんども計算し直した。780円(2015年現在)の本書は,その10倍,20倍の価値がある。私は特に,日本漢字音が,現在の中国語よりも,古代中国の音を残しており,擬音感に留意して『論語』を読むと,より深く含意が味わえる(p.144)という著者の指摘になるほどと思った。
大野裕之著/265頁/岩波書店/2015年6月25日発行/ISBN978-4-00-023886-1 C0074
(本文から)
|
◆チョビ髭は偶然の一致 チャップリン作品がドイツとオーストリアで初めて上映されたのは,ヒトラーがチョビ髭を生やし始めた一年後の1915年のことなので,意識的にも無意識的にも,ヒトラーがチャップリンの髭をまねたという事実はない。(p.16) ◆同じチョビ髭なので チャップリンは,ある提案を受ける。『自伝』によると1937年のある日,ユナイテッド・アーティスツの映画プロデューサー,アレグザンダー・コルダが,ヒトラーと放浪者チャーリーとが同じチョビ髭を生やしているための,「人ちがいが起こるというテーマで,ひとつヒトラーの話を映画にしてみないか」とチャップリンに提案した。チャップリンは,もちろん独裁者と庶民との二役をする。(p.77) ◆アメリカはチャップリンが『独裁者』を製作を断念してほしかった 建前上,『独裁者』は民主主義にとって素晴らしいもので,チャップリンの勇気はたたえるが,本音で言えば製作を断念してほしいという声が,アメリカ国内で支配的だったのだ。その理由は単純で,当時のアメリカは,世論調査で反ユダヤ主義を標榜する人が90%を数え,財界はナチス政権に多額の投資をしており,親ファシズムとも呼べる国だったからである。(p.125)
|
【私のコメント】
本書はチャップリンとヒトラーをめぐるメディア戦争というようなテーマで書かれている。チャップリンは『独裁者』を製作したのは,まさにヒトラーが他国への侵略を開始した時期と重なる。微妙な国際情勢の中で,イギリスはもとよりアメリカさえもその製作には反対だった。しかし,チャップリンは突き進む。彼が『独裁者』の最後の名演説にかける執念はすさまじいものだったことが本書よりわかる。そしてマッカーシー旋風吹き荒れる中で,チャップリンは「共産主義者」とのレッテルを貼られ,アメリカ入国を拒否されてしまうのである。しかし,今,紛争が起きるたびに,チャップリンが『独裁者』の最後に渾身を込めて行った演説が人びとを励まし続けている。
トム・リース Tom Reiss著・高里ひろ訳/本文330頁/白水社/2015年5月15日発行/ISBN978-4-560-08426-7 C0022
(本文から)
|
◆天国へ神さまを殺しに行く こうして銃で武装してから,わたしは階段を登った。二階の踊り場で,母と出くわした。母は(父の)死の部屋から出てきたところだった…涙でほおが濡れていた。「どこに行くの?」母はわたしに尋ねた。伯父の家にいると思っていたわたしがいたので,驚いていた。「天国に行くんだよ!」わたしは答えた。「どういうことなの,天国に行くって?」「いいから行かせて」「天国に行ってどうするの? かわいそうな坊や」「天国に行ったら,神さまを殺すんだ。神さまがパパを殺したんだから」母はわたしを抱きしめ,あまりにも強く力を込めたので,わたしは息がとまってしまうんじゃないかと思った。(p.10) ◆奴隷だった息子は,侯爵の父親に買い戻された 14歳のトマ=アレクサンドル・デュマ・ダヴィ・ド・ラ・パイユトリーは,1776年8月30日,ル・アーヴルの波止場に降り立った。(略)つい先日までポルトープランスで奴隷だったトマ=アレクサンドルにとって,ノルマン人の城での暮らしは驚くことばかりだったろう。同様に,ほぼ全員が金髪碧眼のヴェルヴィルの人びとにとって,新しい侯爵の黒い肌をした息子は驚きだったはずだ。(p.63) ◆モンテ・クリスト伯のモデル 言うまでもなく,タラントの城砦でデュマ将軍が監禁された事実は,彼の息子によって,無実の罪で投獄された『モンテ・クリスト伯』の主人公エドモンド・ダンテスの体験の題材としてつかわれた。(p.273)
|
【私のコメント】
作家「アレクサンドル・デュマ」には親子二人いて,それを区別するため「三銃士」を書いた父親のほうは「デュマ・ペール(父親のデュマまたは大デュマ)」,「椿姫」を書いた息子のほうは「デュマ・フィス(息子のデュマまたは小デュマ)」と呼ばれる。しかし,私は,「デュマ・グラン・ペール(祖父のデュマ)」がいるとは知らなかった。彼は作家ではなかった。フランス人貴族がカリブ海のサン=ドマング島で黒人の女奴隷に生ませた子どもで,彼自身,奴隷として育ったのである。後に父親に買い戻され,フランスにやってくる。そして自らの力で将軍にまで上りつめるのだ。その勇敢さに敵は「黒い悪魔」とあだなした。この本の出だしは,デュマ将軍が死んだとき,まだ4歳に満たなかった息子が神を殺しに行くと銃を手にしたというデュマ・ペールの自伝の抜粋から始まる。デュマ家は3代にわたって,フランスの中の人種差別に苦しめられることになる。デュマがなぜ「モンテ・クリスト伯」を書いたのか,何を訴えたかったのか,そうした真相が垣間見える。黒人奴隷が将軍になり,ナポレオンと渡り合う――嘘のような真実の物語だ。
佐々木閑著/本文296頁/角川ソフィア文庫/2013年10月25日初版/ISBN978-4-04-409447-8 C0115
(本文から)
|
◆釈尊時代の仏教と密教を結びつけるのは危険 釈尊時代の教団生活と密教での菩薩観を無理に結びつけることで,「この世には殺してあげた方がよい人たちがいる。(略)」というポアの思想を生み出したオウム真理教がよい例である。それぞれが単体として極めて穏当な教義であるのに,化合させたとたんに劇薬に変貌する。(p.210) ◆アーリア人が持ち込んだ「ヴァルナ」がカースト制度のもと アーリア人の侵入は,もともとインド亜大陸で暮らしていた下縫うの人たちの間に(略)身分差別社会を作っていった。上に立つのはアーリア人,下で差別されるのが土着に人たちである。この支配者と被支配者の二重構造を基盤として成立するのが,ヴァルナと呼ばれる身分制度である。このヴァルナが今でいうカースト制度のもとになる。(p.222) ◆たくさんいた反バラモン(反カースト)たち 反バラモン教の立場に立って,努力こそ人の価値があると主張した人たちは,その主張のないようから「努力する人」と呼ばれた。インド語ではシュラマナという。それが中国に伝えられ,音写されて「沙門(しゃもん)」となった。現在の日本で沙門というと仏教のお坊さんを指すが,本当は,バラモン教に反対して(生まれではなく)自分の努力で最高の幸福を手に入れようと考える修行者すべてが沙門である。(p.228) ◆ブッダの死後数百年たって,仏教は突然多様化した たとえば『般若経』,『法華経』,『華厳経』,『大無量寿経』など,日本でもおなじみのお経は,それぞれが異なる系統を形成している。これらは今でこそ「大乗経典」として一括されるア,もともとは別個の起源を持つ別系統の経典なのである。それまでは単一の宗教として,一つの固定された教義を守ってきた仏教が,ブッダの死後数百年たって突然一挙に多様化し始め,やがて系統のことなる様々な新仏教を生み出したのである。(p.274)
|
【私のコメント】
京都や奈良に行くと「○○菩薩」や「○○如来」がたくさんあって,私は何が何だかよく分からなかった。それが佐々木閑(しずか)氏の本(この本もその一つ)を読んで,目からうろこが落ちた。そもそも「超越者」を認めなかった釈迦の唱えた仏教(だいたい釈迦自身が人間であって神ではない)が,釈迦の死後数百年経って,もともと存在しなかった「超越者(たとえば菩薩や如来)」を認める経典が次々と現れた。そして中国(そして日本)はこちら(大乗仏教の経典)を釈迦自身の言葉を書き留めたなものと受け止め,それらを受け入れたのである。菩薩や如来が乱立しているのはそういうわけだったのだ。
佐々木閑著/本文206頁/ちくま新書783/2009年5月10日第1刷, 2011年10月5日第7版/ISBN978-4-480-06485-1
(本文から)
|
◆瞑想修行と自転車は似ている もしお釈迦様が自転車に乗ったら,必ず「瞑想修行と自転車は似ている」と言ったに違いない。(略)修行者が瞑想に入って精神を集中させていく過程は,これ(自転車)とそっくりだ。(p.22) ◆お坊さんは肉食してよい (仏教のお坊さんは)人々の食べ残しをもらって,それで命を繋ぐ。(略)食べ残しだから,そこには肉や魚も入っている。(略)もらったものはなんでも食べねばならない。だから,お坊さんはもともと,肉や魚を食べても構わない。それが,お釈迦様が決めた仏教本来の生活方法なのである。(p.42) ◆本来,仏教は超越者の存在を認めない お釈迦様が創った本来の仏教では,超越者の存在を認めない。つまり我々に,神秘的な救いの手を差し伸べたり,罰を与えたりする者はどこにもいないと考えるのである。(p.44) ◆自殺は悪でない 仏教は本来,我々をコントロールする超越者を認めないから,自殺を誰かに詫びる必要などない。(略)人が強い苦悩の中,最後に意を決して一歩を踏み出した,その時の心を,生き残った者が,勝手に貶めたり軽んじたりすることなどできないのだ。自殺は,本人にとっても,残された者にとっても,つらくて悲しくて残酷なものだが,そこには,罪悪も過失もない。弱さも愚かさもない。あるのは,一人の人の,やむにやまれぬ決断と,胸詰まる永遠の別れだけなのである。(p.89)
|
【私のコメント】
本書は2007年4月5日から2009年3月26日まで,朝日新聞のコラムに載った記事を加筆修正したものである。著者,佐々木閑(しずか)氏の著書はどれをとっても面白い。工学部を卒業した著者が理系の目で見ているからである。特に「自殺は悪ではない」の文章には,自ら命を絶った人を近くに持つ方々から胸打つ手紙が数多く寄せられたと聞く。私もこの文章は何度読んでも,目頭が熱くなる。説得力ある内容である。
ジョアオ・マゲイジョ著/塩原通緒訳/本文450頁/NHK出版/2013年5月25日第1刷/ISBN978-4-14-081605-9 C0042
(本文から)
|
◆エットーレの失踪 1938年3月26日の夜,31歳になっていたエットーレは,シチリア島のパレルモから船に乗り,それっきり消息を絶った。数通の遺書が残されていたし,彼が少なくとも5年ほど抑うつ状態にあったのも事実だった。にもかかわらず,それでこの一件がすっきり落着とならなかったのは,遺体がついに収容されなかったうえに,以後数十年にわたって,あちこちからエットーレの姿を見かけたという話が出てきたからだ。(p.12) ◆「数光年」の厚さの鉛 ルドルフ・パイエルが計算により,非常にとらえにくいユートリノをとられて検出器と相互作用させるには,数光年とうい厚みの鉛が必要であると導き出した。それは太陽と地球の距離の数百万倍に相当する。そんな鉛があるものか。というわけで,ニュートリノは決して幻ではなかったが,それに近いものではあったのだ。(p.73) ◆シカゴの真ん中で世界初の原子炉が臨界に! 1942年,フェルミはよく考えもしないまま,シカゴの街のど真ん中で原子炉第一号の試運転をした。フェルミが計算尺で計算しながら,室内の反対側にいる減速材の調整係に大声で指令を出しているなかで,世界初の原子炉がしだいに臨界に達していくところは,記事を読んでいるだけでも胃が痛くなる。この初めての「制御された」原子炉は,大都市の真ん中でチェルノブイリのような結末を招く可能性だってあったのだ。(p.193)
|
【私のコメント】
ニュートリノが観測される25年も前に,この粒子の性質について予言していた男がいた。エットーレ・マヨラナである。しかしかれは
31歳で船の上から消えてしまう。素粒子そして原子爆弾――この本はエットーレを中心にその時代の物理学者たちの動きをわかりやすく描く。
増田俊也著/本文689頁/新潮社/2011年9月30日発行,2011年11月30日第11刷/ISBN978-4-10-330071-7 C0095
(本文から)
|
◆力道山の騙し討ち 昭和29年(1954)12月22日。時に木村37歳。(略)この一戦で,双葉山と並ぶ国民的大スターだった木村政彦の名は,表舞台から消えていく。力道山とのプレオレス選手権試合――。戦後プロレス史,いや戦後スポーツ史最大の謎とされるこの戦いはどんなものだったのか。引き分けにする約束になっていたこの試合は,力道山の騙し討ちによって凄惨な流血試合となった。不敗の柔道王は,全国民の前で血を吐いてKOされた。マットに直径50センチの血溜まりができるほどの惨劇だった。(p.18) ◆嘉納はPRで勝った 社会学者の井上俊は,(略)古流柔術を抑え講道館が最終的に一人勝ちした理由を《(対古流柔術の)実戦の市売りというよりもむしろ「言説の勝利」であった》と断言している。まだ雑誌媒体などほとんどない時代,東京開成学校(後の東京帝大,現在の東京大学の前身)出身のインテリ嘉納は講道館機関紙をつくって精力的に自身の考えを発表していた。そのなかから生まれたのが「道」という概念である。嘉納は,大量に残した活字のなかでこの「道」について多くの意味を付与している。(p.52) ◆張本と力道山 張本(勲)は力道山が在日ではないかという噂だけは聞いていた。(略)「リキさん,やっぱり朝鮮の人だったんですか。だったらみんなに言ってくれればいいじゃないですか,俺は朝鮮人だって胸を張って」力道山は激昂した。「おまえは昔の差別を知らないからそんなことが言えるんだ!」(p.638)
|
【私のコメント】
「木村政彦」という名を,この本で初めて知った。彼が昭和29年に力道山に敗れるまで,最強の柔道家として知れ渡っていたということも。この本には木村と関係する人物として,力道山をはじめ,ジャイアント馬場,大山倍達など多数の有名人が出てくる。戦後,日本中が力道山の空手チョップに沸いていた,その裏側で一体何が起きていたのかを知ることができる。
ラッセル・ショート著/松田和也訳/本文336頁/青土社/2010年10月29日第1刷/ISBN978-4-7917-6575-1 C0000
(本文から)
|
◆デカルトはすでに生前から大きな影響力を持っていた 彼の生前,そして死後の数十年間,デカルトの影は今よりも遥かに大きかった。多くの同時代人は彼を,近代という包括的プログラムの知的基盤を築いた人物と見なしていた。(p.16) ◆精神と身体の統合はまだできていない デカルトが精神と脳を峻別して以来,現在に至るまで誰一人としてこの両者を再統合する決定的かつ普遍的な方法を見出したものはいない。1646年にデカルトはそれは不可能かもしれないと宣言した。1998年,トマス・ネイゲルはにべもなく言った,「精神=身体問題に関しては,誰一人納得できる答えを持つ者はいない」。(p.245) ◆デカルトは心こそが精神と身体のインターフェイスと考えた 彼(デカルト)は最後の著作に着手した。それが「魂の情念」に関する論文だったのは偶然ではない。デカルトはかなり以前から,リアリティを精神と身体に分割することの困難さ――その二つの実体の相互作用の様式を解明することの困難さ――に気づいていた。そして遂にこの困難な課題に取り組んだのである。彼の結論は,この両者を繋ぐ組織があるというものだった。アルモガト言うところの「コード化」である。このコード化を示す17世紀の用語は「情念(パション)」だった。「心」と呼んでも良いだろう。心こそが精神と身体のインターフェイスなのだ。愛,歓び,怒り,悔恨。われわれはこれを身体と精神の双方において感ずる。そしてこれらの情念こそ,何らかの形でこの二つを繋いでいるのだ。(p.335)
|
【私のコメント】
デカルトは死後もなかなか落ち着くことはできなかった。1650年スウェーデンで客死。1666年,その墓が暴かれ遺骨はフランスへ。フランス革命を経て1793年再び彼の墓が暴かれ,フランス記念碑博物館に移されるが,このときすでに頭蓋骨は無くなっていた。1821年,デカルトの頭蓋骨というものがスウェーデンで発見されるが,その骨にはびっしりと様々な所有者の手によって署名や詩が書きこまれていた。本書はデカルトの死後,その骨にまつわる様々な関係者についてその時代背景を踏まえて解説していく。デカルトには知人の家の女中であったヘレナ・ヤンスとの間にフランシーヌという娘がいた。当時婚外子を作ることは重罪であった。デカルトは表向きはヘレナを自らの女中,娘を「姪」として暮らしていた。ただ洗礼記録ではフランシーヌを実子と認知している。デカルトは生涯にわたってこの娘フランシーヌを愛した。しかし娘は猩紅熱にかかり,たった5歳で彼の腕の中で死ぬ。その後,デカルトはヘレナと別れた(捨てた)ということになっていた。ところが最近になってライデン市の記録の中に,娘の死後4年たってヘレナは別の男性と結婚したという事実が判明した。そしてその持参金1,000ギルダーを,なんとデカルトが用意していたのである。あのデカルトも一般人と同じ愛や悩みを持っていたのだと思うと,うれしくなる。
西嶋定生,講談社学術文庫1273,1997年3月10日第1刷,2008年5月8日第13刷
(本文から)
|
◆秦漢帝国の出現が日本を未開から脱皮させた 注目すべきことは,日本にとって,文明社会への発展が,秦漢帝国によって示される中国文明の影響下になされたことである。(略)日本の歴史にとって,中国における秦漢帝国の出現と,その国家構造の形態と,そしてその時代の文化形態とは,無視することのできない重要な意味をもつものであったと言えよう。(p.22) ◆秦王「政」は,死後自らを「始皇帝」と呼べと言った 諡法(しほう)とは,君主の死後,その君主の業績に適したおくり名を定めることである。かれ(秦王政)はこのような諡法は,子として父を批判することであるから,今後いっさい廃止して,みずから始皇帝と称し,二世,三世と万世に伝えることとしたといわれる。これによると,かれは生前から始皇帝と称したかのようであるが,それは誤った解釈である。生前かれは,ただ皇帝と称されていたのであって,始皇帝とよばれることはなかった。すなわち始皇帝とはかれの死後はじめて使用された名称なのである。(p.49) ◆革命期には地縁血縁を超えた絆が重視された 秦末の反乱諸軍団は,指導者の出身のいかんをとわず,そのもとに集まったひとびとに,このような(下層出身者が多いという)特色があったのであり,まさに時代の特徴というべきものであった。指導者とかれらとを結ぶものは,同族であるという血縁関係や,同郷であるという地縁関係を超えたものであり,いわが心情的な信頼関係であった。このような関係を主客関係と言い,人徳すぐれた有力者を主人として,地縁・血縁から離れたひとびとが参集し,その賓客となったものである。これは春秋時代末期以降,中国社会の変革期における集団形成の原理であった。(p.107) ◆三人以上が理由なく会食すれば罰金 奇妙なことに,漢代では三人以上のものが理由なくして群飲食すれば,罰金四両が科せられるという法律が施行されていたからである。この群飲食の禁止は,治安を目的とするために集会を禁止したのではない。ひとびとが集会して酒を飲むということは「礼」を行うことであり,「礼」こそは国家が社会秩序の基本とするものであるから,みだりに群飲食をすれば,この「礼」を破壊する行為となる,という思想から生まれた禁止令であった。(p.148)
|
【私のコメント】
本書はもともと,講談社の『中国の歴史』全10巻の第2巻として1973年に執筆されたものである。著者や岡山出身の中国史学者。1998年に死去。けっこう厚い文庫本であるが,非常にわかりやすい説明で飽くことなく一気に読むことができた。講談社学術文庫には他にも類似の歴史書があるが,この本のように読み易くはない。西嶋氏の力量だろう。
浅野裕一,岩波書店,1998年2月20日第1刷,1998年7月15日第4刷
(本文から)
|
◆孔子は「天子」を志した 孔子は,周の文化的伝統の守護者たる地位を失いつつ有った,既存の周王室を見限る。そして比類なき礼学者としての自信から,「吾は其れ東周を為さんか」と,周公旦を国祖と仰ぐ魯に,周道を継承し発展させる新たな王朝を建国せんとする,大胆不敵な空想を抱く。(p.18) ◆天子になり損ねた自分を自己弁護する ある人が孔子に訊ねた。「子は奚ぞ政を為さざる」。どうしてあなたは,政治をなさらないのですか。孔子にとって,これだけは絶対にして欲しくない質問であったろう。動揺を隠して孔子は答える。「書に云く,孝なるかな惟れ孝,兄弟に友にして,有政に施すと。是れ亦た政を為すなり。奚ぞ其れ政を為すを為さんや」。『書』にはこうあります。なんて孝なんだろう。兄弟仲良くして,それを政治に適用すると。だから親族が仲良く暮らすだけでも,それで立派に政治をしていることになるのです。どうしてそれ以上に,わざわざ政治をしたりする必要がありましょうか。孔子は『書』の一節を援用しながら,孝の実践は為政に連続するとの,苦しい自己弁護を行う。(p.44) ◆孟子も荀子も天子になりたかった かつて孔子は,魯に新王朝の建設を夢見た。そして孟子は,孔子の後継者たる自分こそ,孔子が果たせなかった新王朝創建の天命が下ると信じた。さらに荀子学派は,わが師匠たる荀子こそ,帝王として新王朝を樹立すべきだったと主張した。(略)なぜに先秦の儒家のみが,入れ替わり立ち替わり,我こそ王者たらんとの野望を抱くのであろうか。その原因は,儒家が唱える徳治主義にある。(略)孔子教団においては,わが師匠たる孔子こそが有徳の聖人であるとされ,御本人もまた心中ひそかにその自負を抱く。同様に,孟子学派にあっては孟子がそうであり,荀子学派にあっては荀子がそうであった。この両者が合体するとき,その必然的帰結として,孔子も孟子も,そして荀子も,その偉大な徳よりすれば,王者になって然るべきだと考えられるのである。我こそ王者たらんとする野望は,かくして誕生する。(p.98) ◆孟子の企み 孟子は,孔子こそ周に代わる新王朝を創立すべき聖人であったと吹聴した。もし孔子が,真に孔子王朝を創始すべき王者だったとすれば,孔子はそれまでの聖王たちと同じく,わが手で孔子王朝固有の礼楽を制作していなければならない。だが,孔子が王者であったとの主張自体が,全くの虚偽でしかない以上,孔子の手に成る礼楽など,どこを探してもありはしない。そこで孟子は,本来,「天子の事」である『春秋』を孔子が著作したと偽る方策により,『春秋』に礼楽の肩代わりをさせ,孔子王者説の矛盾を解決せんとする姦計を企んだ。(p.99)
|
【私のコメント】
7500円という高値にもかかわらず,わずか5ヶ月で4刷が出ている。私もこの本には驚いた。なにしろあの孔子が自ら天子になろうとしていたというのだ。そしてその後の儒家はこの開祖の野望を実現してやろうと,孔子が自ら書いたという偽作を作っていったというのだ。儒教はそもそも儀式のプロフェッショナルである。しかし,孔子自らが言うように,孔子の出身は「貧にして且つ賤」。どんなに努力しても宮廷の儀式を深く知るわけはない。そこは孔子の「イマジネーション」で補ったということだ。しかし後に,さまざまな経典が作られて,儒学が宗教としての装いを整えていく。この本を読めば,これまでの儒教のイメージが一変する。
冨谷至,中公新書2134,2011年10月25日
(本文から)
|
◆時代が英雄を作る それぞれの時代の丈夫(ますらお)が堅持すべき意識,矜持(きょうじ),自負,丈夫たらしめる固有の何かがあり,それが命よりも重要だと考え,また人々の心に共鳴し,賛美されたというべきである。いささか陳腐な言葉を連ねれば,英雄は時代が作るものであり,時代によってその英雄観は異なるであろう。(p.49) ◆皇帝の使者の証明書「節」
節(せつ)とは,身長より若干長い190センチぐらいの竹の杖で,その先に三重の旄牛(ぼうぎゅう=ヤク)の毛の房飾りがついている。(略)
◆節侠(せつきょう) 「節侠」の「侠」は,日本語の「義侠」「侠客」のそれに近い。男気をもち操のしっかりした丈夫(ますらお)と訳してもよかろう。その「節」は,節義,節操,節行という「守るべき義」「守るべき操」「きとんとした正しい行い」という意味であり,原義である竹の節目がきちんと符号するように,「人に信頼され,その信頼に確実に応える」ことに他ならない。つまり節とは人間同士の守るべき信頼という意味になる。(p.53) ◆筋を通した顔真卿(がんしんけい) 顔真卿は,玄宗,粛宗,代宗そしてこの徳宗と四代の皇帝に仕えたのだが,一貫して正論を主張して筋を通し,そのために時の宰相と対立し,幾度か左遷され,しかしながら彼の持つ学識,度量のゆえに中央にもどるということを繰り返す。「正論に反論為し,されど正論に敵多し」(p.111) ◆ 学問とは何か 繰り返しいうが,ここ(顔子推の『顔氏家訓』)でいう学問とは,経書に精通し,かつあまたの書を渉猟することで自己の生きる糧を養うことであり,単に「学問」「勉強」をするのではない。(p.121) |
【私のコメント】
「中公新書の中国もの」はよくできたものが多い。本書もまた期待を裏切らなかった。時代によって英雄や「ますらお」の意味も変わる。しかし,それでもその底には一貫したものが流れているように思う。それは相手を恐れず,正論を主張する勇気であり,信頼には信頼で応えようとする態度であろう。著者は本書の最後で「科挙」について語っている。宋の時代の科挙は,徹底して不正を除去するため,何とすべての受験生の答案をいったん別の紙に写して,そのコピーを採点者が採点したという。それは,採点者が受験者の筆跡を見て,相手を特定する可能性を除去するためだったというのだ。科挙についてはカンニングなどの不正行為がしばしば指摘される。しかし筆者はこう言う――あえて言おう,やはり科挙は公平な試験であったのだ。そういったことが科挙に絶対的な信頼を与え,信頼が進士及第に絶対的権威を賦与することになる。
大山誠一著,日本放送協会 NHKブックス1146,2009年11月30日第1版
(本文から)
|
◆古墳時代から,聖徳太子が忽然と登場するのはなぜか? 日本古代史を学ぼうとすると,誰しもが一種の戸惑いをもつものではなかろうか。旧石器から縄文,弥生,古墳という考古学の時代区分が続いた後,突然,飛鳥時代になり聖徳太子が登場する。その聖徳太子は,まだ中国との交流がほとんどなかった時代なのに儒教・仏教・道教という中国思想の聖人で,国内では皇太子・摂政として天皇中心の政治を整え,さらに中国・朝鮮とならば,以後,日本の歴史は聖徳太子の示したままに進行することになる。言ってみれば,本来はあったはずの未開から文明への葛藤,つまり考古学が明らかにした日本固有の社会が巨大な中国文明を認識し,悪戦苦闘しながら学び,そのうえで取捨選択し,その結果として独自の秩序と文化を構築するという,そういう長期にして困難かつ複雑な価値観の相克を,聖徳太子という一人の聖人ですましているのである。(p.3) ◆天孫降臨神話をプロデュースした男 どう考えても,中大兄王が蘇我入鹿を暗殺した段階では中大兄王は宗教的存在ではなかったであろう。ところが,大宝律令が編纂され,律令国家が完成した段階では,天皇は実権のない宗教的存在となっていた。ひとりでになったわけではあるまい。誰かがしくんだに違いない。(略)宗教的権威として天皇を利用するなら,思いきって天皇を神としたらどうか。その途方もない企てを構想し,実現した人物がいた。『日本書紀』編纂の最高責任者藤原不比等である。そして,そのために彼の手によって創造されたのが高天原(たかまがはら)・天孫降臨・万世一系という神話であった。(p.7) ◆聖徳太子のイメージ作りでは儒教関係は不比等,道教関係は長屋王,仏教関係は道慈(どうじ)が担当した 『日本書紀』の聖徳太子は儒仏道の聖人であるが,その人物像の成立に大きな影響を与えた人物としては,儒教関係は藤原不比等,道教関係は長屋王,そして太子の関係記事の大部分を占める仏教関係と中国的聖天子としての表現は道慈と考えてよいであろう。(p.54) ◆「厩戸王」を消して,そこに「聖徳太子」を書き込んだ 一般に,聖徳太子という人物像は,厩戸王をモデルにとか,厩戸王に仮託してとか言っているが,現実には,厩戸王という人物を消して,そこに聖徳太子を書き込んだと言ったほうが正確なのである。(p.124) ◆記紀神話は「地域に根づく伝承」なんかではない 一般には,神話と言えば,さまざまな氏族や地域に古くから伝えられたものと考えられてるのではないかと思う。しかし,記紀神話に関しては,そのようなものはほとんどない。すべて記紀の編纂段階で,藤原不比等を中心とする編者たちによって作られたものである。(p.257) |
【私のコメント】
実に面白く,かつ説得力のある説である。すでに子孫が絶えていた120年前の実在の人物「厩戸王」を「聖徳太子」に仕立て上げたとは。いわれてみると「記紀」はそれまでの各地の伝承を集めたものでもなく,特定の個人が作り上げた感がある。稗田阿礼が暗誦していた物語を筆写したなどというのはどうも怪しい。聖徳太子が「ねつ造」だとすると,法隆寺はどうなるのか。数多く残っている聖徳太子の遺品はどう説明するのか。これに対しても著者はちゃんと解答を用意している。いわゆる聖徳太子遺愛の品と言われる品々は,怪僧行信が厩戸王の死後120年もたって,しかも厩戸王の一族が滅亡しているにもかかわらず,どこからともなくかき集めてきたものである。
植木雅俊著,中公新書 2135,2011年10月25日初版,ISBN978-4-12-102135-9
(本文から)
|
◆なぜ仏教はインドで根を下ろすことができなかったのか? 仏教とほぼ同時期に興起したジャイナ教も初めは仏教と同じ立場を取っていたが,後世になってカースト制度を承認し,妥協してしまっている。それに対し,仏教徒は最後までカースト制度を承認することはなかった。中村(元)先生は,カースト制度の支配的なインド社会において,仏教が永続的に根を下ろすことが出来なかった理由の一つとしてこの点をあげておられる。(p.17) ◆漢訳経典が独り歩きを始める 中国では,仏典をサンスクリット語やパーリ語から漢訳した後,それらの原本を試みることがなかったのか,原本が散逸してしまっている。(略)漢訳した後は,サンスクリット原典よりも漢字になった訳文のほうに重心を置いてしまい,漢訳の独り歩きがはじまったのである。(略)シッダーンタは(略)「達成された究極」という意味で,転じて「確立された結論」だとか「立証された真理」という意味になる。それが中国において,日本語の片仮名のような感覚で,「悉檀(しつだん)」と音だけ写された。「悉」も「檀」も「発音記号」なのである。(略)後世になると「悉」と「檀」という漢字自体の持つ意味に戻って意味づけがなされた。(略)もともとは「確立された結論」であったものが,「あまねく衆生に施すこと」にすり替わってしまった。(p.76) ◆菩薩様は「男」だった サンスクリット原典によると,観音は16の姿を現すとされ,そのすべてが男性である。しかも,ガンダーラの観音菩薩の彫像は,ほとんどが口ひげを蓄えており,インドでは,この菩薩は男性であったことを示している。サンスクリット原典では,女性の姿はあり得ないことであった。観音の女性化が起きたのは,中国においてである。(略)観音の住む所は,ポータラカ(補陀落山(ふだらくせん))という南方の海上の山だとされているが,中国ではそれが東シナ海海上の舟山(しゅうざん)群島のことだとされた。そこで道教の女神で航海・漁業の守護神である媽祖(まそ)に対する信仰と観音信仰が結びついて,観音の女性化が始まった。
|
【私のコメント】
考えてみれば,当時の日本人にとってインドはさぞ遠かったことだろう。ガンダーラは果てしなく遠かったのだ。仏教が中国に渡り,そこで漢訳され道教などの影響を受けながら,日本に渡って来た時には,はや原典の意味は大きく変わっていたことだろう。私たちはお経といえば「漢字」というイメージを持つ。でも考えてみればそれは「通過地点」なのだ。本書はインドから日本への長い旅の過程で仏教がどう変遷していったかを教えてくれる。とりわけ,本来男女平等であったインド仏教が,中国で男尊女卑となってしまって日本に伝えられてくるところが興味深かった。カースト制度に妥協しなかったがゆえに,仏教は結局インドに根を張ることはなかった。しかし,この悪しき伝統のカースト制度を打ち破るのはヒンズー教にはできないとして,今,インドでは仏教への改宗運動がわずかながら生じつつあると聞く。
菊池章太(のりたか)著,朝日新書,2008年2月28日第1刷,ISBN978-4-02-273198-2 C0216
(本文から)
|
◆「神々を信じるか」との問いにソクラテスはどう答えたか
舞台は2400年前のアテネの町はずれ。ソクラテスがひさしぶりに若い友人と出会い,小川のほとりをそぞろ歩きながら語り合っていた。友人はおもむろにたずねた。あの神話の神々の話をあなたは信じているのか,と。ソクラテスは答える。
◆難病治療と悪魔祓いがイエスを有名にした 「マルコ伝」には,「非常に大勢の人々がイエスが行ったことを聞いて,彼のところに来た」と記されている。少なくとも初めのころイエスは,その「行ったこと」によって存在が知れわたったのである。(略)その行ったことと言えば,それは難病治療と悪魔祓いであった。(p.140) ◆「悪魔憑き」は現代病 アメリカ精神医学会が作成する精神疾患の診断のための手引き書がある。DSMと略称されるこの本は,患者に対する臨床的判断と治療にむけての診断基準を提供することを目指したものである。(略)この最新版には,「今後の研究のための基準案」という項目が最後にずらっと並んでいる。DSMの編集委員会によって,(略)早急に検討すべきだと判断された精神疾患ばかりである。そのなかに「解離性トランス障害」という項目がある。これは最新版によって新たに加わった項目である。「解離性トランス障害」とはつまり,憑きもの障害のことである。憑きものの例として「死者の魂」だの「悪魔」(!)だのが上がっている。くりかえすが,この本はアメリカ精神医学会が現代の精神疾患に対して診断基準を示したものなのだ。(p.172)
|
【私のコメント】
著者菊池章太(のりたか)氏はユニークな経歴を持つ。筑波大大学院中退の後,フランスのトゥールーズ神学大学でカトリック神学を学んでいる。1992年に韓国に行き仏教や道教に関心を抱く。著書に「老子神化」(春秋社,2002)などあるように,道教にもめっぽう詳しい。どうして古代中国文献を読みこなしているのかと思ったら,どうやら英訳本にも目を通しているようだ。この人の本はわかりやすく面白いので,お薦めである。「悪魔憑き」も一概に否定するのではなく,悩みを持つ人間の一つの症状の現れとしてみるべきだというスタンスは共感できる。
織田正吉著,岩波書店,2010年6月17日第1刷
(本文から)
|
◆漫才と落語を表面的な印象でみると,落語のほうが古く漫才はその後に生まれたもののような印象を与えるが,歴史的には漫才のほうがはるかに古い。文献で確認できるものは平安時代すでにあった。漫才は千秋万歳(せんずまんざい)として発生し,その略称が表記を変えたものである。(p.5) ◆現在の漫才の出発点に位置するのは玉子家円辰(たまごやえんたつ)である。円辰の時代は江州音頭をはじめさまざまな音曲を聞かせるものが漫才で,そのつなぎとして間に笑いを呼ぶ会話をはさんだ。音曲の間のつなぎに過ぎなかった会話を演芸として独立させたのが横山エンタツ・花菱アチャコのコンビである。(p.6) ◆落語はマクラが終わり,「こんにちは」「ああ,お前さんか。まあお上がり」というセリフで本題が始まると,話し手自身は高座にいながら姿を消し,登場人物の会話だけで話が展開する。落語の特徴を「演者が消えてしまう話法」というのは桂米朝の指摘である。(p.12) ◆江戸時代には,まじめな話を笑いごとにしてしまうのを「茶にする」と言った。まじめな問題を冗談ごとにする,話をはぎらかす,からかうという意味である。「茶にする」は「茶化す」とも言った。(略)まじめを尊重する人が笑いを嫌う理由の一つには,笑いの持つこの破壊力がある。(p.19)
|
【私のコメント】
インパクト指数が27.1というのは尋常ではない。ほぼすべての頁が参考になる,おもしろいということである。著者は笑いの専門家。何しろ漫才のシナリオを手掛けた経歴を持つ。笑いの本質を理解している。たとえば,ジョークには言葉の多義性を利用するものがあるといって,次のような例を挙げる。
A 頼む。おれを男にしてくれ。
B おまえ,男じゃなかったのか?
また,屋久島にある「縄文杉」は樹齢4000年とも5000年とも言われているが,かなり曲がりくねった形をしている。実は屋久杉の中で姿形がよいものは「薩摩杉」とも呼ばれてことごとく伐採されてしまったのである。今ある「縄文杉」は使い物にならないが故にまだそこにあるのだ。『荘子』の言う「無用の用」を実例で示しているのがこの「縄文杉」なのである。本書にはこうしたエピソードがふんだんにある。読んで得する本だ。
村田晃嗣著,中公新書2140,2011年11月25日第1刷
(本文から)
|
◆2004年6月5日に,レーガンは93歳で他界したが,(略)その1年後のインターネット調査では,レーガンは再びリンカーンを抜いたのみならず,ついに「最も偉大なアメリカ人」になってしまった。(p.iii) ◆米軍がヨーロッパでナチスの強制収用所を開放し,ホロコーストの凄惨な様子を撮影した。そのフィルムがレーガンの所属部隊に送られ,編集されることになった。「恐怖に襲われたわれわれが見守る中で,”死体”の一つがひじをつついて身を起こし,手を差し伸べた。死体の海の中から出てきた一本の手は,必死に救いを求めているかのようであった」と,レーガンはその衝撃を物語っている。しかし問題は,このフィルムを見た経験から,自分が実際に強制収用所の解放に立ち会ったと,彼が語りはじめたことである。(p.60) ◆FBIのファイルには,レーガンの名前が「内通者T10号」と記されることになる。(略)戦時中には戦意高揚映画の中でしか活躍しなかったレーガンだが,ついに現実の世界で公安の一翼を担うことになったのである。レーガン大統領在職中の1985年に,この事実は明らかになった。(p.68) ◆レーガンはめったに激昂することはなかった。老眼鏡を机の上に投げ捨てるのが,彼の最も強い怒りの表現であった。(p.190) ◆(銃で撃たれて)担架で運ばれている最中に,大統領は意識を半ば取り戻した。看護婦が柔らかい手で,瀕死の患者の手を握っていた。「ナンシーには内緒だよ」と,レーガンはつぶやいた。次に目を開いた時,そのナンシーが夫を蒼白な面持ちで見つめていた。今度は,「ハニー,頭を下げてかわすのを忘れたよ」と,レーガンは言った。ジャック・デンプシーというボクサーが1926年に世界チャンピオンを奪われた夜,妻に語った言葉だという。(略)手術室に運ばれて麻酔をかけられる前に,レーガンは医師たちを見回して今度はこう言った。「あなた方がみな共和党員だといいんですがね」。医師たちの答えも気が利いていた。「大統領閣下,今日はわれわれ全員が共和党員です」(実は,彼は民主党員だった)。(p.195)
|
【私のコメント】
レーガンはタカ派で,あまり頭もよくないというイメージがあった。しかし,彼はリーダーズ・ダイジェストを読み,必要な数字を頭に入れて演説をした。彼の演説はわかりやすく説得力があった。なにしろ世界最大のコングロマリット,ジェネラル・エレクトリック社に雇われてアメリカ中の支社を訪れて演説をした経験を持っているのだ。レーガンは楽天的でジョークが上手かった。73歳のとき56歳のモンデールと大統領のイスを争った。公開討論会の席で司会者から「年齢はハンディキャップになるか」と聞かれ,レーガンはこう切り返した。「私は政治的目的のために,ライバルの若さや経験不足を利用するつもりはありません」。この答えに聴衆は爆笑し,ライバルも苦笑した。もっとも,モンデールはのちに「私も笑っているように見えただろう。だが近くから見れば,私は涙を流していたのに気づいたはずだ。というのも,これでやられたと悟ったからだ」と書いている。ジョークが過ぎてゴルバチョフを怒らせたり,マイクテストで「5分後にソ連を爆撃する」と言ったのが,そのままオンエアされてしまったりと,いろいろ失敗もあったが,憎めない大統領だった。インパクト指数がなんと21.3! ほとんどすべての頁がおもしろい。
ブライアン・マギー著,須田朗監/近藤隆文訳,NHK出版,2001年3月25日第1刷
(本文から)
|
◆私たちの心の働きのなかで最も大切なものも,やはり言葉にすることはできない。たとえば,恋愛感情,友情,(略)。それから(略)善悪の感覚,死すべき運命の予感といったものがある。どのレベルにしても,私たちにとってきわめて重大なものは,内面の世界や外の世界での直接の経験と同じく,まったくと言っていいほど言語では適切に表現できないように思われる。(p.135) ◆デカルトほど読んでおもしろい哲学者はまずいない。(略)文体の特徴も,それによって伝えられる文学的個性の鮮烈さも際立っているし,彼の本は偉大な芸術作品さながらで,一度読んだら手放せない。(略)すべての教養人はデカルトを読むべきだと思う。(p.161) ◆ポパーと会うようになった当初,何より印象的だったのは,私が過去に出くわしたことがなかったほどの知的攻撃性だった。あらゆる話題をポパーは執拗に,会話が許容できる攻撃性の限度を超えて追及した。(p.301)
|
【私のコメント】
ポパーやラッセルなど著者のブライアン・マギーが直接出会った人物についての批評もおもしろいが,カントやデカルトなど過去の偉人についての言及も,非常におもしろい。この本のタイトルは「てつがくびと」(てつがくじんではない)。半分は,ブライアン・マギーの自伝的な要素もある。なぜオックスフォード大学から大哲学者が出ないのか,などユニークな持論も展開される。哲学とはいうものの,堅苦しくなく読める本である。
瀧井一博著,中公新書2051,2010年4月25日初版,2011年2月10日5版
(本文から)
|
◆現在の近現代史研究をリードする立場にある板野潤治氏が,かつて司馬遼太郎氏と行った対談の一節である。 板野「どうしても伊藤博文がわからないのは,彼がいつも二つのはっきりした対立の間を動いていますから,明治史を書いていても伊藤博文の姿が出てこないんです。」 板野氏ははっきりと「伊藤はわからない」と言い切っている。氏ほどの深い学殖を持った専門家でも手に負えないと思わせる厄介な存在,それた伊藤博文なのである。(p.iv) ◆松陰が伊藤のなかに認めたのは,勉強熱心で快活だが,才覚には劣った愚直な足軽の倅であった。「周旋家」という形容に表われているように,松陰は伊藤のことを交渉能力に長けた能吏になるかもしれないとは思ったであろうが,国家の経綸を差配する地位に立つ器とはよそ考えていなかったに違いない。(p.6) ◆イギリスへの密航留学をきっかけに培った外国人とのコミュニケーション能力によって,伊藤は「周旋家」として認められ,身分を超えて藩政治の最前線で活躍することになる。西洋文明とは,彼にとってまたとない立身出世の梃子だったと言える。(p.16)
|
【私のコメント】
あまりにも低い身分であったため,松下村塾では塾の外から講義を聴いていたともいわれる伊藤博文だが,そのコミュニケーション能力によってついには初代総理大臣にまで登りつめる。私が感心するのは,彼はイギリスに密航留学をするのだが,わずか半年で帰国している。にもかかわらず,その後岩倉使節団では旅行添乗員のような役割を務めたり,外国との条約交渉の最前線で働いたり,英語で外国代表に手紙を書いたりしている点である。彼はどのようにしてこうした英語力を身につけたのだろう? 私が最も驚いたのは,日本女性として初めて米国に留学する津田梅子に,「アメリカを知る最良の本」として,トクヴィルの『アメリカのデモクラシー』の英訳を渡したことである。アレクシ・ド・トクヴィルは現代においてもなお卓越したフランス人政治思想家として評価が高い人物である。伊藤はどのようにしてトクヴィルの存在をしったのだろう。伊藤が諸外国の代表に送った英文の手紙はそれぞれの地で保存されているが,その英文は難しい言い回しはないものの,正確な英語で書かれているという。
シモン・ラックス/ルネ・クーディ著,大久保喬樹訳,音楽之友社,昭和49年6月25日第2刷,昭和56年2月20日第4刷
(本文から)
|
◆アウシュビッツは,ある意味で私たちがそこに入ることによって離れなければならなかった世界の”陰画”だった。そこでは私たちの最も本質的な崇高さというものが悪徳とみなされた。(略)反対に,それまで教育の力によって押さえられてきた最も卑しい本能が疑うべからざる徳となり,生きのびるための一つの条件となった。こうして収容所内の貴族階級は無頼漢や公民権剥奪者や職業的殺人者によって占められ,一方,知識人,宗教家,芸術家,学者はドイツの天才によって発明されたこの新しい社会の最下層民となったのである。(p.14) ◆一方には,収容所の外からやってきて即座に,大量に皆殺しにされる人間の集団があり,もう一方には,収容所内部でよりゆっくり,より計画的に,より経済的に,より効率的に死へと追いこまれていく人間の集団がある。(p.122) ◆調理場から,食堂から,衣料品倉庫から,はては病院から,肉,油,野菜,衣服,布,囚人治療法の薬品までさまざまな公共品がぬきとられてこの市場にまわしてこられると私有財産に姿を変えて流通した。これらすべてに,まっすぐガス室に送りこまれる何万という人間からとってきた品物を加えると,最後には,巨大な経済市場ができあがった。(略)ここで使用される通貨はかなり以前から決まっており,誰もそれに異を唱える者はいなかった。それは私たちにとって唯一の価値基準となるのだった。これがなければどんな品物に値をつけることもできないのだ。この通貨単位,それは煙草だった。(p.126)
|
【私のコメント】
わたしはひょんなことから本書の存在を知った。すでに市販はされておらず,古本としてインターネットで入手した。これまでアウシュビッツの様子は,たとえば「夜と霧」のような本によって知ることができたが,この本は異色である。筆者が生きのびたのは「音楽ができた」からである。アウシュビッツの中にあって労働に向かう人々を送り迎えするために所内に音楽隊が組織された。彼はその中にいたのである。もちろんそれだけでは生き残ることはむりだっただろう。上記にあるように,筆者はこれまでの価値観を変え,収容所に「順応」したのだ。どうすれば生きのびられるか――これを注意深く考え実行したのである。本書は訳者がフランス留学中に友人の部屋で古本としてこの本を手にしたのが発端である。この友人は,この本を,本書の著者の息子から借りていたのだった。さっそく著者とコンタクトをとり日本語に訳すことの許可を得た。著者のシモン・ラックスはワルシャワ生まれのユダヤ系ポーランド人だが,作曲を学ぶため,パリに家族ときていたときドイツ軍のとられられ,アウシュビッツの送られたという。アウシュビッツ内では「タバコ」が貨幣代わりになっていたということも,本書で初めて知った。実に稀有な書として,多くの人に読んでもらいたい本だ。
アントワーヌ・ヴィトキーヌ著,河出書房新社,2011年5月30日初版,ISBN978-4-309-22546-3 C0031 C1210
(本文から)
|
◆ヒトラーの世界観の基盤となるもの,その恐るべき思想構築の中心となるのは,「ユダヤ人」という言葉だ。当然のようだが,『わが闘争』のなかで,使用頻度がもっとも高い言葉は「ユダヤ人」である。(略)実にその数は373回を数える。(p.38) ◆『わが闘争』は,個人的な妄想によってユダヤ人排斥を心に誓った強迫的な精神病者が,ユダヤ人への憎悪を書き綴っただけの本ではない。『わが闘争』に綴られた感情は,西欧世界がつねに存在してきた憎悪,しかもかなり昔からずっとあった反感なのだ。(略)反ユダヤの思想は,キリスト教主義者や王政主義者が煽りたて,何世紀にもわたって強化され,欧州に定着してきたものだ。(略)この本は,欧州の暗い一面から生まれた憎しみの教書なのだ。(p.42) ◆ヒトラーが近代のほかの独裁者と違うのは,彼が法に則って権力の座についたことだ。ただの偶然などではなく,時間をかけ民主的に選挙を通じて,のし上がってきた。ナチスは血なまぐさい戦闘よりも,投票,開票,選挙運動の繰り返しのなかで権力にたどり着いた。つまり,ほかの全体主義国家,独裁国家に比べ,国民の関与が大きかったということになる。だからこそ,次のような問いが生まれる。ドイツ国民はヒトラーに権力を与えてしまった責任があるのか。いやそもそも,彼らは本当にヒトラーの意図がわかっていたのだろうか。(略)1933年,前年までの売り上げ部数30万部を加えると,(『わが闘争』は)実に130万部が人々の手にわたっていたはずなのだ。(p.68) ◆1945年5月,敗戦のまさに翌日から何百万という人々が『わが闘争』を破棄したり,隠そうとした。物置の奥に押し込んだり,川に投げたりした者もあった。ほとんどの人が「読んでいない」と公言しているにもかかわらず,この本を所有していたことに何らかの後ろめたさを感じていた。この本が本棚や卓上にあるところをソヴィエト,イギリス,フランス,アメリカといった連合国軍の兵士に見られてはまずいと思う程度には,この本の内容を把握していたことになる。(p.178)
|
【私のコメント】
インパクト指数が非常に高い本である。本書は2008年,独仏共同テレビ局「アルテ」で放映されたドキュメンタリー番組「『わが闘争』――すべてはそこに書かれていた」がもとになっている。ヒトラーは実に民主的に,選挙を勝ち残り,実権を掌握した。国民は熱狂的に彼を支持し,彼の著書『わが闘争』を進んで買った。ヒトラー自身は,逆にこの本の売れ行きに驚き,自分の手の内をさらけ出しすぎたと,後悔したくらいだ。しかし,他国の指導者はこの本をたわごとととらえ,本気にしてはいなかった。またヒトラーがしばしば見せる平和希求のパーフォーマンスにすっかり騙されてしまった。実際は,ヒトラーは『わが闘争』に書いていることを着実に実行していたのである。これはなにもドイツ国民に限ったことでもない。太平洋戦争は軍部の独走によるものだ,という声を聞くが,別に軍部がクーデターを起こして政権を奪取したわけではない。二.二六事件は結局頓挫した。国民の圧倒的な支持のもと,その方向に進んでいったという点ではドイツとなんら変わることはない。民主主義というものがいかにもろいものであるかを,この本は教えてくれる。著者は1977年生まれの若いフランス女性だが,社会を見る目が実にしっかりとしている。「日本の若者よ,本当にそれで大丈夫なのか」と言いたい。
冨山至著,20030年5月25日第1刷,中公新書,ISBN4-12-101695-5 C1210
(本文から)
|
◆かくてここから韓非の有名な教訓が導き出されてくる。 人主の患は,人を信ずるにあり。人を信ずれば則ち人に制せらる。(備内) 「人は信用でみない。信義など期待しない」,人間に対する不信,これが韓非の思想の基礎であり,出発点だったのである。(P.100) ◆不信の哲学の上に立つ韓非,およびその継承者たちが,信を置くべきものとしたのは,仁や義といったあいまいな頼りにならない主観ではなく,法・刑罰といった客観的基準であった。法を第一義に,法による統治,法治主義を主張する思想家を法家と称し,韓非はその代表であったこと,いうまでもない。(P.105) ◆「建前と本音」「名と実の使い分け」,これらは今日もわれわれが中国の政治,社会に対して抱くイメージではないか。(略) 『韓非子』の中には「実は与して,文は与せず」といった思考は微塵も見られないし,法律の徹底と断固たる刑の執行を主張してやまない韓非にあって,かかる二元論は断じて認められなかったであろう。しかしながら,韓非思想の神髄ともいえる現実主義,とりわけ現実をそのまま肯定し,それを考えの起点とする現実立脚主義は,「実は与す」を受け入れる余地を以後の中国の法執行において,十分に提供したと考えられる。これは,韓非の徹底した現実主義が韓非思想の不徹底を許容したという,皮肉な変形(デフォルメ)であった。(P.203)
|
【私のコメント】
韓非子の徹底した人間不信には嫌になる。途中でこの本を投げ出したくもなったが,最後まで読み切った。冒頭に紹介される2200年前の「警察調書」は驚くほど緻密,かつ科学的で,これはもう現代の警察官が書いたものとして紹介しても十分通じるほどの驚くべきものである。白秋の「待ちぼうけ」の歌で知られる「守株」の話や,「何でも貫く矛」で「何も通さない」盾をつくとどうなるか,という「矛盾」の話も,実は韓非子が儒家の理論がいかにいい加減なものかを説くための,前置きとして使われた話だったことも紹介されている。『韓非子』は本来『韓子』という書名だったが,唐の韓愈が韓子と称せられるのと区別するために後世,『韓非子』といわれるようになったらしい。
東理夫(ひがしみちお)2010年3月10日第1刷,作品社,ISBN978-4-86182-275-9 C0022
(本文から)
|
◆アメリカでは,「九=ナイン」が不運で悲しみの数であるらしいことが,いろんな曲を聞いているうちにわかってくる。アメリカの歌では,「九」は避けてはいない。むしろ他の数字よりも露出度が高い。そしてそのほとんど,いや,ほぼすべてといってもいいが,不吉で不運で,悲劇の象徴として九という数字が使われているのである。(P.28) ◆アメリカには世界のどの国にもない,独特の音楽ジャンルがある。なぜそういうものがあるのか,長い間不思議でならなかった。(略)それは「殺人」を歌ったものだったのだ。(P.75) ◆(「聖者の行進」は)本来は墓地へ向かう葬送の時に歌われたもので,(略)聖者とは,その葬列に参加している人びとなのだと言われてきた。(略)「我われは先に行った人びとの足跡をたどる旅をする。けれど,その人びととは新しく光り輝く岸辺で再会するのだ」これは何を意味しているのだろうか。「聖者」というのが「死者」であって,彼らが旅立ったあの世で再び会うことができるという,天国で再会を歌っているのだろうか。(略)少なくとも,死んだ後,先に旅立った人びとの仲間に加わって聖者になりたいというほうが,葬列の聖人たちの仲間に入りたいという解釈よりもはるかにわかりやすい。(P.148) ◆どうしてこうも川が問題なのか。川がキーワードであることは,これまで見てきた数々のニグロ・スピリチュアルでわかる。では,その川はどこにあるのか。それはまぎれもなく北部と南部の境界をなす川,オハイオ川なのだ。(P.191)
|
【私のコメント】
著者は作家でブルーグラス奏者。本書によって私がこれまで疑問に思っていた多くのことが理解できた。蒸気ドリルとの競争で勝利を得たものの命絶えた黒人坑夫ジョン・ヘンリー。彼のハンマーはなぜ9ポンドなのか。「クレメンタイン」の靴のサイズはなぜナンバー・ナインなのか? カントリー・ミュージック発祥の地,アパラチア地帯はなぜかくも閉鎖的で貧しいのか。「漕げよ,マイケル」のマイケルとは誰か? 南部の奴隷を北部の自由州へ逃がす秘密組織はなぜ「地下鉄道(アンダーグラウンド・レイルロード)」と呼ばれるのか。「聖者の行進」の聖者とは誰か? 本書はアメリカの「演歌」ともいうべき,カントリー・ミュージックが持つ様々な謎を,その背景を語ることで解き明かしてくれる。アメリカの文化のルーツを理解するには最適の本である。
福永光司,1992年3月25日初版発行,富士通ブックス,富士通経営研究所,ISBN4-938711-01-X C0314
(本文から)
|
◆現在荘子が生きていたなら「皆さんは,神は死んだといいますが,私たちは初めから神を持たなかったのです」と言うでしょう。さらに,神々は生きているのか,もう死んでしまったのかというニーチェに問い掛けに対して,「そう簡単には決められない,コンピューターのファジー理論のように,死んだとか生きたとかいうように一つでは決められない問題を人類は抱えている」と答えるでしょう。(P.44) ◆老子の有名な言葉として,人生の秘訣を問われ”剛強な「歯」となるよりも柔軟な「舌」になれ”と答えたというものがあります。老子の人生態度の基本は,万事に無理せず,負けて勝つ人生を強調している点です。(P.134)
|
【私のコメント】
インパクト指数を計算して,最初間違いではないかと疑った。これまで30代が出たことはない。インパクト指数35ということは,ほぼ前頁にわたって得る個所があるということだ。この本はビジネスマン向けに書かれた本ではあるが,それだからこそ非常にわかりやすく書かれており,道教の真髄を容易に理解することができる。古本でしか入手できなかもしれないが,インターネットなら簡単に手に入れることができよう。
渡辺裕,2010年9月25日発行,中公新書2075,ISBN4-978-4-12-102075-8
(本文から)
|
◆明治政府にとって西洋音楽導入の意味は,決して「芸術」などにはなく,近代国家の構成員たる「国民」の身体や精神を作り上げてゆくツールとしての役割にあったということが実感されます。(P.14) ◆戦前の小学校では,祝祭日にはそれを祝う式典を行うことが義務づけられていました。そのやり方を定めた「小学校祝日大祭日儀式規程」なるものが1892年に設けられ(略)たのです。(略)≪1月1日≫もまた,この「祝日大祭日儀式唱歌」の一つ(略)だったのです。(略)教師用に作られた解説には,この曲の歌詞については「一月一日は一年の元首にしてしかも我国にては神武天皇紀元辛酉の御即位も即ち朔日にましまし…爾来今日に至るまで皇統連綿一日の如く君臣の間その親一家の如くなれば慶賀すべき日なり」などと書かれています。こうなってくるともう,何から何まで天皇に結びつけられているという感があり,すべてが「将軍様」のおかげであるということを刷り込むために算数の教科書にまで「将軍様」が登場する北朝鮮の教科書とほとんど同じようなものです。正月に全国各地の学校でこれを歌うことによって,子供たちは自らが天皇の赤子として今ここに存在していることを確認し,自らの日本国民としてのアイデンティティをあらためて自覚させられたのです。(P.116)
|
【私のコメント】
実におもしろい本である。「唱歌」といえば,「春の小川」「あかとんぼ」など,なんとなくほんわかとした童謡のような歌であるとういのイメージを誰もが持っている。しかしそれが,全く誤りであることが本書の一頁目に書いてある。そこには「夏季衛生唱歌」なるものが挙げられ,「およいだのちはてぬぐひで,からだをきよきふきあげよ。なみかぜたつ日やちゝはゝのゆるしなき日はおよぐなよ」などという歌詞が延々と続く。明治政府は「唱歌」を情操教育としてではなく,国民を啓蒙し,近代国家にふさわしい国民を創出しようという意図で作ったのだ。その証拠に,なんと「郵便貯金唱歌」「栄養の歌」「国勢調査の歌」「火の用心行進曲」…などもある!近代国家にふさわしい国民づくりのために,新しい制度の趣旨や理念を歌で理解させようとしたのだ。明治政府が発足してまだ10年そこそこのうちに「音楽取調掛」を創設したのも,そういう意図があったのである。彼らには「芸術鑑賞」などという余裕は全くなかった。本書には「唱歌」以外にも,「ラジオ体操」「校歌」「県民歌」などおもしろいテーマでこれまで我々が知らなかったことが数多く語られている。
福永光司,1997年5月6日初版第1刷,人文書院,ISBN4-409-4166-0 C0014
(本文から)
|
◆『古事記」に執筆者グループは,この5世紀後半の「九天」における「生神(かみうみ)」を記述した道教教理書を読んでいて参考にしたと考えられます。(P.61) ◆天武天皇は漢の武帝をモデルに国家元首を神とし,宮廷歌人・柿本人麻呂らに『万葉集」で「大君は神にしませば」と歌わせました。この神がどんな神か,となります。この「神」がキリスト教系のゴッドでないことは言うまでもありません。結論を言うと,私は道教の系列の「神」と思っています。(略)「神人」(略)の「神」ですね。この「神人」は古代日本の上皇(退位された天皇)を呼ぶ言葉として用いられていたように,(略)神のような人といえます。(略)人間が修業努力することによって超越的な存在である「神」の境地に達し得たということで,「神」と「人」のうち,基礎はあくまで「人」にあります。(P.68) ◆(上田)秋成がタオイストであったと同じく,(本居)宣長も日本固有の道を「古道」と称して尊んだように,初めはタオイストでした。ただ,宣長は京都遊学以降は儒教の経典解釈学に毒されます。(P.141) ◆彼(岡倉天心)は典型的なタオイストです。本名は覚三で,天心はペンネーム。これは儒教文献にも見えますが,それよりも古く道教経典『淮南子」(秦族篇)に「聖人ハ天ノ心ヲ懐(いだ)ク」などと,5回も使われており,それに基づきます。(P.147)
|
【私のコメント】
本書は1994年~1995年に43回にわたって『中日新聞』に連載された原稿がもとになっている。インパクト指数は最高値を示した。黒住隆興の質問に福永が答えるという形式になっており,非常にわかりやすい。すべての頁が目からうろこの記述となっている。福永の主張を理解するのにはうってつけの本である。
福永光司,1997年1月25日初版第1刷,1997年4月20日初版第5刷,人文書院,ISBN4-409-54050-5 C0039
(本文から)
|
◆神社,神官,初詣などは,日本固有のものと見られているが,果たしてそうなのか。日本の多くの伝統や風習が中国に源があるように,ここにも古代中国の影響がはっきりとうかがえる。(P.11) ◆八幡は,3世紀,蜀の劉備に軍師として仕えた諸葛孔明(181-234)の四頭八尾の八陣図戦法の武勲を象徴する軍旗なのである。(P.14 ◆北魏王朝は,平城を国都とし,皇居を紫宮,その正殿を太極殿と呼んだ。元号には神亀・天平の道教用語を使っている。(略)皇帝の子孫は臣籍降下させて「源氏」の姓を与え,その親衛隊を組織する皇室制度を創設している。(略)これらはいずれも古代日本の天皇家,たとえば聖武天皇や嵯峨天皇などによって採用されている。(P.15)
|
【私のコメント】
しばらく福永光司の著書が続くことをかんべんしてもらいたい。この本は中でも彼の主張を代表するものである。中国北部と南部の文化を「馬」と「船」にたとえるのは,福永のアイデアではない。すでに「淮南子」に出ている。ただこの二つがどのような点で異なり,それがどのような形で日本に入り,現在の日本文化に影響を与えているかは,福永自身の研究成果だ。くどいほど出典・根拠を明らかにする福永の態度はさすがだ。それにしてもものすごい読書量である。しかもそれがすべて古代中国語で書かれているのだ。これまで日本独自と思われてきた日本文化の多くは,中国をお手本にしていた――別に,そのことは少しも恥ずかしいことではない。隣接する国の文化が互いに影響しあうのは当たり前のことである。それをまるで日本で降ってわいたように考えることの方が無理がある。人麻呂は「大君は神にしませば」と歌ったが,この「大君」である天武天皇は,天皇の神格化を漢の武帝から学んでいる。本書は実に説得力のある本である。
福永光司,1982年3月15日第1刷,1985年10月20日初版第8刷,人文書院,ISBN4-409-41021-0 C0014
(本文から)
|
◆神話時代をも含めて古代日本の医学薬学は,大陸の道教医学の受容とともに始まり,この道教医学を主軸として展開しているといっても過言ではない。そしてまた,この事実は,日本の古代における医学医療,薬学,さらに学術・思想・文化一般の問題を考える上にも,かなり重要な意味を持つのではなかろうか。(P.85) ◆「茶道は変装した道教であった」と喝破して,道教――哲学的な道教――を「独立と個性を目的とし,宇宙と共に遊ばんことを願い」,「自然の中に生きんと」する茶の「道」と結びつける岡倉(天心)は,さらにこれを,「禅宗は老子の影響による」と喝破する禅の道と結びつけて次のようにいう。「仏教徒の中で南方禅の宗派は,道教の教義をたいへん多く取りいれていて,凝った茶の儀式をつくりあげた。僧たちは菩提達磨の像の前に集まって,深遠は聖餐の形式で一箇の碗から茶を飲んだ。この禅の儀式が,ついに十五世紀日本の茶道に発展した」(P.177) ◆吾が日本国においては,老荘無為自然の思想は永く「官」もしくは「公」とは無縁の存在であった。欧米の富国強兵を必死に追い求めた十九世紀の後半,明治以後の日本においても,老荘思想が「父を棄て君に背く」虚無頽廃の独善の教,国家の富国に百害あって一益のない“懶”と“慢”と“狂”の哲学と決めつけられる事情に変わりはなかった。(P.191)
|
【私のコメント】
本書は,福永が日本の古代史,神道,聖徳太子,山上憶良,中江藤樹,三浦梅園,岡倉天心等さまざまな人々や事象と,道教との関連について語られている。道教の存在を理解することで,なるほどそうだったのかと目からうろこが落ちる体験を私は何度もしてきた。著者は,自分がなぜ天皇や神道にとりわけ関心を寄せるのかを考えたとき,そこには一兵卒として大陸を彷徨した原体験があると,あとがきに換えた「道教の研究と私」の中に書いている。福永先生は,道教の経典「道蔵」1120冊の読破をライフワークとされておられたが,果たして念願を果たして鬼籍に入られたのだろうか。いずれにせよ,我が国の道教に関する最高の権威を失った痛手は大きい。願わくは,福永光司全集なるものが早急に出版されることを。
田中伸尚,2010年5月28日第1刷,岩波書店,ISBN978-4-00-023789-5 C0036
(本文から)
|
◆宮下太吉の爆裂弾の製造を手がかりに,天皇暗殺を企てたとみなされた幸徳伝次郎(号秋水)ら26人が「大逆罪」で公判に付された事件で,大審院特別刑事部は非公開裁判で,1人の証人も採用せず,わずか1カ月ほどの審理で,11年1月18日に24人に死刑,2人に爆発物取締罰則違反で有機系の判決を言い渡した。死刑判決を受けた秋水や運平ら12人は,判決から1週間後の1月24,25日に縊られてしまった。(略)戦後の諸研究の積み重ねでこの事件は,当時の政府が無政府主義者,社会主義者,またはその同調者,さらに自由・平等・博愛といった思想を根絶するために仕組んだ国家犯罪だった事実が明らかになっているが,敗戦後までは事件の真相は闇の中に置かれていた。(P.3) ◆「諸君,幸徳君らは時の政府に謀反人と看做されて殺された。諸君,謀反を恐れてはならぬ。謀反人を恐れてはならぬ。自ら謀反人となるを恐れてはならぬ。新しいものは常に謀反である」(略)処刑からわずか一週間後,言論弾圧の烈風が吹く中で,一高という限られた場ではあったが,公開の場で公然と「大逆事件」とその裁判を真っ向から(徳富蘆花は)批判したのである。(略)中野(好夫)は(略)「公然と東京の真中で叛徒弁護を行ったのは,ほとんどまず(徳富)蘆花ひとりだった。(略)」と『謀叛論」(岩波文庫)解説の中で激賞している。(P130-131)
|
【私のコメント】
私の尊敬する住井すゑは,小学校の訓示の中でで校長が「大逆事件」に触れ,憎々しげに幸徳らを非難したとき,「いつか幸徳の仇をうってやる」と思ったと書いている。
この「大逆事件」は完全な国策裁判であり,その後の戦争への道の露払いとなったことは今ではわかっている。1972年の「新宮市史」には「大石(誠之助)も成石(平四郎)も,他の死刑囚とともに東京監獄の絞首台で殺された」と記した。刑死や処刑でなく「殺された」と公的な文書に記録されているのである。しかし,100年たった今でも,その関係者について触れることがはばかられているような町もある。フレームアップを行った時の政治家,裁判官,マスコミ,そして無知からとは言え,それらに乗せられて関係者家族を長く差別してきた一般市民たちの罪は重い。
中津燎子,2010年8月4日初版,三五館,ISBN978-4-88320-509-7 C0095
(本文から)
|
◆日本人学校のクラスには数組の混血児がいて,休み時間にはロシア語・日本語・中国語・韓国語・その他見当もつかない言葉が学校中,自由きままにプカプカ流れ,私たちはその中から気に入った「コトバ」を引き寄せて使っていた。語順とか言語の意味をまじめに勉強したわけではなく,音色のいいプカプカ語をただつかみ寄せただけだから,どちらかといえば,口から調子よく飛び出る出まかせ語である。(P.35) ◆私は,子供時代から生きつづけることそのものが私の人生だと感じていた。だからこそ,近いうちに死ぬだろうとまわりで陰口をどんなに叩かれても,生きつづけることに必死に努力した。国の大人やエライさんたちが何を言おうと私は生きつづける。もし,万一,私がアッツ島にいたとしても,泥水を飲み,土に穴を掘ってでも,ミミズとなってでも生きてやる。そういう私は,同じ挺身隊員同士でも,他の少女たちとまったくちがう位置に立っていて,お互いの距離は絶対に埋まらないのであった。私はいまさらながら自分の孤独な世界に愕然となったが,考え方を変えようとは決して思わなかった。どう考えても私は変わりようがなかった。(P.117)
|
【私のコメント】
英語教育者なら,中津燎子を知らない人はいないだろう。『なんで英語やるの?』を読んだ時の衝撃は今でも忘れられない。大学の先生でもない普通のおばさんが,英語学習の本質を述べていたのだ。フィラデルフィアで最寄りのバス停を尋ねた私に,元気のいい黒人女性警官が,「ああ,*パ*ウクサイド・ストリートにあるよ」と教えてくれた。私にはこの「パウクサイド」の「パ」が我々の「パ」の100倍ほど大きく感じられた。日常会話では,英語の「破裂音」は我々の想像を絶するほど大きいのだ。中津はすでにそのことに気づいており,生徒にマットの上を一回転させたあと,起き上がると同時にこの破裂音を発音させる訓練をあみ出していた。
私はその中津が,今や85歳とは知らなかった。彼女は死ぬ前に,これまで自分が無意識のうちに抑圧していた過去の記憶をもう一度思い出して,若者たちに贈ろうと考えてこれを書いたのだ。日本陸軍の下級情報工作員として働いていた父のもとでの生活,父のDV,挺身隊,人間爆弾として特攻訓練に従事した兄,・・・中津の封印していた過去の記憶がこの本には語られている。
宮城谷昌光,2009年5月25日発行,中公新書2001,ISBN978-4-12-102001-7 C1222
(本文から)
|
◆太公望といえば,釣人と同義語になってしまったが,彼は羌(きょう)族という遊牧民族の出身で,魚を獲る術はまったく知らなかったといってよい。(P.27) ◆周王から諸侯として認めてもらえた者には爵号が与えられる。 公(こう),侯(こう),伯(はく),子(し),男(だん) という五爵がそれである。(P.49)
|
【私のコメント】
日本独自と思っていたことが実は中国からの借り物だったということは多い。公侯伯子男の爵位ももとは中国の周からきたものだった。本書は「孟嘗君と戦国時代」というタイトルだが,かなりの部分は戦国時代について語られている。それもまたなかなか面白い内容になっている。
宮崎市定,1963年5月25日初版,1999年4月25日58版,中公新書1989,ISBN4-12-100015-3C1222
(本文から)
|
◆このような貴族のわがままにがまんしきれなくなったのが隋の文帝である。彼は地方政府に対する世襲的な貴族の優先権をいっさい認めず,地方官衛の高等官はすべて中央政府から任命派遣することに改めた。このためには中央政府が常に多量の官吏予備軍を握っていなければならないが,この官吏有資格者を製造するために科挙制を樹立したのである。(P.2) ◆経典の本文から試験問題を出すといっても,実際に出題に適当な個所はあまり多くない。そこで似たような問題がしばしば繰り返して出題される。そこをねらって坊間の本屋が問題解答集を編纂して売り出すのである。これを十分習っておけば,うまく山が当たると労せずしていい成績がとれることがある。しかし,本式の勉強をしていたい悲しさ,もし山が外れた時には手も足も出ないで,試験管が首をかしげるほど不手際な答案を出すのが落ちである。(P.17) ◆(北宋の宰相)王安石は,官吏を採用するのに,ただ試験を行うだけでは不十分で,もっと優れた人材を養成する必要があり,そおんためには根本的な教育からやり直さねばならぬと考え,新たに学校の建設にのりだした。これは当時としてははなはだ進んだ考え方であった。この時代に,都に立派な国立大学を立て,80棟の寄宿舎に学生30人ずつ,合計2400人を収容して授業を行ったという事実はまことに驚嘆すべきものがある。(P.188)
|
【私のコメント】
本書は1963年の初版以来,今日まで版を重ねているロングセラーである。巻頭のびっしりと文字の書かれたカンニング下着も面白いが,私は1~2万人が一度に受験したという南京貢院の写真が面白かった。厩のような個室が延々と続くのである。受験生はここに寝具食料を持ち込み,一週間,問題と格闘するのである。ヨーロッパでは依然として世襲貴族が幅を利かせていたというのに,中国では広く民衆から逸材を発掘するための試験制度が完備していたのである。さらには公立学校を作ったのだ。ただ,教育には金がかかる。勉強は各自に任せ,その成果だけを試験で選抜する方が金がかからない。かくして世界に先駆けての公立学校も,結局はしりすぼみになってしまった。
湯浅邦弘,2009年3月25日発行,中公新書1989,ISBN978-4-12-101989-9 C1210
(本文から)
|
◆孔子の思想を知りうるのは『論語』であるが,それは,弟子や門人たちとの短い問答,あるいは,孔子自身のつぶやきからなり,いわば断片的な言葉の集積である。そこで,孔子の思想の全体像を復元するためには,まず,こうした言葉を整理し,総合的に考えてみなければならない。(P.84) ◆諸子百家の時代,儒家とその勢力を二分したという墨家とは,いったいどのような思想集団だったのか。(略)墨家の首領である「鉅子」の統率により,やがて彼らは精鋭な思想集団,軍事組織へと変容していった。侵略戦争によって落城の危機に瀕した城邑があると,その救援にかけつけ,多彩な守城技術によって弱小国の危機を救った。「墨守」とは,堅い守りの意。墨家の守城能力の高さを賞賛する言葉である。(P.128)
|
【私のコメント】
諸子百家の中に,侵略戦争を嫌い,侵略を受けている弱小国の要請を受けて,守城活動に奔走した思想集団がいたことは知らなかった。兼愛を説くこの思想集団「墨家」は中国にあっては極めて特異な思想であった。しかし諫言しても受け入れない場合は自ら命を絶つという過激性故に,秦漢時代には完全に消滅してしまう。そして2000年後,現代中国で科学技術の先駆者として再評価され,創始者は「科聖墨子」と呼ばれているという。本書は戦乱の世にあって,諸子百家,とりわけ儒家,墨家,道家,法家,孫子について,彼らが何を主張し,民衆にどのような影響を与えたかをわかりやすく説明してくれる。
田中善信,2010年3月25日初版発行,中公新書2048,ISBN978-4-12-102045-2 C1295
(本文から)
|
◆(芭蕉の)深川移住の理由について記した文献がない以上,その理由については推測するほかはない。私もここで自分の推測を簡単に述べておきたい。私の推測はごく単純である。芭蕉の内縁の妻であった寿貞と彼の甥の桃印が駆け落ちをしたからだ,というのが私の推論である。(P.104) ◆芭蕉はきわめて情緒的な人であり,感情移入をしやすいタイプの人であったとみて間違いなかろう。(P.228) ◆漢詩・漢文を読む訓練をした痕跡のない芭蕉が,杜甫の詩を独力で理解することができるようになったとは考えられない。彼が理解できたのは仏頂の教えがあったからであろう。(P.133)
|
【私のコメント】
私は松尾芭蕉については,いわば高僧のようなイメージを抱いていた。しかし本書を読めば,等身大の芭蕉が見えてくる。お笑い好きで,駄洒落を連発しては周囲を和ませる話し好きの男。悲しい話にはすぐ涙ぐむ情緒的な男。甥が内妻を連れて駆け落ちし,大きく人生を変えざるを得なかった男。百姓の出で十分な学問が受けられなかったが,路地の講釈師から得た知識等を最大限に活用して自らを磨いていった男。そんな愛すべき芭蕉を本書は描き出してくれる。芭蕉がますます好きになる本だ。
ベン・シャーウッド著,松本剛史訳,2009年6月10日初版発行,講談社インターナショナル,ISBN978-4-7700-4118-0 C0030
(本文から)
|
◆何か予期しないことが起こると,人はどう反応すればいいかわからなくなる。自分の経験や予測と一致しないためだ。だから何もしない。指示があるのを待つ。そしてしばしば命を落とす。(P.101) ◆今度,空の旅をするなら,出口から五列以内の座席に座るようにすること。脱出プランを記憶に刻み込んでおくこと。そしてこれがおそらく最も重要だ――リラックスしようと心がけること。(P.126)
|
【私のコメント】
これはよくある「サバイバル本」ではない。恐ろしい事故を生き延びた人びとにインタビューをし,何が生死を分けたのかを科学者の意見を聞きながらまとめたものである。題名に「クラブ」とあるが,別のそのような会があるわけではない。そうした人びとに共通するものは何かを分析したということだ。この本にあるが「誰もがサバイバー」である。冷静な判断があなたの命を救う。自らの命だけでなく家族や周囲の人びとの命を救うためにも,是非読んでおきたい本だと思う。
野中広務,辛淑玉著,2009年6月10日初版発行,角川oneテーマ21 A-100,ISBN978-4-04-710193-7 C0295)
(本文から)
|
◆2001年4月の頃だったけれども,ある新聞社の記者が僕に手紙をくれたんです。手紙には,こんな内容のことが書かれていた。<麻生太郎が,3月12日の大勇会の会合で「野中やらAやらBは部落の人間だ。だからあんなのが総理になってどうするんだい。ワッハッハッハ」と笑っていた。これは聞き捨てならん話だと思ったので,先生に連絡しました>(略)私自身が亀井君に確認したら,「残念ながらそのとおりでした」と。(P.163)
|
【私のコメント】
麻生氏の「差別発言」については2005年2月の衆院総務委員会で民主党議員が質問したことがある。麻生氏は「そのような発言をしたことは全くありません」と否定したそうだ。朝日新聞の坪井ゆづる氏がその発言の場にいた約10人の議員に取材したところ,2人は「差別発言はあった」と認め,残りは否定したという。(2009年6月29日朝日新聞「差別発言はあったのか,なかったのか」)私は2005年の時点でこの問題をもっときちんと取り上げ,真偽を明らかにしておくべきだったと思う。本書は,魚住昭氏の『野中広務 差別と権力』(04年,講談社)と併せて読むとおもしろい。
(本文から)
|
◆本体から万物が生じ,もしくは,神がこの世界を造ったとしても,その本体なり神なりはさらに何ものによって造られたのか。(略)一切存在は神が造ったものでも,本体から生じたものでもなくて,おのずからにして生じたのである。おのずからして生じたものはおのずからにして変化する。(略)おのずからという思考は神や本体を原因とし,万物をその結果とする因果的な思考を破砕する。万物はただ自生自化するのである。(P.133) ◆賢愚美醜の区別や対立は必ずしも絶対的なものではない。(略)美を価値あるもの,醜を価値なきものとして差別し対立させるのは,人間の愛憎好悪の主観的な判断にほかならない。物それ自体は人間の主観的な判断を超えて,美でもなく醜でもなく,したがって,また,美でも醜でもあるのである。(略)一切存在はあるがままの姿において本来斉(ひと)しい。(P.144)
|
【私のコメント】
福永光司(ふくながみつじ)氏の『老子』(朝日選書)はこの種のものでは最高の本であるとどこかで読んだので購入したが,まだ机の脇に置いたままである。無知ながら私は彼を新進気鋭の学者と思っていたら,なんと1918年の生まれで,私の死んだ父より6歳年上であった。福永氏は2001年に亡くなっている。本書はなんと60版というから,超ロングセラーだ。インパクト指数は私の記憶では最高点。実に得るところの多い本だった。「生きること,死ぬこと」に深い関心のある私は,とくにこの本の著者自身による「あとがき」が印象に残った。福永氏は子どもの時,母から「裏山の曲がりくねった松の木をどうすればまっすぐに見られるか」と問いかけられ,答えに困ったという。私は同じ話を一休禅師が言ったということをどこかで読んだ。福永氏は幼いころから死というものにこだわり,兵隊として中国でそれこそ死線をさまようが,その中にあって彼は「荘子」を読んだという。
荘子は,宋の国に生まれた。この国は殷を征服した周によって殷民族の子孫にお情けで与えられた弱小国家であった。絶えざる戦乱の中で泥まみれの現実と苦闘しながら,荘子は独自の思想を打ち立てる。それが「荘子」である。
現在,挫折や失望で心が弱っている人にはぜひ本書を読んでもらいたい。
(本文から)
|
◆曹操の人物採用方針は,終始一貫,一芸一能あれば足る,である。逆に言えば,万能は求めない。人格者たることを求めない。あることに有能でさえあれば,金にきたなくても,女たらしでも,親不孝者でも,卑怯でも陰険でもかまわない。これが曹操の新しいところである。特に,不孝者でもいい,というところは革命的新しい。 (P.336)
|
【私のコメント】
高島さんの本は誠におもしろい。また,わかりやすい。何度もいうようだが,「わかりやすい」文章が書けるということは,頭のいい証拠だ。たとえばサイモン=シンという科学ものを書く人がいるが,この人は非常に難しい物理学のテーマなどでも実にわかりやすく書く。そのことの深く知っている人が必ずしもわかりやすい文章が書けるとは言えないが,しかしわかりやすく内容のある文章が書ける人は,必ずその分野について深く理解している人である。三国志に興味のある人,この本はおすすめ。
(本文から)
|
◆とっておきのトリックをあなたに仕掛けてみたいと思います。自分で体験することができますので,必ず実際にやってみてください。(略)一度だけ大きく深呼吸して,次のページの図1のイラストを十秒間見つめてください。さらに今から,ゆっくりと口にだして,5まで数えます。それでは頭の中で,1から5の間の,どれか一つだけ数字を思い浮かべてください。(略)もう一度その数字を強く思い浮かべたら・・・本書の177ページをご覧ください。(P.153)
|
【私のコメント】
皆さんがもし,上記のような指示に従って「4」という数字を思い浮かべたとします。そして117ページをめくってみるとそこに「あなたの思っている数字は,確実に4です。」と書かれていたら,どう思いますか?
私は軽いめまいが生じるほどの衝撃を受けました。私の思い浮かべていた数字は確かに「4」だったのです!
本書は,なぜかくも「振り込め詐欺」の被害者がいるのか,なぜ人はいとも簡単に騙されてしまうのかについて,奇術師の立場から書かれています。私は同じ著者によって書かれた同内容の本(タイトルは異なっていた)をすでに一読んでいたのですが,再度読んでもおもしろかった。読んで損はしない本です。ちなみに,上記の件は,魔術でも,トリックでもなく,ただ単に「確率」の問題だったのです。
(本文から)
|
◆「われわれにとっては,今ここで投降するか,あるいは終戦の日までこのまま頑張るか,二つに一つしか道はない。貴様たちはどの道を選ぶか? 副長は,前者,つまり投降を選ぶと言っている」 兵たちの視線がいっせいにさっと私に集中した。私はぎくっとした。つぎの瞬間,何が起きるか,ピストルを握る私の掌はじっとり汗ばんだ。卑怯者め! 私は佐藤大尉の青白い横顔をにらみつけた。彼は自分の採る態度には一言半句もふれずに,いきなり私を兵たちの判断の前に突き出したのだ。(P.185) ◆自らの意志で投降したインテリ捕虜たちには別の論理があった。彼らにとって前線では数十万の兵隊たちに,あるいは餓死を,あるいは明日なき戦いを強制し,本土では彼らの愛する家族,故郷を戦火のるつぼに巻きこもうとしている一握りの軍首脳部の操る日本はすでに彼らが死を賭してまで守るべき祖国ではなくなっていたし,もともと大学出の兵士にとっては天皇のために戦おうという意識など,はじめから持っていなかった。いや,むしろ「天皇陛下万才」といって,無為に死んでいったジャングルの中の兵隊たちのことを思うと,天皇制への疑問というより,ふつふつたる怒りさえ覚えていた。(P.299)
|
【私のコメント】
この文庫本の表紙には日本兵が背の高いアメリカ兵にタバコの火をつけてもらっている写真が載っている。私はこの写真と「投降」というタイトルを見て,この本はおもしろそうだと思った。内容は期待以上のもので,一気に読んだ。こうした経験は久しぶりだ。慶応を出て戦艦大和の暗号兵となった海軍中尉が,運命のいたずらで小さな隊を率い餓えながらルソン島の山中をさまよう。桜の如く散ることを,生きて虜囚の辱めを受けずの戦陣訓をたたきこまれた兵たちが意味のない死を迎えている中で,彼は投降を決意する。そして早く戦争を終えねばならぬと考える。本当の愛国心とは何なのかを考えさせる本である。残念ながら筆者は平成14年に亡くなっている。しかし,こうして書物の形で我々に戦争とは何なのか,本当の勇気とは何なのかを教えてくれている。
(本文から)
|
◆スパイ要員として厳選される者は,イングランド,否,ヨーロッパ屈指の名門大学である,12世紀創設のオックスフォードや,13世紀創設のケンブリッジの在学生か卒業生だった。(略)つまり,これほど由緒ある特権階級の家柄の出であれば,あえて祖国に弓を引かないだろうし,加えて「オックスブリッジ」の卒業生であれば,教養や外国語などの優れた即戦力を当てにでき,やがて官・政・財界にも幅広い人脈が期待できるようになるからである。これこそ,現在に至るまでのイングランドの世界戦略を担う秘密情報部の揺るぎない伝統であり,「紳士だからこそ,汚い仕事に手を染めることができる」という,パラドキシカルな矜持なのである。(P.11) ◆(サマーセット・モームは)第二次世界大戦直後,アメリカのCIAの創設に関して,MI6のベテラン工作員として,大統領のアドバイザーの一人となる。ことほどさように,モームは,第一次大戦から第二次大戦直後までの重大な歴史の展開点に関与したのだった。(P.106)
|
【私のコメント】
かのシェイクスピアの師匠であったクリストファー・マーロー,「ロビンソン・クルーソ」の生みの親ダニエル・デフォー,ボーイスカウトの創設者ベーデン・パウエル,「人間の絆」のサマーセット・モーム,「第三の男」の作者グレアム・グリーン・・・・若き日にこうした人々の作品に触れなかった者はいないだろう。だが,この人たちは皆,大作家はカバー(偽装)であり,その実スパイとして(今風に言えば「インテリジェンス」)活躍していたというのだ。ウォールト・ディズニーも「赤狩り」の時代には反共スパイとして活動していたというし,有名人であればあるほど,秘密工作員として活動しやすいのかもしれない。本書には,ジェームズ・ボンドのモデルの話も出てくるし,なかなか面白い。
(本文から)
|
◆哲学者は自殺しない。なぜかは知らないが名をあげた哲学者で自殺をしたものはいない。この点も作家や芸術家とはちがう。多分,ひとつには,あまり若いうちに,すごい哲学思想を生みだすというのはむずかしいためである。哲学は年季が必要なのである。(略)60を超えてから自殺するなんてのは,なんとなくばかみたい,という気持ちが生まれるのではないか,と思う。(P.24)
◆1)俺はたしかにナチスだったよ。それでなぜ悪い。こういう対応もありうる。
|
【私のコメント】
下に挙げた「エピソードで読む西洋哲学史」があまりにもおもしろかったので,同著者の前著を買ってしまった。多少重複するところもあるが,これもおもしろかった。「エミールと少年探偵団」を書いたケストナーが,あれほどナチスに加担したハイデガーは許せないと言った。大戦中,ケストナーの著書はナチスの手で焚書の憂き目にあったのだ。一方,ハイデガーはヒトラーに傾倒し,とうとう自ら軍服をきてチョビ鬚をたくわえ,ヒトラーそっくりの格好をして写真を撮らせている(このコーナーで紹介した『ナチスと民族原理主義』にその写真が掲載されている)。
(本文から)
|
◆よく考えてみよう。もしイエスが神であるとすれば,「生まれた」というのはおかしくないか?神が生まれるのか?神は物事を生み出す原因であり,それ自身は何からも生まれるものではない。生まれたとすれば,神を生んだもの,つまり神以上にすごいものがあることになるのではなかろうか。あるいは,イエスが神で,神を生んだのがマリアとすれば,マリアのほうが偉いのではないか?(略)ともかく,三位一体説はかなり問題のある理論なのである。しかし,めちゃくちゃであろうとなかろうと,イエスが神だ,とするのがキリスト教である。イエスは神でない,とするとキリスト教の存在理由がなくなってしまう。(P.16) ◆キリスト教徒の中には,幽霊が夜中に教会や墓場を歩いているという人がいる。しかし,何で無形の幽霊が服を着ることができるのか?おまえさんたちはアホか?どうして,形のない幽霊が墓場を歩くことができるというのか?こう問いつめると,彼らは,「いや,現世的にではなく,霊的に歩くのだ」とごまかす。「<霊的に歩く>とはどういう歩き方か?」と問えば,彼らは何も答えることができないのであった。これが神についてのホッブスの哲学である。(P.66)
|
【私のコメント】
著者は,上のような口調で実にわかりやすくそれぞれの哲学者の考え方や生き様を描いてくれる。あまりにもおもしろくて一気に読んだ。それぞれの哲学者の主たる考え方とその弱点が実にわかりやすく書かれている。見事な「ガイド」の案内で西洋哲学史ツアーが楽しめる。難しい哲学用語は一切ない。ここまでわかりやすく書けるのは,著者自身がそれぞれの作品を深く読みこんでいるからであろう。
(本文から)
|
◆当時の日本政府は「中華」という呼称を嫌い,わざわざ「大支那共和国」という独自の呼称を案出し,それを公文書のなかで使った。日本側の言いぶんは,中華民国の英訳名は「チャイナの共和国」なのだから,日本人にもこの呼称を使う権利がある,というものだった。中国人が日本人にだけ「中華」という尊大な呼称をおしつけるのは不公平だ,という気持ちである。中華民国政府は,これに対して何度も抗議した。しかし日本政府は,1930年まで「支那共和国」とか「大支那共和国」という呼称を使いつづけた。なおかつ日本人は,国名としての「中華民国」を承認したあとも,「中国」「中国人」という呼称を使わず,「支那」「支那人」という呼称を使った。中国人は,同じ漢字文化に属す日本人が,「中国」という自称を認めてくれぬことに屈辱を感じた。これが,ボタンの掛け違いの始まりだった。(P.199)
|
【私のコメント】
加藤徹氏の本は「京劇」「漢文力」「西太后」「漢文の素養」といずれも読んだがすべておもしろい。彼のスタンスは常に是々非々である。現代中国の欠点についても鋭く批判する。今回の本書の主眼は,近くて遠い隣国同士ではあるが,互いに国家やマスコミなどの「タテマエ」の報道に惑わされるのではなく,そこに見えない民衆の本音を見落とすなという警告である。私は本書の最後の方で語られているエピソードに感動した。――1966年,文革の嵐が吹きすさぶ中国で,京劇俳優宋宝羅(そうほうら)が群集のターゲットとなっていたとき,群衆の中から二人の人間が現れて,あたかも宋宝羅を荒々しく引きずり回すように振る舞いながら,昏倒寸前の宋を群集の暴力から守り支えていたというのである。
(本文から)
|
◆彰子自身が読む本なら急いで作る必要はない。ならばこれ(源氏物語)は彰子の物ではない,内裏にいる誰かに,里帰りからの手土産として贈る品だ。では贈る相手は誰か。それを問題にした研究者は実は必ずしも多くない。が,目に入った限りでは,数少ない論のすべてが一条と考えている。(P.227)
|
【私のコメント】
この本はとてもおもしろかった。一条天皇をめぐる二人の后定子と彰子。この二人が同時に入内したことはなかったが,前者に清少納言,後者に紫式部と双璧が控えていた。道長との関係など,「源氏物語」が誕生したときの背景が非常によくわかった。さらには,当時の閣議である「陣の定め」においては,位の低い者から順に意見を述べることになっていた――位の上の者から意見を述べると,位の下の者は遠慮して反対意見が言えなくなるからである,とか,当時は「一種物(いっすもの)」といって,参加者各自がそれぞれに酒肴を持ち寄る,いわば「ポトラック・パーティ」があったなど面白い記述も見られる。
(追記)著者の山本淳子氏(京都学園大准教授)はこの本によって,2007年11月にサントリー学芸賞を受賞した。
(本文から)
|
◆『黙示録』を専門の神学者とメディアに精通した説教師と少数の狂信者のためだけの奇書として切り捨てるわけにはいかない。現実に,権力と影響を持つ人間が『黙示録』を,神の手引書とまでは言わぬまでも,現実世界の戦争や外交や政治を遂行するための霊感の源と見なすようになっているのだ。666という街路番号を持つ建物に入る時,ロナルド・レーガンはその悪魔的な住所を改めるように主張し,リビアにおける何ということもない事件を,聖書の予言の成就と見なしたのである。(P.35)
◆『黙示録』ほど,西欧史上の幾多の社会的・文化的・政治的闘争において,「言語の武器庫」として利用されてきた書物はない。(p.36) ◆<オウム真理教>と呼ばれる日本のカルトは,仏教,ヒンドゥー教,道教,それに「『黙示録』の予言と少々の反ユダヤ的陰謀論」の奇怪なごたまぜを信じていた。教祖である麻原彰晃は,ハルマゲドンが迫っていると説き,自家製の生物科学兵器を備蓄させた。1995年,彼らはその兵器の実施試験として神経ガスであるサリンを東京の地下鉄に散布し,12人を殺害,数千人に障害を負わせた。(P.301) |
【私のコメント】
イエス,パウロ,ヨハネらはいずれも終末は「すぐにも起こるはずのこと」と見なしていた。しかし本書の著者は,『黙示録』を書いたのはこのヨハネではないという。2000年近く前,ユデア地方の戦争難民で,小アジアの町から町を放浪していたカリスマ説教師(当時この手の人々が男女を問わずかなりいた)がパトモス島で神秘的法悦のトランス状態に達し,そこで「見た」奇奇怪怪なヴィジョンを記録したものではないかという。この書は他の福音書とあまりにも異なっている。他の福音書には「愛」があるが,この書にあるのは何かに取りつかれたような扇動とグロテスクな描写である。トマス・ジェファソンは「単なる狂人の戯言に過ぎない」と言い切り,バーナード・ショウは「麻薬中毒患者の幻覚の興味深い記録」と言っている。キリスト教会側もこれまで何度かこの異様な書を新約聖書から除こうとしたが,果たせなかった。さらに悪いことには,この書が世界中の様々なカルトに信者獲得の手段として利用され,テキサス州ウェイコでの悲劇的な事件へと発展することもあったということである。本書の原題は A History of the End of the World。著者はアメリカのコラムニストでニューヨーク大学の非常勤講師。
(本文から)
|
◆運命を賭けた大勝負が吉と出るか凶とでるか,不安のあまり緊張で押しつぶされそうになる瞬間。こうした瞬間を,ローマ人は「ディスクリメン(discrimen)」と呼んでいた。(略)「ディスクリメン」には,「運命の分かれ道」という意味の他に「境界線」という意味もある。そしてルビコンこそ正真正銘の「境界線」だった。これを越えたカエサルは,世界中を戦争の渦に巻き込んだばかりか,昔から守られてきたローマの自由を葬り,その残骸の上に君主政を打ち立てたのである。(P.6)
◆一人の支持者が思い切って,いつまで暗殺隊を野放しにしておくおつもりですかと尋ねてみた。それから急いでこう言い添えた。「あなたが罰したいと思っている人の名簿を見せてください」。スッラは,ニタリと笑って「そうしよう」と言うと,名簿をフォルム(須賀注:広場のこと)にはり出した。なんとそこにはマリウス政権の主要人物が一人残らずずらりと並んでいるではないか。しかも全員死刑。財産は没収し,その子と孫は公職への立候補を禁ずるとある。名簿に載っている人物を助けようとした者も,同様に死刑。早い話,ローマ政界のエリート層が,スッラの独断であっというまに丸ごと死刑者リストに載せられたのである。(P.134) |
【私のコメント】
本書は,カエサルがルビコン川を渡ろうとするところから始る。そしてそれまでのローマ共和制の歴史を振り返り,最後にまたカエサルのルビコン川の話にもどる。そして「ブルートゥス,お前もか」を経て,オクタウィアヌスの代で終わる。しかし,本書は教科書風の無味乾燥な記述ではなく,「こんなすごい遺産は,これまで見たことも聞いたこともない」というような文体で書かれているので非常に読みやすい。本書が2003年にイギリスで出版されると各方面から絶賛され,2004年には優れた歴史ノンフィクションに与えられるヘッセル・ティルトマン賞を受賞している。ただ,忍耐力のない私は後半は読み飛ばしてしまった。^_^;
(本文から)
|
◆「正確に言うと,きみはひとつだけ誤りをおかした。上陸したらすぐに,自分の拳銃でビリーの眉間を撃ち抜くべきだった。アメリカ人は,誰も反対はしなかっただろう」
「次からは忠告に従うよ」私は答えた。(p.210)
◆「私は彼を愛しています」ジョアンはあっさりとその言葉を口にした。
|
【私のコメント】
第二次大戦の末期,敗北目前のドイツはUボートでアメリカ本国にスパイを送り込んだ。マンハッタン計画による原爆製造の実態を探ろうというのだ。結局愚かな相棒のためにFBIに捕まり,一時は絞首刑寸前までいったが運良く免れ,その後アルカトラズを始めいくつかの刑務所で10年間を過ごす。この本は,数奇な運命をたどった男の実体験である。一気に読めて面白い。
(本文から)
|
◆私は司令官棟に座って口述を筆記している。彼は口述中も窓の外に取り付けられた鏡で,建物の前方一帯を見渡している。突然彼が立ち上がり,壁にかけられた銃の一丁をとり,すばやく窓をひらく。数発の銃声が響き,あとはただ悲鳴が聞こえるだけ。電話のために中断したあと口述をつづけるときと同じ口調で,デスクに戻ったゲートが尋ねる,「どこまでだったかな?」
それ以前もそれ以後も生涯で何度となく耳にした同じく冷静な口調の同じ言葉。それ自体は無色透明のこの言葉が,60年以上経ったいまものあのときの出来事の一齣一齣を私の心の鮮やかに蘇らせるのです。(P.61)
◆「下等人間――手足に頭脳らしきもの,目,口を備え,生物学的に外見上は人間とそっくりのこの自然創造物は,しかしながら,まったく異なる恐ろしい生き物であり,あともう少しで人間になりそうなほど,人間に似た容貌をもってはいるが,しかし精神的,心情的にはどんな動物より下にある。この人間の内部には野獣的で放縦な情熱のひどい混沌,名状し難い破壊意志,原始的な欲望,剥き出しの卑劣さがある。下等人間――まさにそのものなのだ」。
◆シンドラーがありのままのシンドラーでいてくれたことが幸いだったと思います。あれほど軽率で,あれほど勇敢で,あれほど大胆で,あれほど酒に強く,あれほど恐れを知らないでいてくれたことが。戦争前にも戦争後にも特別の仕事を成し遂げなかった彼が,その妻とともに救出作戦を実行し,そのおかげで直接間接に今日,世界中に散らばっている配偶者と子どもたち,孫たちと暮らす6000人の人々がいるのです。それが大切なことなのです。それ以外は重要ではないのです。(P.166) |
【私のコメント】
インパクト指数は低いが,それは本書が自伝的側面を持つからにすぎない。著者は「プワシュフの屠殺人」のいう異名を持つ殺人鬼クラクフープワシュフ強制労働収容所司令官アーモン・ゲート直属の囚人速記者として,540日間死と背中あわせの中で仕事をしつつ,自分の職務で知りえた情報を他の多くのユダヤ人を救うために利用するのである。そしてついにはオスカー・シンドラーと出会い,彼のリストに入れらてホロコーストの時代を生き延びる。映画「シンドラー・リスト」にも彼の役を演じる人が登場する。「そうはいってもシンドラーは女道楽だったのではないか」という人に対して彼はこう問いかける。「溺れかけた自分を勇気を持って救出しようとしている人に,『ちょっと待った。あなたは奥さんを裏切ってやしませんか』などという人がいますか?」
ナチはなぜかくも簡単にユダヤ人を殺すことができたのか――それは繰り返し繰り返し流され続けた反ユダヤ宣伝戦略や教育の結果である。このことは『ナチと民族原理主義』に詳しい。
(本文から)
|
◆清の選秀女(后選び)の最大の特徴は,秀女(后妃候補)を八旗の女子に限定したことである。(略)これによって,清の皇室が圧倒的多数の漢民族に同化して呑み込まれる事態は防がれた。こう書くと,選秀女は清朝にとって理想的な制度のようだが,副作用もあった。清の歴代の后妃はおおむね不美人であった。(略)若き日の西太后は,清の歴代后妃の平均からいえば美人だった。(P.39-40)
◆臣下どうしを対抗させ,臣下の勢力を分散すること。これは中国の政治の常道であった。晩年の毛沢東も,周恩来と林彪,四人組らを互いに闘わせることで,自分の権力を維持した。道光帝は厚く信頼していた林則徐を,更迭したのちに復権させた。咸豊帝が恭親王を,毛沢東が鄧小平を失脚させたのち復権させたのも,みな同じ理由である。勢力が特定の臣下に集中することを避けるため,わざと失脚させて調整したのである。(P.103) |
【私のコメント】
この本は単なる西太后の伝記ではない。むしろ清という国が実は現代の中華人民共和国の原形となっていることを示す実に興味深い本なのである。西太后がどうして権力を握るようになったのか。なぜ独裁を40年以上も続けることができたのか。中国という国の政治のメカニズムを理解するのに大いに役立つ。「今の」中国を知るためにも是非読んでいただきたい。
(本文から)
| ◆ふと,バリケードの隅の暗闇で何かが動く気配がした。よく見ると,毛布にくるまった男女がセックスをしている。注意深く観察すると,そこここで,毛布や寝袋に入った男女がセックスをしているのがわかった。私が驚いている様子を見て,あごひげ外交官が言った。「そろそろ緊張が限界に達しているのだよ。緊張が高まると子孫を残したいという本能が刺激されてものすごくセックスがしたくなる」(P.292) |
【私のコメント】
出版して4ヶ月もたたないうちに,はや第4刷が出ていることからも本書がいかに読まれたかがわかる。名前は聞いていたが,読んでみるとやはりおもしろかった。佐藤氏がどのようにしてソ連で人脈を広げて行ったのかがよくわかる。ただ,全くの下戸である私にはウオトカを数本空けるなどということを聞いても想像ができない。肝臓の悪い私など,一口飲んでも卒倒するだろう。もちろん,著者はウオトカだけで信頼を勝ち得たのではない。同志社大学大学院で学んだ神学が物を言ったのだ。人生何が役に立つかわからない。あとがきに,著者が宮崎学とソ連崩壊について研究をしたとある。ここにも宮崎が出てくるとは。
(本文から)
| ◆財産と名声,そして豊富な人脈をもつ上流階級に生まれたゴールトンは,すべての特権を当然のこととして受け入れながら成長した。加えて彼は,彼ほどの幸運に恵まれなかった人たちに対し,自分の特権的地位を平然と行使することでも有名だった。上流階級の人間は,生まれながらにして一般庶民よりも優秀である。そう信じたゴールトンは,低い階級の者の懸命な努力が自分の利益になると思えば,生得の権利としてその成果を無断で奪いとった。(略)ゴールトンにとって,ヘンリー・フォールズは無名のスコットランド人医師にすぎなかった。対して(略)ハーシェル家に与えられている貴族の肩書きも,ゴールトンには魅力的に映ったのかもしれない。こと指紋研究に関しては,フォールズのほうがはるかに重要かつ貴重な実績をあげていたにもかかわらず,どこまでもエリート主義者のゴールトンは,ハーシェルと手を組むことにした。(P.144) |
【私のコメント】
本書は「指紋を発見した男」ヘンリー・フォールズを主に書かれた本である。指紋が科学捜査に使われるきっかけを作ったのが,開国まもない日本に医療伝道者としてやってきていたイギリスでは無名に近いスコットランド医師ヘンリー・フォールズだった。しかし,彼の業績はフランシス・ゴールトンをはじめ,スコットランドー・ヤードからも死ぬまで無視され続ける。彼の復権は死後57年後の1987年,ふたりのアメリカ人指紋検査官が共同墓地の片隅にフォールズの墓を発見してからである。
私は前々から,チャールズ・ダーウィンの従兄弟にして,顔つきもそっくりな男,フランシス・ゴールトンが嫌いでたまらなかった。ダーウィンがジギル博士なら,ゴールトンはハイド氏であろう。この男ほど「傲慢・陰険・卑劣」といった言葉が似合う者はいない。統計学もやるので,ある程度頭もよかったのかもしれないが,人格的にはダーウィンと比べることすら失礼である。「優生学」の創始者であるこの男の考えが,ナチスの断種法にも影響を与えたことは否めない。本書の中には,共にアフリカを探検した仲間を平気で裏切り,一人栄誉を手にして平然としている彼の姿も出てくる。彼は同じことをヘンリー・フォールズに対してもやったのである。指紋とは関係ないが,フランシス・ゴールトンの人となりを知る上でもおもしろい本である。
(本文から)
◆わたしは九州は熊本市内の熊本駅近くにある韓国・朝鮮人集落で生まれた。韓国名,姜尚中。日本名,永野鉄男。後者の「通名」が,わたしの思春期までの名前だった。「鉄男」から「尚中」に変わるまでに20数年の歳月を要したのである。(P.23)
◆[指紋押捺拒否をめぐって]「(略)だから姜さん,今あなたが犠牲をこうむる必要はないんです。だれもそれを求めることはできないし,求めてはダメなんです。姜さんがこんなふうに悩まなければならない状態を作っているわたしたち日本人にこそ,問題があるのですから」。土門先生の言葉は,わたしの心に深く染み入った。(P.154 [ ]は須賀)
【私のコメント】
状況は異なるが,この本を読んで私は松本清張を思い,宮崎学を思った。宮崎の「近代の奈落」の解説をなぜ姜尚中が書いているのかと一瞬思ったが,やはり共通するものが互いにあったのだろう。日本で自らの出自を隠した力道山や大山倍達,逆に韓国に戻り,日本での憲兵としての過去を隠した姜の叔父。国を越えて生活をする人々は大なり小なり,自らのアイデンティティを自らの生き方とどう折り合わせていくかに苦悶するのであろう。
(本文から)
◆彼ら(ネオコン)はニューヨーク市立大学出身のトロツキストグループなんです。学生時代から世界革命の思想を持っています。ただし,それはマルクス主義に基づく世界共産革命ではなくて,世界自由民主主義革命なんです。つまりネオコンというのは,独裁者や悪い奴はやっつけて,普遍的な一つの理念で世界を統一していいこうという革命家たちなんです。(P.66)
【私のコメント】
「ネオコン」とは「Neoconservatism」(新保守主義)のことで,ブッシュのイラク政策を理論的に支えている人たちである。「民主党くずれの保守主義」「ユダヤ系」「トロツキスト」が特徴ということだ。
『国家の罠』で佐藤優は知っていたが,よくテレビで見かけた手嶋がこれほど情報通なのは知らなかった。日本もインテリジェンスの専門家を育てていかないとこれからの情報戦略では負けるという内容である。今は外務省から干されている佐藤が今後どういう形で復帰するかが楽しみだ。
(本文から)
◆大逆事件は,1910年5月15日に検挙がはじまり,6月3日に起訴は7名にとどめる方針が採られたかに見えた。ところがその直後,5日に捜査は一転して拡大方針に転じ,それから熊野・新宮グループの大石・高木らが検挙・起訴されている。(略)どうも権力側が熊野・新宮という土地柄じたいに何か異物性を感じていたのではないか,という気がする。やつらは,こういうところには割合と敏感なのである。そして,それに関連して大きかったのは,やはり被差別部落への予断にもとづく警戒心だったのではないか。(P.237)
◆その親父が1967年に死んだ。葬式のとき,兄貴が,ワシ,ずっと気になっておったんやが,親父は部落の出身と違うやろか,と言いだした。(略)Nというその男は,スリの元締めである。(略)そのNが,もうええやろ,といって,話をしてくれた。「学チャン,オヤジさんは,たしかに部落のもんや。そして,スリの頭目やったんよ」(略)そうとわかっておれば,こんな中途半端な生き方はしなかっただろう。それが,残念だったのである。(略)もう,遅いのか,中途半端でない生き方をするのは――。いや,いまからでも遅くはない。俺は,これから,部落民として生きていく。ここで,そう宣言することによって,この終章は私の序章になるであろう。(P.451)
【私のコメント】
この作品は2002年11月解放出版社より刊行されたものである。作者はさまざまな被差別部落をたずね歩き,かつて部落解放に尽くしながらも,今や忘れ去られた過去の人物を再発見する。私は自分が和歌山県出身ということもあり,特に大逆事件で検挙された熊野・新宮グループに関心を持っていたので,この話のところがおもしろかった。また,最終章で,著者が父母が隠していた事実,すなわち父が被差別部落出身であったことを知るという驚くべき展開がある。「文化人」でなく「生活者」であることを目指す著者だが,いつもその筆力には舌を巻く。インパクト指数そのものは小さいかったが,部落問題に関心のある人には本書を勧める。
(本文から)
◆エルヴィスの独特の体の動かし方は,南部の黒人に特有の,体の内側から出てくるような自由な身振りだった。(略)エルヴィスは「骨盤(ペルヴィス)エルヴィス」というありがたくないニックネームがつき,彼こそが若い白人男女を救いようのない堕落に導いていると思う大人たちにとって,まさしくエルヴィスの踊り方は脅威であった。エルヴィスを呪わしく思う連中は彼を「白い黒人(ニグロ)」と呼んだ。それほどエルヴィスは黒人の身体表現を吸収していたともいえる。(P.30-31)
◆集団作業のときに全員が声を合わせて歌う仕事唄は,1865年に南北戦争が終わって奴隷制度が廃止され,奴隷労働に支えられていた大農園(プランテーション)が少なくなるにつれて自然消滅しつつあった。それに代って聞かれるようになったのが「野唄(フィールド・ハラー)」で,これは集団ではなくひとりかふたりで働くときに歌う,叫び声にも似た唄である。(略)この野唄にリズムを刻む楽器が加わったときにブルースが誕生したと考えられるが,それは1890年から1900年にかけてのころと推測されている。
【私のコメント】
インパクト指数がずば抜けて高いことが本書の良さを示している。本書は,この手の本にありがちな自己陶酔的で他のものにはよくわからないマニアックな本ではない。日本人の頭にもすっと入るような内容である。なぜブルースの発祥地が「ミシシッピー・デルタ」であり,ジャズの発祥地が「ニューオリンズ」でなければならなかったのか,またエルヴィスが当初なぜあれほど白人から嫌われたのか――こうしたことが実にわかりやすく説明されている。アメリカのTV番組「エド・サリヴァン・ショウ」はアメリカを中心に各分野で人気のある人をゲストに招待していたが,プレスリーが出演したときは彼の上半身しか写さなかった。
本書は音楽だけでなくアメリカの歴史を知る上でも非常に参考になる。日本人にわかりやすく書かれているのも道理で,共著者はいずれも早稲田の現役の教授である。
(本文から)
◆元来アメリカは,国家も国民も未完成な状態から出発した。いわば人為的な集団統合を宿命づけられた実験国家である。現実にはまだ達成されていない理念を掲げて出発した理念先行の国家なのである。
◆アニタ・ヒル事件とO・J・シンプソン裁判は,黒人男性と白人女性という組み合わせに対して,アメリカ社会がいまだに神経を尖らせている様子を浮き彫りにした。また,こうした偏見に対して,黒人男性の側が,自分は差別の犠牲者だと開き直ったことは,アメリカの人種対立の根深さをかえって印象づける結果にもなった。差別があれば,その差別を逆手にとって自分の立場を有利にしようとする,二つの事件に共通する”戦術”は,性と人種をめぐる呪縛からアメリカ社会がまだ解き放たれていない様子を物語っているのである。
【私のコメント】
若者の間に麻薬が蔓延している現状が一方でありながら,どうしてあれほど未成年の喫煙や飲酒に厳しいのだろう――アメリカにいたときにこうした矛盾をいくつも感じた。この本はそうした疑問に答えてくれる。ヴィクトリア主義の厳しい性道徳がある一方で,奴隷主は奴隷に次々と子どもを生ませる。暴力に対してあれほど厳しい態度をとりながら,銃規制には反対する。一見矛盾しているようでありながら,彼らには彼らの論理があるのだ。妊娠中絶は殺人とまでいう意見がある社会で,なぜ銃によっていとも簡単に人が殺されているのか。今や唯一の超大国となってしまったアメリカにこうしたダブルスタンダードを気づかせるためには,国際社会がアメリカに対して「論理的」に説得していく他ないのではないかというのが著者の結論である。
(本文から)
◆1935年後半,ヒトラーが全面的方向転換と呼んだ後をうけて,新しい学術研究機関が,どうにもならないユダヤ人の他者的性格について,実証的解明なるものを次々と提供した。引用や図表,脚注,あるいは参考文献目録をつけて,学術的な体裁をととのえたいかさま記事やレポートが,悪名高いナチのメディアに代って,信用のおけそうな「ユダヤ情報」をせっせと供給してくれたのである。強まりゆく迫害を見て,良心に痛みを感じているかもしれない人々に対して,ユダヤ人の同義的退廃に関する一見客観的な情報が,安心感を与え,道義的責任の伴う共同体からユダヤ人を追放するうえで,一役かった。1933年時点で,「理性的」反ユダヤ主義の提案者にとって,ユダヤ人の脅威についての信用ある証拠はなかった。1930年代中頃に始まる似非(えせ)科学の研究は,在来型の学者からお墨付きを得て箔がつき,誇り高くて傲慢なフォルクの中にいるユダヤ人を異邦人化した。
【私のコメント】
ヒトラーはクーデータのように武力で政権を勝ち取ったのではなかった。民主的選挙によって選ばれて首相になったのである。だがかろうじて過半数を勝ち取ったあとのヒトラーは実にたくみに世論を反ユダヤ主義の方向へ導いていった。そこには日本の戦前と同様に巧みなブレーン(イデオローグ)がいた。ヒトラーはあからさまなユダヤ人迫害は大衆の賛同が得られないと悟るや,トーンを落としてフォルク(民族)の純潔のみを語るようになった。一方では上記のようなもっともらしい客観性を装った反ユダヤ情報が大衆に毎日のように与えられ,ファッション雑誌にさりげなく挿入される反ユダヤ主義記事や,講習会,教材などの提供という形でが何度も何度も繰り広げられる反ユダヤ主義キャンペーンなかで,大衆の中に「なるほどそれほど悪いユダヤ人なら迫害されてもやむをえないな」という集団心理を作り出していったのである。
ホロコーストへの道を作った代表的イデオローグは3人。哲学者マルチン・ハイデガー,憲法学者カール・シュミット,神学者ゲルハルト・キッテルである。この3人はゲッペルスに匹敵する役割を演じ,その分,罪が重い。ハイデガーの友人だったカール・ヤスパースはハイデガーのナチへの信奉ぶりを次のように書いている。
「あいさつしようとハイデガーの部屋へ行った。開口一番私が『まるで1914年の時のようだね・・・』と述べて,「人を惑わす大衆陶酔が再び・・・」と言いかけると,ハイデガーは「我々は哲学がめざすゴールを隷属の中にみる・・・総統はこの意志を民族全体に呼び覚まし,それをひとつの意志に融合された。総統が己の意志を示される時,何人といえど不参加を決め込むことはできない。ハイル・ヒトラー!」
ハイデガーはとたんにしゃんとなり,そうともそうともとうなずくのである。私は二の句がつげなくなった。あの陶酔感に彼自身がひたりきっており,その姿を目のあたりにして,私は,道を踏みはずしているよとは言わなかった。以来私はさま変わりした彼の人格を全然信用しなくなった。私は,ハイデガーの参加している暴力を考え,身の危険を感じた。」
この本は立花隆の「天皇と東大」と同様,世論というものはたやすく操作されやすいということを教えてくれる。若い人にはぜひ読んでほしい本だ。
(本文から)
◆(野中は)政調会長の麻生のほうに顔を向けた。
「総務会長に予定されておる麻生政調会長。あなたは大勇会の会合で『野中のような部落出身者を日本の総理にはできないわなあ』とおっしゃった。そのことを,私は大勇会の三人のメンバーに確認しました。君のような人間がわが党の政策をやり,これから大臣ポストについていく。こんなことで人権啓発なんてできようはずがないんだ。私は絶対に許さん!」
野中の激しい言葉に総務会の空気は凍りついた。麻生は何も答えず,顔を真っ赤にしてうつむいたままだった。
【私のコメント】
「彼(野中)はうっすらと涙をにじませた目で私(著者)を睨みつけながら言った。
「君が部落のことを書いたことで,私の家族がどれほど辛い思いをしているか知っているのか。そうなることが分かっていて,書いたのか」(略)
「ご家族には本当に申し訳ないと思っています。誠心誠意書いたつもりですが・・・これは私の業なんです」
著者はエピローグでこのようなことを書いている。権謀術数の中で町長から首相一歩手前まで言った政治家の成長過程を書いた本である。表面上はひどく対立していたよに見える蜷川(元京都都知事)と野中であるが心の底では互いに尊敬し合っていたということも本書には描かれている。この本は友人から紹介された本だ。私はふだんこうした政治がらみの本は好まないのだが,これはおもしろかった。
(本文から)
◆幕末の洋学の中心となった蕃書調所であるが,これを中心になって組織していったのが,誰あろう,実は勝海舟である。勝海舟は,当時小普請組に属していた微禄の下級武士にすぎなかった。それが,なぜそのような大役をになうことになったのかというと,ペリー来航に際して,勝が老中に提出した意見書によってである。ペリーが来航したとき,これにどう対応すべきか,良策に窮した幕府は,誰でもよいから,いい考えがあったら述べてみよと広く呼びかけた。(略)勝海舟は,(略)軍事面に広く及ぶ具体的な提案を行なっていた。(略)勝はこの提案で一躍幕府中枢の注目を浴びるようになるのである。(略)この提案書に示された見識がかわれて,勝は(略)蕃書調所の設立準備委員のような役目をおおせつかった。(略)こうしてみると,東京大学のいちばんの基礎作りをしたのは,勝海舟であったといえるだろう。(P.42)
◆阿部猛『太平洋戦争と歴史学』(吉川弘文館)は,こんなエピソードを紹介している。
「平泉の言動については,多くの人びとの証言がある。昭和のはじめ学生だった中村吉次は,平泉の自宅で卒業論文の計画を問われ,漠然と戦国時代のことをやるつもりだと答えると,平泉は『百姓に歴史がありますか』と反問したという。意表をつかれた中村が沈黙していると,平泉はさらに『豚に歴史がありますか』といったという。」
【私のコメント】
立花隆は「いったいなぜ戦時中に日本全体があれほどまでファナティックになったのか」,そのわけを知りたいと思った。そして調べていくうちに二つのキーワードに集約されることを知る。それは「天皇」と「東大」である。上巻は,まともなことをいいながらも次第に体制に合わせて方向転換していく東京帝大初代学長加藤弘之,徹底して中央に入ることを嫌った福沢諭吉,東大教授で右翼イデオローグ上杉慎吉から五・一五事件までが語られる。下巻は滝川事件の仕掛け人である「奇怪な人物」蓑田胸喜の天皇機関説(美濃部達吉)攻撃,東条英機が心酔した皇国日本最大のイデオローグ東京帝大教授平泉澄(きよし)などと続く。
確かに,この本を読むとなぜ「天皇と東大」なのかがよくわかる。得るところの多い本であった。一つのテーマについて書くのに,数メートルにおよぶ資料図書を読むという立花ならではの緻密で説得力のある筆遣いである。難解な資料も読者にわかりやすく説明してくれている。今,この本を読まずしてどうするという気持ちがする。大部であるが買って得をした気分になる本だ。
(本文から)
◆モントゥリオールが潜水艇の意義を初めて論じたとき,その論拠は世界の労働者階級の少なくとも一部,すなわち珊瑚採りの潜水夫の生活を改善するということにあった。P.118
【私のコメント】
1859年は日本では安政の大獄の翌年にあたる。そのころスペインのカタルーニャ地方でユートピアをめざす若き革命家が世界初の本格的潜水艇イクティネオ号を完成した。全長17メートル,排水量72トン,潜航深度30メートル。推進力用のスクリューは人力で回された。彼はさらに,8時間もの潜航を可能にする酸素発生装置・二酸化炭素除去装置を開発した。それまでのナンセンスな潜水艇とことなり,彼は海洋学,気象学,化学,物理学,工学といった分野をマスターすることから始めたのである。世界初の潜水艇は「珊瑚を採るため」であり,戦争のためではなかった点が面白い。もっとも,資金を得るため彼は魚雷開発など戦争目的へ次第にシフトしていく。
(本文から)
◆新穂大尉は力強い口調で,「よく来てくれた。大いに歓迎する。お前たちは死んでも靖国神社へはやらない。七度人間と生まれて,皇国に尽くす覚悟で働いてくれ。しかし,神機関は普通の部隊と違う。決して死んではならん。どんな時でも絶対に生きて帰れ。お前たちが生きて帰ってこそ,情報を得ることが出来るのだ。それが我々の使命なのだ,ということをよく肝に銘じておけ」と,軍人とは思えないような肩肘はらない訓示をされ,私はすっかり感激してしまった。
【私のコメント】
陸軍衛生兵として徴収された著者が,運命のめぐり合わせで特殊工作班神機関に配属されニューギニアで作戦を展開する。そして結果的には一発も発砲することもなく,終戦を迎える。現地に溶け込み,餓死者が続出したニューギニアの奥地を転進しながらも上官の命令どおりに生きて帰ってきた。この本は,結局はその人の人格や品格がものをいうのだということを教えてくれる。戦後60年の今,戦争の記憶を持つ世代が次々と鬼籍に入りつつある中で,貴重な本と言える。
(本文から)
◆(筆者は,第二次世界大戦)当時,学校やメディアで見聞きすることは,何でもかんでも熱心に信じていた。たとえば,ドイツ人はみな悪魔であり,日本人はみな卑劣で油断できない。それに対してアメリカ人はみな品格があり,正直でフェアな精神の持ち主であり,信用できる。そう考えていたのである。(p.i)
◆あなたは『コンシューマー・レポート』誌を調べて,修理回数が最も少ないのは明らかにトヨタ車であることを知る。(略)車を買いに行こうとする前夜,あなたはディナー・パーティに出席し,居合わせた友人の一人にそのことを話す。すると彼はいぶかるような様子で答える。「それ本気?僕の従兄弟が去年トヨタ車をかったんだけど,ホントに故障続きだよ。(略)」『コンシューマー・レポート』誌が行ったランキングが,トヨタ車の所有者1000名に対する調査に基づいたもとだとしよう。そうすると,あなたの友人の従兄弟の不幸な経験は,サンプル数を1001名に増加させたことになる。(略)論理的に考えると,このことがあなたの決定に影響を及ぼすはずはない。(略)しかし,たいていの人は,多量の統計データよりも,一つの鮮明で身近な事例の影響を強く受けるものなのである。(p.150)
【私のコメント】
原題は "Age of Propaganda"。著者は二人ともカリフォルニア大学の教授で,一人は消費行動およぼ説得技法の専門家であり,もう一人は世界的な社会心理学者である。ビジネスから戦争・社会体制にいたるまで,あらゆる場面で用いられている情報戦略が紹介されている。本書を一読することで,いま身の回りで行われている様々な宣伝活動や宗教勧誘に対する免疫ができることだろう。本書の最終章には「カルトの教祖になる方法」が載っている。なぜあのカルト集団があのような行動をとったのかが,これを読むことで納得がいくはずだ。
(本文から)
◆19世紀末期のクラカトア噴火のころ,状況はがらりと変わる運命にあった。その大噴火のような悲惨な出来事が何回か起き,それが一つのきっかけとなってイスラム教正統派が勢いを取り戻し,19世紀のジャワは,イスラム原理主義や闘争心,異教徒に対する激しい敵意を軸に一変する。 (p.53)
◆これ(クラカトアの大噴火)は世界についての,そして同時に世界に向けて語られた,ほんとうに大規模な自然現象の前例のない物語だった。(p.224)
【私のコメント】
19世紀後半に東南アジアの小さな島で起きた火山の大噴火。本書はただ単にそうした出来事を記録しただけのものではない。副題に「世界の歴史を動かした火山」とある通り,1883年に起こったクラカトア島の大噴火は,社会的には東南アジアにおけるイスラム原理主義台頭の引き金となり,地質学的にはウォーレスをプレートテクトニクス理論の一歩手前まで導き,情報科学的には海底ケーブルで地球の片隅の出来事が世界が共有するニュースとなりうることを示す契機となったのである。448ページという大著であり,オックスフォード大学で地質学を専攻した著者だから,地質学的説明にどうしても力が入るため,こうしたことに興味のない人にはつまらないかもしれない。ただ,ジャワ島近くの小島の大爆発がその後の世界の動きに大きな影響を与えた事実は,私にはとても面白かった。
(本文から)
◆ナチズムとは,アーリア人種の優越という概念を抱き,ハンディキャップのある人々を貶め,抹殺するというだけのものではなかった。領土を拡大し,ユダヤ人とジプシーを殺戮する,というだけのものでもない。ナチズムは,こうした概念を極端に推し進めたものではあったが,と同時に職を創出し,街を清潔にし,「ドイツ民族の生殖性」を長期的に管理しようとする運動でもあった。(p.12)
◆ドイツ国民の肉体はドイツ国家の資産なのだ。そして国家はすなわち総裁と同一なのだから,当然国民の身体は総裁に属する,という論理は宣伝ポスターなどで繰り返されたものである(「おまえの身体は総裁のもの!」)。
【私のコメント】
この本は「そうはいうけどナチスにもいいところがあったんだよ」などということを主張する本ではない。むしろ逆である。ナチスはユダヤ人を虐殺する一方で,ガンの予防,合成着色料を使わない自然食を提案し,反アルコールや反タバコ運動を国策として推し進めた。しかし,それはなにも国民一人一人の幸福を考えたものではなく,国民を「国家に奉仕する労働力」と考えてのものである。たとえそれがどんなに良いと思えることであっても,それを国是として全国民に押し付け強制することがいかに危険なことかを本書は教えてくれる。ちなみに,ヒトラーは肉食を避け,酒やタバコもたしなまなかったそうである。こうした健康国家ナチスをパロディー化したと思われる本に「チョコレート・アンダーグラウンド(アレックス・シスラー著,求龍堂,2004)」がある。
(本文から)
◆エリックは立ち止まった。そして,ぼくをまっすぐに見つめた。「ブルックス,おまえのことは嫌いじゃない。ここから離れろ。家に帰るんだ」(略)それからさらに何度か,ピシッという音を聞いた。(略)その瞬間,恐ろしいことが起きていると気づいた。
【私のコメント】
マイケル・ムーア監督の「ボウリング・フォー・コロンバイン」に,Kマートでの拳銃販売を止めるように訴えるコロンバイン高校生の集団がいた。この本の著者はその中の一人である。1999年,コロラド州リトルトンのコロンバイン高校で起こった二人の高校生による銃の乱射事件では,13人の生徒・教師が犠牲になった。この本は,その犯人のエリックとディランと友人であった生徒によって書かれたものである。この事件の背景には陰惨ないじめがあったこと,郡警察が著者のブルックス・ブラウンを容疑者扱いしたため家族は一時は「村八分」の状態に陥ったことなどが書かれている。合衆国の高校では昔から体育系(特にアメフトやバスケット)選手が尊ばれ,あまり運動が得意ではない生徒を「おかま」と馬鹿にしていじめる傾向がある。「知力より体力」という風潮はいわば社会規範となっており,そのいじめの陰湿さは日本と同じである。なぜコロンバイン事件が起こったのか――そこのところを考えないと今後も校内での銃の乱射事件は続く――著者はこう主張する。
(本文から)
◆まずはユダヤ人を発見し特定しないことには,資産没収,ゲットーへの封じ込め,強制移送,そして最終的には殲滅,といったこともできない。ドイツ全土で――そして後にはヨーロッパ全土で――共同体,教会,および政府の記録を何代にもわたって調べることは,膨大な相互参照作業となるため,コンピュータが必要であった。しかし1933年当時に,コンピュータは存在しなかった。(略)しかし,別の機械なら存在した。IBMのパンチカードとカード選別システム――コンピュータの先駆である。(p.16)
◆私はこれまで長いあいだ歴史家が解明してこなかった,一つの疑問にとらわれていた。ドイツ人は常にユダヤ人の名簿を持っていた。ある日突然,恐ろしい形相のSS(親衛隊)の一団が街の一角に乱入し,名簿に載っている者は明日東方への移送のため駅に集合するように,との通達を張り出していくのだった。しかしその名簿をナチはどこで手に入れたのか。何十年ものあいだ。誰にも分からなかった。疑問を呈した者も少なかった。答えは,IBMドイツの人口調査システムと,類似の高度な人口計数・登録技術である。(p.18)
【私のコメント】
著者の母は絶滅収容所のあるトレブリンカに向かう貨車から脱走して,銃で撃たれ,浅い共同墓穴に埋められた。父はユダヤ人の列から逃げ出して歩いているとき,雪の中から母の足が突き出しているのを見つけた。奇跡的に母は生きていた。二人は飢えとナチの弾圧の中を生き延びた。1993年,著者はワシントンの米国ホロコースト博物館で,偶然IBMのホレリスD-11カード選別機の展示品を発見する。そして,いっしょにいた両親に「私がもっと多くのことを明らかにしてみせる」と約束するのだった。
この本は,堅く口を閉ざすIBMからの協力が得られないまま,インターネットを利用し,膨大な資料から次々とIBMが何をしてきたかを明らかにしていく。著者は「IBMがなくてもホロコーストは起きただろう」という。しかし,もしIBMがナチスへのパンチカードの提供を中止していたら,600万人ものユダヤ人が絶滅させられることはなかったのではないか。少なくともこれほどの規模にはならなかったのではないか。これは単にIBMだけでなく,それを見て見ぬふりをしていた時の米国政府機関,さらにはIBM社長ワトソンと密接な関係のあったハル国務長官やルーズベルト大統領にも責任があるように思える。600万人がお金のために殺されたと思うとやりきれない。
(本文から)
◆当時にあっては,処刑人一族は,不吉な影に包まれた呪われた一族であり,世間から隔離された状態で暮らしていた。バリア,不可触賎民の扱いだった。P.8
◆軍人に,あなたの職業は何かとたずねていただきたい。私と同じように,人を殺すことだと答えるでしょう。それだからといって,軍人を避けようとする人はいませんし,一緒に食事をして名誉を汚されたと思う人もいません。軍人において誉められることが,なぜ私の職業では嫌悪の的になるのでありましょうか? P.42
【私のコメント】
断頭台で,かよわい女性の首をめがけて無表情に斧を振り下ろす死刑執行人をみて,民衆は残酷な奴だと思う。彼らには,この執行人がどれほどの苦しみをなめているかがわからない。こうした理不尽さは,どの時代を通しても存在してきた。
この本は,貴重な資料にもとづいてフィクション風にかかれている。筆者の筆さばきのうまさに,感嘆してしまった。ギロチンの斜めの刃はルイ十六世自身が提案したものであるが,結局彼はそのギロチンで命を落とすことになる。歴史を別な角度から見るこの本は,おすすである。
(本文から)
◆すゑの母さとは,草履売りや農繁期に手伝いに来る被差別部落の人を見ては,「部落に生まれた人は可哀相だ」と,顔を曇らせる優しい女であった。父岩次郎は,明治四十年に幸徳秋水等によって刊行された『日刊平民新聞』を読み,「幸徳は偉いやっちゃ」と言いながら,家族達に幸徳秋水の話をしたりした。
◆彼女は,童話の他に,民話,イソップ童話,劇とあり,理科物語まである。「橋本四郎」という男名で探偵小説まで書いた。
◆櫻本富雄の矛先は,あくまで住井すゑの戦争責任に向けられ,対談は噛み合うことがなかった。住井すゑは,櫻本に素直に答えているのだ。しかし,それは無責任でもなければ,卑劣でもない。彼女は,「私,『橋のない川』を書くことがいっさいの自分の反省であり,もう,ここにすべてを書き込めると思って始めたんですけどね」という決意で,『橋のない川』を執筆しているのである。これ以上の反省があるだろうか。
【私のコメント】
この本を本日書店で手にしたが,家に帰りいっきに読み終えてしまった。
それまで懸賞投稿で常連のように賞品を獲得していた少女が,ついに大人の『文章世界』という雑誌にまで手を伸ばしてきたことから,博文館は投稿者は男性ではないかという疑念を抱き,奈良県まで社員を派遣する。この社員が後の住井すゑの夫となる犬田卯(いぬだしげる)だった。本書にはこうした,これまで知らなかった住井すゑのエピソードがたくさん述べられている。
私は,当時まだ封建的な色合いの残る奈良県の田舎でどうして彼女のような人間が育ったのか不思議でしょうがなかった。本書を読み,やはりある程度は父母の影響があったことがわかった。
老齢に鞭打って「橋のない川」を執筆している住井すゑに対し,彼女が戦争中に体制擁護の文章を書いたことを皮肉った新聞があったが,そのいきさつも書かれている。彼女の態度は「橋のない川」が示している。一方,書店に一歩足を踏み入れると,そこには彼女とは正反対の論理で書かれた本が山積みされている。
(本文から)
◆いっぽうには運転手つきの自家用車や,ボランティアの慈善活動がある。そしてまずしい僻村におもむくため,だれに強いられたわけでもなくウィーンを去るウィトゲンシュタインのすがたがある。もういっぽうには,赤貧に直面したポパーのすがたがある。この乖離の深さを理解するには,アレーガッセにあったウィトゲンシュタインの実家をおとずれてみる必要があるだろう。(注 ウィトゲンシュタインの生家は『宮殿』と呼ばれていた)
◆だれか(ラッセルだったか)の声がきこえた---「ウィトゲンシュタイン,その火かき捧を床におきたまえ」。(略)(ウィトゲンシュタインは)音節ごとに,それにあわせて突き,突き,突く。「ポパー,君はまちがっている」。突き,突き,「まち・がって・いる!」。
【私のコメント】
1946年10月25日の金曜日の夜,ケンブリッジ大学のモラス・サイエンス・クラブの会合でカール・ポパーとルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタインが哲学の問題とはなにか,について激論を交わし,真っ赤にやけた火かき捧を手にして,二人とも自説をゆずらなかったという伝説がある。この「格闘」には様々な異説があるのだが,いずれにせよ,この10数分間の激論というクライマックスを目指して,この本では二人の生い立ちから説明から始まる。そしてついには,二人の人生が交差する激論の10数分間へと突き進んでいくのだ。実に知的刺激に満ちた本である。
(本文から)
◆この四人の原住民をイギリスに連れ帰ったらどうだろう。英語を覚えさせ,畑を作って収穫することや,家を建てることを教えるのだ。キリスト教の基本的な教義を教え込むことができるだろう。そのように仕こんであとでまたここに連れ戻せば,彼らは習い覚えたたくさんの知識を仲間たちに伝えるだろう。(略)船室の中でこのように考えていくうち,フィッツロイはすっかり落ち着いて,気分が良くなった。(p.51)
◆彼(ダーウィン)がそうしなかった(20年間進化論を公にしなかった)大きな理由は,反論の余地のない確実な証拠を集めてから発表しようと決心していたためであるが,理由はそれだけではなさそうだ。宗教への信心がころほど敬われ,賞賛されいた時代(ビクトリア時代)にあって,もしその理論を発表したらどうなるか,彼にはよくわかっていた。(p.163)
【私のコメント】
未開人を文明国イギリスに連れ帰り,教育をした後,再度野生に返す。そうすれば彼らが未開の地において文明の伝達者となるのではないか---いかにも独善的なこうした考えをビーグル号の船長フィッツロイは「善意」から考えついた。ただ,我々はフィッツロイの行為を当時の文脈の中で考えてやらねばならないだろう。
ダーウィン自伝には,このフエゴ・インディオについての話が出てくるが,ここまで詳しくは書かれていなかった。イギリス文明を垣間見た3人のインディオのうち,年少のジェミーは自国に帰されたものの,白人宣教師たちの虐殺を指導した嫌疑がかけられる(本人は否定)。
かつてノーベル平和賞を受賞したデズモンド・ツツ主教が「白人の宣教師がアフリカにやってきて,『さあ,みんな目を閉じて神に祈りましょう』といった。黒人たちは素直に目をつぶった。しばらくして彼らが目を開けてみると,彼らの土地はすっかり白人たちのものになってしまっていた」と述べた。自分たちを一段高いところにおき,「未開人」を「導いてやる」のが使命と考える人たち。本人たちは「良いことをしている」と信じているが故に,性質が悪い。本書の著者が虐殺のところを描く場面ではつい白人の立場に感情移入していまっている感がなきにしもあらずであるが,ダーウィンとフィッツロイのその後の人生を比較する上でもおもしろい本である。
(本文から)
◆演壇に立ったロングは,かならず手始めにその街一番の金持ちを痛快に罵倒してから演説を始めるのだった。(略)そうした「わかりやすさ」と親密さのなかに,ヒューイ(・ロング)はときおり彼らの理解のおよばない話を少しだけまぜることを忘れないのであった。”あの男こそわれわれの仲間だ。でもわれわれとは違う,やってくれる男だ”。聴衆はこうしてロングこそは「民衆のリーダー」に相応しい人物だと感じたのである。(p.21)
◆<民主主義>の形式を遵守しながらその実質を骨抜きにすること。これが<ファシズム>台頭の方法である。そうして民主主義を必至に追い込み,最後の一手で息の根を止める。ドイツのヒトラーもイタリアのムッソリーニも,そうやって”合法的に”独裁制を敷き,当の議会制を無力化した。この点においてキングフィッシュ(注 ヒューイ・ロングのあだ名)は,かれらヨーロッパのファシストとすこしも変りはなかったのである。(p.46)
【私のコメント】
この本は,一介の訪問販売員から身を起こし,弁護士,ルイジアナ州知事,連邦上院議員そしてついには大統領の座をねらった男ヒューイ・ピアス・ロングの物語である。ただのアメリカン・ドリームと違うのは,彼は(本心は別として)常に大金持ちや巨大権力に立ち向かう貧しい民衆の味方というスタンスを保ちつつ,大衆(特に貧困層)の絶大な支持を背景に,自分に権力を集中させる無茶苦茶な法案を次々と可決させ,州議会を骨抜きにしながら,巧にルイジアナ州を私物化していったという点である。著者は「ファシズムは豊かな国が貧しくなったときに出来る」と述べているが,我が日本はどうなのだろうか。今の時代だからこそ,この国ではほとんど知られていないロングという男の生き方(最後には暗殺される)を知ることは意味がある。
(本文から)
◆ある人物が不正義である場合,より悪い行為をなさないうちに殺してやることは,不正義によって被害を受ける人々にとってはもちろん,その不正義をなす人物にとっても,それ以上の悪をなさなくてもすむので,救済であり,むしろ慈悲だ,という発想に基く行為である(これを「度脱(どる)」という)。
◆密教だけが見出しうる特有の発想であり,かつヒンドゥー教がいまだ手をつけていない領域はないか。この問いの果てに密教が発見したのが,「性」という領域だったらしい。
◆性行為という,人間にとって最も根源的であり,誰しも避けては通れないものであるにもかかわらず,いやそれゆえにこそ,世界中のあらゆる宗教が忌避してきたもの,誰の目にも,俗の中の俗としか見えない行為,それこそが,人間を,わけても汚濁にまみれた末世の人間を,解脱や悟りという聖のきわみへと,いわばジャンプ・アップさせる唯一の方途なのだと後期密教経典は説き,インド亜大陸のそこかしこに,熱狂が渦巻いた。
【私のコメント】
空海は密教をもたらしたと学校で習った。実は密教には「前期,中期,後期」とあり,日本に入ったのは主に「中期」の密教であった。後期密教はいわゆるタントリズム(性行為を修業に導入したもの)であり,幸い(?)日本には一部例外を除いて普及しなかった。
オウム真理教が行った「ポア」(殺人)や指導者と女性幹部との性関係は,確かに我々の目には異常に移ったが,その発想はこうした後期密教やチベット仏教の影響を受けたものだった。仏教がヒンドゥー教やイスラム教に押されてインドで勢力を弱めていく中で,起死回生の手段として打ったのが密教であったが,それが極端な形へと変容し,チベット仏教へと受け継がれていく過程がこの本によく現れている。仏教の全般的な歴史を知るには「仏教のことが面白いほどわかる本」(田中治郎,中経出版,2002)が最もわかりやすい。
(本文から)
◆少女時代,むやみやたらに『人民のために』とか『国を愛してやまない』とかいう恥ずかしくなるほどクサイ台詞を吐いていたのは,それに反する想いが強く,それを振り切るために,あれほど強い調子でスローガンじみたことを言っていたのではないか,と思えてきた。年老いた両親に愛され,いつも良い子であり続けなければならなかったアーニャは,常にその時々の体制に適応しようと全身全霊を打ち込んできた。そのたびに,古い主義をきれいさっぱりぬぐい去っていく。
◆「マリ,国境なんて21世紀には無くなるのよ。私の中でルーマニアはもう10パーセントも占めていないの。自分は,90パーセント以上イギリス人だと思っている」
さらりとアーニャは言ってのけた。ショックのあまり,私は言葉を失った。((略))
「本気でそんなこと言っているの?ルーマニアの人々が幸福ならば,今のあなたの言葉を軽く聞き流すことができる。でも,ルーマニアに人々が不幸のどん底にいるときに,そういう心境になれるあなたが理解できない。あなたが若い頃あの国で最高の教育を受けられて外国へ出ることができたのは,あの国の人々の作り上げた富や成果を特権的に利用できたおかげでしょう。それに心が痛まないの?」
【私のコメント】
著者はプロのロシア語会議通訳者であり,エッセイスト。1959~64年に在プラハ・ソビエト学校で学ぶ。この本は当時の3人の友だちに30年ぶりに奇跡的に出会い,彼女たちがどのように変ったか,あるいは変らなかったかを描いている。ユーモアの中に一本筋の通った筆者の世界観を垣間見ることができる。インパクト指数が低いのは,本書が小説的なエッセイであることによるものであり,本書の価値を云々するものではない。
(本文から)
◆ダライ・ラマという言葉は,いろいろの人にいろいろな意味合いをもって受け取られている。ある人には,わたしは活仏(いきぼとけ)であり,アガロキテシュヴァーラ,すなわち慈悲に満ちた菩薩である。またある人にとっては”ゴッド・キング”。1950年代後半は,全国人民代表会常務委員会副委員長。そして亡命後は,反革命的寄生虫,といった具合である。だが,このどれもわたしの考えるものとは異なる。わたしにとって”ダライ・ラマ”とは,わたしが占めている職務を意味する称号である。わたし自身は一個の人間にすぎず,たまたま,仏教僧たらんとする一チベット人なのだ。
◆たとえわたしが彼(ネール首相)の意見に反発しても,チベットに対する彼の態度に少しも変りはなかったのである。おかげで,彼の言葉にもっと耳を傾ける気になっていった。これは中国とはまるで正反対である。ネールはほとんど笑わなかった。答える前--答えはいつも率直で正直だった--それが彼の癖の,小刻みに震える下唇をちょっと突き出しながらじっと人の話に聞きいっていた。とりわけ彼はわたしが己の良心に従うことに対し完全な自由を与えてくれていた。逆に,中国人は,満面に笑みを湛え,そして騙した。
◆西欧社会の考え方にいくつかの疑念を抱くこともある。その一つは,物事を"黒と白”,”あれか,これか”で考え,相互依存,相対性を無視する傾向である。つまり二つの観点の間には灰色の部分が必ずあるという目が欠けているように思われる。
◆性的欲望を満たすことは,つねに一時的な満足に過ぎないということだ。インドの偉大な学僧竜樹はこういっている。
「痒いから掻く。だが,どんなに掻いても,掻くことで痒みはなくならない。だったら初めからまったく掻かないに越したことはない」
(私のコメント)
私がこの夏(2002年),もっとも感動した本の一つである。ダライ・ラマのすぐれた人柄は以前からわかっていたが,この自伝でそれがさらに深まった。最初の引用にあるように,彼は自分を生き仏とは思っていない。自分の職務への称号ととらえている。それが偉い。日本にあれほど苦しい被害を受けた中国が,日本がやったのと同じことをチベットに対して行っていることにやりきれなさを感じた。チベットへの中国の殖民はすさまじいものがあり,現在ではチベット人の3倍の中国人が入り込んでいる。イスラエルがやっているのと同じことを中国もやっている。チベットの状況をもっと世界が知るべきだと思う。力による征服は結局は崩壊することは歴史が証明している。
 【インパクト指数】4.4
【インパクト指数】4.4
(本文から)
◆スコットランドで犯罪が激減した。理由を探ると,刑務所の入り口に次の看板が出ていた。
「今後,囚人は食事代と宿泊費を払わなければならない」
◆独立した一国としてのスコットランドの歴史は,実に血なまぐさいものであり,この傾向は特に中世において顕著だった。歴代の国王の多くは,あるいは戦いで命を落とし,あるいは謀略によって暗殺された。「暗く陰鬱な日々」とは,この国の歴史を形容してしばしば使われる言葉である。
◆実際,スコットランドの歴史に触れた書物では,必ずといっていいほど,この国の振幅の揺れの大きさが指摘され,その原因としてスコットランド人の気まぐれな性格があげられる。たとえば,戦いに臨んでも,一糸乱れぬ行動をとるというより,勝手な戦い方をして,少し形勢が不利になると,戦場から離脱する兵が多く出るというのである。
◆ハーリーがデフォーに与えた,あるいは示唆した具体的な仕事,それは主に二つのことである。第一は,ハーリーの意図をできるかぎり円滑に実現するために必要な文書を執筆,出版して,世論を思う方向へ導くこと,(略)第二は,(略)要するに秘密諜報員,スパイに一般に要求される仕事にほかならない。
(私のコメント)
イギリスの正式名称は The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland であり,ブリテン島でも西のウェールズ,北のスコットランド,そして南のイングランドの連合国であることは一応理解していた。しかし,スコットランドとイングランドの関係は今ひとつわかっていなかったが,本書によってその関係がかなり明確になった。本書で特に驚いたのは,「ロビンソン・クルーソー漂流記」のダニエル・デフォーと,「ガリバー旅行記」のジョナサン・スウィフトがいずれも時のイングランドの政治家ハーリーの手先となり,世論を思う方向に導くプロパガンディストとして暗躍していたという事実であった。
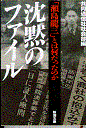 【インパクト指数】1.9
【インパクト指数】1.9
(本文から)
◆「陸軍内部の権力が最も下降したのは1939年8月でした。陸軍省の1課長が実質的に内閣をつくるという前代未聞のことが起きたんです」(略)この急速な権力下降の契機になったのは36年2月に起きた二・二六事件だった。(略)「この時,陸軍上層部はすっかり自信を喪失していた。ある将軍は青年将校が自分を殺しにきたと思い,門を閉じ,部屋に逃げ込むようなありさまでね」
◆「瀬島さんは『大本営命令は第1項に敵情を書かず,ずばり天皇の決心を書く。天皇は敵情などで決心を左右されないからだ』と言った。なるほど大本営参謀は作戦命令を起案することで天皇と同格になり,強大な権限を持つんだと納得したよ」
◆「冒頭に瀬島氏が『日本は自存自衛のために立ち上がった』,侵略戦争ではないと語る場面がありますね。結局この人は戦前は国家,戦後は一転伊藤忠に忠誠を誓い,戦後の賠償を商売の機会にした。なぜああ堂々としていられるのか。驚きですね」
(私のコメント)
下部の者が起案し,それを上部の者が判断するという稟議制は今なお日本の社会のシステムとして働いている。しかし,下部の者が団結し力を持ち,上部の者が部下にきらわれたくないという気持ちが強く働いていると,起案されたものがすべて認められてしまうということになってしまう。こうしたシステムの欠陥は早急に正していくべきであると思う。
国家が重要な事態になっている時に,下部の1官僚が国家全体を動かしていくという恐るべき事態が起こった。戦争責任を考えるときに,この本は新たな視点をなげかけている。
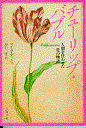 【インパクト指数】6.1
【インパクト指数】6.1
(本文から)
◆チューリップはオランダ原産ではない。そのルーツは東方にあり,想像を絶するばかりに広大な中央アジアの地で生まれた。この花がオランダに伝わるのは,知られるかぎりようやく1570年になってからである。
◆イスラムの教えに命を捧げることは天国行きが保証されることであると信じるトルコ軍兵士は,見渡す限りにチューリップに覆われた楽園で美しい天女を相手に地上ではご法度のワインを嗜む,そんな光景を見て戦闘に生命を投げ出したのであった。
◆もっとも価値があるとされた「最上級」のチューリップは,花弁全体がほぼ白か黄色で,花弁の中央か縁に沿って紫,赤,または茶の斑点が細い縞状に入ったものであった。(略)野生種のチューリップは丈夫ながら,花が素朴で単色であるのに対して,オランダ黄金時代の園芸品種は,なぜあれほどまでに複雑で華やかな模様をなすようになったのであろうか?答えは簡単かつ不気味なものである。花は病気におかされていたのである。(略)人気の新品種はみな,チューリップにだけ感染するウイルスにおかされていた。
◆もっとも珍重されたセンペル・アウグストゥスが急騰したのは当然のことで,1633年の5500ギルダーから,1637年1月の1万1千ギルダーへと跳ね上がった。(略)その金額は1家族の衣食住を生涯の半分にわたってまかなえる金額であり,アムステルダムの運河沿いにある最高級住宅地に建つ大邸宅を,馬車置き場と24平方メートルの庭付きで買える金額であった。しかも,アムステルダムの不動産は当時世界一高かった。
◆パニックはオランダ中に広まっていた。ありとあらゆる街のすべての酒場で,フロリストたちは一日か二日前には何千ギルダーという値で取引されていた球根が,いまやどんな値段でも売れなくなったことに気づいた。
(私のコメント)
この本はバブルがどのように形成され,そして崩壊するかを見事に描いている。本来は中央アジアでひっそりと咲いているチューリップがモザイク病に冒された故に,莫大なお金で取引されるようになる。病気のせいで十分な子孫を残せないことが品種の希少価値を高めていく。たった1個の球根が大邸宅が買える値段で取引される。そしてついにはクズ同然のチューリップまでもが品薄のため高い値段で投機の対象となっていく。民衆はチューリップを鑑賞するためでなく,投機の対象として売り買いしていたのである。そして,クズ同然の花に高額なお金をかけているばかばかしさに気づいたとたん,バブルははじける。この「チューリップ」を「土地」に置き換えると,まさにこれはついこの間の日本ではないか!
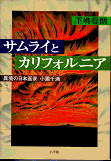 【インパクト指数】3.7
【インパクト指数】3.7
(本文から)
◆鉄棒は大男の頭上に振り下ろされた。気味の悪い悲鳴を聞いた。頭が割れたか,鮮血が迸った。現場監督が飛んできた。たちまち黒山のような野次馬に取り囲まれた。「かかって来い!日本人の血を見せてやる!」千浦は叫んだ。(略)結局「凶器殺人罪」との罪名で起訴されたのである。大事件となった。(略)意外にも被告小圃千浦の証人として,反日排斥の旗手,サンフランシスコ市長がたった。市長はたまたま事件を目撃,千浦の行為の正当性を証言したのである。(略)反日の波高い時しかも陪審員は全員は白い人。死罪の可能性があった。これに千浦は,「アメリカのように自由と民主主義の国で白昼,ジャップと差別し,しかも顔にツバをはきかけられた。私は正当防衛である」(略)これは裁判史上稀に見る大公判となった。(略)「私はレン(国務大臣)に問われるままに迫害の実情を正確に,ありのままに,申し上げました。そして戦うという決意と覚悟について,サムライは辱められたら,名誉の保持のために肉を切らせても骨を断て,と小さいころから教えられております。私はそれを実行しました,と述べました。そのとき言ったレンの言葉が偉いと思います。
『ジェントルマン』
と私に言ったのです。それから
『I understand very well.』
そういって私を慰めてくれたのでした。」(P.95)
◆「白人はある人はライトなのよね。でもほとんどはずいぶん悪かった。それというのも,日本人は殴られても何をされても辛抱したからなのよ---お金を貯めるために来たのだから,もう少しお金を貯めて帰ればいいんだって。アゲインストしないから,白人はもっとやるのよ。だけどパパは決して怯まずに進んでいった。だから白人は私には何も起さなかったし,兄のキムもいじめられなかった」(P.130)
◆千浦がステップに足をかけたこのとき,だれかが歌を歌いだした。それへ数人が加わり,やがて空気を揺るがす大合唱になった。OH,HAVE YOU SEEN THE HEAVEN'S BLUE ... 教え子たちは,カリフォルニア大学のカレッジ・ソング『THE GOLDEN BEAR』の大合唱で,(強制収容される)プロフェッサー・オバタを見送ったのである。<ああ,きみは天国の青をみたのか,天国の青を>はオバタ・ブルーを表した。(P.227)
◆「非常時に芸術が何の役に立つのか?」(略)
「平和を生み出すためには,全ての人に教育が必要なのだ。ことにこのような厳しいとき,創造の努力に積極的に手助けすることは,非常に望ましいと強く信じる。芸術はこの点から,もっとも建設的な教育の形であると感じている。芸術を通して,強調の精神と正しく判断する意思がついてくるであろう。(略)
芸術は何も難しいものではない。なぜなら芸術は万人に備わるものだからである。芸術は芸術家の特権なのではない。ただルック アット ザ ネイチャー! 大いなる自然を見よ!感じよ!これで良いのだ。」(P.236)
(私のコメント)
1885年岡山県井原の小さな旅籠屋の8人目の子として小圃千浦(おばたちうら)は生まれた。5歳で仙台の武士の家に養子に入っていた次兄のさらに養子となる。兄である父。千浦はこの父を憎み,そして尊敬した。15歳でアメリカに渡る。彼が他の日本人と異なっていたのは3点。1つは日本画家として突出していたこと。2つ目は差別を許さず,果敢に立ち向かったこと。3つ目は大の釣り好きだったこと。白人には敵も多かったが,また見方もいた。そして縁あってカリフォルニア大学の美術教授となるも,日米戦争となり強制収容される。しかし,千浦はなんと収容所の中に美術学校を作るのである。
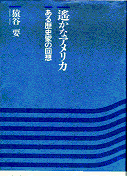 【インパクト指数】4.6
【インパクト指数】4.6
(本文から)
◆自分の国の中の少数派集団(日本人)に対し,これだけはっきりと政府が犯した罪を認めて,正式に謝罪する(日系人強制収容の政府が陳謝し一人二万ドルを支払う)国が他にあるだろうか。そしてまた,声をあげて求めなければ何もしてくれないというのも,この国のデモクラシーの姿を示していたのだった。(P.135)
◆「私はこうしてアメリカという国を研究するために来ているんですが,アメリカも少しは日本を知る努力をしてもいいのではありませんか」
すると彼(アメリカの若い政治学者)はすぐにこういい返した。
「あなたたちはアメリカのことだけを考えていればいいのですが,アメリカ人は全世界を考えなければならないのですよ」
この言葉はひどく傲慢な響きをもっていた。(P.289)
◆新聞の第一面に中曽根首相の差別発言が載っていたのだ。アメリカの黒人やプエルトリコ人,メキシコ人は知的水準が低いという発言である。(略)実は人種や民族の問題こそ,戦後のアメリカ社会が解決をめざして取り組んだ最大のテーマである。生命がけの闘いだったことは,非暴力主義のキング牧師が暗殺された事実だけでも明らかだった。(略)アメリカでは"racist"と呼ばれると,その人の政治生命は終わりなのである。首相の発言はこの微妙な領域へ,ズカズカと土足で踏み込んだ感じだった。(P.290)
(私のコメント)
本書は猿谷氏の自伝的性格も併せもっている。私はこの良心的な歴史家の活動には志満夫人という存在が大きな役割を果たしていることを知った。民族主義が血で血を洗う状況の中,さまざまな問題を抱えながらも多民族国家アメリカがどこまでやっていけるのだろうか。アメリカ合州国は,時には単純で傲慢で暴力的な国ではあるが,一方,少数ながらも必ず良心的に行動する人がいる国でもある。
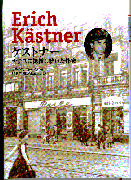 【インパクト指数】1.3
【インパクト指数】1.3
(本文から)
◆ベルリンのスポーツパレスで,アマチュア・ボクシング選手権が開催されたときのことだ。勝者が表彰されるたびごとに,観衆は立ち上がって,片手をまっすぐあげて,ヒトラー式のあいさつをしながら,ドイツの国家を歌った。観戦にきていたケストナー一人だけが,その場にすわったまま,じっとしていた。《ボクシングの試合がひとつ終わるたびに,観衆のぼくに対する関心は,ふくれあがっていった。(略)》(p.179)
◆《ぼくのやったことは,いや正確には,やらなかったことは,けっして英雄的なものではなかった。ただ,ぼくは,ヒトラー式のあいさつをするのが,気分が悪くなるほどいやでたまらなかっただけなのだ。ぼくは,ずっと受け身だった。このときも,ぼくたちの本が焼かれたあの日でさえも》
受け身のままでいるといっても,群集の流れに従わないということは,一人の人間にとって,どれほど勇気のいることだろうか。(p.180)
◆のちにジャーナリストとして,あるいは哲学者として著名になったヴォルフガング・ハーリヒは,ケストナーの詩についてこう証言している。
《あの時代に,わたしたちがなにを必要としただろうか。行進のためのかけ声?そうじゃない。大理石のぴかぴかな床でもない。みんなを憂鬱にさせる気分でもない。鈍くなりかけたわたしたちの良心を,ひっぱたいて起こしてくれるものだった。ケストナーの詩は,まさにそれだった。『もうひとつの可能性』や,『きみ知るや,大砲の花咲く国を』などの彼の詩を読んでも,理性がもどらず,支配者たちの嘘が見抜けなかったようなやつらは,もう救いようがなかった》(p.222)
(私のコメント)
「どうしてナチスの支配するドイツを逃れ,亡命しなかったのか?」戦後多くの人々がケストナーにある種の不審な気持ちを持ちながらこう聞いた。しかし,考えようによっては亡命よりももっと危険な方をケストナーは選んだのである。全体主義のうずまくなかで一人反対を唱えることがいかに恐ろしいことか,いかに勇気がいることかは,ともすると全体主義に走りがちな我々日本人にとって痛いほどよくわかる。クラス全体が一人の生徒をいじめている中で,「いじめるのはやめなさい」ということがどれほど難しいかを考えて見ればよい。
インパクト指数こそ大きくはでなかったが,中学生から大人まで是非読んで欲しい一冊である。
「傷心を演じるのはやめなさい。
生きながらえよ,悪人どものじゃまをするために!」(『自動発射装置への警告』より)
 【インパクト指数】君の人生観を変えるかもしれない!
【インパクト指数】君の人生観を変えるかもしれない!
(私のコメント)
◆これは本ではない。カセットの録音された住井すゑの講演である。1992年10月31日大阪府立体育館でお「第24回大阪府同和教育研究会」の記念講演から収録したものである。内容は,
(A面)である。「橋のない川」がなぜ書かれたかがここで語られている。直接の動機となった「綴り方兄弟」の映画はわたしも小学校のとき先生に連れられて映画館へ観にいった記憶がある。次の「九十歳の人間宣言」と合わせて聞いていただきたい。
・ある識字学級の話
・被差別部落の悲しい実態
・まちがいだらけの教科書
・社会が作る差別構造(B面)
・「橋のない川」を書く直接の動機
・取材先でみた「闘争」
・被差別部落の子供が泣く理由
・「橋のない川」第8部の構想
 【インパクト指数】必ず感動します!
【インパクト指数】必ず感動します!
(私のコメント)
◆これは本ではない。カセットの録音された住井すゑの講演である。1992年6月19日日本武道館で「橋のない川」第7部刊行を記念して行なわれた講演の収録である。内容は,
(A面)である。もし入手可能なら是非聞いていただきたい。おもわずひきこまれる内容である。
・憲法第1条への疑問
・住井流憲法改正論
・「文化国家」とはなにか(B面)
・国家解体のすすめ
・老子に学んだ「兵器は凶器」の思想
・「差別」を認める日本国憲法
・「橋のない川」を何故書いたか
 【インパクト指数】2.8
【インパクト指数】2.8
(本文から) ◆小林(よしのり)が,いわゆる「マンハッタン計画」に関して,オッペンハイマーがユダヤ人であることを強調し,「日本人はユダヤ人を二万人も救ったのだが,ユダヤ人は原爆を作って日本人大虐殺に手を貸したわけである」などと非難しているのは,いかにも奇異である。(P.35)
◆『戦争論』において反米プロパガンダのついでのように出てくる小林(よしのり)のユダヤ人に対する言及には,読者にユダヤ人に対する予断と偏見を植えつけるためでないとするならば,一体何が意図されているのであろうか,と疑問がもたれる。(P.37)
(私のコメント)
◆ユダヤ人がほとんどいないこの日本でどうしてかくも「ユダヤ陰謀説」が蔓延しているのか。
この本には戦前からの根深い「ユダヤ陰謀説」の歴史が語られている。かのチョムスキーでさえもが
よく考えもしないで,「ガス室はなかった」説を唱える名うてのロベール・フォリソンの本の序文を書くという失態を演じた驚くべき事実も述べられている。
 (本文から)
(本文から)
◆幸徳(秋水)は私の同志で,先輩であり先生であり,神様でもあったわけです。
(私のコメント)
◆住井すゑと様々な分野の人々との対話集。3部作。住井すゑは6歳で人間はみな平等
であることを認識し,8歳のときに起こった幸徳事件(大逆事件, 1910)で社会の矛盾
を見抜いた。彼女は人から周囲の人から影響されたとか読書から感化されたというので
はなく,本質的にそれを理解したのである。対話者の中には途中で「転向」した人もいる
が住井すゑは最後まで首尾一貫していた。
 (本文から)
(本文から)
◆(マルセ)いろいろおっしゃっていたり何かしていると,「あの婆ア!けしからん」
というようなことをいう人が来ませんか・・・・。
(住井)きませんねえ。私は来るのを待っているんですがね。もし来てくれれば帰りに
は左翼にして帰しますから。
◆(永)あの,突然ですが,ご主人のお墓はありますか。
(住井)墓?ないです。
(永)そこまで徹底しているんだ。そうすると住井さんのお墓,ご自身のお墓のことを
考えたことあります?
(住井)考えないですね。
(私のコメント)
住井すゑは一切の人為的な形式を排除し,常に自然体で生きた。この本には『橋のない川・四部』
を書いた時,児玉誉士夫が「いい小説を書いてくれてありがとうございました」といって
きたという驚くべきエピソードも語られている。
 (本文から)
(本文から)◆私は常に蔑視されていることを承知していた。だから負けまいとする意欲はいつも持っていた。 私の独学など勿論言うに足りないが,その闘志自体が何か心の支柱のような気がした。大学を出 ているくせに,詰まらない男に出会うと,やはり安らぎを覚える。
◆宴会の席では習慣的に部長や課長や次長が末座にも酌をして回ってくる。そこで部下の一人一人 と短い話を交わすのだが,私の前にくると,上役はついと隣の男に移るのだった。
(私のコメント)
伊能忠敬は52歳で天文学の学習を志すが,松本清張は40代後半から小説家として歩み出す。
清張のそれまでの生活は「半生の記」(河出書房新社,1992)にくわしい。すさまじい貧困の中で
育ち,小学校卒への学歴差別・職業差別の中でそれをバネに小説を志した。そしてこうした経験
が,弱いもの貧しいものへの思いやりとして彼の小説に影響している。
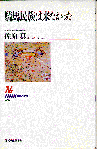 (本文から)
(本文から)◆しかも江上さんは元気で自説をくりかえしています。このくりかえして何度もいう,と いうのはとてもこわいことです。ナチス=ドイツの宣伝相ゲッペルスが「嘘も百回言うと 真実になる」といったのを思い出します。一方,江上説に反対する人は散発にしか声をあ げない。「そして誰もいなくなった」。そこで私は立ち上がったのです。
◆かつて,騎馬遊牧民族征服王朝説という仮説がありました。
(私のコメント)
この本は上記(二番目)の言葉でしめくくられている。もうこれでナンセンスな説は終わりに
したいという著者の気持ちがあらわれている。佐原氏の論理は実証的で説得力がある。どんな
におもしろい説であろうとも,多数の理性を納得させるだけの事実に裏づけられていなければ,
ただのSFにすぎない。
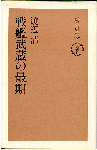 (本文から)
(本文から)◆長身の杉本の体がいつのまにか半分になっている。両足の膝から下を,破片かなにか ですっぱりともぎとられてしまったのだ。彼は甲板にその膝をたてたまま,うしろにふんぞる ようにあおのけ,眼をつりあげ,苦しまぎれに両手をふるまわしながら,口から泡をふいて喚いている。
(私のコメント)
一度戦闘となると,戦艦の上は恐ろしい修羅場に変わる事がこの本を読んでわかった。鉄で囲まれた環境では,いったん爆弾が破裂すると無数の鉄片が宙を舞い,恐ろしい惨事に変わるのだ。本書は九死に一生を得た筆者の体験に基づくものであり,淡々と語られていく事実の中に執念のようなものを感じる。戦争とは理念ではなく,肉片が飛び血しぶきの舞う地獄であることがわかる。語らずとも本書の全編を通じて戦争の惨さ,愚かさが伝わってくる。
 (本文から)
(本文から)
◆ひとつの群れの中でまわりより目立つというのは,とくに軍隊のようなとこ ろではけっして望ましいことではなかった。まして時が時であるだけに,にっくき敵国であるイギリス人の血を持った"毛唐"となればなおさらだ。それだけ でも十分差別の理由になるのに,おまけにというべきか兵隊になってまだ日の 浅い二等兵である。だれもがてぐすね引いて待ち構えていた,というのが実情 だったろう。
(私のコメント)
一人の西洋人が陸軍二等兵の服をきて銃剣を構えている。しかもその二等兵
は40代の人なら皆よく知っているあの英会話のJ・B・ハリスである。
どうみても西洋人としか見えない男があの陰湿でいじめに満ちた軍隊に放り
込まれたらどういうことになるか---ハリス氏の受けた体験は想像を絶する。
ハリス氏はイギリス人である父が亡くなり,日本に帰化した直後に軍隊に召集される。彼はその地獄を見事に生き抜き,そして生還するのである。
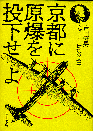 (本文から)
(本文から)◆京都・奈良など日本の古都は,アメリカ軍がその文化財を守るために爆撃を控えていたのだ,という<文化財保護説>は,敗戦直後から今日まで,長い間,日本人の間に言い伝えられてきた。しかし,この"常識"が真実かどうか確かめようとした研究は,これまでなされたことがなかったのである。
◆これはアメリカ軍統合参謀長会議が南西太平洋方面軍最高司令官・マッカーサー将軍,太平洋方面軍総司令官・ニミッツ提督,第20航空軍司令官・アーノルド大将にあてて出した6月30日付の指令である。
「新しい指令が統合参謀長会議によって発せられないかぎり,貴官指揮下のいかなる部隊も,京都・広島・小倉・新潟を攻撃してはならない。
右の指令の件は,この指令を実行するのに必要な最小限の者たちだけの知識にとどめておくこと。(MED.TS)」
これこそ,まぎれもなく原爆投下目標に対する通常爆撃の禁止命令であった。これらの都市はこうして原爆投下用に<予約>されていたのである。
(私のコメント)
「京都が米軍の爆撃から免れたのはその歴史的価値のせいである。」一体誰かこんなことをいいだしたのだろう。私の周囲の人々も皆,それを聞いたという。本書の最終章では日本占領直後,早急に反米感情を親米的にする使命を帯びていたCIE(GHQの民間情報教育局)が,その巧みな宣撫工作により,「ウォーナー伝説」の美談を形成していく過程が実に見事に語られている。本書は感情的になることを努めてさけ,資料によって事実を語らしめており,反論を許さない。非情な戦争の中においても文化を尊重する心が残っていて欲しいと思う気持ちはわかるが,戦争がそんなに甘いものではなかったということ,所詮戦争は狂気に過ぎないということがよくわかる。
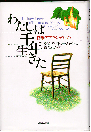 (本文から)
(本文から)
◆「ママ,うじ虫がスプーンにいる!見て,ママ,うじ虫がたくさん,ママのボウルに入っている!わたしのにも!見て!」
「ばかなこと言わないで!これはうじ虫じゃないわ。食べなさい。わたしのことは放っておいて」
「でも,ママ,これはうじ虫よ。生きているうじ虫だわ。はってるもの。見て」
わたしは自分のボウルに群れている虫を一匹つまみ,地面に置いた。それははいはじめた。そのあと,わたしはもう一匹つまんだ。それもはいはじめた。
(略)
「この食べ物を捨てるわけにはいかないわよ。とてもおなかがすいているんだから。ママに餓死してほしいの?」その声は,とても母のものとは思えなかった。「それに,ここにはうじ虫なんて入ってないわ!もうその話はやめなさい!」
母は食べ続けたが,わたしはボウルをひっくりかえして中身を地面にぶちまけ,走り出した。そして,遠くの岩に腰かけ,泣きはじめた。神さま。ああ,神さま,これは本当に起こっていることなんですか?
(私のコメント)
「夜と霧」をはじめ,ユダヤ人強制収容所について書かれた本はいくつかあるが,アンネと同じ13歳でアウシュビッツに送られ恐怖の一年を経て生還した少女の体験談として異色の本である。解放された時,14歳のエリは民間のドイツ婦人から60歳と間違えられた。「わたしは14歳で,千年も生きたような気がしていた」と彼女は語っている。
訳者あとがきによれば,彼女は後にアメリカに渡り,博士号を取得した後,ニューヨーク州立大学で30年間教鞭をとったということである。
 (本文から)
(本文から)
◆彼(レヴィ=ストロース)のメッセージは,人間味にあふれている。ひとくちで言えば,こうである。「未開人だ野蛮人だ,文明にとり残されて気の毒だと,偏見でものを見るのはよそうではないか。彼らは,繊細で知的な文化を呼吸する,誇り高い人びとだ。われわれのやり方とちょっと違うかもしれないが, そして,物質生活の面では簡素かもしれないが,なかなか"理性"的な思考をする人びとなのだよ。」
◆構造主義にいちばん縁が深いのは,人類学でも言語学でもない。じつは,数学なのだ!ところがどういうわけか,わが国で紹介された構造主義は,そこが分かりにくい。<構造>と数学のつながりがすっぽりぬけ落ちている。なぜだろう。構造主義に興味をもつような人間は,仏文とか哲学とか,たいてい文科系だし,文科系だと(私も含め)数学に弱い。案外,そんなとこかもしれない。しかし本場で構造主義とか,現象学,ポスト構造主義とかやっているバリバリの連中は,数学にめっぽう強いのが多い。
(私のコメント)
構造主義は方法論の一種である。文体の研究に数量化理論を持ちこむことに似ていないでもない。かつて神話や文学は理科系の学問とは無縁と考えられていた。レヴィ=ストロースはヤーコブソンから学んだ音韻論の分析法を神話学に応用したのである。
私は今や文系も理系もないと思う。全く異質の分野の方法論を応用することで様々な学問の発達があると考えるからである。そうした意味では「私は文系人間です」などと自ら決めつけるのはよくない。
構造主義がどんなものかを「感じる」ことのできる本である。
 (本文から)
(本文から)
◆三井物産の試験のときだと思うが,面接が終わって帰ろうとすると,面接に立ち会った一人が,わしを呼びとめて,きみはこの会社に絶対に入るなって。妙なことをいうなあと思って聞いていると,その人はこういうたのです。わたしはイギリスのオックスフォードを出ているけど,出世ができずに苦労している。この会社には東京帝国大学という学閥があって,外国の大学を出た人間は,たとえ能力があっても,上にいくことはむずかしい。心からいうけど,おやめなさい,と。
わしは面接を受けて合格といわれているし,困った。で,どうしたらいいかと聞くと,その人は会社に来なければいいんですというんです。ああ,そうですかということで,それから,わしの運命が変わっていくんです。
◆陸軍に志願したとき,わしは二つの条件を出したんです。一つは,とにかく第一戦に出すこと,もう一つは,わしの上に上司をつけないでくれということ。とにかく,わしでなかきゃできんことをやりたいといったんです。外務省の手伝いをしたり,陸軍省でも内勤で語学力を生かす手もあったんだが,わしのように,外国の会社にいた者は,日本のああいう組織では下の下ということになる。第一戦なら,実力主義だと思った。
(私のコメント)
ハワイで漁師をする両親のもとで育ち,ハーバード大学に入学,国際公法を学び,日本に帰国後は日本GMの幹部となる。しかし,戦争により会社はつぶされ,自ら志願してフィリピンの第一戦へ。ラウレル大統領の特別補佐官をつとめ,東条英樹・山下泰文とも親しく付き合うが,彼は常に「民間」の立場を貫いた。昭和史の表に出てこなかった人物であるが,その果たした役割は大きい。
 (本文から)
(本文から)
◆ウォルフはこう説明した。「家を燃やすことを語るのは残酷に見える。しかし,我々は国家的な生き残りのために生死の戦いをしているのであり,それゆえに,アメリカ人兵士と水兵の生命を救うあらゆる行動が正当化される。我々は,敵に最大の被害を与えうる場所で,あらゆる手段を用いて,激しく攻撃しなければならない」
◆彼(スチムソン陸軍長官)は即座に言った。「京都は爆撃してほしくない」
そして彼は,日本文化の中心としての古都,京都の長い歴史と,彼がなぜそこに爆撃されるのを見たくないか数多くの理由を私に話し続けた。
◆「それ(原爆投下)はアメリカ国民の心理だった」とI・I・ラビは考えた。「私はそれを,軍事的理由で正当化しているのではなく,アメリカ国民の支持を得た軍部のこうしたムードの存在のうえで正当化しているのだ」
(私のコメント)
著者のリチャード・ローズは本書で1988年ピュリッツァー賞を受賞した。アイザック・アシモフは本書を「20世紀前半の物理学の発展について,私が読んだ本のうちで最良であり,最も示唆に富み,最も内容が深い」と絶賛している。原子爆弾がどのようにして生まれ,どのようにして使用されたかが実に詳しく述べられており,上下合わせて1,365頁にのぼる本書を読みとおすにはそれなりの覚悟がいる。第19章では121頁にわたって広島・長崎の惨状が述べられているが,それははるか上空から見たものではなく,きのこ雲の下の地獄のような状況の中で右往左往している日本人の目線で描いている点は好感がもてる。
本書によれば,京都は最後まで原爆投下目標に上がっていたが,陸軍長官スチムソンの強い反対にあって,攻撃目標からはずされたという。最も,そのために広島や長崎が攻撃目標になったわけであり,スチムソンに恩を感じる必要はない。
 (本文から)
(本文から)
◆「チン」とおちんこを押さえ,「オモーニ」とおっぱいを押さえ,「ワガ」と鼻を押さえながら,相手の様子をうかがい,油断を見はからって,相手のわきの下を,「コチョコチョ」と先にくすぐった方が勝ちでした。
◆悪いのは朝鮮の子だけで,日本の子がそんなことをするはずがないと,先生は信じ切っていたのでしょうか。(略)わたしは,この時のことを,一度もサイさんたちにあやまったことがありません。けれど,サイさんたち・朝鮮の子どもが,わたしたち日本の子ども,日本の先生,日本人を,どんなに憎み,軽蔑したかを,感じとる力はあったのです。
◆「あんたア,お国に大きゅうしてもろたか。お国の配給もんで,そこまで大きゅうなったか。ヤミをしてあんたをやしのうたんは誰じゃ。親じゃねえんか。その親を,あんたア非国民と言うんか。お国が何じゃ。取るばアして。ひとの大事な息子を取ってしもうて・・・」おばあさんは泣きました。
(私のコメント)
一人の主婦が小学生の子どもに読ませるために戦争の体験談を書いた。子どもの目を通して見た戦時中の日本の学校や社会の様子がするどく描かれている。
わたしがこれまで読んだ戦争に関するどんな本よりも心に響くものがあった。
子どもでありながら,正しく世の中を見る力には驚嘆するばかりである。今,入手可能かはわからないが是非多くの人に読んで欲しい本である。