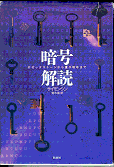 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏係
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏係
巹偑偙傟傑偱撉傫偱偍傕偟傠偐偭偨偲巚傢傟偨杮傪埲壓偺徯夘偟傑偡丅偡傋偰巹偺撈抐偲曃尒偵傛偭偰偐偐傟偰偍傝傑偡偑丆壗偐偺偛嶲峫偵側傟偽偲懚偠傑偡丅昡壙傕巹屄恖偺敾抐偱偁傝丆媞娤揑側傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅傑偨丆偡偱偵愨斉偺傕偺傕偁傞偐傕偟傟傑偣傫偺偱偛彸抦偍偒偔偩偝偄丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃 巹偑柺敀偄偲姶偠偨暸亐乮憤暸悢亐侾侽侽乯偮傑傝丆偦偺杮傪侾侽侽暸偵姺嶼偟偨応崌丆巹偑柺敀偄偲姶偠偨暸偑偳偺偔傜偄偁傞偐傪帵偟偰偄傑偡丅偙偺悢帤偑戝偒偄傎偳僀儞僷僋僩偑偁傝傑偡丅
傾儈乕傾丒傾儗僋僒儞僟乕挊乛杮暥307暸乛俀侽侾俆擭丂俉寧俀俉擔戞侾嶞乛娾攇彂揦乛ISBN978-4-00-006049-3 C0041
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俀侽丏俁
|
仧恾宍傕帪娫傕乽尨巕乿偐傜偱偒偰偄傞両 偄偐側傞楢懕偟偨戝偒偝傕丆偦傟偑慄偱偁傟丆柺偱偁傟丆帪娫偱偁傟丆屳偄偵撈棫偟偨丆柍尷偵彫偝側尨巕偱偱偒偰偄傞偲偄偆偺偱偁傞丅傕偟偙偺妛愢偑惓偟偗傟偽丆巹偨偪偺栚偵偼妸傜偐偵塮傞慄偼丆偦偺幚丆柍悢偺撈棫偟丆晄壜暘偱偁傞尨巕偱峔惉偝傟偰偍傝丆傑傞偱僱僢僋儗僗偺嬍偺傛偆偵椬傝崌偭偰偄傞偙偲偵側傞丅摨條偵丆柺偼晄壜暘側嵶偄慄偑椬傝崌偭偰偍傝丆帪娫偼旝彫偺弖娫偑楢側傞偙偲偵傛偭偰惉傝棫偭偰偄傞丆摍乆偲偄偆傢偗偱偁傞丅(棯)1651擭偵偼斵傜乮僀僄僘僗夛偺専墈幰乯偺擡懴傕尷奅偵払偟偰偄偨丅僀僄僘僗夛偺巜摫幰偨偪偼旕岞擣偺堄尒偺懅偺崻傪巭傔傞偙偲傪寛抐偟丆嫵偊傞偙偲傕丆巟帩偡傞偙偲傕塱媣偵嬛偠傞妛愢偺儕僗僩傪嶌惉偟偨丅晄壜暘幰偺妛愢偼丆尵偆傑偱傕側偄偑丆儕僗僩偺拞偱嵟廳梫偺埵抲偵偁偭偨丅(p.21) 仸晄壜暘幰偲偼晄壜暘偱偁傞乽尨巕乿傪巜偡丅 仧乽柺乿偼暲峴偡傞嬌嵶偺乽慄乿偐傜丆乽棫懱乿偼廳側傝崌偆嬌敄偺乽柺乿偐傜 偳傟傎偳妸傜偐偱偁傠偆偲丆偳偺暯柺恾宍傕幚偼椬傝崌傢偣偵攝楍偝傟偨嬌彫偺暯峴側慄暘偱偱偒偰偄傞丅偦偟偰丆3師尦偺恾宍偼丆偳傟傎偳屌懱揑偵尒偊偰傕丆偍屳偄偵廳側傝崌偭偰偄傞旕忢偵敄偄柺暘偺愊傒廳偹埲奜偺壗暔偱傕側偄丅偙偺傛偆偵嵟傕敄偄堦枃偼暔幙偺嵟傕彫偝側梫慺丆偡側傢偪尨巕偲摨摍偱偁傝丆僇償傽儕僄儕偼偙傟傪乽晄壜暘幰乿偲屇傫偩丅(p.98) 仧備傞偓側偒拋彉傊偺嫼埿 婔壗妛偑僩僢僾僟僂儞悢妛偩偲偟偨傜丆晄壜暘幰偺曽朄偼儃僩儉傾僢僾悢妛偩偭偨丅嵟傕婋尟側偺偼丆婔壗妛偑尩枾偱丆弮悎偱丆媈偄傛偆傕側偄恀棟偱偁偭偨偺偵懳偟丆怴偟偄曽朄偼僷儔僪僋僗偲柕弬偵偁傆傟丆恀幚偲摨掱搙偵岆昑傊摫偔壜擻惈偑偁偭偨丅僀僄僘僗夛偵偲偭偰偼丆晄壜暘幰偑枲墑偡傟偽丆塱墦偵偟偰斾椶側偒婔壗妛偺戝揳摪偑丆晄埨掕側搚戜偺忋偵棫偰傜傟偨丆崱偵傕搢傟偦偆側僶儀儖偺搩偵抲偒姺偊傜傟偰丆憟偄偲晄挷榓偺応偲側偭偰偟傑偆偩傠偆丅(p.123) 仧乽柍尷彫偺棟榑乿偼乽旝愊暘乿傊偲敪揥偟偨 僂僅儕僗偺撉幰偺拞偱嵟傕廳梫側恖暔偼傾僀僓僢僋丒僯儏乕僩儞偱偁偭偨丅23嵨偺僯儏乕僩儞偼1665擭偵丆棳棪榑丆偡側傢偪斵棳媀偺柍尷彫悢妛傪峫埬偟偨偺偩偑丆屻擭亀柍尷偺嶼弍亁偑庡側僀儞僗僺儗乕僔儑儞偺尮偱偁偭偨偲柧偐偟偰偄傞丅(p.302)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
媣乆偵抦揑嫽暠傪枴傢偆偙偲偑偱偒偨丅撉傫偱摼偡傞丆偍偡偡傔偺杮偱偁傞丅僈儕儗僆偺亀揤暥懳榖亁偱僐働偵偝傟偨偲巚偭偨僂儖僶僰僗嫵峜偑丆僈儕儗僆傪敆奞偟偨偲偺愢偑偁傞丅杮彂偼丆僈儕儗僆偺揮棊偼丆庡偲偟偰丆儘乕儅偱尃椡傪庢傝栠偟偨僀僄僘僗夛偺揋堄偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨傕偺偩偲偡傞丅惍慠偲偟偨婔壗妛傪怣忦偲偡傞僀僄僘僗夛偲僈儕儗僆傪昅摢偲偡傞乽柍尷彫偺棟榑僌儖乕僾乿偲偺愴偄偑丆偦傟偧傟偺帪戙偺幮夛偲枾愙偵棈傒偁偭偰偄偨偲偄偆帇揰偼丆偲偰傕巃怴偱柺敀偄丅僀僄僘僗(Jesuit)夛偲僀僄僗(Jesuat)夛丅偨偭偨1暥帤偺堘偄偩偑丆慜幰偼乽柍尷彫乿傪敆奞偟丆屻幰偼乽柍尷彫乿傪庡挘偟偨丅
僒儉丒僉乕儞挊乛杮暥443暸乛俀侽侾俆擭侾侽寧侾俆擔戞侾嶞乛憗愳僲儞僼傿僋僔儑儞暥屔乛ISBN978-4-15-050447-2 C0143
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俀丏侽
|
仧揹巕偺暻 尨巕傪僗億乕僣僗僞僕傾儉傎偳偵朿傜傑偣偨偲偟偰傕丆梲巕傪偨偔偝傫帩偮妀偝偊僼傿乕儖僪拞墰偵抲偐傟偨僥僯僗儃乕儖傎偳偺戝偒偝偵偡偓偢丆揹巕偵偄偨偭偰偼廃埻傪旘傃夞傞恓偺摢傎偳偱偟偐側偄乗乗偩偑丆旘傃夞傞偺偑偁傑傝偵懍偔丆枅昩悢偊愗傟側偄傎偳壗搙傕偁側偨偵摉偨傞偺偱丆偁側偨偼僗僞僕傾儉偵擖傟側偄偩傠偆丅恓偺摢偳偙傠偐屌偄暻偺傛偆偵姶偠傞偼偢偩丅偦偺偨傔丆尨巕偳偆偟偑傇偮偐偭偰傕丆側偐偺妀偼岥傪弌偝偢丆揹巕偩偗偑斀墳偵偐偐傢傞丅(p.29) 仧壗搙傕儕僒僀僋儖偝傟偨壓嵻丆傾儞僠儌儞 傾儞僠儌儞偺娵栻偼壓嵻偲偟偰廳曮偝傟偨丅尰戙偺忶嵻偲偼堘偭偰丆寴偄傾儞僠儌儞娵栻偼挵偱徚壔偝傟側偐偭偨偺偩偑丆偙偺娵栻偼傂偠傚偆偵壙抣偑崅偄偲尒側偝傟偰偄偰丆摉帪偺恖偼曋傪傂偭偐偒傑傢偟偰夞廂偟偰偼嵞棙梡偟偰偄傞丅塣偺偄偄堦懓偵側傞偲丆壓嵻傪晝偐傜巕傊偲戙乆揱偊傑偱偟偰偄偨丅偳偆傗傜偙偺岠擻偺偣偄偱丆傾儞僠儌儞偼杮摉偼撆側偺偵栻偲偟偰懡梡偝傟偨丅儌乕僣傽儖僩偺巰場偼崅擬偲偺摤昦偵偁偨偭偰傾儞僠儌儞傪堸傒夁偓偨偙偲偵堘偄側偄丅(p.34) 仧懢梲宯偼挻怴惎敋敪偺徴寕攇偑墶愗偭偨偙偲偱惗偠偨 46壄擭傎偳傑偊丆偁傞挻怴惎敋敪偱敪惗偟偨徴寕攇偑丆暆24壄僉儘偲偄偆塅拡恛偺暯傜側塤乗乗偐偮偰峆惎偩偭偨傕偺偺彮側偔偲傕擇屄暘偺巆奫乗乗傪撍偭愗偭偨丅恛偺棻偑挻怴惎偐傜偺暚弌暔偲崿偞傝崌偄丆朇寕傪庴偗偨嫄戝側抮偺傛偆偵帄傞偲偙傠偱塓偑偱偒巒傔偨丅枾搙偺崅偄塤偺拞墰晹偼幭偊偨偭偰懢梲偲側傝乮偮傑傝丆懢梲偼偐偮偰偺峆惎偺巆傝暔偐傜偱偒偰偄傞乯丆榝惎懱傕枾偵側偭偰夠偵側傝巒傔偨丅(p.93)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
廃婜昞偵嵹偭偰偄傞尦慺偵傑偮傢傞榖傪廤傔偨杮偩偑丆扨側傞壔妛杮偱偼側偄丅尦慺傪傔偖傞條乆側恖娫柾條偑幚偵偆傑偔愢柧偝傟偰偄傞丅棟宯偱側偔偰傕偍傕偟傠偄丅掜巕偺敪尒傪墶庢傝偟偨僔儑僢僋儗乕丆戝敪尒偺拏慺屌掕朄傛傝傕敋抏傗撆僈僗偺惢憿偵娭怱偑偁偭偨僴乕僶乕丆彈惈偱偁傞偑備偊偵側偐側偐偦偺嵥擻偑擣傔傜傟偢丆僲乕儀儖徿傪偲偭偰傕怴暦偵乽僒儞僨傿僄僑偺偍曣偝傫丆僲乕儀儖徿傪庴徿乿偲彂偐傟偨儊僀儎乕側偳嫽枴怺偄榖偑偄偭傁偄弌偰偔傞丅
媑揷偨偐傛偟挊乛杮暥197暸乛俀侽侾俁擭俋寧俀侽擔戞侾嶞乛島択幮尰戙怴彂 2226乛ISBN俋俈俉亅4亅06亅288226亅2 C0240
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俀俀丏俉
|
仧僫僩儕僂儉偺擹搙偺廳梫惈 恖懱偱偼丆寣塼傕儕儞僷塼傕丆僫僩儕僂儉僀僆儞偺擹搙偑135乣145mEq/L偺斖埻撪偵廂傑傞傛偆丆尩枾偵僐儞僩儘乕儖偝傟偰偄傞偐傜偱偡丅傕偟丆壗傜偐偺堎忢偑惗偠偰僫僩儕僂儉僀儞偑憹偊夁偓偨傝尭傝夁偓偨傝偡傞偲丆恖懱偵偼怺崗側徢忬偑偨偪偳偙傠偵尰傟丆嵟埆偺応崌丆柦傪棊偲偟偰偟傑偄傑偡丅(棯) 堛幰偵偲偭偰僫僩儕僂儉傪偼尒棊偲偡偙偲偑嫋偝傟側偄廳梫側僠僃僢僋崁栚側偺偱偡丅(p.15) 仧僆僔僢僐偼廘偔側偄 曋婍偑廘偆偺偼丆曋婍偵摿暿側嵶嬠偑惐傒拝偄偰偄傞偨傔偱偡丅嵶嬠偑僆僔僢僐偵娷傑傟偰偄傞柍廘偺擜慺傪戙幱偟偰丆偔偝偄傾儞儌僯傾傪嶌偭偰偄傞偺偱偡丅恖懱偼僄僱儖僊乕傪巊偭偰娞憻偱桳奞側傾儞儌僯傾傪柍奞側擜慺偵嶌傝曄偊偰偄傞偺偱偡偑丆嵶嬠偼偦偺媡偺偙偲傪峴偆偙偲偵傛傝僄僱儖僊乕傪庢傝弌偟偰惗偒偰偄傞傢偗偱偡丅(p.87) 仧恖懱偼傢偞偲梋暘側揝暘傪庢傜側偄傛偆偵偟偰偄傞 巹偨偪偼丆昗弨揑側怘帠傪偟偰偄傞応崌丆怘暔傪捠偟偰侾擔偵40儈儕僌儔儉偐傜50儈儕僌儔儉偺揝傪愛庢偟偰偄傑偡丅偟偐偟丆挵偐傜媧廂偟偰偄傞偺偼丆偦偺偆偪丆傢偢偐1儈儕僌儔儉掱搙偵偡偓傑偣傫丅偮傑傝丆岥偵偟偨揝暘偺戝敿偼丆偦偺傑傑挵傪慺捠傝偟偰丆戝曋偲堦弿偵幪偰傜傟偰偟傑偭偰偄傞偺偱偡丅偙傟偼丆揝偲偄偆尦慺偑恖懱偵偲偭偰摿偵媧廂偟偵偔偄惈幙傪帩偭偰偄傞偐傜偩偲偄偆傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅挵偺擲枌偺峔憿忋丆揝偺媧廂棪傪崅傔傞偙偲偼梕堈偱偡丅傓偟傠丆恖懱偼丆昁梫埲忋偵揝傪庢傝崬傑側偄傛偆偵丆媧廂棪傪梷惂偡傞儊僇僯僘儉傪傢偞傢偞敪払偝偣偨偲偄偊傞偺偱偡丅乮p.184)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
挊幰偼偪傚偭偲捒偟偄宱楌偺帩偪庡偩丅搶戝偺岺妛宯偺戝妛堾傪弌偰丆NHK傾僫僂儞僒乕偵側傝丆杒棦戝妛堛妛晹偵擖傝捈偟偰堛巘柶嫋傪庢摼偟丆庴尡惗愱栧奜棃傪奐嬈偟偰偄傞丅偦偺偨傔丆杮彂偺撪梕傕丆堛妛傪棟壢揑晽枴偱枴晅偗偟偨傛偆側姶偠偵側偭偰偄傞丅揝暘偼懱撪偺嵶嬠偑嵟傕梸偟偑偭偰偄傞傕偺偱偁傝丆昻寣偩偐傜偲偄偭偰埨堈偵Fe偺僒僾儕儊儞僩傪愛傞偙偲偼梫拲堄偱偁傞丅姶愼嬠偵僄僒傪傗偭偰偄傞傛偆側傕偺偩偐傜偩丅
儅僀働儖丒僽儖僢僋僗挊乛灳堜峗堦栿乛杮暥332暸乛俀侽侾侽擭俆寧侾擔戞侾嶞丄俀侽侾侽擭俉寧俀擔戞俆嶞敪峴乛憪巚幮乛ISBN978-4-7942-1757-8 C0040
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏俉
|
仧旝嵶峔憿掕悢兛乮1/137乯 旝嵶峔憿掕悢偑戝偒側堄枴傪帩偮偺偼丄偦傟偑偒傢傔偰廳梫側暔棟妛棟榑偺傂偲偮偱偁傞検巕揹帴椡妛偺丄嵟傕廳梫側掕悢偩偐傜偩丅検巕揹帴椡妛偼丄壸揹棻巕丄偡側傢偪梲巕傗揹巕偺偁傝偲偁傜備傞憡屳嶌梡傪巟攝偡傞丅傑偨丄検巕榑丄憡懳惈棟榑丄揹婥妛丄帴婥妛傪摑崌偟偰丄揹帴婥椡偺尮傪婰弎偡傞丅堦曽偱偼乮棯乯尨巕妀偺曻幩惈曵夡側偳偺尰徾傪堷偒婲偙偡乭庛偄椡乭偲傕寢傃偮偗傜傟偰偄傞丅揹帴婥偲乭庛偄椡乭偼帺慠奅偺巐偮偺婎杮揑側椡偺偆偪傆偨偮偩偐傜丄兛偑塅拡嬻娫偱悤梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偲昡偡傞偺偼懨摉偩傠偆丅(p.86) 仧忢壏妀梈崌偼乽杺彈庪傝乿偝傟偨偑丄偦傟偱傛偐偭偨偺偐? 忢壏妀梈崌偺暔岅偼丄偙傟傑偱偺偲偙傠嶴滈偨傞幐攕偺楌巎偩偭偨丅怺墦側棟榑傪扵媮偡傞帋傒偲偟偰巒傑傝側偑傜丄僗僉儍儞僟儖埲忋偺傕偺偼惗傑偢丄恖娫惈偺嵟埆偺懁柺乮偦偟偰丄壢妛偲偄偆傕偺偺恖娫揑側懁柺乯偽偐傝傪敀擔偺傕偲偵偝傜偟偰偒偨丅偟偐偟丄暔岅偼傑偩廔傢偭偰偄側偄丅傓偟傠丄偙傟偐傜壗偐壙抣偺偁傞傕偺偑惗傑傟偰偒偦偆側挍偟偑尒偊傞丅偦偺怴偨側壗偐偼丄岝偲塭偺岎嶖偡傞楌巎傪揾傝懼偊丄儅乕僥傿儞丒僼儔僀僔儏儅儞偲僗僞儞儗乕丒儃儞僘偑壢妛奅偺婏恖乮僉儏儕僆僔僥傿乯偵側傞慜偼丄慺杙側岲婏怱乮僉儏儕僆僔僥傿乯偺帩偪庡偩偭偨偙偲傪帵偟偰丄傢偨偟偨偪傪婌偽偣偰偔傟傞偙偲偩傠偆丅(p.114)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
旝嵶峔憿掕悢兛丄悢帤偱偄偊偽137暘偺1丄堦斒偵偼乽137乿丅巹偼偙偺悢帤傪変偑幵偺僫儞僶乕僾儗乕僩偵偟偨偐偭偨丅乮寢嬊柪偭偨偁偘偔丄惗傑傟擭偺1951偲偄偆偟傚偆傕側偄斣崋偵偟偰偟傑偭偨乯偁傞壢妛幰偼丄乽巰傫偱揤崙偺栧偵峴偭偨帪丄恄偵壗傪偒偒偨偄偱偡偐乿偲偺栤偄偵丄乽傢偨偟偼丄亀恄傛丄偄偭偨偄側偤侾俁俈側偺偱偡偐亁偲暦偒偨偄乿偲摎偊偨偲尵偆丅偙偺悢帤偙偦丄塅拡偺崻尮傪宍嶌傞掕悢側偺偩丅僼傽僀儞儅儞偼乽偙偺悢抣偼丄50擭埲忋慜偵敪尒偝傟偰埲棃偢偭偲撲偺傑傑偱丄桪廏側棟榑暔棟妛幰偼傒傫側丄偙偺掕悢傪晹壆偺暻偵揬傝偮偗偰丄摢傪擸傑偣偰偒偨乿偲尵偭偨乮杮彂 p.96)丅
杮彂偼偙偺乽旝嵶峔憿掕悢兛乿偺懠偵丄埫崟暔幙丄忢壏妀梈崌丄塅拡偐傜偺怣崋丄偝傜偵偼乽側偤僙僢僋僗乮桳惈惗怋乯偑偁傞偺偐乿側偳丄偄傑偩壢妛偱夝柧偝傟偰偄側偄侾俁偺撲傪傢偐傝傗偡偔愢柧偡傞丅敪攧俁儢寧偱偡偱偵俆嶞偲偄偆恖婥杮偱偁傞丅
僔儍儘儞丒僶乕僠儏丒儅僌儗僀儞挊乛晊塱丂惎栿乛杮暥449暸乛俀侽侾俁擭侾侽寧俀俋擔戞侾嶞敪峴乛憪巚幮乛ISBN978-4-7942-2001-1 C 0041
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俉丏俆
|
仧敪尒偝傟丆幪偰傜傟丆廍傢傟傞 僩乕儅僗丒儀僀僘巘偼1740擭戙偵偁傞偡偽傜偟偄敪尒傪偟偨丅偲偙傠偑偳偆偄偆傢偗偐杮恖偼丆偺偪偵帺暘偺柤慜傪姤偝傟傞偙偲偵側傞偦偺敪尒傪曻傝弌偟偨丅傗偑偰儀僀僘傛傝偼傞偐偵桳柤偩偭偨僺僄乕儖丒僔儌儞丒儔僾儔僗偑丆偙傟偲摨偠撪梕傪撈帺偵嵞敪尒偟丆嬤戙悢妛偵傆偝傢偟偄宍偵傑偲傔偰壢妛偵墳梡偟偨丅偩偑儔僾儔僗偼丆傗偑偰偙傟偲偼暿偺庤朄偵娭怱傪堏偟偨丅20悽婭偺執戝側摑寁妛幰偨偪傕儀僀僘偺朄懃偵拲栚偟偨偑丆拞偵偼丆儀僀僘偺庤朄傗偦偺怣曭幰偨偪傪偗側偟偰扏偒偺傔偟丆栶棫偨偢偩偲尵偄愗傞幰傕偄偨丅偟偐偟偙偺朄懃傪巊偆偲丆傎偐偺庤朄偱偼帟偑棫偨側偄尰幚揑側栤戣傪夝偔偙偲偑偱偒偨丅偙偺朄懃傪巊偭偰丆僪儗僼儏僗戝堁偺曎岇恖偼戝堁偺柍幚傪帵偟丆曐尟夛幮偼曐尟椏棪傪寛傔丆傾儔儞丒僠儏乕儕儞僌偼僪僀僣孯偺埫崋僄僯僌儅傪夝偄偨丅乮棯乯儀僀僘偺朄懃傪巟帩偡傞恖乆偺懡偔偼丆偙偺朄懃偑壢妛偵偲偭偰偄偐偵戝偒側堄枴傪帩偭偰偄傞偐傪廆嫵揑側妎惲偲偲傕偵屽傝側偑傜傕丆儀僀僘偺朄懃傪巊偭偨偙偲傪塀偟丆傎偐偺庤朄傪梡偄偨偐偺傛偆偵憰偭偨丅偙偺庤朄偺墭柤偑偦偦偑傟偰丆峀偔擬嫸揑偵庴偗擖傟傜傟傞傛偆偵側偭偨偺偼丆21悽婭偵擖偭偰偐傜偺偙偲偩偭偨丅(p.21) 仧儀僀僕傾儞偲偄偆傛傝儔僾儔僔傾儞 1781擭偵偼丆儔僾儔僗偼儀僀僘偺朄懃偲偄偆柤慜埲奜偺偙偺朄懃偺偡傋偰傪庤拞偵廂傔偰偄偨丅偙偺朄懃偺掕幃傕曽朄榑傕尒帠側妶梡傕丆偡傋偰僺僄乕儖丒僔儌儞丒儔僾儔僗偑惉偟悑偘偨傕偺偩丅乮棯乯儔僩僈乕戝妛偺僌儗儞丒僔僃僀僼傽乕偼丆乽巚偆偵丆偡傋偰傪惉偟悑偘偨偺偼儔僾儔僗偱偁偭偰丆傢偨偟偨偪偑偁偲偐傜偦傟傜傪僩乕儅僗丒儀僀僘偺側偐偵撉傒庢偭偰偄傞偩偗偺偙偲側偺偩傠偆丅儔僾儔僗偼偙偺朄懃傪嬤戙揑側尵梩偱昞尰偟偨丅偁傞堄枴偱丆偡傋偰偑儔僾儔僔傾儞側偺偩乿偲弎傋偰偄傞丅
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偑摑寁妛偵娭怱偑偁傞偺偼丆偦偺悢妛揑側庤朄傛傝偼丆偦偺敪払偺楌巎偵偁傞丅摑寁妛偵懡戝側峷專傪偟偨僠儍乕儖僘丒僟乕僂傿儞偺廬掜偺僼儔儞僔僗丒僑儖僩儞偼丆偦偺堦曽偱桪惗妛偺晝偲側偭偨丅偙偺抝偼丆幚偵旲帩偪側傜偸搝偱丆挰偱岦偙偆偐傜傗偭偰偔傞彈惈傪傂偦偐偵昳掕傔偟偰丆億働僢僩偺拞偱婰榐傪庢傝丆僀僊儕僗偺偳偺抧曽偵旤恖偑懡偄偐摑寁傪庢傞傛偆側偙偲傕偟偰偄偨乮偍梀傃偩傠偆偗偳乯丅恖庬嵎暿揑側強傕偁傝丆僸儏乕儅僯僗僩偺僟乕僂傿儞偲堎側傝丆恖娫揑偵壓昳側姶偠偺抝偩丅偦偺屻宲幰偺僇乕儖丒僺傾僜儞傕桪廏側摑寁妛幰偱偁傞偲摨帪偵傗偼傝桪惗妛幰偩偭偨偟丆儘僫儖僪丒僼傿僢僔儍乕傕偟偐傝偱偁傞丅摑寁妛偺敪揥偺攚宨偵偼丆側偤偐偙偆偟偨乽晧偺堚嶻乿偑偁傞丅
嵟嬤丆恾彂娰偺摑寁妛偺僐乕僫乕側偳偱乽儀僀僘摑寁妛乿偲偄偆尵梩傪偟偒傝偵栚偵偡傞傛偆偵側偭偨丅偦偟偰偙偺杮偱丆乽儀僀僘乿偑偄偐偵乽嵎暿偝傟偰乿偒偨偐傪抦傝丆嬃偄偨丅偙傟偼傑傞偱壓懞屛恖偺乽師榊暔岅乿傗搰尨偺乽塀傟僉儕僔僞儞乿偺傛偆偱偼側偄偐丅偟偐偟丆晄摉側嵎暿偵傕傔偘偢丆偟偨偨偐偵惗偒墑傃偰偒偨偺偼丆偦傟偑乽栶偵棫偭偨乿偐傜偱偁傞丅崱偙偦丆儀僀僘摑寁妛偺壙抣傪惓摉偵昡壙偟偰傗傝偨偄丅偪側傒偵悢妛寵偄偺奆偝傫丆偙偺杮偵偼悢幃偑弌偰偙側偄偺偱戝忎晇偱偡傛丅
儅儞僕僢僩丒僋儅乕儖挊乛惵栘孫栿乛杮暥468暸乛俀侽侾俁擭俁寧俁侽擔弶斉乛怴挭幮乛ISBN978-4-10-506431-0 C0042
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侾丏俁
|
仧庫嬍偺榑暥偲僑儈偺榑暥 乽塣摦暔懱偺揹婥椡妛偵偮偄偰乿偲戣偡傞榑暥傪撉傫偩恖娫偺傂偲傝偑丆亀傾僫乕儗儞丒僨傾丒僼傿僕乕僋亁偺棟榑暔棟妛偺屭栤傪柋傔偰偄偨丆儅僢僋僗丒僾儔儞僋偩偭偨丅僾儔儞僋偼懄嵗偵丆斵偑乗乗傾僀儞僔儏僞僀儞偱側偔丆斵偑乗乗偺偪偵乽憡懳惈棟榑乿偲屇傇偙偲偵側傞偦偺棟榑偺巟帩幰偲側偭偨丅岝偺検巕偵娭偡傞榑暥偵偮偄偰偼丆僾儔儞僋偼偦偺峫偊曽偵廳戝側栤戣傪姶偠偨偑丆榑暥傪宖嵹偡傞偙偲偼擣傔偨丅僾儔儞僋偼偦偺偲偒丆庫嬍偺榑暥偲僑儈孄偺傛偆側榑暥傪摨帪偵彂偔偙偲偺偱偒傞偙偺暔棟妛幰偼丆偄偭偨偄壗幰偩傠偆偲巚偭偨偵堘偄側偄丅(p.58) 仧2,3擭偔傜偄壢妛側偟偱傗偭偰傗傠偆偱偼側偄偐 1933擭5寧16擔丆僾儔儞僋偼乮棯乯僸僩儔乕偵柺夛偟偨丅乮棯乯儐僟儎恖偺壢妛幰傪廫攃傂偲偐傜偘偵偟偰捛偄弌偡偙偲偼丆僪僀僣偺偨傔偵側傜側偄偲僾儔儞僋偼尵偭偨偺偩丅偦傟傪暦偄偰丆僸僩儔乕偼寖崅偟巒傔偨丅乽偨偲偊壢妛幰偺偨傔偩傠偆偲丆傢傟傢傟偺崙壠惌嶔偑庢傝徚偝傟偨傝丆廋惓偝傟偨傝偡傞偙偲偼側偄丅儐僟儎恖壢妛幰傪柶怑偡傟偽尰戙僪僀僣壢妛偑徚柵偡傞偲偄偆側傜丆俀丆俁擭偖傜偄丆壢妛側偟偱傗偭偰傗傠偆偱偼側偄偐!乿(p.383) 仧尋媶幒偺旛昳偼巻偲墧昅偲孄饽 1933擭10寧偵崅摍尋媶強偵傗偭偰偒偨傾僀儞僔儏僞僀儞偼丆怴偟偔帺暘偺尋媶幒偲側傞晹壆偵埬撪偝傟偰丆偳傫側旛昳偑昁梫偱偡偐偲恞偹傜傟丆乽婘偐偰僥乕僽儖偲堉巕丆偦傟偲巻偲墧昅偑昁梫偱偡乿偲摎偊丆偙偆尵偄揧偊偨丅乽偁偁偦偆偦偆丆戝偒側孄饽傕偹丅娫堘偭偨傕偺傪慡晹曻傝崬傔傞傛偆偵乿丅
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
検巕椡妛偼杮摉偵傢偐傝偵偔偄丅偲偄偆偐丆忢幆傪挻偊偰偄傞丅偨偲偊偽擇廳僗儕僢僩偺幚尡偱丆扨側傞乽棻巕乮傑偨偼攇乯乿偱偟偐側偄乽岝巕乿偑偳偆偟偰丆傑傞偱姶忣傪帩偮変乆偺傛偆偵丆恖娫偑愝抲偟偨僙儞僒乕傪乽尒攋傝乿丆僙儞僒乕傪晅偗偨偲偒偲晅偗側偄偲偒偲偱丆偦偺懺搙傪曄偊傞偺偐丅検巕椡妛偼杮摉偵摢偑偔傜偔傜偡傞丅杮彂偼偦偆偟偨検巕椡妛偺抋惗偺楌巎傪傢偐傝傗偡偔嫵偊偰偔傟傞丅
僨僀償傿僢僪丒僀乕僌儖儅儞挊乛戝揷捈巕栿乛杮暥297暸乛俀侽侾俀擭係寧侾俆擔弶斉乛憗愳彂朳乛ISBN978-4-15-209292-2 C0045
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俋丏俀
|
仧帺暘偺拞偺乽壗偐乿 1862擭丆僗僐僢僩儔儞僪偺悢妛幰僕僃乕儉僘丒僋儔乕僋丒儅僢僋僗僂僃儖偼丆揹婥偲帴婥傪摑堦偡傞婎杮曽掱幃傪峫偊偩偟偨丅偟偐偟斵偼巰偺彴偱丆偪傚偭偲曄側崘敀傪偟偨丅偁偺桳柤側曽掱幃傪敪尒偟偨偺偼乽帺暘偺側偐偺壗偐乿偱偁偭偰丆帺暘偱偼側偄偲尵偭偨偺偩丅傾僀僨傾偑偳偆偟偰晜偐傫偩偺偐偼傢偐傜側偄丆偨偩崀傝偰偒偨偺偩偲擣傔偰偄傞丅(p.17) 仧帺暘偺拞偺摯寠 儔僀僾僯僢僣偼庒偄偙傠丆偁傞擔偺挬偩偗偱300峴偺儔僥儞岅偺彇帠帊傪彂偒偁偘偨丅偦偺屻丆寁嶼朄丆擇恑朄丆偄偔偮偐偺怴偟偄揘妛棳攈丆惌帯棟榑丆抧幙妛偺壖愢丆忣曬媄弍偺婎慴丆塣摦僄僱儖僊乕偺曽掱幃丆偦偟偰僜僼僩僂僃傾偲僴乕僪僂僃傾傪嬫暿偡傞奣擮偺嵟弶偺巺岥傪峫偊弌偟偨丅偙傟傜偺傾僀僨傾偑偡傋偰帺暘偐傜偁傆傟弌偟偰偒偨偙偲偐傜丆斵偼乗乗儅僢僋僗僂僃儖傗僽儗僀僋傗僎乕僥偲摨偠傛偆偵乗乗帺暘偺側偐偵怺偔偰傾僋僙僗偱偒側偄摯寠偑偁傞偺偐傕偟傟側偄偲巚偆傛偆偵側偭偨偺偩丅(p.25) 仧恖偼乽懠恖偵塮傞帺暘乿傪垽偡傞孹岦偑偁傞 2004擭丆怱棟妛幰偺僕儑儞丒僕儑乕儞僘偺僠乕儉偑丆僕儑乕僕傾廈僂僅乕僇乕孲偲僼儘儕僟廈儕僶僥傿乕孲偺崶堶偺岞婰榐1枩5000審傪挷傋偨丅偦偟偰幚嵺偵丆柤慜偺嵟弶偺暥帤偑帺暘偲摨偠恖偲寢崶偟偰偄傞恖偺悢偼丆嬼慠偺堦抳偵偟偰偼懡偡偓傞偙偲偑傢偐偭偨丅偱傕側偤偩傠偆?廳梫側偺偼昁偢偟傕暥帤偱偼側偄乗乗傓偟傠丆偦偺傛偆側攝嬼幰偼側傫偲側偔帺暘帺恎傪楢憐偝偣傞偲偄偆帠幚偩丅恖偼懠恖偵塮傞帺暘傪垽偡傞孹岦偑偁傞丅怱棟妛幰偼偙傟傪柍堄幆偺帺屓垽丆偁傞偄偼傛偔抦偭偰偄傞傕偺傊偺埨怱姶偩偲夝庍偡傞乗乗偦偟偰偦傟傪乽愽嵼揑帺屓拞怱惈乿偲屇傇丅(p.88)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偨偪偼帺暘偑帺暘偺庡恖偱偁傞偲巚偭偰偄傞丅僐乕僸乕傪堸傓偺傕丆傆偲傫偵擖傞偺傕丆偡傋偰乽帺暘偑偦偆偟傛偆偲巚偭偨偐傜乿偩偲峫偊偰偄傞丅偟偐偟丆條乆側幚尡偑偦偆偱偼側偄偙偲傪帵偟偰偄傞丅幚偼偐側傝偺晹暘偑乽偁偲偯偗乿側偺偩丅偙偺杮偼丆偦偆偟偨乽柍堄幆乿偵偮偄偰栚傪奐偐偣偰偔傟傞丅挊幰偼儔僀僗戝妛偱塸暥妛傪妛傫偩屻丆儀僀儔乕堛壢戝妛偱恄宱壢妛偺攷巑崋傪庢傞偲偄偆乽暥棟崌懱乿偺恖暔偱偁傞丅偩偐傜偙偦丆偙偺杮偼偍傕偟傠偄丅
儅僀働儖丒俽丒僈僓僯僈挊乛幠揷桾擵栿乛杮暥542暸乛俀侽侾侽擭俁寧侾侽擔敪峴乛僀儞僞僔僼僩乛ISBN978-4-7726-9518-3 C0040
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俋
|
仧側偤変乆偼孮傟傞偺偐丠 巹偨偪偼崻偭偐傜幮夛揑偩丅偦偺帠幚偼摦偐偟偑偨偄丅巹偨偪偺戝偒側擼偼壗傛傝傕幮夛揑側栤戣偵懳張偡傞偨傔偵偁傞偺偱偁傝丆尒偨傝丆姶偠偨傝丆擬椡妛偺戞擇朄懃偵偮偄偰弉峫偟偨傝偡傞偨傔偵偁傞偺偱偼側偄丅(棯)惗偒墑傃偰斏塰偡傞偨傔偵偼丆巹偨偪偼幮夛揑偵側傜偞傞傪偊側偐偭偨偺偄偆偺偑恀憡偩丅(P.122) 仧婲偒偰偄傞帪娫偺俉妱偼懠恖偲堦弿偵嶨択偟偰偄傞 恖偼婲偒偰偄傞帪娫偺俉侽僷乕僙儞僩傪懠幰偲偄偭偟傚偵夁偛偟偰偄傞偙偲偑丆偝傑偞傑側尋媶偵傛偭偰傢偐偭偨丅巹偨偪偼枅擔暯嬒偟偰俇乣侾俀帪娫傪丆偨偄偰偄偼抦傝崌偄偲侾懳侾偱丆夛榖偟偰夁偛偟偰偄傞丅儘儞僪儞丒僗僋乕儖丒僆僽丒僄僐僲儈僋僗偺幮夛怱棟妛幰僯僐儔僗丒僄儉儔乕偼丆夛榖偺撪梕偵偮偄偰尋媶偟丆俉侽乣俋侽僷乕僙儞僩偼(棯)悽娫榖偩偲偄偆偙偲傪撍偒巭傔偨丅乮P.138乯
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偼乽恖娫傜偟偝乿傪丆恑壔偺娤揰傪拞怱偵愢柧偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅500暸傪挻偊傞戝嶌偱偁傝丆撉傒墳偊偺偁傞杮偱偁傞偑丆栿偑偟偭偐傝偟偰偄傞偺偱丆僗儉乕僘偵撉傔傞丅乽愒傫朧偼傢偢偐敿擭偱乮戝恖偐傜尒偰乯枺椡揑側婄傪岲傫偱尒偮傔傞傛偆偵側傞乿側偳偲偄偭偨巚偄偑偗側偄帠幚偑悘強偵弌偰偔傞丅忋偵嫇偘偨傛偆偵丆変乆恖娫偼乽孮傟傞乿摦暔偩丅尩偟偄娐嫬偺拞偱孮傟傞偙偲偱恖娫偼懳墳偟偰偒偨丅堦旵僆僆僇儈偱偼惗偒巆傟側偐偭偨丅廤抍偐傜偼偢傟傞偲偄偆偙偲偼丆懄丆巰傪堄枴偟偰偄偨偺偩丅乽偄偠傔乿偑側偤栤戣偱偁傝丆愨懳偵偡傋偒偙偲偱偼側偄偺偐丅偦傟偼偙偺廤抍偵懏偟偰偄偨偄偲偄偆恖娫偺怱偺墱怺偔偵偁傞杮擻傪懪偪嵱偔偐傜偱偁傞丅乽僔僇僩乿傪偟偨傝丆拠娫奜傟偵偡傞偙偲偼丆乽巰偹乿偲偄偭偰偄傞偙偲偲摨摍側偺偩丅
僕僃僀儉僘丒僌儕僢僋挊乛灳堜峗堦栿乛杮暥532暸乛俀侽侾俁擭侾寧侾俆擔敪峴乛怴挭幮乛ISBN978-4-10-506411-2 C0040
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俆丏俁
|
仧忕挿偝偑幚偼忣曬揱払偵栶棫偭偰偄傞 乮傾僼儕僇偺乯僩乕僉儞僌丒僪儔儉偱丆娙扨側尵偄夞偟傪偡傞幰偼偄側偐偭偨丅屰庤偼乽壠偵栠傟乿偱偼側偔丆偙偆尵偄昞偟偨丅乽椉偺懌偵丆棃偨摴傪摜傑偣傛丅椉偺媟偵丆棃偨摴傪偨偳傜偣傛丅偍偺偑椉偺懌偲媟傪傢傟傜偑傕偺側傞懞偵棫偨偣傛乿(棯)忕挿偝乗乗掕媊忋偼丆岠棪偺埆偝乗乗偑丆崿摨傪杊偖庤抜偵側偭偰偄傞丅偮傑傝丆惓偟偄棟夝偺偨傔偺曗懌傪偟偰偄傞傢偗偩丅偳偺帺慠尵岅偵傕丆忕挿偝偑慻傒崬傑傟偰偄傞丅偩偐傜丆岆傝偩傜偗偺暥復偱傕棟夝偱偒傞偟丆偆傞偝偄幒撪偱偁偭偰傕夛榖偑惉傝棫偮丅(P.35) 仧OED偵嵹偭偨怴岅 乽Kool-Aid乿偑怴岅偲擣傔傜傟偨偺偼丆OED偑彜昗柤傕嵹偣傞媊柋偑偁傞偲姶偠偨偐傜偱偼側偔乮暡枛懄惾惔椓堸椏偺僋乕儖丒僄僀僪乻摉弶偺捲傝偼乽Kool-Ade乿乼偼丆1927擭偵傾儊儕僇偱彜昗搊榐偝傟偰偄偨乯丆乽僋乕儖丒僄僀僪傪堸傓偙偲丆揮偠偰丆慡柺揑側暈廬偁傞偄偼拤惤偺堄傪昞偡偙偲乿偲偄偆摿庩側梡朄傪傕偼傗柍帇偱偒側偔側偭偨偐傜偩偭偨丅偙偺婏堎側昞尰偑恖岥偵鋂鄑乮偐偄偟傖乯偟偨偺偼丆1978擭偵僈僀傾僫偱婲偙偭偨丆僇儖僩廆嫵抍懱偵傛傞廤抍暈撆帠審偱偙偺暡枛堸椏偑巊傢傟偨偐傜偱偁傝丆悽奅婯柾偺捠怣偑憡摉側枾搙偱峴傢傟偰偄傞偙偲偺昞傢傟偩偲尵偊傞丅(P.90)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
乽忣曬乿偺楌巎偵偮偄偰彂偐傟偨杮偱偁傞丅僶儀僢僕傕僄僀僟傕僔儍僲儞傕摉慠弌偰偔傞丅偟偐偟巹偵偼杮彂偺朻摢偺榖偑傕偭偲傕偍傕偟傠偐偭偨丅傾僼儕僇偵偼怷偺拞偺揱払庤抜偲偟偰乽僩乕僉儞僌丒僪儔儉乿偑偁偭偨丅俀庬偺壒傪巊偄暘偗偰忣曬傪揱払偡傞偺偱偁傞丅偙偺僪儔儉偑揱偊傞忣曬偼丆幚偵忕挿偱丆乽偡偖棃偄乿偲尵偊偽傛偄偺偵丆忋婰偺傛偆側傕偭偰傑傢偭偨尵偄曽傪偡傞丅偟偐偟丆忕挿偩偐傜偙偦丆彮乆搑拞偺忣曬偑徚偊偰偟傑偭偰傕丆撪梕偑揱傢傞偺偩丅乽梀傃乿偑偁傞偑屘偵丆懡彮偺忣曬偺寚棊偵懳偟偰傕乽嫮偄乿偺偱偁傞丅崱丆塅拡偼寢嬊偼乽忣曬乿偩偲尵傢傟傞丅傢傟傢傟偺懚嵼傕撍偒媗傔偰傒傟偽丆乽忣曬乿偵備偒偮偔偺偩丅杮彂偼丆恖椶偑偳偺傛偆偵忣曬偲娭傢偭偰偒偨偐傪嫽枴怺偄僄僺僜乕僪傪岎偊偰岅偭偰偔傟傞丅500暸傪挻偊傞戝嶌偩偑丆柺敀偄丅
僯僐儔僗丒僂僃僀僪挊乛徖怟桼婲巕栿乛杮暥344暸乛俀侽侽俈擭俋寧俀侾擔戞侾嶞丆俀侽侽俉擭侾寧俁侾擔戞係嶞乛僀乕僗僩丒僾儗僗乛ISBN978-4-87257-828-7
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俀俁丏侽
|
仧僔儔儈偺DNA偐傜恖椶偑暈傪拝巒傔偨帪婜傪抦傞 堚揱妛幰偺嵟嬤偺尋媶惉壥傪嫇偘傛偆丅壗偲丆恖娫偑偼偠傔偰堖暈傪朌偭偨帪戙傪悇掕偟偨偺偱偁傞丅(棯)恖娫偑堖暈傪拝偼偠傔傞偲丆傾僞儅僕儔儈偼幐傢傟偨撽挘傝傪扗娨偡傞僠儍儞僗偲偲傜偊偰丆堖暈偺側偐偱惗偒偰偄偗傞僸僩僕儔儈偵恑壔偟偨丅(棯)僸僩僕儔儈偑傾僞儅僕儔儈偐傜恑壔偟偼偠傔偨偲偒偺俢俶俙偺曄堎偵拝栚偡傟偽丆恖娫偑堖暈傪敪柧偟偨帪戙傪摿掕偱偒傞偼偢偩偭偨丅(棯)偡傞偲丆僸僩僕儔儈偑偼偠傔偰傾僞儅僕儔儈偐傜恑壔偟偨偺偼丆悢愮擭偺岆嵎偼偁傞偲偟偰傕丆偍傛偦俈枩俀侽侽侽擭慜偱偁傞偙偲偑敾柧偟偨丅(P.12) 仧恖椶偼偨偭偨侾俆侽恖偐傜弌敪偟偨 俆枩擭慜丆傾僼儕僇杒搶晹偺曅嬿偱丆彮悢偺廤抍偑屘嫿傪棧傟傛偆偲弨旛偟偰偄偨丅摉帪丆悽奅偼傑偩峏怴悽偺昘壨帪戙偵偁偭偨丅傾僼儕僇偺戝晹暘偺抧堟偱偼恖岥偑尭彮偟丆恖椶偺慶愭廤抍偼傢偢偐俆侽侽侽恖偵傑偱尭偭偰偄偨丅傾僼儕僇傪弌敪偟傛偆偲偟偰偄偨廤抍偼丆梒帣傪娷傔偰偨偭偨侾俆侽恖掱搙偩偭偨偼偢偩丅(p.22)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮傪乽幮夛乿偱側偔乽壢妛乿偺僐乕僫乕偵擖傟偨丅偦傟偼悘強偵嵟怴偺壢妛揑惉壥傪惙傝崬傫偱偄傞偐傜偩丅僀儞僷僋僩巜悢偺崅偝偐傜傕杮彂偺壙抣偑傢偐傞偩傠偆丅攦偭偰懝傪偟側偄杮偱偁傞丅巹偼亀僫僔儑僫儖僕僆僌儔僼傿僢僋亁帍偺乽僕僃僲僌儔僼傿僢僋丒僾儘僕僃僋僩乿偵嶲壛偟偰偄傞丅偙傟偼帺暘偺俢俶俙傪採嫙偡傞偲丆帺暘偺慶愭偑俆枩擭慜偵傾僼儕僇傪弌偰偐傜偳偆偄偆宱楬傪偨偳偭偰尰嵼偺抧偵摓払偟偨偐傪暘愅偟偰偔傟傞乮旓梡偼侾枩墌偔傜偄乯丅巹偼僴僾儘僌儖乕僾俷偺俵侾俈俆偵懏偟丆晝曽偺慶愭偼傾僼儕僇傪弌偰搶偵岦偐偄丆拞崙傪墶愗偭偰擔杮偵傗偭偰偒偰偄傞丅偄偢傟傕俢俶俙偲偄偆乽婰榐乿傪撉傒夝偔偙偲偱夁嫀傪抦傞偙偲偑偱偒傞偺偩丅
彫愹塸柧挊乛妏愳SSC怴彂122乛杮暥222暸乛俀侽侾侾擭俁寧俀俆擔戞侾嶞乛ISBN978-4-04-731545-7 C0247
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾係丏侽
|
仧暥朄偵娭學偡傞堚揱巕FOXP2 FOXP2偼尵岅偵娭學偡傞堚揱巕偱丆偦偙偵堎忢偑婲偙傞偲丆敪払忈奞偲偟偰尵岅偵栤戣偑婲偒傑偡丅乮棯乯僠儞僷儞僕乕傕乮棯乯傢偢偐偵堎側偭偰偄傑偡丅帺暵徢偺応崌傕偦偙偵堎忢偑偁傞働乕僗偑傢偐偭偰偄傑偡丅乮棯乯扨岅偺梾楍傑偱偼僠儞僷儞僕乕傕儃僲儃傕傢偐傞偲巚傢傟偰偄傑偡乮棯乯偑丆偄傢備傞庡岅丆弎岅丆廋忺岅側偳傗丆娭學戙柤帉側偳偑偁傞暥朄峔憿偼丆帩偭偰偄側偄偺偱偡丅偦傟傪傕偮偨傔偵偼旕忢偵傢偢偐側偙偲偱偡偑丆堚揱巕偺墫婎攝楍丆偦傟偨偨偭偨俀売強堘偆偩偗偱戝偒側摥偒傪偟偰偄傞傜偟偄丆偲偄偆偲偙傠傑偱傢偐偭偰偒偰偄傑偡丅(p.172) 仧搤偵旛偊傞摦暔偼枹棃傪峫偊偰偄傞偺偐 墇搤偺偨傔偵偄傠偄傠側傕偺傪棴傔崬傓彫摦暔偑偄傑偡偑丆乮棯乯婫愡偺曄壔偲偲傕偵丆怘傋暔傪棴傔崬傓廗惈偑堚揱巕偺宍偱巆偭偰偄傞壜擻惈偑嫮偄丅乮棯乯偨傑偨傑偦偆偟偨庬偑惗偒巆偭偰丆僯僢僠側椞堟偱偆傑偔惗懚偱偒偨偐傜丆堚揱巕偲偟偰慻傒崬傑傟偰偄傞偩偗偱偡丅(p.175) 仧憺偟傒偼恖娫摿桳偺姶忣 帺暘偺巕偳傕偑儃僗僓儖偵嶦偝傟偰傕丆偦偺偁偲儃僗偵廬偭偰堦弿偵側傞偲丆傕偆嶦偝傟偨巕僓儖偺偙偲偼朰傟偰偟傑偆丅憺偟傒偺姶忣偑側偄偺偱偡丅偙傟偼婰壇偺栤戣偱丆憺偟傒偲偄偆崅師側姶忣傪帩偨側偄偨傔偵婲偙傞偙偲偱偡丅恖娫摿桳偺姶忣偵堦偮偑憺偟傒側偺偱偡丅(p.209) |
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偺拞偱乽愨懳壒姶偼傓偟傠堦斒揑偱丆憡懳壒姶偺曽偑摿庩偱偁傞乿偲偄偆婰弎偑偁傝傑偡丅壒偺愨懳揑側崅偝偑暯峴堏摦偟偰傕乽摨偠壒乿偩偲姶偠傜傟傞乽憡懳壒姶乿偙偦廳梫偩偲偄偆偺偱偡丅娗妝婍側偳偼悂偄偰偄傞偆偪偵妝婍偑壏傑傞偲旝柇偵壒掱偑曄壔偡傞丅愨懳壒姶傪帩偮壒妝壠偼偦偆側傞偲暿偺嬋偵巚偊偰偟傑偆偺偩偲偄偆丅挊幰偼乽愨懳壒姶乿偼壒妝壠偵偲偭偰偼偄傜側偄傕偺偩偲尵偄愗傞丅儘僟儞偼僨傿僗儗僋僔傾偩偭偨偨傔偵丆晝恊偑怱攝偟偰斵傪挙崗偺摴偵恑傑偣偨側偳丆擼偵娭偡傞偍傕偟傠偄僄僺僜乕僪偑杮彂偵偼嵹偭偰偄傞丅
愇愳姴恖挊乛島択幮僽儖乕僶僢僋僗怴彂乛俀侽侾侾擭俈寧俀侽擔戞侾嶞乛
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俀丏侾
亂杮暥偐傜亃
|
仧儔儞僟儉側僨乕僞偺拞偵乽婯懃惈乿傪撉傒庢偭偰偟傑偆 僀僊儕僗偺怱棟妛幰僗乕僓儞丒僽儔僋儌傾偼丆挻忢尰徾傪怣偠傗偡偄恖偑丆嬼慠曄摦偡傞僨乕僞偐傜婯懃揑側僷僞乕儞傪傛傝懡偔拪弌偡傞孹岦傪巜揈偟偰偄傞丅愯偄岲偒偼丆偁傞帠暱偑偨傑偨傑嬼慠偵婲偒傞偲峫偊傞傛傝傕丆偦傟偑壗偐偺朄懃偵廬偭偰偄傞偲傒側偟偨偄偺偩傠偆丅(p.174) 仧僸僩偼乽懠幰偺榖傪怣偠傞乿偑婎杮 彫婯柾偺嫤椡廤抍偺拞偱巹偨偪偺怱偼丆乽懠幰偺榖傪怣偠傞乿曽岦偵恑壔偟偨丅怣擮嫟捠壔傪峴偄傗偡偄偲偆棙揰偑偁傞偐傜偩丅懠幰偼嫤椡廤抍偺儊儞僶乕側偺偱丆傑偢偼怣偠傞傎偆偑廤抍偲偟偰桳棙側偺偱偁傞丅乮棯乯偡偱偵懡條壔偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞傕偺偺丆埶慠偲偟偰懡偔偵恖乆偺怱偵偼丆乽懠幰偺榖傪怣偠傞乿偲偄偆孹岦偑懚嵼偡傞丅乮棯乯偟偐偟丆悢昐恖埲忋偺婯柾偱岎棳偑偍偙側傢傟傞幮夛偵側偭偰偟傑偭偨埲忋丆嵟掅尷偺夰媈傪恎偵偮偗偰偍偐側偄偲丆幮夛偲偟偰傕儅僀僫僗偱偁傞丅(p.149) 仧桯楈傪尒偨偲偒偼偳偆偡傞偐 桯楈偑尒偊偨傝怱楈幨恀偑偲傟偨傝偟偨側傜偽丆幮夛揑抦擻偑摥偒偡偓偰偄傞偺偩側丆偲尒側偡偺偑揔摉偩丅偦偺偆偊偱丆恖娫廤抍偺嫤椡娭學傪幚尰偟偨惗暔恑壔偺楌巎偵巚偄傪偼偣傟偽丆嫲晐姶傪崕暈偱偒傞偺偱偼側偐傠偆偐丅傑偨丆憐憸偺婎杮揑側栶妱傪抦傝丆婼傗梔惛側偳偲憐憸傪朿傜傑偣偡偓側偄偙偲偑廳梫偩丅偦偆偡傟偽丆愻擼摍偺丆埆堄傪帩偭偨峴堊傪杊巭偱偒傛偆丅(p.131)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
恖偼偦傕偦傕閤偝傟傗偡偄偺偩偲偄偆丅偣偄偤偄侾侽侽恖掱搙偺廤抍偱偼丆憡庤傪媈偆傛傝偼傑偢怣梡偡傞曽偑惗懚偵桳棙偩偭偨偐傜偩丅拠娫偐傜乽儔僀僆儞偑偄傞偧両乿偲尵傢傟偨偲偒丆傑偢偼怣梡偟偰摝偘傞丅偨偲偊忕択偱偁偭偨偲偟偰傕摝偘偨曽偑桳棙偩丅恖椶偼挿偄娫偙偆偟偨彫婯柾廤抍偺拞偱丆乽傑偢偼憡庤偺榖傪怣梡偡傞乿偲偄偆曽岦偵恑壔偟偰偒偨丅僀儞僞乕僱僢僩傗旘峴婡側偳偱晄摿掕懡悢偺恖乆偲僐儈儏僯働乕僔儑儞傪偲傞傛偆偵側偭偨偺偼丆恖椶偺楌巎偱偼偮偄嶐擔偺偙偲偩丅変乆偼乽惈慞愢傪怣偠傞乿偲偄偆偺偑僨僼僅儖僩側偺偱偁傞丅媡偵尵偊偽丆僌儘乕僶儖壔偺幮夛偵偍偄偰偼丆偁傞掱搙偺夰媈惈偑昁梫偲側偭偰偄傞偲傕尵偊傞丅
撊撪怴挊丆島択幮僽儖乕僶僢僋僗怴彂丆俀侽侽俋擭侾寧俀侽擔戞侾嶞丆ISBN978-4-06-257626-0 C0245
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俈丏俁
亂杮暥偐傜亃
|
仧俋俆俆侽嵨偺徏 庽栘偼挿惗偒偡傞傕偺偑懡偔抦傜傟偰偍傝丆擔杮偱偼撽暥悪偲屇偽傟傞壆媣悪偺僗僊偑丆庽楊俁侽侽侽擭偔傜偄偲尵傢傟偰偄傞丅偙傟偩偗偱傕丆惗暔偺屄懱擭楊偲偟偰偼攋奿側傕偺偱偁傞偑丆嵟嬤僗僂僃乕僨儞偺僣儞僪儔抧懷偱俋俆俆侽嵨偺儅僣乮Noerway spruce丗僲儖僂僃乕僄僝儅僣乯偑敪尒偝傟偨丅偨偩偟丆俋俆俆侽嵨側偺偼偙偺儅僣偺崻偺晹暘偱丆偦偙偐傜墑傃偰偄傞庽偲偟偰擣幆偝傟傞晹暘偺擭楊偼偣偄偤偄俇侽侽嵨偲撽暥悪傛傝庒偄丅(p.178) 仧巰偼師悽戙傊偺憽傝暔 抧媴忋偱惗暔傪嶌傞偙偲偺偨傔偵棙梡偱偒傞帒尮偺傎偲傫偳偼丆偡偱偵惗暔偺恎懱偲偟偰巊傢傟偰偄偨偙偲傪峫偊傞偲丆抧媴忋偵師偺悽戙偺惗暔偑尰傟傞偨傔偵偼丆偦傟傑偱偵惗偒偰偄偨惗暔偑棙梡偟偰偄偨帒尮傪庴偗搉偝側偗傟偽側傜側偄丅偮傑傝丆慜偺悽戙偺巰偼忢偵師悽戙偺僄巵暔傊偺憽傝暔偵側傞偺偩丅(p.188) 仧側偤偦偺堚揱巕偑崱擔傑偱揱傢偭偨偐傪峫偊傛 乽昦婥偺堚揱巕傪帯椕偡傞乿偲偄偆傛偆側椡偢偔偺懳墳傪偲傞偺偱偼側偔丆姵幰偺嬯捝傪庢傝彍偔懳徢椕朄傪偟側偑傜丆偦偺堚揱巕偑崱擔傑偱揱偊傜傟偰偒偨棟桼傪丆恑壔偺娤揰偐傜棟夝偟偰偍偔偙偲偑丆僸僩偺昦婥偺棟夝偵傕偮側偑傞偲偄偆偺偑丆僟乕僂傿儞堛妛偺棫応偩丅(p.136)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
僟乕僂傿儞堛妛偵偮偄偰偼偡偱偵杮僐乕僫乕偱傕儔儞僪儖僼丒M丒僱僔乕懠挊偺亀昦婥偼側偤丆偁傞偺偐亁傪徯夘偟偨丅変乆偵偲偭偰昦婥偼幚偵婖傓傋偒傕偺偱偁傞偑丆偟偐偟丆側傜偽乽偦傟偼側偤崱傕懚嵼偡傞乿偺偐丠丂乽揔幰惗懚乿傪彑偪敳偄偰偒偨偺偑変乆偱偁傞偺側傜丆偙偆偟偨惗懚偵晄棙側傕偺偼偲偭偔偺愄偵徚偊偰偄偰偄偄偺偱偼側偄偺偐丠丂乽崱偁傞乿偲偄偆偙偲偼丆尒曽傪曄偊傟偽乽昁梫偲偟偰偁傞乿偺偱偼側偄偐丠丂偙偆僟乕僂傿儞堛妛偼帺栤偡傞丅慡偔偺敪憐偺揮姺偩丅敪擬丆歲揻丆奝丆偔偟傖傒乗乗偙傟傜偺乽晄夣姶乿偼懱偑僂僀儖僗傗嵶嬠偵斀墳偟偰丆懱傪惓忢偺傕偳偦偆偲偟偰偄傞夁掱偱偁傞丅偄偨偢傜偵栻偵棅傜偢丆偙偺晄夣姶偵偟偽傜偔偼恎傪擟偣傞偙偲偑帯桙偵偮側偑傞偲偄偆偺偩丅僟乕僂傿儞堛妛偼寛偟偰乽塻偄愗傟枴乿偺妛愢偱偼側偄偑丆偟偐偟愢摼椡偼偁傞丅
僕僃僼儕丒D丒儘乕僛儞僞乕儖挊丆僲儞僼傿僋僔儑儞丂僴儎僇儚暥屔丆俀侽侾侽擭俈寧侾俆擔敪峴丆ISBN978-4-15-050369-7
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俆丏俁
亂杮暥偐傜亃
|
仧戝悢偺朄懃 儔儞僟儉側弌棃帠傕搙廳側傞偲丆寢壥偺妱崌偼暯嬒抣偵偳傫偳傫嬤偯偔丅(棯)偙傟偼偨傫側傞悇應偱偼側偔丆乽戝悢乮偨偄偡偆乯偺朄懃乿偲屇偽傟傞朄懃側偺偩丅偙偺朄懃傛傟偽丆壗偱偁傟儔儞僟儉側帠徾傪廫暘側夞悢孞傝曉偡偲丆傗偑偰岾塣傕晄塣傕挔徚偟偵側傝丆傎傏乽揔惓側乿暯嬒抣丆偮傑傝丆恀偺妋棪偵嬤偄暯嬒抣偑摼傜傟傞偙偲偵側傞丅(p.50) 仧儘僀儎儖丒僼儔僢僔儏偺妋棪偼65枩暘偺1 乮惣晹寑偱乯偁傝偑偪側偺偼丆庤嶥偑偦傠偆偲丆僸乕儘乕偑儘僀儎儖僼儔僢僔儏乮摨堦慻偺10丆僕儍僢僋丆僋僀乕儞丆僉儞僌丆僄乕僗偲偄偆慻傒崌傢偣乯偱彑偮偲偄偆応柺偩偗傟偳丆偙傫側偙偲偼丆傎傫偲偆偵婲偒傞偺偩傠偆偐丠丂尰幚偵偼5枃偺庤嶥偺慻傒崌傢偣偼260枩捠傝嬤偔偁傞偲偄偆偺偵丆偦偺偆偪儘僀儎儖僼儔僢僔儏偼偨偭偨4捠傝偟偐側偄丅(棯)儘僀儎儖僼儔僢僔儏偵側傞妋棪偼260枩暘偺4丆偮傑傝丆65枩暘偺1偟偐側偄丅偲傫偱傕側偔婬側弌棃帠側偺偩丅(p.86) 仧僎乕儉偵彑偮僐僣 塣偺僎乕儉偵彑偮僐僣偼嶰偮偁傞丅戞堦偵丆僎乕儉傪擮擖傝偵尋媶偟偰丆暯嬒偡傟偽彑偪偵側傞愴棯傪尒偮偗弌偡偙偲丅戞擇偵丆偦偺愴棯傪壗搙傕孞傝曉偟偰幚峴偡傞偙偲丅偦偟偰丆戞嶰偵丆恏書嫮偔懸偮偙偲偩丅偄偮偐傗丆乽戝悢偺朄懃乿偑偁側偨偵彑棙傪傕偨傜偟偰偔傟傞偼偢側偺偩偐傜丅(p.110) 仧婲偙傞妋棪偑偒傢傔偰掅偄弌棃帠偼柍帇偣傛 儔儞僟儉惈偵偐偐傢傞寛抐傪壓偡偲偒偺戞堦偺儖乕儖偼丆乽婲偒傞妋棪偺偒傢傔偰掅偄弌棃帠偼丆偍偍傓偹柍帇偟偨曽偑偄偄乿偩丅偙傟偼側傫偲傕扨弮側儖乕儖偩偗傟偳傕丆偨偄偰偄偺恖偼庣傜側偄丅(棯)崱廡傕扤偐偑乮曮偔偠偵乯摉慖偡傞偐傕偟傟側偄丅偗傟偳巹偑曐徹偟傛偆丅偦傟偼丆偗偭偟偰偁側偨偱偼側偄丅(p.134) 仧儐僯乕僋側嬛墝僐儅乕僔儍儖 侾擭娫偱棊棆偱巰偸恖偼丆傾儊儕僇恖偺偍傛偦600枩恖偵1恖偵偡偓側偄丅(棯)傂偳偄棆塉偺拞丆嶳偺偰偭傌傫偵堦恖偺彈惈偑挿偄嬥懏偺朹傪埇傝掲傔偰棫偭偰偄傞丅棆偝傑丆偝偁偳偆偧丆偲尵傢傫偽偐傝偩丅偦偺斵彈偑丆偙偆愢柧偡傞丅偙傫側偙偲傪偡傞側傫偰丆摢偑偍偐偟偄偲巚偆偐傕偟傟側偄偗傟偳丆僞僶僐傪媧偆嬸偐偝偵斾傋偨傜側傫偱傕偁傝傑偣傫丆偲丅(p.197)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
妋棪傪埖偭偨杮偩偑丆偗偭偟偰擄偟偔偼側偄丅悢幃偼偱側偄偺偱晐偑傞昁梫傕側偄丅傓偟傠丆妋棪偵傑偮傢傞條乆側僄僺僜乕僪偑師乆偲弌偰偔傞丅堦椺傪偄偆偲丆戞擇師戝愴拞暷崙偼嬌旈偱尨敋惢憿偺儅儞僴僢僞儞寁夋傪恑傔偰偄偨丅偟偐偟尨敋傪嶌摦偝偣傞偺偵昁梫側擹弅僂儔儞偺検偑偳偆偟偰傕傢偐傜側偐偭偨丅偦偙偱斵傜偼抋惗傑傕側偄僐儞僺儏乕僞傪巊偭偰楢嵔斀墳偲拞惈巕偺怳傞晳偄傪儔儞僟儉偵僔儈儏儗乕僔儑儞偟偨丅偦傟傪傂偨偡傜孞傝曉偡偆偪偵丆尨巕敋抏偺拞偱拞惈巕偑暯嬒偡傞偲偳偺傛偆偵怳傞晳偄丆偦偺偆偪偺偳傟偩偗偑弌偰偔傞偐偑丆偟偩偄偵惓妋偵偮偐傔偰偒偨丅偦偟偰偮偄偵15僉儘僌儔儉偲偄偆椪奅検傪嶼弌偟偨丅偙傟偑乽儌儞僥僇儖儘丒僒儞僾儕儞僌朄乿傪棙梡偟偨嵟弶偺僐儞僺儏乕僞丒僔儈儏儗乕僔儑儞偲側偭偨丅
億乕儖丒僽儖乕儉挊丆儔儞僟儉僴僂僗島択幮丆俀侽侽俇擭俀寧俉擔戞侾嶞丆ISBN4-270-00119-4
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俆
亂杮暥偐傜亃
|
仧恖庬偼崻怺偔偰埆偄峫偊 恖庬僇僥僑儕乕偼惗暔奅偵偍偗傞晄婯懃惈偲懳墳偟偰偄側偄丅垷庬傗宯摑偑偼偭偒傝暘偗傜傟偰偄側偄偟丆庬偛偲偺堚揱揑側堘偄傕嵟彫尷偟偐側偄丅惗暔妛幰傗恖椶妛幰偑乽恖庬側偳偲偄偆傕偺偼懚嵼偟側偄乿偲尵偆偺偼丆偦偺偨傔側偺偩丅(棯)恖庬揑側暘椶偼幮夛揑丆暥壔揑側梫場偵戝偒偔塭嬁偝傟傞丅(棯)傕偟恊偺堦恖偑傾僼儕僇弌恎偱丆傕偆堦恖偑儊僉僔僐弌恎偩偭偨傜丆偦偺巕偳傕偼崟恖偩傠偆偐丠(棯)偦偙偐傜丆恖庬偼恖岺偺嶻暔偱偁傞偲偺廳梫側峫偊曽偑弌偰偔傞丅偮傑傝恖庬偲偄偆奣擮偼恖娫偑嶌傝偩偟偨傕偺偱偁傝丆帺慠偵傛傞傕偺偱偼側偄丆偲偄偆傕偺偩丅(棯)恖椶妛幰偺儘乕儗儞僗丒僸儖僔儏僼僃儖僩偑偙偆婰偟偰偄傞丅 乽恖庬偲偄偆峫偊偼扨側傞埆偄峫偊偱偼側偄丅崻怺偔埆偄峫偊側偺偩乿(p.70) 仧僒僀僐僷僗 斵傜乗乗偦偺傎偲傫偳偼抝惈乗乗偼娫敳偗偱傕柍抦偱傕側偔丆帺暘偺峴摦偺寢壥傪棟夝偡傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丆偩偐傜偲偄偭偰峴摦傪曄偊傞偙偲偼側偄丅斵傜偼摴摽姶忣傪傑偭偨偔寚偄偰偄傞偐丆彮側偔偲傕晛捠偺恖乆偲摨掱搙偺摴摽姶忣傪傕偭偰偼偄側偄偺偩丅斵傜偼埆傪峴偄丆帺暘偱傕偦傟傪擣幆偟偰偄傞丅(棯)戇曔偝傟偨楢懕嶦恖斊偺僥僢僪丒僴儞僨傿偼丆恖乆偑嶦恖傪傔偖偭偰戝憶偓偡傞偙偲偵崲榝偟偨丅乽偩偭偰丆恖娫偼偨偔偝傫偄傞偠傖側偄偐乿 僒僀僐僷僗偼惛恄忈奞幰偲偟偰埖傢傟偰偄傞偑丆惓幃側昦柤偼乽斀幮夛揑恖奿忈奞乿偱偁傞丅(棯)僒僀僐僷僗偺尨場偼夝柧偝傟偰偄側偄丅偙偺忈奞偼丆憗偗傟偽巕偳傕偺偙傠偵尰傟傞丅僒僀僐僷僗偼彫摦暔偵巆媠側峴堊傪偟丆忢偵塕傪偮偒丆懠幰傊偺摨忣傗嫟姶傪傎偲傫偳昞偝側偄丅(p.130) 仧侾嵨偵側傞偲懠幰傊偺嫟姶偑尰傟傞 侾嵨偺抋惗擔傪寎偊傞崰偵偼丆懠幰偵恀偺嫟姶傪婑偣傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傞丅侾嵨帣偼憡庤傪彆偗傛偆偲丆側偩傔傞傛偆側惡傪忋偘偰桪偟偔側偱傞丅偙偺峴摦偐傜偼丆懠幰偺捝傒偑帺暘偺捝傒偲堎側傞偙偲偲丆壗偑捝傒傪寉偔偡傞偐傪棟夝偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅(p.152)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
彫摦暔傊偺巆媠側峴堊偐傜巆媠側嶦恖乗乗偲偒偍傝僯儏乕僗偱尒傞偙偲偩偑丆懠幰傊偺嫟姶丆摴摽姶偑姰慡偵寚偗偨徢椺偲偟偰杮彂偱傕怗傟傜傟偰偄傞丅偍偦傜偔崱屻偺尋媶偱丆怱棟妛偱偼側偔堚揱妛丒擼奜壢妛偑偦偺尨場傪撍偒偲傔傞偙偲偩傠偆丅杮彂偼懠幰傊偺嫟姶偑偄偮尰傟傞偺偐丆傑偨偦傟傜偑寚擛偟偨昦婥偵偳偺傛偆側傕偺偑偁傞偐側偳偑傢偐傝傗偡偔愢柧偝傟偰偄傞丅
俹丏儖僋乕僞乕丆俰丏僶乕儗僒儞挊丆拞墰岞榑怴幮丆俀侽侾侾擭侾侾寧俀俆擔弶斉丆ISBN978-4-12-004307-9
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俀侾丏俀
亂杮暥偐傜亃
|
仧僫億儗僆儞孯偼儃僞儞偺偣偄偱晧偗偨丠 側偤丆偦傟傑偱彑偪懕偗偰偄偨僫億儗僆儞孯暫巑偑儘僔傾墦惇偱偮傑偯偄偨偺偐丠丂(棯)丂嬃偔偐傕偟傟側偄偑丆僫億儗僆儞孯偺攋柵偼丆儃僞儞偺憆幐偺傛偆側彫偝側偙偲偵婲場偡傞偐傕偟傟側偄丅(棯)庎偺儃僞儞偼丆彨峑偺奜搮偐傜曕暫偺僘儃儞傗忋拝偵傑偱巊傢傟偰偄偨丅壏搙偑壓偑傞偲岝傝婸偔嬥懏偺庎偼曄壔偟巒傔丆嬥懏傜偟偐傜偸傕傠偄奃怓偺暡偵側偭偰偟傑偆丅(棯)斵傜偼丆孯暈偺儃僞儞偑側偔側傝丆姦偝偵懴偊傜傟側偔側偭偰丆暫巑偲偟偰摥偗側偔側偭偨偺偱偼側偄偐丠丂儃僞儞偺憆幐偼丆椉庤偑晲婍傪塣傇傛傝奜搮偺慜傪崌傢偣傞偺偵巊傢傟偨偙偲傪堄枴偟側偄偐丠 (p.6) 仧儅僛儔儞偺悽奅堦廃偱婣偭偨偺偼偨偭偨侾妱 1519擭偐傜1522擭偵傢偨傞儅僛儔儞偺悽奅堦廃峲奀偱偼丆90%埲忋偺忔慻堳偑惗偒偰婣傟側偐偭偨丅偦偺戝晹暘偼夡寣昦偵傛傞丅偙傟偼傾僗僐儖價儞巁暘巕丆偡側傢偪怘帠偐傜愛傞價僞儈儞俠偺晄懌偱婲偒傞嫲傠偟偄昦婥偱偁傞丅(p.39) 仧屆戙儘乕儅婱懓偼墧拞撆偩偭偨 偙傟乮恷巁墧乯偼儘乕儅掗崙偺帪戙丆儚僀儞傪娒偔偡傞偺偵巊傢傟偨丅(棯)堦斒偵墧偺墫偼娒偄偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅偟偐偟(棯)偡傋偰偼桳撆偱偁傞丅恷巁墧偼旕忢偵傛偔梟偗丆撆惈偼儘乕儅恖偵偼偼偭偒傝暘偐傜側偐偭偨丅(棯)儘乕儅恖偼傑偨儚僀儞傗懠偺堸傒暔傪墧偺梕婍偵擖傟偰偄偨丅傑偨墧偺僷僀僾偱悈傪壠傑偱堷偄偰偄偨丅墧拞撆偼拁愊惈偱偁傞丅墧偼恄宱宯丆惗怋婍姱丆偦偺懠偺憻婍傪怤偡丅嵟弶偺拞撆徢忬偼丆悋柊忈奞丆怘梸晄怳丆偄傜偩偪丆摢捝丆暊捝丆扙椡姶偱偁傞丅惛恄慡懱偺晄埨掕偝偲杻醿偵偮側偑傞偺擼偺忈奞傕彊乆偵婲偙傞丅偁傞楌巎壠偼儘乕儅掗崙偺悐戅傪墧拞撆偺偣偄偵偡傞丅峬掕僱儘傪娷傓懡偔偺巜摫幰偑偙偆偟偨徢忬傪帵偟偨偲偄偆婰榐偑偁傞偐傜偩丅(p.71)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
傑偨傑偨僀儞僷僋僩巜悢俀侽傪撍攋偟偨杮偺弌尰偱偁傞丅杮彂偼壔妛暔幙偑恖娫偺楌巎偵偳偺傛偆側栶妱傪壥偨偟偨偐偵偮偄偰彂偐傟偰偄傞丅崅峑偺壔妛偺帪娫偵廗偭偨乽婽偺峛乿傗壔妛幃傕弌偰偔傞偑偦傟偑傢偐傜側偔偰傕戝忎晇偩丅戝峲奀帪戙傪惗傫偩層灒偺僺儁儕儞傗僫僣儊僌偺僀僜僆僀僎僲乕儖丆僶僀僉儞僌傗儅僛儔儞傪擸傑偣偨價僞儈儞俠乮傾僗僐儖價儞巁乯偺晄懌丆嶻嬈妚柦丒撿杒愴憟丒敋栻丒幨恀丒塮夋丒崌惉慇堐側偳暆峀偄暘栰偲娭學偡傞僙儖儘乕僗丆搝楆杅堈丒僠儏乕僀儞僈儉丒僑儉丒僞僀儎側偳偲娭學偡傞僀僜僾儗儞丒丒丒杮彂傪撉傔偽丆偙偆偟偨壔妛暔幙偺敪尒偑側偗傟偽崱偺暥柧偼偁傝摼側偐偭偨偙偲偑傛偔傢偐傞丅
D丒傾僋僯乕儖丆P丒僼儔僀僶乕僈乕挊丆怴梛幮丆侾俋俋俆擭俁寧侾俆擔戞侾嶞丆ISBN978-4-7885-0515-0
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俋
亂杮暥偐傜亃
|
仧嵒嶳偺僷儔僪僢僋僗乗乗楢嵔幃悇榑 嵒嶳偐傜堦棻偺嵒傪庢傝嫀偭偰傕丆偦偙偵偼嵒嶳偑偁傞丅傕偆堦棻庢傝嫀偭偰傕丆偦傟偼嵒嶳偱偁傞丅偦傟傪懕偗偰偄偗偽丆偄偮偐偼堦棻偺嵒偑巆傞丅偦傟偼傑偩嵒嶳偐丅嵟屻偺堦棻傪庢傝嫀傟偽丆偦偙偵偼壗傕側偔側傞丅偦偆側偭偰傕嵒嶳偐丅嶳偱側偄偲偡傟偽丆偄偮丆偦傟偼嵒嶳偱偁傞偙偲傪傗傔偨偺偐丅(p.31) 仧懚嵼偡傞傕偺偼偡傋偰楢懕偡傞 僷乕僗偼悽奅傪恀偐婾偵傢偗傞乽慞恖偲埆恖傊擇暘偡傞懚嵼乿傪攏幁偵偟偰偄偨丅傓偟傠丆懚嵼偡傞傕偺偼偡傋偰楢懕偟偰偄偰丆偦偆偟偨楢懕偑抦幆偺婎弨偲側傞偲峫偊偰偄偨丅(p.34) 仧柧擔偼愥偑崀傞偐傕偟傟側偄
偙偺暥偺斲掕偼,
乽柧擔偼愥偼崀傜側偄乿偼恀偱偁傞丅
儖僼傽僔僃償傿僢僣偼丆偙傟偵暿偺暥傪壛偊傞丅
乽柧擔偼愥偑崀傞乿偐傕偟傟側偄丅
偙偺暥偼1/2偺抣傪傕偮丅偙偺暥偺斲掕偼丆
乽柧擔偼愥偼崀傜側偄乿偐傕偟傟側偄丅
偙偺暥傕1/2偺抣傪傕偮丅摉慠丆1/2=1/2偩偐傜乽暥亖斲掕暥乿偩偲傢偐傞丅(棯)壠偑敿暘偱偒偨偲偄偆偙偲偼丆壠偼敿暘偱偒偰偄側偄偲偄偆偙偲偩丅(p.37)
仧擼偼忣曬傪乽埑弅偟偰乿棟夝偡傞
恖娫偺擼傕偨偊偢姶妎婍姱偐傜偺忣曬傪梫栺偟偰偄傞丅嵶晹偐傜側傞朿戝側検偺忣曬傪擣抦偱偒傞戝偒偝偵埑弅偟偰偄傞偺偩丅偨偲偊偽丆恖娫偺栐枌傪嶌偭偰偄傞偍傃偨偩偟偄岝傪姶偠傞嵶朎偼丆擼偑撉傒夝偔偵偼偁傑傝傕偵懡偡偓傞忣曬傪庴偗偲傔偰偄傞丅偦偙偱丆棳傟崬傓忣曬傪傆傞偄偵偐偗丆埑弅偡傞曽嶔偑偲傜傟傞丅梫栺偡傞偺偱偁傞丅(p.61)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
惣梞偼婎杮揑偵擇暘朄傪岲傓丅敀偐崟偐丆偒偭傁傝偟偨偄偺偩丅奃怓側偳偲尵偆乽偁偄傑偄乿側懚嵼偼擣傔偨偔側偄丅榩娸愴憟偱僽僢僔儏偼悽奅偵岦偗偰壗偲偄偭偨偐丅乽傾儊儕僇懁偵偮偔偺偐丆偦傟偲傕僥儘偺懁偵偮偔偺偐乿偲擇幰戰堦傪敆偭偨丅偟偐偟搶梞偵偼偙偺揱摑偼側偄丅傓偟傠擔杮偼偁偄傑偄偝傪寍弍偺堟傑偱杹偒忋偘偨丅乽偦傟偼偳偺偔傜偄偺帪娫偐偐傝傑偡偐乿偲偄偆栤偄偵丆乽俀帪娫偐偐傝傑偡乿偲偄偆摎偊曽偼偒偭傁傝偟夁偓偰偄偰擔杮揑偱偼側偄丆乽俀帪娫傎偳偐偐傝傑偡乿偑惓偟偄丅杮彂偵偼偙偺傛偆側惣梞偲搶梞偺堘偄偵偮偄偰傕徻偟偔怗傟偰偄傞丅僼傽僕傿棟榑偼丆傓偟傠偦偆偟偨乽偁偄傑偄偝乿傪愊嬌揑偵昞尰偟丆乽悢抣揑偵乿昞偟偰偄偙偆偲偡傞丅偨偲偊偽恎挿侾m75cm偱慄傪堷偔丅偙傟傛傝崅偗傟偽乽攚偑崅偄乿丆掅偗傟偽乽攚偑掅偄乿偲擇暘朄偱偼側傞丅傢偢偐1cm忋夞偭偰1m76cm偺恖偱傕乽攚偑崅偄乿偲側偭偰偟傑偆偺偩丅偟偐偟僼傽僕傿棟榑偱偼丆偨偲偊偽乽0.6偩偗攚偑崅偄乿偲偄偆傛偆側尵偄曽偵側傞丅
嶁尦巙曕挊丆壔妛摨恖幮丆俀侽侾侽擭侾寧俁侾擔戞侾嶞丆ISBN978-4-7598-1294-7
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俆丏俀
亂杮暥偐傜亃
|
仧SRY偑抝惈壔傪寛掕偡傞 庴惛屻7廡栚崰偵丆惗怋態偺嵶朎偱Y愼怓懱忋偵偁傞SRY偲偄偆堚揱巕偑偼偨傜偒巒傔傞偲丆抝偺巕傊偲惉挿傪巒傔傞偙偲偵側傞丅SRY偼惛憙寛掕堚揱巕偲屇偽傟丆偙偍値堚揱巕偑偼偨傜偔偲丆偦偺壓埵偵偁傞堚揱巕偺僗僀僢僠偑師偮偓偲擖傝丆惗怋態偑惛憙傊偲曄壔偟偰偄偔丅(棯)偨偲偊丆嵶朎偑XY宆乮抝惈宆乯偱Y愼怓懱傪傕偭偰偄偨偲偟偰傕丆傕偟SRY堚揱巕偑偼偨傜偐側偗傟偽丆恎懱偼彈惈偵側傞丅(p.13) 仧摦揑暯峵 傾儊儕僇偺暘巕惗暔妛幰偱偁傞儖僪儖僼丒僔僃乕儞僴僀儅乕攷巑偺儅僂僗偺幚尡偵傛傟偽丆3擔娫偱丆恎懱傪峔惉偡傞敿暘埲忋偺暔幙偑擖傟姺傢傞丅僔僃乕儞僴僀儅乕攷巑偑敪尒偟偨乽摦揑暯峵乿偲屇偽傟傞帠幚偩丅乮恵夑拲丂暉壀怢堦巵偺亀摦揑暯峵 亁傪嶲徠乯(p.17) 仧惗偒暔偺嵶朎偱嵟戝偺傕偺偼棏巕丆嵟彫偼惛巕 惗偒傕偺偑偮偔傞嵶朎偺側偐偱丆棏巕偼嵟傕戝偒側嵶朎偱偁傝丆惛巕偼捠忢嵟傕彫偝偄嵶朎偱偁傞丅(p.23) 仧戀帣婜偵偱偒偨擼偺偟傢偼堦惗曄傢傜側偄 庴惛屻6儠寧偔傜偄傑偱偺戀帣偺擼偼丆昞柺偑僣儖僣儖偟偰偄傞丅(棯)庴惛屻25廡栚偙傠偵偼丆僯儏乕儘儞偺宍惉丆堏摦丆楢寢偑恑傒丆旂幙偼愜傝偨偨傑傟巒傔傞丅懡悢偺恄宱慇堐偱寢偽傟偨椞堟偺娫偑嫮偔堷偭挘傜傟偰乽夞乿偲偄偆棽婲偵側傝丆庛偔偮側偑偭偨椞堟偑乽峚乿偵側傞丅偙偆偟偰丆偟傢傗峚偺埵抲偑屌掕偝傟丆惗奤偵傢偨偭偰曄傢傞偙偲偼側偄丅(棯)偟傢傗峚側偳偺戝擼旂幙慡懱偺宍忬偑丆峫偊偰偄傞埲忋偵巹偨偪偺惈奿傗惈幙傪巟攝偟偰偄傞壜擻惈偑偁傞丅(p.186) 仧擼偺僯儏乕儘儞偼巰偸傑偱惗偒懕偗傞 僯儏乕儘儞偼傎偐偺懡偔偺嵶朎偲偼堎側傝丆堦搙惉弉偡傞偲丆屄懱偺堦惗偺娫摨偠嵶朎偑惗偒懕偗傞偙偲偑懡偄丅(棯)偮傑傝丆100嵨偺榁恖偺擼偺傎偲傫偳偼丆100嵨偺恄宱嵶朎偵傛偭偰峔惉偝傟偰偄傞丅(p.188)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偼偙偺杮偺1暸偵偁傞婰弎偵嬃偄偨丅巹偼棏巕傕惛巕偲摨偠偔彈惈偺暵宱傑偱偼偨偊偢嶌傜傟懕偗偰峴偔傕偺偲偽偐傝巚偭偰偄偨丅幚偼偦偆偱偼側偄丅杮彂偵傛傞偲丆棏巕乮棏尨嵶朎乯偼丆彈惈偑傑偩曣恊偺戀撪偵偄傞偲偒偵500枩屄嶌傜傟丆偦偺屻偼擇搙偲惗嶻偝傟側偄丅偟偐傕丆偙偺500枩屄偼抋惗帪偵偼200枩屄丆巚弔婜傑偱偵偼4枩屄偵傑偱尭傝丆50嵨偔傜偄偱0偵側傞丅偟偐傕丆惗怋壜擻側帪婜偵攔棏偝傟傞偺偼偨偭偨400屄偩偲偄偆偺偩丅抝惈偑堦惗偵栺1挍屄嶌傞惛巕偲堎側傝丆棏巕偼婱廳側懚嵼側偺偩丅偙偺杮偼丆偙偆偟偨変乆偑抦傜側偐偭偨帠幚傪嫵偊偰偔傟傞丅
僙僗丒僔儏儖儅儞挊丆媑揷嶰抦栿丆擔宱BP幮丆俀侽侾侽擭俋寧俀俈擔戞侾嶞丆ISBN978-4-8222-9439-8
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧乽儚僩僜儞孨丆棃偰偔傟丅梡偑偁傞傫偩乿偼僂僜 偙偺揹榖抋惗偺弖娫偺榖傪丆僉儍僢僜儞偲摨偠傛偆側宍偱昤偄偰偄傞暥專傕丆島榖傕丆怴暦婰帠傕丆偙傟偑婲偙偭偨偼偢偺1870擭戙偵偼傑偭偨偔尒偁偨傜側偐偭偨丅巹偑巊偊傞忣曬尮偡傋偰挷傋偰丆儀儖帺恎偝偊傕丆崱擔偱偼桳柤偵側偭偰偄傞丆偙偺榖傪岞偵岅偭偨偙偲偼堦搙傕側偐偭偨偙偲傪妋擣偟偨丅(p.249) 仧偄偭偨傫掕拝偟偨僀儊乕僕偼梕堈偵偼曄偊傜傟側偄 悽娫堦斒偵偼丆儀儖偼揹榖偺桞堦偺敪柧幰偲偟偰婰壇偝傟偰偄傞丅乮棯乯斵偵晄棙側徹嫆偑師乆偲朄掛偱柧傜偐偵側偭偨偵傕偐偐傢傜偢丆儀儖偑撈椡偱揹榖傪敪柧偟偨偲偄偆揱愢偑偄偭偨偄偳偆偟偰柍彎偱惗偒巆傟偨偺偐丆傢偨偟偵偼偳偆偟偰傕銬偵棊偪側偄丅乮棯乯戝惃偺偝傑偞傑側尋媶幰偨偪偑100擭埲忋偵傢偨傝丆婰榐傪掶惓偟傛偆偲椡傪拲偄偱愨偊偢栆峌寕傪偐偗偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丆戝廜偑帩偭偰偄傞儀儖偼執戝側恖暔偩偲偄偆僀儊乕僕偑偙傟傎偳傑偱偵梙傞偓側偄偺偼偳偆偟偰偐丆偲偄偆偙偲偩丅(p.237) 仧儀儖偼僌儗僀偺摿嫋傪搻傒尒偰丆帺暘偺傕偺偲偟偰怽惪偟偨 僌儗僀偺摿嫋僋儗乕儉偺3暸栚偵偁傞丆斵偑昤偄偨帺恎偺敪柧昳偺棯恾傪尒偰丆傢偨偟偼(棯)僔儑僢僋傪庴偗偨偺偱偁傞丅傢偨偟偼偡偖偝傑丆偙傟偲傎偲傫偳傑偭偨偔摨偠恾傪偮偄愭擔丆尒偨偽偐傝偩偲婥偯偄偨偺偩乗乗偦傟傕丆儀儖偺幚尡僲乕僩偺側偐偱丅偙傟偑壗傪堄枴偡傞偐偼弖娫揑偵傢偐偭偨丅(棯)儀儖偼儚僔儞僩儞傊偺椃偐傜儃僗僩儞偺幚尡幒偵栠偭偰丆偦傟傑偱懕偗偰偒偨堦楢偺宯摑偩偭偨扵媶傪曻婞偟偰丆嫞憟憡庤偺敪柧傪傎傏偦偭偔傝帺暘偺僲乕僩偵昤偄偨偺偩丅 仧儀儖偼偦偺敪柧偺妀偲側傞尨棟傪丆屻偱巚偄偮偄偨偐偺傛偆偵怽惪彂偵乽庤彂偒乿偱彂偒壛偊偨 偙偺乮儀儖偺弌婅摿嫋乯偺尨杮偱偼丆傂偲偮偺僷儔僌儔僼偑丆儀儖偺傕偺偲巚傢傟傞昅愓偱丆嵍懁偺梋敀偵彂偒崬傑傟偰偄傞丅(棯)偙傟偧傑偝偟偔丆揹榖傪壜擻偵偟偨嫮椡側僋儗乕儉偱偁傝丆偙偺僋儗乕儉偑偁偭偨偐傜偙偦丆(棯)嵟廔揑偵偼偳偺朄掛傕儀儖偺摿嫋傪巟帩偟偨偺偱偁偭偨丅(棯)僀僊儕僗偺媄弍幰丆僕儑儞丒僉儞僌僘僶儕偑憗偔傕1915擭偵師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅 敪柧幰偑丆帺暘偺敪柧偺梫偲側傞摿挜傪丆嵟屻偺弖娫傑偱尒棊偲偟偰偄傞側偳丆偁傑傝偵柇偱偼側偄偐丠(p.219)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
懡悢偺僲乕儀儖徿庴徿幰傪攜弌偟偰偄傞偁偺乽儀儖尋媶強乿偵傑偱丆柤慜偑巊傢傟偰偄傞傾儗僋僒儞僟乕丒僌儔僴儉丒儀儖偩偑丆傕偆100擭埲忋偵傕傢偨偭偰丆乽揹榖婡敪柧偺晝乿偵偮偄偰偼庢傝偞偨偝傟偰偒偨丅杮彂偼偦傟傪偝傜偵嫮偔棤偯偗傞傕偺偱偁傞丅儀儖偑儚僔儞僩儞偺摿嫋挕偵峴偭偰丆摿嫋怰嵏姱僂傿儖僶乕偵100僪儖巻暭傪搉偟丆儔僀僶儖偱偁偭偨僀儔僀僔儍丒僌儗僀偺壖摿嫋傪侾帪娫偐偗偰尒偨丅偙傟偼摿嫋怰嵏姱僂傿儖僶乕杮恖偑嫙弎彂偵偙偺傛偆偵弎傋丆彁柤偟偰偄傞偺偩丅偦傕偦傕儀儖偼丆桾暉側婇嬈壠偺僷僩儘儞偵偟偰丆摉帪巊傢傟偰偄偨揹怣婡傪巊偭偰暋悢偺忣曬傪憲傟側偄偐偲偄偆尋媶傪偟偰偄偨丅斵偼壒惡偺揱払憰抲偵偮偄偰偼慡偔峫偊偰傕偄側偐偭偨偺偩丅偦傟偑撍擛丆摿嫋怽惪偺捈慜偵壒惡揱払曽幃偑乽庤彂偒偱乿彂偒崬傑傟偰偄傞丅夁偪傪惓偡偵抶偡偓傞偲偄偆偙偲偼側偄丅壢妛傗楌巎丆偄傗偄偐側傞暘栰偱偁傠偆偲傕丆怴帠幚偑柧傜偐偵側偭偨応崌偼丆惀惓偝傟傞偺偼摉慠偩傠偆乗乗揹榖婡傪柧偟偨偺偼僌儔僴儉丒儀儖偱偼側偄丅
愳岥弤堦榊挊丆旘捁怴幮丆俀侽侾侾擭俀寧侾俁擔戞侾嶞丆ISBN978-4-86410-063-2
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俉丏俀
亂杮暥偐傜亃
|
仧斱孅偵側傜側偄 偙偺乮NASA偲偺乯岎徛夁掱偱丆堦偮偩偗巹偑娞偵柫偠偰偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅偦傟偼斱孅偵側傜側偄偙偲丅NASA偼塅拡奐敪偺戝愭攜偱偁傝丆嫄恖偱偼偁傞偗傟偳丆巹偨偪傕崙壠僾儘僕僃僋僩偲偟偰擔偺娵傪攚晧偭偰偄傑偟偨丅壗偐傪屼婅偄偡傞偩偗偩偲摢傪壓偘懕偗傞偙偲偵側傝傑偡丅偦偆偱偼側偔乽巹偨偪偼偙偆偄偆採嫙偑偱偒傞偐傜丆偙偺晹暘偱椡傪戄偟偰傎偟偄乿偲偄偆巔惃傪娧偒傑偟偨丅巹偨偪偑怱偺掙偐傜乽偼傗傇偝乿偺惉岟傪屩傟傞強埲偱偡丅(p.175) 仧墦偔偲傕丆岝偑尒偊偰偄傟偽曕偄偰峴偗傞 惻廂偑棊偪崬傒丆幮夛暉巸偵峴偒媗傑傞偺偼丆彮巕壔偑尨場偲尵傢傟傑偡偑丆彮巕壔傪彽偄偰偄傞偺偼丆彨棃偵懳偡傞晄埨偱偟傚偆丅崱偼側傫偲偐曢傜偟偰偄傞偗傟偳丆偙偺愭偳偆側偭偰偟傑偆偺偩傠偆偐偲偄偆晄埨丅偙傟傪夝徚偡傞偙偲丆偮傑傝乽擔杮偺枹棃偼柧傞偄乿偲姶偠偰傕傜偆偙偲傪丆彮巕壔懳嶔偺婎杮偲偡傋偒偱偡丅偦偺偨傔偵偳偆偟偨傜偄偄偐偲尵偭偨傜乽搳帒乿偟偐偁傝傑偣傫丅崱偼嬯偟偄偐傕偟傟側偄偗傟偳丆10擭丆20擭屻偵偼丆偙偺搳帒偑奐壴偡傞帪戙偑棃傞丅偦偆巚偭偨傜婃挘傟傑偡丅墦偔偲傕丆岝偑尒偊偰偄傟偽曕偄偰偄偗傞偺偱偡丅墦偔偺岝傪乽擱椏偑傕偭偨偄側偄乿偲尵偭偰徚偟偰偼偄偗傑偣傫丅(p.219)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
偁傟傎偳偺僩儔僽儖偵尒晳傢傟側偑傜傕丆乽偼傗傇偝乿偼婣偭偰偒傑偟偨丅偙傟傑偱偺幐攕偵妛傃丆乽偼傗傇偝乿偱偼堦偮偺僩儔僽儖偑婲偒偰傕偦傟偑慡懱偵攇媦偟側偄傛偆側岺晇偑側偝傟偰偄偨偺偱偡丅乽憐掕奜乿偼偳傫側偲偒偱傕婲偙傝摼傞偺偱偡丅戝愗側偙偲偼偳傫側偙偲偑婲偒偰傕偦傟傪抳柦彎偵偝偣側偄丆僱僢僩儚乕僋揑側岺晇偑戝愗偱偡丅杮彂偼乽偼傗傇偝乿僾儘僕僃僋僩丒儅僱乕僕儍乕偺愳岥弤堦榊巵偑乽偼傗傇偝乿偺宱尡傪摜傑偊偰丆擔杮偺彨棃偵偮偄偰採尵偟偰偄傑偡丅
儅僀働儖丒儌乕僘儕乕丆僕儑儞丒儕儞僠挊丆媣朏惔旻栿丆搶嫗彂愋丆俀侽侾侾擭俉寧俀俀擔戞侾嶞丆ISBN978-4-487-80525-9
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俀丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧僔儑僢僋儗乕偲偄偆抝 僂傿儕傾儉丒僔儑僢僋儗乕偲偄偆暔棟妛幰偑偄偨丅戞擇師戝愴枛婜偵傾儊儕僇孯偑擔杮杮搚偵忋棨偟偨応崌偵偼丆懡悢偺媇惖幰傪弌偡偲偺曬崘傪傑偲傔丆尨敋搳壓偺寛掕偵塭嬁傪梌偊偨恖暔偱傕偁傞丅乮棯乯慺僢僋儗乕偼尋媶幰偲偟偰偼暥嬪側偟偵堦棳偩偭偨偑丆恏書偺岤偄忋巌偲偼偲偰傕尵偊側偄柺偑偁偭偨丅1947擭丆奐敪僠乕儉偑僩儔儞僕僗僞偺帋嶌偵惉岟偟摿嫋傪怽惪偡傞嵺丆晹壓偼僔儑僢僋儗乕偺柤慜傪傢偞傢偞奜偟偰偄偨丅偙傟傪抦偭偨僔儑僢僋儗乕偼孅怞傪惏傜偦偆偲丆儂僥儖偵攽傑傝崬傫偱係廡娫屻偵偼傛傠婃忎偱幚梡揑側僩儔儞僕僗僞偺愝寁傪巇忋偘偰偟傑偭偨丅偙傟偑崱擔巊傢傟偰偄傞僩儔儞僕僗僞偺尦偵側偭偨傕偺偱偁傞丅(p.94) 仧儈儖僋僐僐傾傪敪柧偟偨抝 僇僇僆傪乮僕儍儅僀僇偺乯搰柉偼栻梡偲偟偰堸傫偱偄偨丅乮傾僀儖儔儞僪偺堛巘寭怉暔妛幰僴儞僗丒乯僗儘乕儞偼偦偺岠擻偵偮偄偰乽堓偺傓偐偮偒丆徚壔晄椙偵岠偔乿偲婰偟偰偄傞丅儈儖僋偲崿偤偰堸傫偩偲偙傠戝曄偍偄偟偐偭偨偺偱丆儘儞僪儞偵婣偭偰偐傜乽堓偑偡偭偒傝偡傞乿堸傒暔偲偟偰摿嫋傪怽惪偟偨丅僗儘乕儞偼偙偺摿嫋偵傛偭偰敎戝側廂擖傪摼偨丅偦偺屻丆壻巕儊乕僇乕丆僉儍僪僶儕乕壠偑攦偄庴偗丆摨壠偼尰嵼丆桪椙側壻巕儊乕僇乕偵側偭偰偄傞丅(p.102) 仧傢偨偟偨偪偼嬼慠偙偙偵偄傞 偐傝偵帪寁偺恓傪惗柦偑惗傑傟偨懢屆偺帪戙偵栠偟偰丆傕偆堦搙丆惗暔偺恑壔偲抧媴偺曄壔傪偁傞偑傑傑偵擟偣偰傒偨傜丆巹偨偪偑偙偙偵偙偆偟偰偄傜傟傞偐偼丆偼側偼偩媈栤偱偁傞丅忕択偱尵偆偺偱偼側偄丅巹偨偪偼丆嬼慠偙偙偵偨偳傝拝偄偨偺偩丅(p.138)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
2011擭3寧11擔偺捗攇偵傛傞暉搰尨敪偺帠屘偵傛偭偰丆巹偨偪偼偁傜偨傔偰曻幩擻偺嫲傠偟偝傪妛傫偩丅幚偼1898擭丆僉儏儕乕晇嵢偑儔僕僂儉傪敪尒偟偨丅儔僕僂儉傪抁帪娫梺傃傞偲曻幩擻偺奞偵懳峈偟偰丆懱偼愒寣媴傪憹傗偡丅偙傟傪変乆偼乽尦婥偵側偭偨乿偲姶偠傞丅偦偙偱彜攧偵挿偗偨楢拞偑丆壗偲乮儔僕僂儉擖傝偺乯乽曻幩擻楙傝帟杹偒乿乽旤梕僋儕乕儉乿乽忶嵻乿乽儔僕僂儉扽巁悈乿側偳傪攧傝弌偟偨偺偩丅傄偮t僶乕僌偺偁傞婲嬈壠偼儔僕僜乕儖偲偄偆柫暱偺儔僕僂儉悈傪枅擔垽堸偟偰偄傞偆偪偵丆偁偛偺崪偑梟偗偩偟丆嬯偟傒傕偩偊偰巰傫偩乗乗杮彂偱偼丆懠偵傕丆偨偲偊偽僼儘僀僩傗僀僃乕僣偼惛椡憹嫮偺偨傔巰孻廁偺嵛娵傪堏怉偟偰傕傜偭偨側偳偲偄偆丆婏柇側僄僺僜乕僪傕岅傜傟偰偄傞丅
儗僫乕僪丒儉儘僨傿僫僂挊丆揷拞嶰旻栿丆僟僀儎儌儞僪幮丆俀侽侽俋擭俋寧侾俈擔戞侾嶞丆ISBN978-4-478-0052-4 C0033
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侾丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧幎傞偙偲偼朖傔傞偙偲傛傝桳岠偐丠 乽巹偼丆尒帠側憖廲偵偼丆孭楙惗偨偪傪偟偽偟偽抔偐偔朖傔偰偒傑偟偨偑丆偡傞偲師夞偼寛傑偭偰埆偔側傝傑偡丅乮棯乯傑偨壓庤側憖廲偵偼惗搆偨偪傪搟柭傝偮偗偰偒傑偟偨偑丆偍偟側傋偰師夞偼憖廲偑夵慞偝傟傑偡丅偱偡偐傜丆曬廣偼偆傑偔偄偔偑敱偼偦偆偱偼側偄丆側偳偲嬄傜側偄偱偔偩偝偄丅巹偺宱尡偼偦傟偲崌抳偟傑偣傫乿丅懠偺嫵姱偨偪傕傒側摨堄尒偩偭偨丅乮棯乯堦曽丆僇乕僱儅儞偼丆曬廣偼敱傛傝偆傑偔偄偔偙偲傪徹柧偟偨摦暔幚傪怣偠偰偄偨丅乮棯乯偦偟偰撍慠傂傜傔偄偨乗乗搟柭偭偨偁偲夵慞偑尒傜傟傞偺偼妋偐偩偑丆尒偐偗偲堘偄丆搟柭偭偨偙偲偑夵慞傪傕偨傜偟偨偺偱偼側偄偺偩丆偲丅乮棯乯偦偺摎偊偼丆乽暯嬒夞婣乿偲屇偽傟傞尰徾偵偁傞丅暯嬒夞婣偲偼丆偳傫側堦楢偺儔儞僟儉側尰徾偄偍偄偰傕丆偁傞摿暿側帠徾偺偁偲偵偼弮悎偺嬼慠偵傛傝丆廫拞敧嬨丆偁傝偒偨傝偺帠徾偑婲偙傞丆偲偄偆傕偺丅(p.14) 仧擻椡偑偁偭偰傕丆偡偖偵惉岟偵偼寢傃偮偐側偄 僕儑儞丒僌儕僔儍儉偺亀昡寛偺偲偒亁偺尨峞偼26偺弌斉幮偵偼偹傜傟偨丅斵偺戞擇尨峞亀朄棩帠柋強亁偑弌斉幮偺婥傪堷偄偨偺偼丆僴儕僂僢僪偵棳傟偰偄偨偦偺奀懐斉偑60枩僪儖偺塮夋曻塮尃傪堷偒弌偟偨偁偲偵偡偓側偐偭偨丅乮棯乯傑偨J丒K丒儘乕儕儞僌偺亀僴儕乕丒億僢僞乕亁偺嵟弶偺尨峞偼9幮偵偼偹傜傟偨丅乮棯乯偡傋偰偺暘栰偺惉岟幰偑丆傎偲傫偳椺奜側偔丆偁傞摿掕偺恖娫廤抍乗乗偗偭偟偰掹傔側偄恖娫廤抍乗乗偺堦堳偱偁傞偺偼偦偺偨傔偩丅偙偲偺戝彫傪栤傢偢丆巇帠偱偺惉岟丆搳帒偱偺惉岟丆寛抐偱偺惉岟側偳丆傢傟傢傟偺恎偵婲偙傞偙偲偺懡偔偼丆媄検丆弨旛丆嬑曌偺寢壥偱偁傞偺偲摨偠偖傜偄丆儔儞僟儉側梫慺偺寢壥偱傕偁傞丅偮傑傝丆傢傟傢傟偑擣幆偟偰偄傞悽奅偼丆偦偺崻掙傪側偡恖娫傗忬嫷偺捈愙揑側昞傟偱偼側偄丅偦偆偱偼側偔丆偦傟偼梊尒偱偒側偄丆偁傞偄偼愨偊娫側偔曄壔偡傞奜椡偺儔儞僟儉側嶌梡偵傛偭偰傏偐偝傟偨憸偩丅擻椡偼栤戣偱偼側偄丆偲尵偭偰傞偺偱偼側偄丅擻椡偼惉岟偺妋棪傪憹偡梫慺偺堦偮偱偁傞丅偟偐偟峴摦偲寢壥偺寢傃偮偒偼丆傢傟傢傟偑婅偆傎偳捈愙揑偱偼側偄丅偩偐傜丆夁嫀傪棟夝偡傞偺偼梕堈偱偼側偄偟丆枹棃傪梊應偡傞偺傕偦偆偩丅偳偪傜偵偮偄偰傕丆昞柺揑側夝庍傪挻偊偰峫偊傞偙偲偑桳梡偩丅(p.18)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偼嫵堢偺悽奅偵恎傪抲偄偰偒偨偑丆偮偔偯偔乽恖娫丆搘椡俁妱丆塣俈妱乿偲巚偆傛偆偵側偭偨丅傕偪傠傫搘椡偼昁梫偩丅偙傟側偔偟偰柌偼払惉偱偒側偄偺偼帠幚偩丅偟偐偟丆搘椡偟偨偐傜偲偄偭偰惉岟偡傞偲偼尷傜側偄偺傕丆扤傕偑宱尡懃偲偟偰棟夝偟偰偄傞偙偲偩傠偆丅変乆偼扨側傞嬼慠傪偲傕偡傞偲丆棟孅傪偮偗偰乽昁慠乿偲傒側偟偰偟傑偄偑偪偩丅恖娫偼暔帠偵棟桼傪偮偗偨偑傞摦暔偩偐傜偩丅杮彂偼丆擔忢偵愽傓乽儔儞僟儉乿傪傢偐傝傗偡偔徯夘偟偰偔傟傞丅戞擇師悽奅戝愴拞偵丆儘儞僪儞偵棊偲偝傟偨僪僀僣偺V2儘働僢僩偺拝抧揰傪尒傞偲丆柧傜偐偵堄恾揑偱偁傝丆V2儘働僢僩偺惂屼擻椡丆傂偄偰偼僪僀僣偺媄弍偑憐憸傪愨偡傞傎偳恑傫偱偄傞傛偆偵尒偊偨丅屻偵儘儞僪儞巗傪576偺嬫夋偵嬫暘偟丆V2拝抧揰偲偺娭學傪悢妛揑偵専徹偟偨寢壥丆慡懱揑側僷僞乕儞偼乽儔儞僟儉乿側暘晍偲堦抳偟偰偄偨側偳偺僄僺僜乕僪偑枮嵹偱偁傞丅杮彂偼偦偺懠偵傕丆乽偨傑偨傑廂惻巎偺巇帠傪偟偰偄偨儔儃傾僕僃偼丆僼儔儞僗妚柦偱抐摢戜偺業偲徚偊偨偑丆儔僾儔僗偼亀墹幒傊偺梷偊偒傟側偄寵埆亁傪昞柧偟偨儔僾儔僗偼嫟榓崙壠偐傜怴偟偄摿尃傪庤偵擖傟偨丅偦偟偰僫億儗僆儞偑峜掗偵側傞偲丆庒偐傝偟崰偵僫億儗僆儞偑朇暫戉傊偺擖戉傪怰嵏偟偨偙偲傕偁傝丆偨偩偪偵嫟榓庡媊傪偐側偖傝偡偰偰攲庉偺徧崋傪梌偊傜傟偨丅偲偙傠偑1813擭偵僽儖儃儞墹挬偑暅妶偡傞偲丆慜擭偵偼乽僫億儗僆儞戝峜掗乿偵專掓偟偰偄偨帺挊偺拞偱丆僫億儗僆儞傪扏偄偨乿側偳偺偍傕偟傠偄僄僺僜乕僪傕偁傞丅傑偨丆儔儃傾僕僃偑僊儘僠儞戜偵忋傞悺慜偵丆彆庤偵岦偐偭偰乽愗傝棊偲偝傟偨摢偑尵梩傪偄偔偮偟傖傋傠偆偲偡傞偐傪悢偊傞傛偆偵乿偲尵偭偨偲偝傟偰偄傞側偳偲偄偆榖傕嵹偭偰偄傞丅
僒儉丒僉乕儞挊丆徏堜怣旻栿丆憗愳彂朳丆俀侽侾侾擭俇寧俀俆擔弶斉丆ISBN978-4-15-209221-2 C0043
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏侾
亂杮暥偐傜亃
|
仧儊儞僨儗乕僄僼偺恖惗偵傑偮傢傞傟傗偙傟傗偵楌巎壠傗壢妛幰偑嫽枴傪朿傜傑偣偨偺傕傛偔傢偐傞丅尵偆傑偱傕側偄偑丆偁偺廃婜昞傪偮偔偭偰偄側偐偭偨傜丆斵偺堦惗偼崱偛傠扤偺婰壇偵傕巆偭偰偄側偐偭偨偵堘偄側偄丅儊儞僨儗乕僄僼偺巇帠偼傛偔丆恑壔榑偵偐傫偡傞僟乕僂傿儞偺巇帠傗丆憡懳惈棟榑偵偐傫偡傞傾僀儞僔儏僞僀儞偺巇帠偲暲傋傜傟傞丅嶰恖偲傕丆帠傪壗偐傜壗傑偱帺椡偱惉偟悑偘偨傢偗偱偼側偄偑丆偦偺傎偲傫偳傪丆傎偐偺壢妛幰傛傝僄儗僈儞僩偵傗偭偰偺偗偨丅(p.68) 仧1919擭丆僴乕僶乕偼嬻惾偵側偭偰偄偨1918擭偺僲乕儀儖壔妛徿傪庴徿偟偰偍傝丆乮僲乕儀儖徿偼戝愴拞偼拞抐偝傟偰偄偨乯丆斵偺旍椏偼愴帪拞偺婹夓偐傜懡偔偺僪僀僣崙柉傪媬偊側偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢丆庼徿棟桼偼拏慺偐傜傾儞儌僯傾傪崌惉偡傞僾儘僙僗偺敪柧偩偭偨丅堦曽丆梻擭偵偼崙嵺愴斊偲偟偰嵸偐傟偰偍傝丆偦偺棟桼偼壗廫枩偲偄偆恖傪巰彎偝偣丆壗昐枩偲偄偆恖傪嫲晐偵娮傟偨壔妛愴傪悑峴偟偨偐偳偩偭偨乗乗傑偭偨偔憡斀偡傞丆帺暘偺塰岝傪帺傜嫒傔傞傛偆側榖偱偁傞丅(p.108) 仧14悽婭偺擔杮偱偺偙偲丆偁傞搧抌栬偑揝偵儌儕僽僨儞傪怳傝傑偄偰丆偐偺搰崙偺晲巑偑傎偐偺偳傟傛傝梸偟偑偭偨擔杮搧傪嶌傝偁偘偨丅偦偺恘偼寛偟偰撦乮側傑乯偭偨傝偙傏傟偨傝偟側偐偭偨偲偄偆丅偩偑丆偙偺擔杮偺僂儖僇乕僰僗偼旈揱偲偲傕偵偟傫偱偟傑偄丆偦偺媄偼500擭埲忋幐傢傟偨傑傑偩乗乗桪傟偨媄弍偑昁偢偟傕峀傑傞傢偗偱偼側偔丆攑傟偰偟傑偆偙偲偑懡偄偲偄偆堦偮偺徹偲尵偊傞丅(p.110)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼扨側傞尦慺偺愢柧偱偼側偔丆尦慺偵傑偮傢傞幚偵條乆側恖娫廘偄僄僺僜乕僪傪廤傔偨傕偺偱偁傞丅乽傾儖儈僯僂儉乿偼偐偮偰偼嬥傛傝傕崅壙偩偭偨偺偱丆僫億儗僆儞嶰悽偼摿暿側媞偵偼傾儖儈偺怘婍傪丆偦傟埲奜偺媞偵偼嬥惢偺怘婍傪弌偟偨偲偐丆尰嵼侾僆儞僗(栺28僉儘僌儔儉乯扨埵偱攦偊傞嵟傕婱廳側乮傛偭偰崅壙側乯尦慺偼丆嬥傗嬧偱偼側偔丆乽儘僕僂儉乿偱偁傞側偳偲偄偆榖傕偁傞丅暥宯棟宯傪栤傢偢妝偟傔傞杮偱偁傞丅
崅娫戝夘挊丆妏愳暥屔丆俀侽侾侽擭俇寧俀俆擔弶斉丆ISBN978-4-04-394359-3 C0195
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俆丏俆
亂杮暥偐傜亃
|
仧僱僢僇乕丒僉儏乕僽偱擇偮偺棫曽懱偑岎屳偵擖傟懼傢偭偰尒偊傞棟桼 偄偭偨偄側偤丆偦傫側愗傝懼偊偑婲偒傞偺偐丅(棯)乽僝僂儕儉僔偺傛偆側扨嵶朎惗暔偵嫟捠偡傞惗柦堦斒偐傜偺椶悇側傫偱偡偗偳乿偲抐偭偨偆偊偱丆乮棟壔妛尋媶強偺乯嶳岥乮梲巕乯偝傫偼偙偆愢柧偟偰偔傟偨丅乽惗偒傞偲偄偆偙偲偼丆愨偊偢曄壔偡傞娐嫬偺側偐偱丆惗柦僔僗僥儉傪堐帩丒敪揥偡傞偙偲偱偡丅帺傜偲娐嫬偲偺娭學傪偮偔傝懕偗傞塩傒偲傕偄偊傑偡丅偩偐傜丆偳傫側惗暔偱傕丆廃埻偺偄傠偄傠側偲偙傠偵拲堄傪岦偗偰惗妶傪偟偰偒偨傢偗偱偡乿(p.5) 仧乽壠懓乿偑偱偒偨棟桼 塀傟傞応強偺彮側偄憪尨偱丆偙傟偲偄偭偨晲婍傪帩偨側偄僸僩偺慶愭偼擏怘廱偵偨傃偨傃廝傢傟偨偺偱偼側偄偐丅摿偵廝傢傟偨偺偼巕偳傕偩偭偨偼偢偩丅偦偺偨傔丆巰朣棪偑崅偔側偭偨恖椶偼丆偦傟傪曗偆偨傔偵懡嶻偵側傜偞傞傪摼側偐偭偨偺偱偼側偄偐丅師乆偲巕偳傕傪嶻傓愴棯偼摉慠丆巕堢偰偺晧扴偑奿抜偵戝偒偔側傞偙偲傪堄枴偡傞丅巹偨偪偺慶愭偼嫄戝側擼傪帩偮慜偐傜丆傕偼傗曣恊偩偗偱堢偰傞偙偲偼柍棟偵側偭偰偄偨偲峫偊傜傟傞偺偩丅偦偙偱丆彮偟偢偮壠懓偲偄偆鉐傪嫮傔丆廤抍偱堢偰傞偲偄偆慖戰偑峀傑偭偰偄偭偨偺偩傠偆丅(p.56)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偺僞僀僩儖偼僑乕僊儍儞偺戙昞嶌乽変乆偼偳偙偐傜棃偨偺偐丂変乆偼壗幰偐丂変乆偼偳偙傊峴偔偺偐乿偐傜僸儞僩傪摼偨傕偺偱偁傞丅
挊幰偼NHK僠乕僼僾儘僨儏乕僒乕偱丆乽僒僀僄儞僗 ZERO 亀僔儕乕僘丂僸僩偺撲偵敆傞乿傪傕偲偵杮彂偼峔惉偝傟偰偄傞丅偦傟偧傟偺暘栰偺嵟愭抂偵偄傞壢妛幰偵僀儞僞價儏乕傪偟偰丆僸僩偵娭偡傞條乆側晄巚媍偺撲傪夝偙偆偲帋傒偰偄傞丅傎偲傫偳偼傑偩壖愢偺抜奒偱偼偁傞偑丆旕忢偵偍傕偟傠偄丅
僨僀償傿僢僪丒僆儗儖挊丆懢揷捈巕懠栿丆憗愳彂朳丆俀侽侾侽擭侾寧俀俆擔弶斉丆ISBN978-4-15-209105-5 C0040
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧恖椶偺楌巎偺戝敿傪偲偍偟偰丆愯惎弍傕揤婥梊曬傕摨堦偺愱栧壠偵傛偭偰峴傢傟偰偒偨丅恖娫傕戝婥傕愾偠偮傔傟偽杮幙偼摨偠偲偄偆傢偗偩丅17悽婭偺揤暥妛幰儓僴僱僗丒働僾儔乕偼丆戝妛偺妛旓傪偙偆偟偰愯惎弍巘傪偮偲傔傞偙偲偱壱偓弌偟丆偠偮偺偲偙傠惗奤偺戝敿傪偙偺壱偓偵棅偭偨丅(p.14) 仧婭尦423擭丆傾儕僗僩僼傽僱僗偼亀塤亁偲戣偡傞婌寑傪彂偄偨丅婌寑偺庡恖岞偼傗偼傝乽僜僋儔僥僗乿偲偄偄丆斵偼塤偦偺懠偺帺慠尰徾傪恄傛傝悞攓偟偨丅(棯)偙偺媃嬋偵傛偭偰僜僋儔僥僗偼傑偢柺敀偑傜傟丆師偄偱垼傟側傾儞僠僸乕儘乕偲側偭偨丅亀塤亁偑敪昞偝傟偰偐傜24擭屻丆僜僋儔僥僗偼堎抂偺恄傪怣偠丆庒幰傪懧棊偝偣偨嵾偵傛傝嵸敾偵偐偗傜傟偨丅偍偦傜偔丆崘慽恖偨偪偼媃嬋偺搊応恖暔偲尰幚偺恖暔傪崿摨偟偰偄偨偺偩傠偆丅(p.46) 仧偁傞傕偺偵帺桼堄巚偑偁傞偐偳偆偐偲峫偊傞応崌丆偦偺傕偺偺嫇摦傪偳偺掱搙傑偱梊應壜擻偲峫偊傞偐偵偐偐偭偰偄傞偙偲偑懡偄丅偁傞僔僗僥儉偑姰慡偵梊應壜擻側応崌丆偁傞偄偼姰慡偵儔儞僟儉偱偁傞応崌偵偼丆巹偨偪偼丆偦偺僔僗僥儉偑奜偐傜偺椡傪庴偗偰偄傞偲壖掕偟偑偪偱偁傞丅偟偐偟丆傕偟僔僗僥儉偑拞娫揑側忬懺偱摦偄偰偄偰丆偦偺嫇摦偵偼擣幆壜擻側偁傞庬偺僷僞乕儞傗拋彉偑偁傞傕偺偺丆梊應偼傑偩擄偟偄応崌偵偼丆巹偨偪偼丆偦偺僔僗僥儉偑撈棫偟偰摦偄偰偄傞偲峫偊傞丅(p.120)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼乽梊應乿偺楌巎偵偮偄偰岅傜傟偰偄傞丅揤婥梊曬傕梊應偺堦偮偱偁傞偑丆偙傟偼19悽婭敿偽丆偐偮偰僟乕僂傿儞偑忔偭偨價乕僌儖崋偺慏挿偱偁偭偨儘僶乕僩丒僼傿僢僣儘僀戝彨偑悽奅偱弶傔偰儘儞僪儞偺怴暦偵宖嵹偟偨乮p.141乯丅斵偼慏忔傝偵朶晽塉傪寈崘偡傞偨傔偵偙傟傪峫偊偨偺偱偁傞丅傕偭偲傕偦偺惛搙偼偍偟偰抦傞傋偟偩偭偨丅20悽婭偵擖偭偰傕丆揤婥梊曬偺寁嶼傪峴偆偨傔偵偼64,000恖偺乽僐儞僺儏乕僞乿偑昁梫偲峫偊傜傟偰偄偨丅偙偙偱尵偆乽僐儞僺儏乕僞乿偲偼乽寁嶼偡傞恖乿偲偄偆堄枴偱偁傞丅揤婥梊曬偺惛搙偼尰嵼旕忢偵崅傑偭偰偄傞偑丆偟偐偟堦廡娫埲忋愭偲側傞偲偲偨傫偵惛搙偑棊偪偰偔傞丅僗乕僷乕僐儞僺儏乕僞偑巊偊傞尰嵼偵偍偄偰傕側偍丆梊應偼擄偟偄偺偩丅
抮扟桽擇挊丆挬擔弌斉幮丆俀侽侽俋擭俆寧侾俆擔敪峴丂ISBN978-4-255-00432-7 C0095
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏侽
亂杮暥偐傜亃
|
仧捿傝嫶偺忋偼崅強偱偡傛偹丅偩偐傜嬞挘偡傞傢偗偱偡丅崅強嫲晐徢偠傖側偔偰傕懡彮僪僉僪僉偡傞丅偦偆偟偰僪僉僪僉偟偰偄傞偲偒偵崘敀偝傟偨傝偡傞偲丆擼偼偍僶僇偝傫側偺偱丆偦偺僪僉僪僉偟偰偄傞棟桼傪姩堘偄偟偰偟傑偆丅乽偁傟丆帺暘偼偲偒傔偄偰偄傞偺偐丠乿偲偹丅偮傑傝丆杮摉偼捿傝嫶偑晐偔偰僪僉僪僉偟偰偄傞偺偵丆乽崘敀偟偰偒偨偁偺恖偑枺椡揑偩偐傜丆巹偼偙傫側偵僪僉僪僉偟偰偄傞傫偩乿偲憗偲偪傝偡傞丅偦偟偰丆憡庤偵岲堄傪帩偭偰偟傑偆傫偱偡丅(p.58) 仧乽惓偟偄乿偲偄偆偺偼丆乽偦傟偑帺暘偵偲偭偰怱抧偄偄乿偐偳偆偐側傫偩傛偹丅偦偺曽偑惛恄揑偵埨掕偡傞偐傜丅偦傟傪柍堄幆偵媮傔偪傖偆丅偮傑傝丆乽岲偒乿偐乽寵偄乿偐偩丅帺暘偑乽怱抧傛偔乿姶偠偰丆乽岲姶乿傪妎偊傞傕偺傪丆杔傜偼乽惓偟偄乿偲敾抐偟傗偡偄丅(p.120)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
挊幰偼偡偱偵傾儊儕僇偺崅峑惗傪憡庤偵擼偵偮偄偰島媊傪偟偰丆偦傟傪乽恑壔偟偡偓偨擼乿偲偄偆杮偵傑偲傔偰偄傞丅崱搙偼丆擔杮偺崅峑惗俋柤偵島媊傪偟偰丆偦傟傪婲偙偟偨偺偑杮彂偱偁傞丅巹帺恎偼乽懳択乿傗乽島媊榐乿宍幃偺杮偼偁傑傝岲偒偱偼側偄偺偩偑丆偙偺杮偼偍傕偟傠偐偭偨丅幚椺傪帵偟側偑傜丆擼乮怱乯偺摥偔巇慻傒傪傢偐傝傗偡偔夝愢偟偰偄傞丅
僒僀儌儞丒僔儞仌僄僣傿傾乕僩丒僄儖儞僗僩挊丆惵栘孫栿丆怴挭幮丆俀侽侾侽擭侾寧俁侽擔敪峴丂ISBN978-4-10-539305-2 C0047
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏侾
亂杮暥偐傜亃
|
仧僫僀僠儞僎乕儖偼丆專恎揑側廬孯娕岇晈偱偁傞偩偗偱側偔丆桪廏側摑寁妛幰偱傕偁偭偨丅(棯)僼儘乕儗儞僗偼僀僞儕傾岅丆僊儕僔儍岅丆楌巎丆偦偟偰偲傝傢偗悢妛傪妛傫偱偄偨丅幚嵺斵彈偼丆僕僃僀儉僘丒僗儖僎僗僞乕傗傾乕僒乕丒働僀儕乕側偳丆僀僊儕僗偱傕戞堦媺偺悢妛幰偨偪偺巜摫傪庴偗偰偄偨偺偩丅偦偺偍偐偘偱僫僀僠儞僎乕儖偼丆塹惗忬懺偺夵慞偵傛偭偰惗懚棪偑岦忋偟偨偲偄偆帺傜偺庡挘傪棤偯偗傞偨傔偵丆悢妛偱恎傪偮偗偨椡傪敪婗偟偰丆幮夛摑寁妛傪棙梡偡傞偙偲偑偱偒偨丅(p.46) 仧摑寁偑摼堄偩偭偨偍偐偘偱丆僫僀僠儞僎乕儖偼惌晎傪愢摼偟丆堦楢偺堛椕夵妚偑偳傟傎偳廳梫偐傪傢偐傜偣傞偙偲偑偱偒偨丅偨偲偊偽丆摉帪偼懡偔偺恖偑丆娕岇晈偺梴惉側偳帪娫偺柍懯偩偲榑偠偰偄偨丅側偤側傜丆孭楙傪庴偗偨娕岇晈偺悽榖傪庴偗偨姵幰偺傎偆偑丆孭楙傪庴偗偰偄側偄幰偺悽榖傪庴偗偨姵幰傛傝傕丆巰朣棪偼崅偐偭偨偐傜偩丅偟偐偟僫僀僠儞僎乕儖偼丆廳撃側姵幰偼丆孭楙傪庴偗偨娕岇晈偺偄傞昦搹偵憲傜傟傞偙偲偑懡偄偙偲傪巜揈偟偨丅傕偟傕擇偮偺僌儖乕僾偺寢壥傪斾妑偟偨偄偺側傜丆姵幰偼擇偮偺僌儖乕僾偵儔儞僟儉偵妱傝怳傜傟偰偄側偗傟偽側傜側偄丅偦偙偱僫僀僠儞僎乕儖偑丆孭楙傪庴偗偨娕岇晈偲丆偦偆偱側偄娕岇晈偵丆姵幰傪儔儞僟儉偵妱傝怳偭偰椪彴帋尡傪峴偭偰傒偨偲偙傠丆孭楙偝傟偨娕岇晈偺悽榖傪庴偗偨姵幰偺僌儖乕僾偼丆孭楙偝傟偰偄側偄幰偺悽榖傪庴偗偨僌儖乕僾傛傝丆偼傞偐偵傛偄宱夁傪偨偳傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅(p.47) 仧斵乮栄戲搶乯偺庡帯堛偩偭偨儕乕丒僕乕僗僀偼丆亀栄戲搶偺巹惗妶亁偲偄偆夞憐榐偺側偐偱丆乽娍曽堛椕傪彠椼偡傋偒偩偲偄偆偙偲偼妋怣偟偰偄傞偑丆屄恖揑偵偼娍曽傪怣梡偟偰偄側偄丅巹偼娍曽偺帯椕偼庴偗側偄乿偲偄偆栄帺恎偺尵梩傪徯夘偟偰偄傞丅(p.67) 仧儂儊僆僷僔乕偱偼丆30C偼偛偔晛捠偺婓庍偩偑丆偙傟偼偼偠傔偺曣塼偑昐攞偵婓庍偝傟傞僾儘僙僗偑丆俁侽夞孞傝曉偝傟傞偲偄偆偙偲偩丅偮傑傝曣塼偼丆1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000攞偵婓庍偝傟傞丅(棯)栤戣偼丆侾僌儔儉偺曣塼偵偼偨偐偩偐1,000,000,000,000,000,000,000,000傎偳偺暘巕偟偐娷傑傟偰偄側偄偲偄偆偙偲偩丅(棯)嬌抂偵婓庍偝傟偨梟塼偵偼丆偼偠傔偺曣塼偵娷傑傟偰偄偨暘巕偼侾屄傕娷傑傟偰偄側偄丅(棯)30C儗儊僨傿乕偵桳岠惉暘偺暘巕偑侾屄娷傑傟偰偄傞妋棪偼丆廫壄暘偺堦偺廫壄暘偺堦偺廫壄暘偺堦偱偁傞丅姺尵偡傟偽丆30C儂儊僆僷僔乕丒儗儊僨傿乕偼丆傎傏妋幚偵偨偩偺悈偩偲偄偆偙偲偵側傞丅(p.131)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
僒僀儌儞丒僔儞偺杮偼偳傟傕偍傕偟傠偄偺偩偑丆崱夞偼傗傗愗傟枴偑側偄傛偆偵姶偠傜傟傞偺偼嫟挊偺偣偄偐丅偦傟偱傕廫暘側僀儞僷僋僩巜悢偱偼偁傞丅儂儊僆僷僔乕丆僇僀儘僾儔僋僥傿僢僋丆鐸偼偄偢傟傕傎偲傫偳偑僾儔僙儃岠壥偲偄偆偺偑杮彂偺寢榑偱偁傞丅僂僃僗僩儈儞僗僞乕戝妛偼丆傑偲傕側暘栰偱懡偔偺妛埵傪弌偟偰偄傞偑丆堦曽丆戙懼堛椕偺妛埵傪侾係庬椶傕弌偟偰偄傞(杮彂 p.320)丅 挊幰偼丆戝妛偱儂儊僆僷僔乕傪嫵偊傞偙偲偼丆乽傑偠側偄巘乿傪梴惉偟偰偄傞偺偲摨偠偩偲抐尵偡傞丅杮彂偺p.190偵堷梡偟偰偄傞僇乕儖丒僙僀僈儞偺師偺尵梩偼帵嵈偵晉傓丅
乽傂偲偮偼丆偳傟傎偳婏柇偩偭偨傝捈娤偵斀偟偨傝偟偰傕丆怴偟偄傾僀僨傾偵偼怱傪奐偄偰偍偔偙偲丅偦偟偰傕偆傂偲偮偼丆屆偄偐怴偟偄偐偵傛傜偢丆偳傫側傾僀僨傾傕夰媈揑偵尩偟偔嬦枴偡傞偙偲偩丅偦偆偡傞偙偲偱丆怺偄恀幚傪怺偄僫儞僙儞僗偐傜傛傝暘偗傞偺偱偁傞丅乿
儕僠儍乕僪丒僪乕僉儞僗挊丆悅悈梇擇栿丆憗愳彂朳丆俀侽侽俋擭侾侾寧俀俆擔弶斉丂ISBN978-4-15-209090-4 C0045
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧僀僰偺壠抺壔偐傜巹偨偪偼偳傫側嫵孭傪妛傇傋偒側偺偩傠偆丠丂(棯)嬃偔傎偳彮悢偺堚揱巕偟偐偐偐傢偭偰偄側偄偐傕偟傟側偄丅偟偐偟曄壔偼偁傑傝偵傕戝偒偄乗乗將庬偺憡堘偼偁傑傝偵傕寑揑偱偁傞乗乗偺偩偐傜丆悢悽婭偳偙傠偱偼側偔壗昐枩擭傪偐偗偨恑壔偑偳偆側傞偐憐憸偑偮偔偩傠偆丅偨偭偨悢悽婭丆偁傞偄偼悢廫擭偱乮將庬偺傛偆偵乯偙傟傎偳偺恑壔揑側曄壔偑傕偨傜偝傟傞偺側傜丆侾壄擭偁傞偄偼侾侽壄擭偲偄偆擭寧偑偁傟偽偳傟傎偳偺偙偲偑払惉偱偒傞偐丆偪傚偭偲峫偊偰傒偰傎偟偄丅(p.91) 仧僟乕僂傿儞偺摿暿側揤嵥偁偭偰偙偦丆帺慠偑慖戰幚峴幰乮僄乕僕僃儞僩乯栶傪壥偨偡偙偲偑偱偒傞偲婥偯偔偺偑壜擻偵側偭偨偺偩丅恖堊搼懣偵偮偄偰偼扤傕偑丆彮側偔偲傕丆擾応傗掚墍丆僪僢僌丒僔儑乕傗僴僩彫壆偱側偵偑偟偐偺宱尡傪傕偮恖側傜扤傕偑抦偭偰偄偨丅偟偐偟丆慖敳幚峴幰乮僄乕僕僃儞僩乯偑偐側傜偢偟傕偄側偔偲傕偄偄偙偲偵偼偠傔偰婥偯偄偨偺偼僟乕僂傿儞偩偭偨丅帺慠搼懣偼惗偒巆傝乗乗偁傞偄偼惗偒巆傝偺幐攕乗乗偵傛偭偰帺摦揑偵偍偙側偆偙偲偑偱偒傞丅(p.125) 仧J丒B丒S丒儂乕儖僨儞偼丆恑壔榑偺斀徹偵側傞傛偆側娤嶡帠幚偍椺傪嫇偘偰偔傟偲媮傔傜傟偨偲偒偵丆傛偔抦傜傟偨曉摎傪偟偨丅乽愭僇儞僽儕傾帪戙偐傜偺壔愇偺僂僒僊偑尒偮偐傞偙偲偩両乿丅偦傫側僂僒僊偼尒偮偐偭偰偄側偄偟丆傑偓傟傕側偄帪戙嶖岆偺壔愇側偳丆偳傫側庬椶偺傕偺偱偁傟尒偮偐偭偰偄側偄丅(p.231)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
乽傾儊儕僇恖偺係侽亾埲忋偼丆恖娫偑懠偺摦暔偐傜恑壔偟偨偙偲傪斲掕乿偟偰偄傞偲偄偆乮杮彂p.52)丅僪乕僉儞僗偼傗傝偒傟側偄偲偄偆婥帩偪偱丆偄傑偝傜偁傎傜偟偄偲敿暘巚偄偮偮傕偙偺乽恑壔偺徹柧乮尨戣偼 The Greatest Show on Earth乯乿傪彂偄偨丅斵偼拞搶偱側偍懕偔帺敋僥儘側偳偵怗敪偝傟偰丆夁寖偵傕乽恄偼栂憐偱偁傞乿偲偄偆杮傕弌偟偰偄傞丅杮彂偼丆恑壔偼扤偑尒偰傕斲掕偱偒側偄帠幚偱偁傞偙偲傪偙傟偱傕偐偲偄偆椺傪嫇偘偮偮丆尒帠偵榑徹偟偰偄傞丅
僀乕償傽儖丒僄僋儔儞僪挊丆撿瀶堣巕栿丆傒偡偢彂朳丆俀侽侾侽擭侾俀寧俀俉擔敪峴丂ISBN978-4-7942-1793-6 C0040
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾係丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧僊儕僔儍揘妛偱偼乮棯乯恀偵姰慡側傕偺偼曄壔偟側偄丅堢偮偙偲傕側偗傟偽悐偊傞偙偲傕側偄丅晄曄偵偟偰塱墦偱偁傞丅僾儔僩儞揘妛偱偼丆姰慡側傕偺偙偦偑懚嵼偡傞丅偦傟偩偗偑恀偺幚嵼側偺偩丅傢偨偟偨偪偑惗偒偰偄傞娫偵尒傞幰偼丆偙傟傜僀僨傾偺偁傢傟側斀幩丆暻偵塮偭偨塭偵偡偓側偄丅偨偩傢偨偟偨偪偼巰屻丆偦傟傜偺尰暔乮僆儕僕僫儖乯傪尒偮傔傞偙偲丆偮傑傝塱墦偺恀丆塱墦偺慞丆塱墦偺旤傪尒傞偙偲傪備傞偝傟丆偺偪偺惗偵偦偺婰壇偺堦晹傪傕偭偰偄偔丅傢偨偟偨偪偼悢妛揑怱棟傪乽敪尒乿偡傞偺偱偼側偄丅偙偺悽偺奜偵偁傞偦偺悽奅傪捠夁偟偨偪偒尒偨傕偺偺婰壇偑慼傞偺偩丅乮棯乯僾儔僩儞揘妛偵偍偄偰偼丆恀棟偼敪尒偡傞傕偺偱偼側偔丆巚偄弌偡傕偺偱偁傞丅乮p.16) 仧偡傋偰傪摨偠堦弖偱嵸抐偟偨塅拡偺椫愗傝傪憐憸偡傞偙偲偼壜擻偩傠偆偐丅僺僒惞摪偺戝怌戜偑梙傟偺搑拞偱巭傑傝丆峜掗偺懌偑曕傒偺搑拞偱巭傑傝丆榝惎偑婳摴忋偱巭傑傝丆嬧壨偑塓姫偒偺搑拞偱巭傑傝丆偡傋偰偑堦弖偵搥傝偮偄偨傛偆側慡塅拡偺抐柺丅偦偆偄偆傕偺傪憐憸偡傞偙偲偵傕偟堄枴偑偁傞偲偡傟偽丆塅拡偺慡楌巎偼偦偺傛偆抐柺傪帪娫偺弴偵廳偹偨傕偺偵側傞偩傠偆丅偪傚偆偳摦夋偑壗枃傕偺幨恀傪帪娫偺弴偵廳偹偰偱偒偰偄傞傛偆偵丅乮p.25) 仧偩偐傜塅拡偵偼丆慹埆側傕偺丆晄栄側傕偺丆巰傫偩傕偺偼堦偮偲偟偰側偔丆熡撟傕丆崿棎傕偨傫側傞尒偣偐偗偵偡偓側偄丅偦傟偼彮偟棧傟偨強偐傜抮傪挱傔傞偲偦偺傛偆偵尒偊傞偺偵帡偰偄傞丅偮傑傝崿棎偟偨摦偒偲丆抮偺嫑偑偄傢偽偆傛偆傛偟偰偄傞偺偑尒偊傞偩偗偱丆嫑偦傕偺傕偺偑尒偊偰偄側偄偺偱偁傞丅乮儔僀僾僯僢僣亀扨巕榑乿乯乮p.71)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
傑偢僞僀僩儖偑偍傕偟傠偄丅乽嵟慞悽奅乿偲偼儔僀僾僯僢僣偑尵偄偩偟偨尵梩偩丅慡擻偺恄偑乮偄傠偄傠側慖戰巿偺拞偱偁偊偰乯偙偺悽傪嶌偭偨偐傜偵偼丆偙偺悽偼乽嵟慞偺悽奅乿偱偁傞偼偢偩乗乗偙偺敪尵偱巰屻斵偼揙掙揑偵攏幁偵偝傟偨丅嶦恖丆偄偠傔丆媠懸偑塓姫偔偙偺悽偺偳偙偑乽嵟慞乿側偺偐偲恖乆偼徫偭偨丅偟偐偟斵偑偄偄偨偐偭偨偺偼堘偆丅側傞傎偳屄乆偵偼條乆側柕弬傪書偊偰偄傞偺偼帠幚偩丅偟偐偟丆僩乕僞儖偱偼偙偺悽偼嵟慞側偺偱偁傞丅儔僀僾僯僢僣偼偙偆尵偄偨偐偭偨偺偩丅斵傪悽偵岆夝偝偣偨斊恖偼丆儃儖僥乕儖偱偁傞丅斵偼儔僀僾僯僢僣偺乽嵟慞悽奅乿傪丆儌乕儁儖僠儏僀偺傕偺偲崿摨偟偰偟傑偭偨偺偩丅儃儖僥乕儖偼儔僀僾僯僢僣偵懳偟偰庢傝曉偟偺偮偐側偄儈僗傪偟偰偟傑偭偨丅
僋儕僗丒僼儕僗挊丆戝杧氭抝栿丆娾攇彂揦丆俀侽侽俋擭俆寧俀俉擔敪峴丂ISBN978-4-00-006312-8 C0045
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏侽
亂杮暥偐傜亃
|
仧偳傫側廤抍偱傕偦偆偩偑丆壢妛幰偵傕恎暘偺忋壓偲偄偆傕偺偑偁傞丅怱棟妛幰偼掙曈偵嬤偄偁偨傝偵偄傞丅乮棯乯妛幰偺僷乕僥傿乕偱偼乽偱丆偁側偨偺屼愱栧偼丠乿偲暦偐傟傞偺偼廻柦偱偁傞丅乮棯乯乽偱丆偁側偨偺屼愱栧偼丠乿偲恞偹傞惡偑偟偨丅乮棯乯偙偺恖暔偼暔棟妛壢偺怴偟偄妛壢挿偩丅傑偢偄偙偲偵丆乽巹偼擣抦恄宱壢妛傪傗偭偰偄傑偡乿偲偄偆摎偊偼帪娫偐偣偓偵偟偐側傜側偄丅乮棯乯偡偖偵斵彈偼乽偁偁丆偁側偨怱棟妛幰偹乿偲崌揰偡傞丅婄偵偼椺偺儊僢僙乕僕偑彂偄偰偁傞乗乗乽儂儞儌僲偺壢妛傪傗偭偨傜偳偆傛丠乿偲丅乮p.1) 仧巹偨偪偺姶妎偑寬慡偱擼偑惓忢偄摥偄偰偄傞偲偟偰丆暔棟悽奅偵捈愙傾僋僙僗偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅巹偨偪偼偦偺傛偆偵姶偠傞偑丆偦傟偼擼偑憂傝弌偟偨嶖妎側偺偩丅(p.50) 仧巹偑抦妎偟偰偄傞偺偼丆奜偺悽奅偐傜栚傗帹傗巜偵擖偭偰偔傞慹嶨偱濨枂側庤偑偐傝偱偼側偄丅巹偑抦妎偟偰偄傞偺偼傕偭偲朙偐側悽奅偩乗乗偦傟偼偙偆偟偨慹嶨側怣崋偑夁嫀偺宱尡偲偄偆嵿嶻偲寢崌偟偰偱偒偨堦暆偺奊偺傛偆側傕偺偱偁傞丅(p.167) 仧恖偺栚偵偼栍揰偲屇偽傟傞岝偺庴梕懱偑懚嵼偟側偄晹暘偑偁傞丅偙偙偼栐枌偐傜擼乮帇恄宱乯傊姶妎怣崋傪揱偊偰偄傞恄宱慄堐偑懇偹傜傟傞応強側偺偱庴梕懱偑擖傞梋抧偑側偄丅帇栰偺寚偗偨晹暘偼擼偑曗偭偰偟傑偆偺偱恖偼栍揰偵婥偯偐側偄偩偗偩丅擼偼栍揰偵椬愙偟偰偄傞晹暘偐傜偺怣崋傪棙梡偟偰寚偗偨忣曬傪杽傔崌傢偣傞偺偱偁傞丅(p.170)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偨偪偑擔忢抦妎偟偰偄傞廃埻偺悽奅偼丆姶妎婍姱偑懆偊偨慹嶨側忣曬傪庴偗庢偭偨擼偑丆夁嫀偺忣曬偵徠傜偟崌傢偣偰尒帠偵昤偒忋偘偨乽嶌昳乿偱偁傞丅巹偼偙傟傪棟夝偟偨偙偲偱丆偍偍偘偝側昞尰傪偡傟偽乽恖惗娤偑曄傢偭偨乿婥偑偟偨丅杮棃偼巹偨偪偼埫偔丆擋偄傕壒傕枴傕懚嵼偟側偄暔幙悽奅偺拞偵懚嵼偟偰偄傞偺偩偑丆巹偨偪偺姶妎婍姱偑偦偆偟偨揹帴攇傗壒攇傗壔妛暔幙傪擣抦偟丆擼偵憲傝丆擼偼偦傟傜傪怓丒壒丒崄傝丒枴偲夝庍偟偰偔傟偰偄傞偍偐偘偱丆巹偨偪偼妝偟偄擔忢傪憲傞偙偲偑偱偒偰偄傞偺偩丅怘墫乮墫壔僫僩儕僂儉乯帺懱偑乽偐傜偄乿偲偄偆惈幙傪帩偭偰偄傞傢偗偱偼側偔丆愒怓偼偦傕偦傕愒偄惈幙傪帩偭偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偦傟傜偼偨偩偺暔幙偱偁偭偨傝丆揹帴攇偱偁傞偵偡偓側偄丅偦偆偟偨乽僋僆儕傾乿傪姶偠傞偺偼丆巹偨偪偺擼偑偦傟傪憂傝弌偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅
傾乕僒乕丒俬丒儈儔乕挊丆嶁杮朏媣栿丆憪巚幮丆俀侽侾侽擭侾俀寧俀俉擔敪峴丂ISBN978-4-7942-1793-6 C0040
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧旝嵶峔憿偼丆尵偭偰傒傟偽奺攇挿偺岝偺摿挜傪昞偡巜栦傗俢俶俙偺傛偆側傕偺側偺偩丅偦偺旝嵶峔憿傪寛掕偟偰偄傞偺偑侾俁俈偲偄偆悢偩偭偨偺偱丆僝儞儅乕僼僃儖僩偼偙傟傪乽旝嵶峔憿掕悢乿偲屇傫偩乮幚傪尵偆偲丆旝嵶峔憿掕悢偺壙偼1/137側偺偩偑丆暔棟妛幰偨偪偼曋媂忋丆侾俁俈偲偄偊偽旝嵶峔憿傪巜偡偲偟偰偄偨乯丅(棯)侾俁俈偲偄偆悢偑偦傟傎偳廳梫側傕偺側傜丆憡懳惈棟榑傗検巕榑傪婰弎偡傞悢帤偐傜摫偔偙偲偑偱偒傞偼偢偱偼側偄偩傠偆偐丅偩偑丆暔棟妛幰偨偪偑崲榝偟偨偙偲偵丆偩傟傕旝嵶峔憿掕悢傪棟榑偐傜摫偔偙偲偑偱偒側偐偭偨丅旝嵶峔憿掕悢偑愨柇偲偟偐尵偄傛偆偺側偄抣偵側偭偰偄偰丆偦偺偍偐偘偱丆抧媴忋偺惗柦偺懚嵼偑壜擻偵側偭偨偙偲傕柧傜偐偵側偭偨丅偟偨偑偭偰丆暔棟妛幰偨偪偑旝嵶峔憿掕悢傪乽恄旈悢乿偲屇傇傛偆偵側偭偨偺傕摉慠偩偭偨丅(P.13) 仧僂僅儖僼僈儞僌丒僷僂儕偵偼晄巚媍側偙偲偑偮偄偰傑傢偭偨丅僷僂儕偑尋媶幰偺摴傪曕傒偼偠傔偨摉弶偐傜丆斵偑幚尡幒偵擖偭偰偔傞偲幚尡憰抲偑傂偲傝偱偵摦偐側偔側偭偰偟傑偆偙偲偵丆摨椈偨偪偼偄傗偱傕婥偯偐偞傞傪偊側偐偭偨丅乽僷僂儕岠壥乿偲屇偽傟傞傛偆偵側偭偨偲偼偄偊丆偦傫側傕偺偑懚嵼偡傞偼偢傕側偄偺偼柧傜偐偩偭偨丅扨側傞嬼慠偵堘偄側偄丅偦傟偵傕偐偐傢傜偢丆摨偠傛偆側尰徾偑壗搙偲側偔惗偠偨丅(P.45) 仧惣墷偱偼丆弌棃帠偼場壥揑夁掱傪捠偟偰師偐傜師偵楢懕揑偵揥奐偟偰偄偔偲峫偊傞偺偑傆偮偆偱偁傞丅偩偑儐儞僌偼丆弌棃帠偲弌棃帠偺偮側偑傝偼廲曽岦偩偗偱側偔丆墶曽岦偵傕怢傃偰偄傞乗乗偁傞弖娫偵悽奅拞偱惗偠傞偁傜備傞弌棃帠偼丆嫄戝側僱僢僩儚乕僋偺傛偆側傕偺偺側偐偱屳偄偵偮側偑偭偰偄傞乗乗偲妋怣偟偰偄偨丅(P.298) 仧儐儞僌偼嫟帪惈偺壢妛揑崻嫆偲偟偰丆検巕暔棟妛偐傜摫偐傟傞偒傢傔偰寑揑側寢壥偺堦偮傪帩偪偩偟偰偄偨丅尨巕儗償僃儖偱惗偠傞夁掱偱偼丆帪嬻撪偺埵抲傪帵偡嵗昗偲偦偺尰徾偺場壥揑婰弎偼屳偄偵偁偄擖傟側偄娭學偄偁傞偲偄偆偺偑偦傟偱偁傞丅偳偪傜偐堦曽傪惓妋偵昞偡偙偲偑偱偒偰傕丆椉曽傪摨帪偵惓妋偵昞偡偙偲偑偱偒側偄偺偩丅(棯)僷僂儕偐傜壢妛偵抦幆傪摼偨儐儞僌偼丆検巕暔棟妛偑倣偨傜偡偙傟傜偺寢壥偼丆帪嬻撪偱偺弌棃帠偲弌棃帠偵偼場壥揑楢嵔埲奜偺寢傃偮偒傕偁傝偆傞偙偲傪帵偟偰偄傞偺偩偲夝庍偟偨丅(P.302) 仧僷僂儕偼丆傕偟儐儞僌偑傑偭偨偔堄枴傪側偝側偄暔棟妛偺榑暥側偳傪敪昞偟丆帺愢偺棤偯偗偲偟偰僷僂儕偺柤傪帩偪弌偡偙偲偵側傟偽丆帺暘偺柤惡偵彎偑偮偔偺偱偼側偄偐偲晄埨偩偭偨偺偩丅偩偑丆儐儞僌偲僷僂儕偺媍榑偼旕忢偵幚傝懡偄傕偺偩偭偨偺偱丆拞搑敿抂側忬懺偱懪偪愗傞暘偗偵偄偐側偐偭偨丅偲傝傢偗僷僂儕傪偲傜偊偨偺偼丆検巕椡妛偲怱棟妛偲偺壦偗嫶傪尒偮偗傞偲偄偆峫偊偱偁傞丅偦偺尞偑嫟帪惈偵偁傞偺偼妋偐偩偭偨丅(P.305)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼偁傞庬偺婋側偝傪姶偠側偑傜傕丆儐儞僌偵庝偐傟偰偄偔僷僂儕偺怱忣偑偆傑偔昤偐傟偰偄傞丅寢嬊僷僂儕偼嵟屻傑偱儐儞僌傪怣棅偟偰偄偨丅侾俋俆俉擭丆僷僂儕偑寖偟偄堓捝傪婲偙偟偰僠儏乕儕僸偺愒廫帤昦堾偵扴偓崬傑傟偨丅桭恖偑尒晳偄偵偄偔偲丆僷僂儕偼嫽暠偟偰乽偙偺昦幒偺斣崋傪尒偨偐丠乿偲暦偄偨丅婥偯偐側偐偭偨偲桭恖偑摎偊傞偲丆僷僂儕偼偆傔偔傛偆偵乽侾俁俈崋幒偩両乿偲偄偭偨丅乽巹偑偙偙偐傜惗偒偰奜偵弌傞偙偲偼側偄乿丅侾侽擔屻僷僂儕偼偡偄憻偑傫偺偨傔偦偺昦堾偱巰傫偩丅
巹偑壀嶳偺嶰徣摪彂揦偱丆昞巻偵戝偒偔乽侾俁俈乿偲彂偐傟偨杮彂傪攦偭偨帪丆巹偺墶偱庒偄彈惈偑暥朳嬶偺傛偆側傕偺傪攦偭偰偄偨丅巹偑杮彂傪儗僕偺僇僂儞僞乕偵億儞偲抲偄偨傑偝偵偦偺弖娫丆椬偵偄偨傕偆堦恖偺儗僕學偑偦偺庒偄媞偵岦偐偭偰偙偆尵偭偰偄傞偺偑暦偙偊偰偒偨丅乽侾俁俈墌偵側傝傑偡乿両丂側傫偲偙傟傕傑偨儐儞僌偺尵偆乽僔儞僋儘僯僔僥傿乮嫟帪惈乯乿側偺偩傠偆偐丠
僺乕僞乕丒俰丒儀儞僩儕乕挊丆嶰巬彫栭巕栿丆怴挭幮丆俀侽侾侽擭俆寧俀俆擔敪峴丂ISBN978-4-10-506181-4 C0098
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俀丏俆
亂杮暥偐傜亃
|
仧捁偺暢偼丆搰傪偮偔傞偩偗偱側偔丆悽奅偺惗懺宯偵偍偄偰廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞丅奀捁偺暢偼丆枅擭侾枩乣侾侽枩僩儞偺儕儞傪奀偐傜棨偵堏摦偝偣偰偄傞偺偩丅悈捁偼丆幖抧偺拏慺偍係侽僷乕僙儞僩偲儕儞偺俈侽僷乕僙儞僩傪奀偐傜堏摦偝偣偰偄傞偲峫偊傜傟偰偄傞丅搚抧傪旍梹偵偡傞偙偆偟偨捁偨偪偑偄側偐偭偨傜丆懡偔偺娐嫬偼塰梴暘偑晄懌偟丆怉暔偑惗偊傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偩傠偆丅(P.71) 仧嬤擭丆峫屆妛幰偑丆僗僂僃乕僨儞偺僆乕儖僗僩搰偵偁傞庪椔嵦廤彫壆偺堚愓偺彴偵丆僇僶僲僉偺庽帀偺夠偑嶰偮棊偪偰偄傞偺傪敪尒偟偨丅庽帀偵偼姎傫偩偁偲偑偁傝丆偦偺帟宆偐傜丆姎傫偱偄偨偺偼僥傿乕儞僄僀僕儍乕偩偭偨偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅俋侽侽侽擭慜偺僈儉偱偁傞丅(P.110)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼丆偙偺僐乕僫乕偺俀偮壓偱徯夘偟偰偄傞傾僢僇乕儅儞偺乽偐傜偩偺堦擔乿偵愗傝岥偑偦偭偔傝偱偁傞丅偁傞恖偺挬偐傜斢傑偱偺堦擔偺弌棃帠傪戣嵽偵丆壢妛揑側愢柧偑壛偊傜傟偰偄傞丅偟偐偟丆偙偺杮偺応崌偼懳徾偼乽偐傜偩乿偱偼側偔丆乽偮偄偰偄側偄弌棃帠乿偱偁傞丅偙偺杮偺庡恖岞偼婥偺撆偵挬偐傜斢傑偱偝傑偞傑側晄塣偵尒晳傢傟傞丅梺幒偱揮搢偟偨傝丆僈僜儕儞偺儗僊儏儔乕偲寉桘傪娫堘偊偨傝偝傫偞傫偩丅偦傟傜堦偮堦偮偵偮偄偰丆壢妛揑偵偼壗偑惗偠偨偺偐偑昅幰偺朙晉側庢嵽椡傪尦偵愢柧偑壛偊傜傟偰偄偔丅偙偺杮偺尨戣偼 "The Undercoverd Scientist"偮傑傝乽暍柺壢妛幰乿乗乗挊幰偼丆偪傚偭偲偟偨晄塣偵尒晳傢傟偨偲偒丆乽偮偄偰側偄両乿偱曅偯偗偢偵丆偳偆偟偰偦偆側傞偺偐傪挷傋偰傒傞恖傪偙偆屇傫偱偄傞丅壢妛揑抦幆偵偮偄偰摼傞偲偙傠偺懡偄杮偱偁傞丅
儅乕僋丒儂僂挊丆嶰堜宐捗巕栿丆婭埳崙壆丆俀侽侽俋擭侾侽寧俀俆擔弶斉丂ISBN978-4-15-209080-5 C0045
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧偙偺杮偼丆僸僩偺敮偺栄偺懢偝偺侾侽侽暘偺侾偐傜侾侽暘偺侾偺戝偒偝傪傕偭偨傕偺偑廧傓悽奅偺暔岅偱偁傞丅(棯)傎偲傫偳偺壢妛幰乗乗戝壢妛幰偱偝偊傕乗乗偑丆偦傫側拞搑敿抂側僗働乕儖偺偲偙傠偱廳梫側偙偲偑搟偭偰偄傞偲偼丆巚偭偰傕傒側偐偭偨丅(P.24)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
儅僋儘乮塅拡乯傗儈僋儘乮尨巕乯偵娭偡傞杮偼偨偔偝傫偁傞丅偟偐偟丆偦偺拞娫偵偁傞悽奅偵偙偦廳梫側傕偺偑偁傞偲挊幰偼偄偆丅侾俉悽婭偵僗僐僢僩儔儞僪偺怉暔妛幰儘僶乕僩丒僽儔僂儞偑敪尒偟偨乽僽儔僂儞塣摦乿傪搚戜偵丆偝傑偞傑側壢妛幰偺僄僺僜乕僪傪傑偠偊偰乽儈僪儖儚乕儖僪乿偵偮偄偰岅傜傟偰偄傞丅
僕僃僯僼傽乕丒傾僢僇乕儅儞挊丆抌尨懡宐巕栿丆憗愳彂朳丆俀侽侽俋擭侾侽寧俀俆擔弶斉丂ISBN978-4-15-209080-5 C0045
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俇丏侽
亂杮暥偐傜亃
|
仧巹偨偪偺敳偗栚偺側偄慶愭偼栭偺埮偵忔偠偰惗偒墑傃偨丅埮偺拞偱偼帇妎傛傝挳妎偑傕偺傪尵偆丅挿偄帪傪宱偰丆斵傜偼帪娫師尦偵娭偡傞忣曬傪壛枴偟偨丆偒傢傔偰惛鉱側挳妎宯傪恑壔偝偣偨丅尰嵼丆巹偨偪偺帹偼堦昩偺悢暘偺堦偲偄偆挿偝偺堦楢偺壒傪惓偟偄弴斣偱暦偒傢偗丆壒尮偺嬻娫埵抲傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅(P.53) 仧偁偲偐傜傗偭偰偔傞嬝擏捝偼丆嬝擏偵偱偒偨旝彫側楐偗栚偑侾乣俀擔屻偵墛徢傪婲偙偡偨傔偵婲偒傞丅彫偝側楐偗栚傪曗廋偟傛偆偲嬱偗偮偗偨敀寣媴偑丆捝傒乗乗懝彎偲媥懅偺昁梫惈傪抦傜偣傞儊僇僯僘儉乗乗傪姶偠偝偣傞壔妛暔幙傪曻弌偡傞偺偩丅(P.195)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼丆変傢傟恖娫偺堦擔偺峴摦傪傕偲偵丆巹偨偪偺懱偺拞偱偼偳偺傛偆側巇慻傒偑摥偄偰偄傞偐傪傢偐傝傗偡偔愢柧偟偰偄傞丅妛傇偲偙傠偺懡偄杮偱偁傞丅
僕儑儞丒俿丒僇僔僆億仌僂傿儕傾儉丒僷僩儕僢僋挊丆幠揷桾擵栿丆壨弌彂朳怴幮丆俀侽侾侽擭侾寧俁侽擔弶斉丂ISBN978-4-309-24506-5 C0011
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俁
亂杮暥偐傜亃
|
仧屒棫姶傪妎偊側偄恖側偳偄側偄丅嬻暊姶傗恎懱揑側捝傒偲柍墢偱偼偄傜傟側偄偺偲摨偠偩丅(棯)偟偐偟丆偄偭偨傫偦傟偑堷偒婲偙偝傟傞偲丆屒撈姶偑惗傓帺屓杊塹宆偺巚峫乮屒撈姶偵榗傔傜傟偨幮夛揑擣抦乯偺偣偄偱丆嵄嵶側幮夛揑帠暱偑偡傋偰戝栤戣偵巚偊偰偟傑偆丅(P.52) 仧恖乆傪摦梙偝偣丆偦偺帺屓挷愡擻椡傪扗偆偺偼丆奺帺偺恖惗偺弶婜偺偙傠偵丆偦偟偰恖椶偺楌巎偺偛偔弶婜偺偙傠偵婲尮傪帩偮嫲傟偩丅偦偺埑搢揑側嫲傟偲偼丆偳偆偟傛偆傕側偄怺崗側屒撈傪姶偠傞偙偲偵懳偡傞嫲晐側偺偩丅(P.75) 仧幮夛偑偳傟傏偳朙偐偵側傝僥僋僲儘僕乕偑岦忋偟偨偲偄偭偰傕丆堦旂傓偗偽恖娫偼丆俇枩擭慜丆棆塉偵偍傃偊尐傪婑偣崌偭偰偄偨偐庛偄惗偒暔偺傑傑側偺偩丅(P.78) 仧巹偨偪偑屳偄偵埶懚偡傞偺偼丆偨傫偵怱尛偄傗堅傔偺偨傔側偳偱偼側偔丆惗懚偦偺傕偺偺偨傔側偺偩丅(P.278)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
帪乆扤傕偑廝傢傟傞晄埨姶傗屒撈姶丅偟偐偟丆偙偺屒撈姶偼墦偔恖椶偑傾僼儕僇傪弌傞慜偵僀儞僾僢僩偝傟偨傕偺側偺偱偁傞丅孮傟偐傜偼偢傟傟偽丆巰傪堄枴偟偰偄偨忬嫷偐傜変傢傟偺擼偼傑偩扙偟偰偄側偄偺偱偁傞丅乽屒撈乿偼扨偵桱烼側婥帩偪傪昞偡偺偱側偔丆変乆偺擣抦擻椡傪掅壓偝偣丆帪偵偼惗懚偵娭傢傞傎偳偺桳奞側傕偺側偺偱偁傞丅杮彂偼丆擣抦壢妛偺娤揰偐傜丆扤傕偑捈柺偡傞乽屒撈乿傪偳偆忔傝墇偊傞偐傪嫵偊偰偔傟傞丅億僀儞僩偼乽偨偲偊嵄嵶偱偼偁偭偰傕丆幮夛偲偺偮側偑傝傪帩偮乿偲偄偆偙偲偱偁傞丅
僨僀價僢僪丒俰丒儕儞僨儞挊丆壞栚戝栿丆僀儞僞乕僔僼僩幮丆俀侽侽俋擭俋寧俁侽擔戞侾嶞丂ISBN978-4-7726-9516-9 NDC401
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾係丏俀
亂杮暥偐傜亃
|
仧変乆偺擼偼姰帏側傕偺偱傕丆旕偺偆偪偳偙傠偺側偄傕偺偱傕側偄偟丆僛儘偐傜廫暘側嬦枴偺忋偱嶌傜傟偨傕偺偱傕側偄丅幚嵺偵偼丆偡傋偰偑娫偵崌傢偣丆偦偺応偟偺偓丆婑偣廤傔丆師慞偺嶔偺嶻暔側偺偩丅(棯)偦偺応偟偺偓偺懳嶔偩偗偱嶌傜傟偨偵傕偐偐傢傜偢丆変乆偼偙傟偩偗偺巚峫椡偲姶忣傪帩偪摼偨丆側偳偲峫偊傞偺偼惓偟偔側偄丅恀幚偼傑偭偨偔偺媡偱丆恑壔偺摴嬝偑嬋偑傝偔偹偭偰偄偨偐傜偙偦丆偦偺応偟偺偓偺懳嶔偺婑偣廤傔偩偭偨偐傜偙偦丆変乆偼崱偺傛偆側巔偵側偭偨偲峫偊傞傋偒側偺偱偁傞丅(P.323)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙傟傑偨柺敀偄杮偱偁傞丅暿偺挊幰偵傛偭偰彂偐傟偨亀擼偼偁傝崌傢偣偺嵽椏偐傜惗傑傟偨亁乮僎傾儕乕丒儅乕僇僗乯偲偄偆椶彂傕偁傞偑丆偙偺杮偺曽偑愭丅偨偩椉幰偺帇揰偼堎側傞丅偙偺杮偼垽丆婰壇丆柌丆恄側偳傪帪偵偼偐側傝愱栧揑偵庢傝忋偘傞偑丆棟夝偟傗偡偄丅摿偵丆姫枛偱丆偣傢偟偔摦偔娽媴塣摦偺擼偑乽曗惓乿偟偰暔岅傪嶌傝忋偘傞傛偆偵丆廆嫵傕嵍擼偑柍娭學偺婰壇偺抐曅傪偮側偓崌傢偣偰嶌傝忋偘偨暔岅偱偁傞偲偄偆榖偼柺敀偐偭偨丅崱傾儊儕僇偱婲偒偰偄傞媈帡壢妛乽僀儞僥儕僕僃儞僩丒僨僓僀儞乿偺偳偙偑娫堘偭偰偄傞偐傪巜揈偟偰偄傞偲偙傠傕尒摝偣側偄丅
傾儞僪儗傾丒儘僢僋挊丆埳摗榓巕栿丆儔儞僟儉僴僂僗島択幮丆俀侽侽俋擭俉寧俆擔戞侾嶞丂ISBN978-4-270-00523-1 C0040
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾係丏侽
亂杮暥偐傜亃
|
仧柌偼嫮偄姶忣傪敽偆偙偲偑懡偄丅儂僽僜儞傜偼旐尡幰偺曬崘偐傜姶忣偵娭偡傞僨乕僞傪廤傔偰傒偨丅偦偺寢壥丆嶰偮偺姶忣偑柌偺拞偱姶偠傞姶忣偺俈侽亾傪愯傔偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅嵟傕傛偔尒傜傟傞偺偼晄埨偱丆崅梘姶偲搟傝偑偦傟偵懕偔丅垽忣傗僄儘僥傿僢僋側姶忣丆抪丆嵾埆姶側偳偼偁傑傝弌偰偙偢丆旐尡幰偺曬崘偱偼偄偢傟傕屲亾懌傜偢偵偡偓側偐偭偨丅(P.54) 仧乽偁側偨偺尒偰偄傞悽奅偑堦楢偺僯儏乕儘儞偺妶惈壔僷僞乕儞偵傛偭偰惗偠偨僀儊乕僕偵偡偓側偄偲傢偐傟偽丆怱恎栤戣偵偼傕偆寛拝偑偮偄偨傛偆側傕偺偩乿偲丆儂僽僜儞偼尵偆丅
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
挊幰偼壢妛幰偱側偔丆堛椕宯僕儍乕僫儕僗僩丅偦偺偨傔丆庢嵽愭偺壢妛幰偺挊彂乮椺偊偽儂僽僜儞偺亀柌偵柪偆擼乗乗栭偛偲怱偼偳偙傊峴偔亁挬擔弌斉幮側偳乯偲廳側傝崌偆晹暘傕懡偄偑丆怴偨側忣曬傕傕偪傠傫偁傞丅乽側偤柌傪傒傞偺偐乿偵偮偄偰偼丆傑偩寢榑偼弌偰偄側偄丅柌偺拞偱乽摝偘傞偐愴偆偐乿偺孭楙傪偟偰偄傞偺偩偲偐丆忣曬偺惍棟傪偟偰偄傞偺偩偲偐偄傠傫側愢偑偁傞丅偨偩丆尵偊傞偺偼丆柌偦偺傕偺偵偼戝偒側堄枴偼側偔丆悋柊拞偵擼偑偁傞嶌嬈傪峴偭偰偄傞偙偲偐傜弌傞乽暃嶻暔乿偵偡偓側偄偲偄偆偙偲偩丅僼儘僀僩偺傛偆偵偦傟偵怺偄堄枴傪帩偨偣傞偙偲偼柍堄枴偱偁傞丅
暉壀怢堦挊丆俀侽侽俋擭俀寧俀俆擔弶斉戞侾嶞丆俀侽侽俋擭俁寧俀係擔戞係嶞丂ISBN978-4-86324-012-4 C0045
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧惗懱傪峔惉偟偰偄傞暘巕偼丆偡傋偰崅懍偱暘夝偝傟丆怘暔偲偟偰愛庢偟偨暘巕偲抲偒姺偊傜傟偰偄傞丅恎懱偺偁傜備傞慻怐傗嵶朎偺拞恎偼偙偆偟偰忢偵嶌傝姺偊傜傟丆峏怴偝傟懕偗偰偄傞偺偱偁傞丅乮棯乯偙偙偱巹偨偪偼夵傔偰乽惗柦偲偼壗偐丠乿偲偄偆栤偄偵摎偊傞偙偲偑偱偒傞丅乽惗柦偲偼摦揑側暯峵忬懺偵偁傞僔僗僥儉乿偲偄偆夞摎偱偁傞丅(P.232)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
仧愨偊偢擖傟懼傢傝丆傕偲偺傑傑偱偼側偄乗乗偙傟偼側偵傕姏挿柧偑尒偨姏愳偩偗偱偼側偄丅巹偨偪偺懱傕暘巕扨埵偱傒傞偲悢擔偱怴媽偑擖傟懼傢偭偰偄傞偺偩丅巹偨偪偑愨偊偢暔傪怘傋懕偗側偗傟偽側傜側偄棟桼偼偦偙偵偁傞丅暘巕扨埵偱傒傟偽悢擔屻偺巹偨偪偼傕偼傗尰嵼偺巹偨偪偱偼側偄丅乽惗偒偰偄傞乿偲偼偦偆偟偨愨偊偢曄壔偡傞摦揑側暯峵忬懺傪偄偆偺偩丅恎懱傪扨側傞晹昳偲尒傞僇儖僥傿僕儍儞乮僨僇儖僩攈偺恖乆乯偼娫堘偭偰偄傞丅杮彂偼偦偆慽偊傞丅暉壀巵偼儀僗僩僙儔乕乽惗暔偲柍惗暔偺娫乿乮島択幮尰戙怴彂乯偺挊幰丅
儅乕僋丒僽僉儍僫儞挊丆嶃杮廏媣栿丆俀侽侽俋擭俇寧俀侽擔戞侾斉戞侾嶞丂ISBN978-4-8269-0155-0 C00470
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俆丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧恖傪乽尨巕乿丆偡側傢偪幮夛揑悽奅偺婎杮揑峔惉梫慺偱偁傞乽幮夛偺尨巕(social atom)乿偲尒側偣偽丆廤抍偺儗儀儖偱偼丆恖乆偺惈奿偲傎偲傫偳娭學偺側偄戝婯柾側僷僞乕儞偑弌尰偡傞偲峫偊偰偄偄偩傠偆丅(p.30)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
仧尨戣偼"The Social Atom"乮幮夛偺尨巕乯丅偙傟傑偱幮夛壢妛偼偲偰傕乽壢妛揑乿偲偼尵偊側偄庤朄偱懳徾傪暘愅偟傛偆偲偟偰偒偨丅恖娫偲偄偆偺偼側偐側偐偦偺峴摦偑悇應乮寁嶼乯偟偑偨偄傕偺偱偁傝丆悢妛傗暔棟妛偵偼側偠傑側偄偲偄偆僀儊乕僕偑偁傞丅偟偐偟丆杮彂偺昅幰偼偦偆偱偼側偄偲偄偆丅妋偐偵屄乆偺恖娫偼條乆側惈奿傪桳偡傞偑丆偦傟傪戝偒側幮夛偺峔惉梫慺乮尨巕乯偲尒側偣偽丆偦偙偵偼旕忢偵扨弮壔偱偒傞僷僞乕儞偑尒偊偰偔傞偲偄偆丅昅幰偼懠偺挊彂偵偍偄偰傕乽傋偒忔懃乿偺廳梫惈傪嫮挷偟偰偄傞偑丆杮彂偱傕慠傝丅側偵偟傠丆尦乽僱僀僠儍乕乿曇廤幰偺儅乕僋丒僽僉儍僫儞偱偁傞丅旕忢偵榑棟揑偐偮慺恖偵傢偐傝傗偡偔愢柧偱偒傞擻椡偼偝偡偑偩丅朚栿傕偙側傟偰偄傞丅偤傂斵偺懠彂乽楌巎偺曽掱幃乿乮憗愳彂朳乯丆乽暋嶨側悽奅丆扨弮側朄懃乿乮憪巚幮乯傕堦撉偟偰傎偟偄丅
僕儑乕丒儅乕僠儍儞僩挊丆栘懞攷峕栿丆俀侽侽俋擭俆寧侾俆擔戞侾嶞丂ISBN978-4-16-371430-1 C0098
亂僀儞僷僋僩巜悢亃係丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧僐儞僩僗慏挿偲偦偺忔慻堳偑奀掙偵柊傞傾儞僥傿僉僥儔偺婡夿傪堷偒梘偘偰埲棃丆昐擭埲忋宱偨偄傑丆婡夿偺撲偑傛偆傗偔夝柧偝傟偨丅偦偺栘憿傝偺敔偺墶偵偁傞僴儞僪儖傪夞偟偨幰偼丆塅拡偺偁傞偠偵側傟偨丅夁嫀偱傕枹棃偱傕丆帺暘偑尒偨偄帪娫偺揤嬻偺摦偒傪丆尒傞偙偲偑偱偒偨偺偩丅昞懁偺恓偼侾俀媨偺拞偱堏傝曄傢傞懢梲丆寧丆榝惎偺埵抲傪帵偟丆寧偺枮偪寚偗傪嫵偊偨丅棤懁偺梿慁偺暥帤斦偼懢梲楋偲懢堿楋偺慻傒崌傢偣偱擭偲寧傪帵偟丆怘偺帪婜傪嫵偊偨丅(p.243)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
仧1900擭抧拞奀偺傾儞僥傿僉儔搰晅嬤偺奀掙偐傜婏柇側婡夿偑僟僀僶乕偵傛偭偰堷偒梘偘傜傟偨丅偦偺婡夿偵偼暋嶨側帟幵偺峔憿偑偁偭偨丅偟偐傕偦傟偼婭尦慜俀悽婭偺傕偺偲偄偆偺偩丅偙傟偼帪寁偺敪柧傛傝1400擭憗偄丅屆戙僊儕僔儍偵偦偺傛偆側婰弎偼偳偙偵傕弌偰偙側偄丅妛幰偨偪偺撲偺夝柧儗乕僗偑巒傑偭偨丅偦偙偵偼棤愗傝丆愨朷側偳偝傑偞傑側恖惗柾條偑孞傝峀偘傜傟偰偄偔丅傑偩尋媶偼懕偄偰偄傞傕偺偺丆寢嬊偼偙偺婡夿偼傾儖僉儊僨僗偺惗傑傟屘嫿丆僔儔僋僒偱嶌傜傟偨夁嫀傗枹棃偺乽揤懱塣峴昞帵婡乿偩偭偨丅巹偼偙偺婡夿偺撲偺夝柧偺柺敀偝偩偗偱側偔丆壢妛幰娫偺恖娫柾條偑偍傕偟傠偐偭偨丅
擔崅晀棽挊丆偪偔傑妛寍暥屔840丆俀侽侽俈擭俋寧侾侽擔戞侾嶞丂ISBN978-4-480-09097-3 C0145
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侾丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧偙偺晹壆偵僴僄偑旘傃崬傫偱偒偨偲偡傞偲丆僴僄偵偲偭偰娭怱偑偁傞偺偼丆怘傋暔偲堸傒暔偩偗偱偁傞丅僴僄偐傜尒傞偲丆偦傟偩偗偑傄偐偭偲岝偭偰尒偊傞丅偟偐偟丆僥乕僽儖偲偐堉巕偲偐丆偦傫側傕偺偼偳偆偱傕傛傠偟偄丅杮扞丆撉彂戜丆偦傫側傕偺偵偼壗偺娭怱傕側偄丅偦傟偼傎偲傫偳奃怓偱偁傞丅偟偐偟丆僴僄偼岝偵岦偐偭偰旘傫偱偄偔惈幙偑偁傞偐傜丆忋偐傜徠偭偰偄傞揹摂偑婸偄偰偄傞偙偲偼傢偐傞丅偩偐傜丆揹摂偑忋偐傜徠偭偰偄偰丆揰乆偲偄偔偮偐偺堸傒暔偲偐怘傋暔偑偁傞丆偦傟偩偗偱偁傞丅懠偺傕偺偼壗傕懚嵼偟偰偄側偄偵摍偟偄丅(p.42)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
仧摦暔偐傜尒傟偽丆変乆恖娫偑尒偰偄傞悽奅偲偼偐側傝堘偭偨悽奅偑尒偊偰偄傞丅斵傜偼斵傜側傝偺恑壔偺夁掱偱妉摼偟偨曽朄偱悽奅傪尒偰偄傞偺偩丅侾俋俁侽擭戙偵僪僀僣偺峴摦摦暔妛幰儐僋僗僉儏儖偑乽娐悽奅乿傪彞偊偨偲偒丆扤傕斵偵拲堄傪暐傢側偐偭偨丅偟偐偟偦偺峫偊偼幚偵妚怴揑側傕偺偱偁偭偨丅杮彂偼儐僋僗僉儏儖偺峫偊傪拞怱偵丆恖娫傕娷傔偰抧媴偺摦暔偨偪偼偦傟偧傟偺庬偑撈帺偺悽奅傪尒偰偄傞偙偲傪傢偐傝傗偡偔嫵偊偰偔傟傞丅僱僐偑丆偨偩巻偵彂偄偨懠偺僱僐偺慄夋偵偝偊斀墳偡傞偲偄偆偙偲偼嬃偒偩偭偨丅
崟栘搊巙晇挊丆拞岞怴彂1898丆俀侽侽俈擭俆寧俀俆擔敪峴丂ISBN978-4-12-101898-4 C1247
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏侽
亂杮暥偐傜亃
|
仧悽偺拞偱枹棃傎偳晄妋偐側傕偺偼側偄偵傕偐偐傢傜偢丆巰偸偙偲偩偗偼侾侽侽僷乕僙儞僩妋幚偱偁傞丅偦傟偑柧擔側偺偐丆俁侽擭屻側偺偐傪抦傜側偄偩偗偩丅偦傟屘偵丆巰傪堄幆揑偵墦偞偗丆偄偮傑偱傕柦偑偁傞傛偆偵怳傞晳偆偙偲偑偱偒傞偵偡偓側偄丅偟偐偟丆偄偮偐丆偡傋偰偺恖偵暿傟偺偲偒偑朘傟傞丅旔偗傛偆偺側偄丆惗偒暔偲偟偰偺潀側偺偩丅(p.208)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
仧偮傂偵峴偔摴偲偼偐偹偰暦偒偟偐偳丂嶐擔崱擔偲偼巚偼偞傝偟傪乗乗嵼尨嬈暯
杮彂偼楌巎偲惗暔恑壔偺帇揰偐傜丆彂偐傟偨堛妛暔岅偱偁傞丅昦尨旝惗暔偺敪尒僄僺僜乕僪傗惗妶廗姷昦偵傛偭偰惗偠傞昦婥偵偮偄偰傢偐傝傗偡偔弎傋傜傟偰偄傞丅摼傞偲偙傠傕懡偄丅
僎傾儕乕丒儅乕僇僗挊丆抌尨懡宐巕栿丆憗愳彂朳丆俀侽侽俋擭侾寧俀俆擔弶斉丂ISBN978-4-15-208997-7 C0045
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俈丏俇
亂杮暥偐傜亃
|
仧帺慠偑僋儖乕僕乮尒偐偗偺椙偔側偄娫偵崌傢偣偺婡擻乯傪偮偔傞偺偼丆偦偺強嶻偑姰帏偐僄儗僈儞僩偐傪帺慠偼婥偵傕棷傔側偄偐傜偱偁傞丅桳梡偱偝偊偁傟偽丆偦傟偼惗偒巆偭偰悢傪憹傗偡丅栶偵棫偨側偗傟偽丆巰偵愨偊傞丅傛偄寢壥傪惗傓堚揱巕偼斏怋偟丆偦傟偑偱偒側偄堚揱巕偼柵傃傞丅偨偩偦傟偩偗偺偙偲側偺偱偁傞丅栤戣偼旤偱偼側偔揔崌惈側偺偩丅(p.15)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
仧崅峑惗偺偲偒乽悽奅巎乿偺嵟弶偺庼嬈偱愭惗偑丆乽恖椶偑抋惗偟丆捈棫偟丆壩傪巊偆偙偲傪妎偊丆傗偑偰擾峩偡傞傛偆偵側傝傑偟偨乿偲偄偭偰丆乽偝偰偙傟偱恖椶巎偺俋俋亾偑廔傢傝傑偟偨乿偲偄偭偨偲偒丆巹偼寉偄嬃偒傪姶偠偨丅挿偄恖椶偺楌巎偐傜尒傟偽丆暥柧埲屻偺楌巎偼乽偛偔嵟嬤乿偺偙偲側偺偩丅巹偨偪偺擼傕偦偺拞偱恑壔偟偰偒偨偙偲傪峫偊傞偲丆偦傫側偵媫偵夁嫀傪朰傟傞偙偲側偳偱偒傞傢偗偑側偄丅偦偆偄偆傢偗偱変乆偼偄傑偩偵挿偐偭偨夁嫀偺堚嶻傪傂偒偢偭偰惗偒偰偄傞丅
仧傾儊儕僇崌廜崙偱乽崟恖乿偺戝摑椞偑弌傞傑偱側偤偐偔傕挿偔懸偨偹偽側傜側偐偭偨偺偐丅偦傟偼変乆偺擼偑乽婋婡姶偑戝偒傟偽戝偒偄傎偳丆尒姷傟偨傕偺偵偟偑傒偮偔乿孹岦偑偁傞偐傜偩丅帡偨傛偆側婄傪偟偨恖庬傗柉懓偵恊嬤姶傪書偒丆偦偆偱側偄傕偺偵偼媈擮傪帩偭偰偟傑偆偺偼丆擼偺恑壔傪峫偊傞偲乽傑偩乿傗傓傪偊側偄偲偙傠傕偁傞丅恑壔偼偦傫側偵媫偵偼恑傑側偄偐傜偩丅乽帡偨傕偺偼枴曽丆堎側傞傕偺偼揋乿乗乗恑壔偺忋偱偼偙偆偟偨斀墳偑惗偒巆傞僠儍儞僗傪憹傗偟偰偒偨偙偲偩傠偆丅偟偐偟丆崱傗偦偆偟偨屆偄擼偑変乆偺峫偊曽傪惂尷偟偰偄傞偺偩丅僟僀僄僢僩傪寛怱偟側偑傜傕丆栚偺慜偵偁傞偍壻巕偵偮偄庤偑偱偰偟傑偆偺偼丆偐偮偰偺乽怘傋傜傟傞帪偵怘傋偰偍偔乿偙偲偑惗偒巆傞僠儍儞僗傪憹傗偟偰偄偨帪戙偐傜丆変乆偺擼偑傑偩廫暘扙媝偱偒偰偄側偄偐傜偩丅
仧杮彂偵偼丆俙偲偄偆峴堊偺捈慜偵丆偦傟偲偼壗偺娭學傕側偔峴傢傟偨俛偲偄偆峴堊偑丆俙偲偄偆峴堊偺敾抐偵柍堄幆偺偆偪偺塭嬁傪梌偊傞乽僾儔僀儈儞僌乿偲偄偆條乆側幚尡椺傕徯夘偝傟偰偄傞丅寢嬊丆変乆偺晄壜夝側峴摦偺尨場偺懡偔偼丆乽屆偄擼偵娫偵崌傢偣揑偵宲偓懌偝傟偰偒偨擼乿偵偁傞偙偲傪杮彂偼偔傢偟偔愢偄偰偄傞丅
拞懞徦擇挊丆挬擔暥屔丆俀侽侽擭侾俀寧俁侽擔戞侾斉丂ISBN978-4-334-02-261583-1 C0195
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧挷崄偺敾掕偵帺怣偑帩偰傞傛偆偵側傞傑偱偵偼丆憡摉偺廋楙傪梫偡傞丅廋楙偱嵟傕戝愗側偙偲偼丆傑偢偦偺暘栰偺嵟崅媺昳偺崄椏偐傜乽偐偓崬傫偱乿偄偔偙偲偱偁傞丅乽椙偄崄傝偲偼壗偐乿傪帺暘偺恎偵偮偗傞偙偲偱偁傞丅寛偟偰幙偺掅偄崄椏偐傜庢傝慻傫偱偼側傜側偄丅偙偺偙偲偼丆偡傋偰偺揤慠崄椏偵捠偢傞揝懃偩丅嵟崅媺昳偼丆崿偤傕偺偑側偔丆嵦庢丆惢憿岺掱傕拲堄怺偔峴傢傟偰偰丆杮暔埲奜偺偵偍偄偑擖傞壜擻惈偑彮側偄丅偦傟偑恎偵偮偗偽丆偦傟偐奜傟傞偵偍偄偼丆偡傋偰偑堎廘側偺偱偁傞丅(P.75)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
偐偮偰乽庼嬈幚慔偺揤嵥乿嵵摗婌攷偼丆巕偳傕傪嫵堢偡傞応崌偵偼乽堦棳偺傕偺傪梌偊傞傋偒乿偩偲尵偭偨丅傑偩宱尡偺朢偟偄巕偳傕偨偪偵擇棳丆嶰棳偺傕偺傪尒偣傞偲斵傜偼偦傟偑嵟崅偺傕偺偩偲巚偭偰偟傑偄丆偦偺屻偺娪徿擻椡偑慾奞偝傟傞偐傜偩丅杮彂偺挊幰偼傑偝偵偦傟偲摨偠偙偲傪尵偭偰偄傞丅
巹偼乽偵偍偄乮歬妎乯乿偵娭怱偑偁傞丅歬妎偼帇妎側偳偺傛傝傕傕偭偲杮擻偵嬤偄傕偺偱偁傞偟丆擼偺拞偱張棟偝傟傞応強傕杮擻偵嬤偄強偵偁傞偲暦偄偨丅杮彂偺挊幰偼帒惗摪偱挿傜偔挷崄巘偲偟偰悢懡偔偺崄悈傪奐敪偝傟偰偒偨恖偱偁傞丅杮彂偼埲慜偵弌偨乽崄傝偺悽奅傪偝偖傞乿偵戝暆壛昅偝傟偨傕偺丅擔杮岅偵偼乽偵偍偄乿傪昞尰偡傞岅渂偼彮側偄偲扱偒側偑傜傕丆挷崄巘偑傛偔巊偆乽僔僩儔僗丒僲乕僩乿乽僂僢僪傿丒僲乕僩乿乽僆儕僄儞僞儖丒僲乕僩乿側偳偼偳偆偄偆崄傝偺偙偲側偺偐傪徻偟偔愢柧偟偰偔傟傞丅乽壛楊廘乿懠乽偵偍偄乿偵娭怱偺偁傞曽偵偼偍偡偡傔丅
暉壀怢堦挊丆岝暥幮怴彂371丆俀侽侽俉擭侾侽寧俀侽擔弶斉戞侾斉丆俀侽侽俉擭侾侾寧侾侽擔戞俀嶞丂ISBN978-4-334-03474-0 C0425
亂僀儞僷僋僩巜悢亃係丏俀
亂杮暥偐傜亃
|
仧偙偆尵偄姺偊傞偙偲偑偱偒傞丅抝惈偼丆惗柦偺婎杮巇條偱偁傞彈惈傪嶌傝偐偊偰弌棃忋偑偭偨傕偺偱偁傞丅偩偐傜丆偲偙傠偳偙傠偵媫応偟偺偓偺丆晄嵶岺側巇忋偑傝嬶崌偵側偭偰偄傞偲偙傠偑偁傞偲丅幚嵺丆彈惈偺恎懱偵偼偡傋偰偺傕偺偑旛傢偭偰偍傝丆抝惈偺恎懱偼偦傟傪庢幪慖戰偟偐偮夵曄偟偨傕偺偵偡偓側偄丅婎杮巇條偲偟偰旛傢偭偰偄偨儈儏儔乕娗偲僂僅儖僼娗丅抝惈偼儈儏儔乕娗傪姼偊偰嶦偟丆僂僅儖僼娗傪懀惉偟偰惗怋婍姱偲偟偨丅(棯)丂傾僟儉偑僀僽傪嶌偭偨偺偱偼側偄丅僀僽偑傾僟儉傪嶌傝弌偟偨偺偱偁傞丅(P.166)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
巕偳傕偺崰偐傜巹偼丆側偤抝惈乮帺暘乯偵擕庱偑偁傞偺偐晄巚媍偱側傜側偐偭偨丅偦偟偰嵟嬤偵側偭偰丆偦傟偼帺暘偑曣恊偺戀撪偱抝偵側傞偐彈偵側傞偐枹寛掕偺帪婜偐傜偡偱偵偱偒偰偄偨偙偲傪抦偭偨丅傂傚偭偲偡傞偲惗柦偼抝偱側偔彈偑婎杮側偺偱偼丠杮彂偼偦偺捠傝偩偲偄偆丅抧媴偵惗柦偑抋惗偟偰偐傜侾侽壄擭傕偺娫丆惗暔偺惈偼偨偭偨堦偮乗乗偡傋偰偑儊僗偩偭偨丅惗柦偼傑偢儊僗偲偟偰敪惗偟丆僆僗偼丆偦偺儊僗偺宯晥偺乽巊偄憱傝乿偵偡偓側偄丅挊幰偼暘巕惗暔妛偺愱栧壠丅栚偐傜椮偺杮偱偁傞丅
楅栘岝懢榊挊丆怴梛幮丆俀侽侽俉擭俋寧俀俋擔弶斉戞侾斉丆俀侽侽俉擭侾俀寧俀俀擔弶斉戞俆嶞丂ISBN978-4-7885-1124-8 C1011
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧傾儅儔偲僇儅儔偼偄偨偺偩傠偆丅僔儞僌偺傕偲偵偼丆儊儌掱搙偺擔婰傕偁偭偨偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丆僔儞僌偺婰榐偼丆屩挘傗媟怓偟偨傕偺偐丆怴偨偵偙偟傜偊偨傕偺偩丅彮側偔偲傕幨恀偼丆婰弎偵崌偆傛偆偵墘弌偟側偑傜嶣偭偨傕偺偱偁傞丅(棯)傾儅儔偲僇儅儔偺榖偼丆擔杮偱偼彫妛峑偺摴摽偺嫵嵽偲偟偰傕巊傢傟偰偄傞偟丆崅峑偺椣棟偺嫵壢彂偵傕嵹偭偰偄傞偙偲偑偁傞丅偮傑傝丆嫵堢尰応偱偼丆婛惉帠幚偲偟偰嫵偊傜傟偰偄傞丅(P.30-33)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
怱棟妛奅偵偼乽搒巗揱愢乿偺傛偆偵崻傕梩傕側偄榖偑乽帠幚乿偲偟偰棳晍偟偰偄傞傕偺偑偄傠偄傠偁傞丅乽僆僆僇儈彮彈乿偺榖丆乽僒僽儕儈僫儖峀崘偱億僢僾僐乕儞偑攧傟偨乿偲偄偆榖丆乽僔儕儖丒僶乕僩偵傛傞堦棏惈憃惗帣偺尋媶僨乕僞偹偮憿乿丆偦偟偰乽僒僺傾亖僂僅乕僼壖愢乿丅傢偨偟偼丆抪偢偐偟側偑傜乽僒僺傾亖僂僅乕僼壖愢乿傪傑偲傕偵怣偠偰偄偨丅恖娫偵偼惗堢娐嫬偑偄偐偵戝愗偐傪嫵偊傞偨傔偵丆昁偢乽傾儅儔偲僇儅儔乿偺榖偑堷梡偝傟傞偺傪傛偔栚偵偟偰偒偨丅偟偐偟丆偙傟傜偼帠幚偱偼側偄偲偄偆偺偩丅杮彂偼扨側傞朶業杮偱偼側偄丅杮棃偁傞傋偒怱棟妛偲偼壗偐傪恀寱偵栤偆傕偺偱偁傞丅媣偟怳傝偺椙彂丅
傾儈乕儖丒D丒傾僋僛儖挊丆悈扟弤栿丆擔宱俛俹幮丆俀侽侽俈擭侾侽寧俀俀擔戞侾斉侾嶞丆ISBN978-4-8222-8332-2
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俋
亂杮暥偐傜亃
|
仧償僃僀儐偼怴偨側桭恖偵(棯)億儖僨償傿傾壢妛傾僇僨儈乕夛堳偱偁傞僽儖僶僉偲偄偆柤偺悢妛幰偵傛傞丆壦嬻偺尋媶偺憤愢榑暥傪彂偄偰傒偨傜偳偆偐偲姪傔偨丅 僐乕僒儞價乕偼偦偺榖偵忔偭偰丆姰慡偵壦嬻偺撪梕偱亀僽儖僶僉偺戞擇掕棟偺堦斒壔偵偮偄偰亁偲偄偆僞僀僩儖偺榑暥傪彂偒丆偦傟傪佱傾僌儔偍傛傃傾僂僪丒傾儔僴僶乕僪廈壢妛傾僇僨儈乕婭曬佲偵宖嵹偟偰傕傜偭偨丅榑暥偵偼丆乽偙偺掕棟偼丆妚柦帪偵撆嶦偝傟偨柍柤偺儘僔傾恖悢妛幰俢丒僽儖僶僉偵傛傞傕偺偱偁傞乿偲婰偝傟偰偄偨丅(P.76)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偼抪偢偐偟側偑傜丆乽僯僐儔丒僽儖僶僉乿偼幚嵼偺屄恖偱偁傞偲巚偭偰偄偨丅幚偼偙傟偼庒偄僼儔儞僗恖悢妛幰偨偪偑埆傆偞偗偐傜嶌傝弌偟偨壦嬻偺悢妛幰偺柤慜偱偁傞丅偟偐偟丆偙偺桪廏側悢妛幰僌儖乕僾偼丆傗偑偰恀寱偵乽儐乕僋儕僢僪偺亀尨榑亁偺傛偆偵崱屻俀侽侽侽擭偼帩偮傛偆側怴偟偄亀尨榑亁傪嶌傠偆乿偲峫偊丆僽儖僶僉偺柤慜偱偳傫偳傫杮傪弌偟偰偄偔乮僽儖僶僉帺恎偼丆僼儔儞僗偵幚嵼偟偨僊儕僔儍宯彨孯偺柤慜偱偁偭偨乯丅偦偟偰偮偄偵丆偙偺僌儖乕僾偺妶摦偑俀侽悽婭偺峔憿庡媊傪惗傒弌偟丆尵岅妛丆怱棟妛丆宱嵪妛丆幮夛妛偦偺懠懡偔偺暘栰偵戝偒側塭嬁傪梌偊傞偙偲偵側傞偺偩丅僺儗僱乕嶳柆偺怷偺拞偵巔傪偔傜傑偟偨婼嵥悢妛幰僌儘僞儞僨傿乕僋偲僽儖僶僉廤抍偲偺娭傢傝傪愢柧偟側偑傜丆僽儖僶僉廤抍偺棽惙偲悐戅傪杮彂偼昤偔丅廐偺栭挿偵撉傓偺偵嵟揔偺堦嶜偱偁傞丅
億乕儖丒僗僩儔僓乕儞挊丆堫揷偁偮巕懠栿丆僶儀儖丒僾儗僗彂朳丆俀侽侽俇擭係寧俁侽擔弶斉戞侾斉丆ISBN4--89449-043-9
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俀
亂杮暥偐傜亃
|
仧儊儞僨儗乕僄僼偑柇埬傪巚偄偮偄偨偺偼丆偙偺帪揰偩偭偨偵堘偄側偄丅尦慺偺栤戣偲丆岲偒側僇乕僪僎乕儉乽儁僀僔僃儞僗乿偲偺娭楢偑傂傜傔偄偨偺偩丅斵偼敀巻偺僇乕僪傪壗枃傕庢傝弌偟丆偦傟偵尦慺偺柤慜傪彂偒巒傔偨丅乮P.309)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂側儊儞僨儗乕僄僼偺揱婰偱偼側偄丅傓偟傠丆壔妛巎偲偄偭偨傎偆偑撪梕揑偵惓偟偄丅杮彂偼儈儗僩僗偺僞儗僗偵巒傑傝丆尦慺偺敪尒偐傜廃婜昞偵帄傞憇戝側壔妛巎側偺偱偁傞丅塮夋乽傾儔價傾偺儘儗儞僗乿偑儘儗儞僗偑僆乕僩僶僀帠屘傪婲偙偡僔乕儞偐傜巒傑傞傛偆偵丆杮彂偼僾儘儘乕僌偑儊儞僨儗乕僄僼偑戝敪尒傪偡傞堦曕庤慜偐傜巒傑傞丅偦偟偰僊儕僔儍丆儓乕儘僢僷偲帪娫偲嬻娫偑曄慗偟丆嵞傃儊儞僨儗乕僄僼偺廃婜昞偺敪尒傊偲棳傟崬傫偱偄偔偺偱偁傞丅側偐側偐撉傒偛偨偊偺偁傞杮偩丅
僺乕僞丒傾僩僉儞僗挊丆惸摗棽墰栿丆憗愳彂朳丆俀侽侽係擭侾俀寧俁侾擔弶斉丆ISBN4-15-208612-2 C0040
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧恖娫偵偲偭偰丆拵悅偼昦婥偵側偭偰巰傪傕偨傜偡偍偦傟偑偁傞偐傜丆婋尟場巕偩丅拵悅偑姶愼徢偵滊偭偰庮傟傞偲拵悅墛偵側傝丆乮棯乯偝傜側傞庮挴傪傕偨傜偡丅乮棯乯拵悅偑彫偝偄偲偙偺僾儘僙僗偑恑峴偟傗偡偔側傞偨傔丆尰忬堐帩傛傝弅彫偡傞傎偆偑婋尟偲偄偆堄枴偱丆拵悅墛偼戝偒側拵悅傪堐帩偡傞慖戰埑偲側偭偰偄傞丅偟偨偑偭偰丆婋尟偼偁偭偰傕恑壔偺夁掱偱拵悅傪側偔偡偺偼偒傢傔偰擄偟偄偺偱偁傞丅(P.37) 仧僈儕儗僆偑柧傜偐偵偟偨傛偆偵丆壢妛偺恑曕偵偼丆傆偮偆嬶懱惈偐傜拪徾惈傊偺堏峴偑偲傕側偆丅偦傟偵傛偭偰揔梡斖埻偑峀偔側傞偐傜偩丅堖暈偼偨偔偝傫偁傞偑丆恖娫偺崪奿偼婎杮揑偵堦庬椶偟偐側偄丅偩偐傜崪奿傪抦傟偽丆堖暈傪傑偲偭偨巔傪尒偨応崌傛傝偼傞偐偵懡偔偺偙偲偑棟夝偱偒傞丅(P.116)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂傪奐偔偲丆僈儔僗偺僐僢僾偵擖偭偨儈僀儔壔偟偨僈儕儗僆偺塃庤偺拞巜偺幨恀偑偁傞丅壢妛尋媶傊偺怴偟偄曽岦惈傪偙偺巜偑巜帵偟偨偲偄偆徾挜揑側堄枴傪崬傔偰偄傞偺偩丅杮彂偼乽恑壔乿乽俢俶俙乶乽僄僱儖僊乕乿乽尨巕乿乽塅拡榑乿側偳偝傑偞傑側暘栰傪徯夘偟側偑傜丆壢妛揑偵峫偊傞偙偲偺戝愗偝傪嫵偊偰偔傟傞丅崅峑惗掱搙偺棟夝椡偑偁傟偽丆廫暘棟夝偱偒傞撪梕偱偁傞丅
儕僠儍乕僪丒僪乕僉儞僗挊丆拞搱峃桾懠栿丆憗愳彂朳丆俀侽侽係擭俁寧俁侾擔弶斉丆ISBN4-15-208557-6
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧帺慠搼懣偼栍栚偺帪寁怑恖偱偁傞丅栍栚偱偁傞偲偄偆偺偼丆偦傟偑尒捠偟傪傕偨偢丆寢壥偵偮偄偰偺傕偔傠傒傪傕偨偢丆傔偞偡栚揑偑側偄偐傜偩丅偟偐偟偦傟偱傕丆尰嵼傒傞偙偲偺偱偒傞帺慠搼懣偺寢壥偼丆傑傞偱榬偺偄偄帪寁怑恖偵傛偭偰僨僓僀儞偝傟偨偐偺傛偆側奜娤丆僨僓僀儞偲僾儔儞傪傕偮偐偺傛偆側嶖妎偱丆埑搢揑側報徾傪傢傟傢傟偵梌偊偰偄傞丅(P.46) 仧傢傟傢傟偼丆恖娫惗妶偵偲偭偰栶偵棫偮偱偁傠偆壜擻惈偺斖埻撪偱丆婋尟棪傗尒崬傒傪摢偺側偐偱寁嶼偡傞椡傪恎偵偮偗偰偄傞丅偙傟偼丆偨偲偊偽(棯乯愳傪塲偄偱搉傠偆偲偟偨偲偒偵揗傟偰偟傑偆偲偄偭偨儗儀儖偺婋尟棪偺偙偲偱偁傞丅偙傟傜偺梕擣偱偒傞婋尟偲偄偆偺偼丆悢廫擭偲偄偆傢傟傢傟偺庻柦偵掁傝崌偭偰偄傞丅傕偟丆傢傟傢傟偑侾侽侽枩擭傕惗偒傞偲偄偆偙偲偑惗暔妛揑偵壜擻偱偁傝丆傑偨偦偆偟偨偄偲朷傓側傜丆婋尟棪傪傑偭偨偔暿側傆偆偵昡壙偡傋偒偱偁傞丅偨偲偊偽丆俆侽枩擭娫丆枅擔摴楬傪墶抐偟偰偄傟偽丆偦偺偆偪幵偵鐎偐傟傞偵偒傑偭偰偄傞偩傠偆偐傜丆摴楬偼墶愗傜側偄廗姷傪恎偵偮偗側偔偰偼側傜側偄丅(P.265)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
儕僠儍乕僪丒僪乕僉儞僗偼僌乕儖僪偲摨偠偔丆擄偟偄撪梕傪悢幃傪巊傢偢偵慺恖偵傢偐傝傗偡偔愢柧偡傞偲偄偆弍偵偨偗偰偄傞丅偙傟偼杮恖帺恎偑偦偺撪梕傪廫暘棟夝偟丆偐偮撉幰偺忬嫷傪傛偔抦偭偰偄側偗傟偽偱偒側偄丅憡摉偵摢偺偄偄恖偺傛偆偩丅忋婰偺擇偮栚偺榖偼丆惗柦抋惗偼婏愓偲偄偆恖傕偄傞偑丆偦傟偼偮偄変乆偺庻柦偺傛偆側僗働乕儖偱峫偊傞偐傜偱丆壗廫壄擭偲偄偆婥偺墦偔側傞傛偆側僗働乕儖偱尒傞偲偦偺妋棪傕偐側傝堘偭偰偔傞偲偄偆榖偺拞偱弎傋傜傟偨傕偺偩丅僌乕儖僪偼巰傫偩偑丆僪乕僉儞僗偼僌乕儖僪偲巚憐揑偵偵偼偐側傝嬤偄傕偺偺丆僌乕儖僪偺廆嫵傊偺傗傗廮擃側懳墳傪斸敾偟偰偄傞丅
價儏乕儗儞僩丒傾乕僞儗僀挊丆崅栘棽巌丒嵅桍怣抝栿丆壔妛摨恖丆俀侽侽俇擭俆寧侾戞侾嶞丆ISBN4-7598-1058-7
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俁丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧恖懱偺側偐偱傕丆儗僆僫儖僪偼偲偔偵偁傞婍姱偵尒偣傜傟偨丅(棯)娽媴偱偁傞丅(棯)娽媴偺撪晹偼塼忬偱偁傞偨傔惓妋偵愗抐偡傞偙偲偼擄偟偄丅偦偙偱儗僆僫儖僪偼丆屌備偱棏傪媅屌嵻偵偟偰娽媴傪屌掕偡傞曽朄傪敪柧偟偨乮娽媴傪敀恎偵捑傔偰娵偛偲備偱傞曽朄偱偁傞乯丅(p.229) 仧儗僆僫儖僪偺惗偒條偐傜摼傜傟傞嫵孭傪偁偘傟偽偒傝偑側偄乗乗壗帠傕偁偨傝慜偩偲巚傢偢丆帋偟偰偐傜擺摼偣傛丅壗嵨偵側偭偰傕屓傪杹偔偙偲傪偁偒傜傔偢丆彂暔傪傛偔撉傒丆撉彂偡傞偲偒偵偼斸敾揑側帇揰傪朰傟側偄偙偲偩偦傑偨丆傢偐傜側偄扨岅偑偁傟偽帿彂傪堷偄偰岅渂傪憹傗偦偆偲偡傞巔惃傕朰傟傞側丅儊儌挔傪傕偪曕偒丆栚偵擖偭偨報徾揑側傕偺傪僗働僢僠偣傛丅(P.310)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
儗僆僫儖僪偺嬈愌偼偁傑傝偵傕懡婒偵傢偨傝丆偁傑傝偵傕廏偱偰偄傞偨傔丆昅幰偼乽偄傠偄傠側暘栰偵廏偱偰偄偨侾侽恖埲忋偺恖暔偑丆摨偠亀儗僆僫儖僪丒僟丒償傿儞僠亁偲偄偆柤慜偱妶摦偟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲媈偄偨偔側傞傎偳偱偁傞乿偲彂偄偰偄傞丅偟偐偟丆幚嵺偺儗僆僫儖僪偼巹惗帣偱偁傝丆惓婯偺嫵堢偼庴偗偰偄側偄丅斵偼撈妛偺恖偱偁傞丅弶傔偰帹偵偡傞扨岅偼儊儌偟偰偍偄偰屻偱挷傋偨偲偄偆丅斵偼朿戝側儊儌傪巆偟偨偺偩偑丆偦偺傎偲傫偳偼嶶堩偟偰偟傑偭偨丅
嶰堜惤挊丆島択幮尰戙怴彂1805丆俀侽侽俆擭俋寧俀侽擔戞侾嶞丆ISBN4-06-149805-3
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俈
亂杮暥偐傜亃
|
仧慜揔墳偲偄偆恑壔偺尰徾偑嫵偊偰偔傟傞偺偼丆壗偐偺摿挜偑恑壔偟偨偲偒偵丆偦偺摿挜偑慡柺揑偵奐壴偡傞傑偱偵帪娫嵎偑偁傝偆傞偲偄偆偙偲偩丅偨傑偨傑曐壏岠壥偵栶偩偭偰偄偨塇栄偑丆悢昐枩偁傞偄偼悢愮枩擭屻偵丆乽旘傇乿偲偄偆奐壴傪悑偘偨丅 乽偡偖偵偼栶棫偨側偔偰傕帪傪宱偰奐壴偡傞乿偲偄偆偺偼丆壗偐嫵孭傔偄偰偄傞丅媡偵偄偊偽丆怴偨側恑壔偺壜擻惈偼偦傟傑偱偺忬懺偵戝偒偔嵍塃偝傟傞偲偄偆偙偲偩丅 乽夁嫀偺庺敍偐傜摝傟傞偺偼擄偟偄乿偲偄偆偙偲偱傕偁傞丅(P.59) 仧塸崙偺尋媶僠乕儉偼俀侽侽侾擭丆尵岅擻椡偵忈奞偺偁傞恖偑帩偮堚揱巕偺曄堎傪扵偟弌偟偨丅偙偺曄堎傪帩偮恖偼丆堦斒揑側抦擻偼曄傢傝側偄偑丆敪榖擻椡傗暥朄傪棟夝偡傞擻椡偵忈奞偑弌傞偲偄偆丅乽俥俷倃俹俀乶偲屇偽傟傞偙偺堚揱巕偼丆尵岅擻椡偵寚偐偣側偄傛偆偩丅(P.211)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
乽僫僔儑僫儖丒僕僆僌儔僼傿僢僋乿帍偑崱乽Genographic Project乿偲偄偆僾儘僕僃僋僩傪俬俛俵幮偲採実偟偰恑傔偰偄傞丅偙傟偼悽奅拞偺恖乆偐傜俢俶俙僒儞僾儖傪憲偭偰傕傜偄丆斵傜偺慶愭偑傾僼儕僇傪弌偰偐傜偳偆偄偆宱楬傪宱偰尰嵼偺抧偵偨偳傝偮偄偨偐傪俢俶俙偐傜扵傠偆偲偄偆寁夋偩丅僒儞僾儖偑廤傑傟偽廤傑傞傎偳偦偺宱楬偼傛傝柧妋偵側偭偰偄偔丅侾枩墌傎偳偱俢俶俙夞廂僉僢僩傪峸擖偟丆僒儞僾儖傪憲傞偲偦傟傪暘愅偟偰慶愭偑傗偭偰偒偨宱楬傪嫵偊偰偔傟傞丅巹傕偝偭偦偔嶲壛偟偨丅尰嵼巹偺俢俶俙偼暘愅偺夁掱偵偁傞丅傑傕側偔寢壥偑弌傞偩傠偆丅
杮彂偼偙偆偟偨暘巕惗暔妛偩偗偱側偔丆偙傟傑偱傢偐偭偰偄傞嵟怴偺帒椏傪傕偲偵傢傟傢傟偺慶愭偑偳偙偐傜偒偨偺偐傪嫵偊偰偔傞丅怴彂偱偁傞偑丆摼傞偲偙傠偑懡偄杮偱偁傞丅挊幰偼撉攧怴暦婰幰偱僒僀僄儞僗儔僀僞乕丅
(嶳岥憂挊丆島択幮僽儖乕僶僢僋僗B1538丆俀侽侽俇擭侾侽寧俀侽擔戞侾嶞丆ISBN4-06-257531-0
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俆丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧偨偲偊偽丆栚偺慜偵偁傞僐僢僾傪偮偐傫偱岥偵塣傇偲偡傞丅偙偺偲偒丆栚偺慜偵偁傞僐僢僾偺戝偒偝傪尒偰丆偳偺傛偆偵庤傪怢偽偡偐丆偲偄偆峴堊偑堷偒弌偝傟傞丅偦偟偰僐僢僾偵庤偑撏偄偰怗傟偨偲偒丆偦偺昞柺偺忬懺傗僐僢僾偺峝偝乮敄偄巻傗僾儔僗僠僢僋偺僐僢僾偐側偳乯偵傛偭偰偦傟傪埇傞嫮偝偑僐儞僩儘乕儖偝傟傞丅偦偺偲偒偵廳梫側偺偑怗妎偺忣曬偩偲偄偆偙偲偵側傞丅嵟揔偺嫮偝偱奺巜偺埑傪僐儞僩儘乕儖偟偰僐僢僾傪偮偐傒丆偙傏傟側偄傛偆偵岥傊偲塣傇偺傕丆怗妎偑偁傞偐傜偙偦偱偒傞丅(P.46) 仧儈儈僘傗崺拵偑醳偦偆偵偟偰偄傞偺傪尒偨偙偲偑側偄偑丆嫑傗椉惗椶埲忋偺摦暔偼醳偑傞傛偆偱偁傞丅偦偺婡擻偼丆旂晢偵偮偄偨僲儈傗夅丆婑惗拵側偳偺懚嵼傪抦傜偣丆堷偭憕偄偰偄偪憗偔庢傝嫀傞偙偲偵偁偭偨偺偩傠偆丅偟偐偟丆姶愼徢傪崕暈偟偮偮偁傞尰戙恖偵偼丆旂晢偺婑惗拵偺懚嵼傪抦傞昁梫偼傎偲傫偳側偔側偭偰偟傑偭偨丅栚揑傪幐偭偨偐傜偲偄偭偰丆偄偭偨傫惗傒弌偝傟偰偟傑偭偨姶妎偼丆娙扨偵側偔偡偙偲偼偱偒側偄丅偦偆偩偲偡傞偲醳傒偼丆尰戙偵惗偒傞巹偨偪偵偲偭偰偼偁傑傝堄枴偺側偄丆扨側傞傗偭偐偄側姶妎偩偲峫偊傞偙偲傕偱偒傞丅(P.123)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
儘儃僢僩傪嶌傞忋偱嵟傕擄偟偄偺偼丆傢傟傢傟恖娫偑傆偩傫壗婥側偔偄偲傕娙扨偵傗偭偰偄傞峴堊傪恀帡偡傞偙偲偱偁傞偲偄偆丅僐僢僾偵庤傪怢偽偟偰偦傟傪嵟揔偺嫮偝偱偮偐傒丆岥偵塣傇偲偄偆偙偲偼儘儃僢僩偵偲偭偰偼帄擄偺傢偞偱偁傞丅挊幰偼丆偦偆偟偨峴堊偵偼旂晢姶妎偑廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偺偩偲偄偆丅旂晢偼帇妎傗挳妎側偳偲斾傋偰丆偳偪傜偐偲偄偆偲儅僀僫乕側僀儊乕僕偑偁傞偑丆幚偼旕忢偵廳梫側姶妎偱偁傞偙偲偑杮彂傪撉傫偱傛偔傢偐偭偨丅媣偟傇傝偵僀儞僷僋僩巜悢俀寘偺杮丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏係
亂杮暥偐傜亃
|
仧俆枩擭慜丆傾僼儕僇杒搶晹偺曅嬿偱丆彮悢偺廤抍偑屘嫿傪棧傟傛偆偲弨旛偟偰偄偨丅(棯)傾僼儕僇傪弌敪偟傛偆偲偟偰偄偨廤抍偼丆梒帣傕娷傔偰偨偭偨侾俆侽恖掱搙偩偭偨偼偢偩丅(P.22) 仧俆枩擭慜偵傾僼儕僇傪弌偰偐傜俁枩擭慜傑偱丆偳偙傕偐偟偙傕恖椶偼摨偠傛偆側奜尒偩偭偨丅(棯)係枩俆侽侽侽擭慜偵儓乕儘僢僷偵摓拝偟偨尰惗恖椶傕丆崟偄旂晢側偳傾僼儕僇恖偺摿挜傪曐偭偰偄偨偼偢偩丅(P.123)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
恖椶偺婲尮傪栤偆乽弌傾僼儕僇愢乿偲乽懡抧堟恑壔愢乿偺懳棫偼挿偐偭偨偑丆僎僲儉暘愅偵傛傝孯攝偼乽弌傾僼儕僇愢乿偵忋偑偭偨丅傢偢偐俆枩擭慜偵傾僼儕僇傪弌偨侾俆侽恖傎偳偺廤抍偑丆慡恖椶偺慶愭偱偁傞丅恖椶偺敡偺怓偼丆栄傪幐偭偨摉弶偼惵敀偔丆傗偑偰崟偄旂晢偲側傝丆偦傟偧傟偺抧堟偵揔墳偟偨偝傑偞傑側怓偵曄壔偟偰偄偭偨丅儓乕儘僢僷恖傕嵟弶偼乽崟偐偭偨乿偲偄偆偺傕柺敀偄丅俆枩擭乗乗抧幙妛揑偵傒傟偽傎傫偺嶐擔偺偙偲偩丅旂晢偺怓傪偁傟偙傟偲尵偆偺偼攏幁偘偰偄傞丅傑偨丆堦曽丆偨偭偨俆枩擭偲偄偆抁偄婜娫偵偐偔傕奜尒忋曄壔偡傞恑壔偺懡條惈偵傕嬃偐偝傟傞丅杮彂偵偼乽恖椶偺慶愭偑榖偟偰偄偨曣岅偵偼悽奅嵟屆偺廤抍丆傾僼儕僇偺僒儞懓偺愩懪偪壒偑偁偭偨乿乽恖椶偼擾峩傪奐巒偡傞慜偵掕廧偟偰偄偨乿側偳柺敀偄榖偑偨偔偝傫徯夘偝傟偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侾丏俁
亂杮暥偐傜亃
|
仧偙偺僕儍僗儈儞偺偵偍偄偺庡惉暘偼乽僗僇僩乕儖乿偲偄偆暔幙偱丆偠偮偼暢曋偺偵偍偄偲摨偠惉暘偱偁傞丅暢曋垽岲傪昞傢偡僗僇僩儘偼丆偙偺僗僇僩乕儖偐傜偒偰偄傞丅偳偆偟偰偙偺傛偆側崄傝偺堘偄偑弌傞偺偐偲偄偆偲丆扨偵擹搙偑崅偄偐傜掅偄偐傜偲偄偆偩偗偺堘偄偱偁傞丅擹偄僗僇僩乕儖偼埆廘偩偑丆偦傟傪婓庍偟偰偄偔偲偩傫偩傫僕儍僗儈儞偺偵偍偄偵側偭偰偄偔傢偗偩丅(P.22) 仧僶僯儔偼丆榁壔偵傛偭偰嬌抂偵姶偠傜傟側偔側傞崄傝偱偁傞丅晛捠丆俇侽嵨傪夁偓傟偽懡偔偺恖偵歬妎偺掅壓偑尰傟傞丅僶僯儔偺偵偍偄偼丆偲偔偵偦偺掅壓偑挊偟偄傕偺偲偟偰抦傜傟傞丅乮棯乯擭攜偺恖偱傕擹搙偑敄偄僶僯儔傪姶抦偱偒偨恖偼丆偍偍傓偹僗億乕僣側偳傪庯枴偲偡傞傾僋僥傿僽側恖偑懡偐偭偨偙偲傪巜揈偟偰偍偙偆丅(P.132)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
乽偵偍偄乿偼懠偺姶妎偲斾傋偰摿暿側懚嵼偱偁傞丅傛傝杮擻偵嬤偄偲偄偭偰偄偄偩傠偆丅偟偐偟丆偙偺偵偍偄偺尋媶偑幚偼懠偺帇妎丆挳妎丆枴妎側偳偺尋媶偲斾傋偰偐側傝抶傟偰偄傞偲偄偆丅悢抣壔偑擄偟偄偲偄偆偙偲傕偦偺尨場偵堦偮側偺偱偁傠偆丅傎偲傫偳偺摦暔偼僶僫僫偺偵偍偄傪岲傓偲偐丆將偼僶儔傗僗儈儗偺偵偍偄偼岲傓偑丆僕儍僗儈儞傗僆儗儞僕偺偵偍偄偼寵偆丆偝傜偵偼僸僩偺惛巕偵傕偵偍偄偺僙儞僒乕偑偁傝丆壴偺崄傝偵斀墳偡傞乗乗側偳丆杮彂偼偵偍偄偵娭偡傞偍傕偟傠偄忣曬偑枮嵹偝傟偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俋
亂杮暥偐傜亃
|
仧柌偼惛恄嶖棎偵帡偰偄傞偲偄偆偙偲偱偼側偄丅惛恄嶖棎偦偺傕偺側偺偩丅柌偼惛恄幘姵偺儌僨儖側偳偱偼側偄丅惛恄幘姵偦偺傕偺側偺偩丅偨偩偟丆寬峃側惛恄幘姵側偺偱偁傞丅(P.79) 仧俀侽侽傕偺柌偺曬崘暥傪嵦庢偟丆旐尡幰偵侾暥侾暥丆偦偺愜乆偵姶偠偨忣摦傪敾暿偟偰傕傜偄丆偝傑偞傑側忣摦偺暯嬒敪惗棪傪嶼弌偟偰傒偨丅懪棪庱埵偵婸偄偨偺偼傗偼傝晄埨偱丆俁妱俀暘侾椥偩偭偨丅乮棯乯偡傋偰偺忣摦棪傪挱傔偰傒傞偲丆慡懱偵懳偡傞晄夣側忣摦偺妱崌偼俇俉丏侾僷乕僙儞僩丆偮傑傝慡懱偺嶰暘偺擇埲忋傪愯傔傞丅乽妝偟偄柌傪尒偨偄乿偲朷傫偱傕丆俁夞偵侾夞偟偐尒傞偙偲偼偱偒側偄丅(P.238)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
壗傜偐偺棟桼偱丆帺暘偺儊乕儖傾僪儗僗傪巻偵彂偙偆偲偡傞偺偩偑丆僀儞僋偑楻傟偨傝丆儁儞偑巻偵傂偭偐偐偭偨傝偟偰丆壗搙彂偙偆偲幐攕偡傞丅巻傪曄偊偨傝丆儁儞傪曄偊偨傝偟偰傕偩傔偩乗乗偙傟偼巹偑嶐栭尒偨柌偱偁傞丅偲偵偐偔丆朰傟傕偺傪偟偨傝丆戝愗側傕偺傪暣幐偟偨傝偲丆忢偵乽徟偭偰偄傞乿柌傪尒傞偙偲偑丆巹偵偼懡偄丅
昅幰偼丆柌偼惛恄嶖棎偦偺傕偺偱偁傞偲偄偆丅栻暔拞撆姵幰偑栂憐傪尒偰偄傞偲偒偺擼偺忬懺偲丆変乆偑柌傪尒偰偄傞偲偒偺擼偺忬懺偼偦偭偔傝傜偟偄丅変乆偼奆丆悋柊帪偵偼惛恄堎忢幰偲側偭偰偄傞偺偩丅寬忢幰偼枅挬丆妎惲偟偰尰幚偵栠傞偑丆擼偵堎忢偺偁傞恖偼丆偦偺傑傑柌偲尰幚偑暲峴偟偰偄偔偺偱偁傞丅
偱偼側偤柌傪尒傞偺偐乗乗巆擮側偑傜偼偭偒傝偲傢偐偭偰偄側偄丅柌傪尒側偑傜妎惲帪偺偲偒偺懳墳傪僔儈儏儗乕僔儑儞偟偰偄傞偲偄偆愢傪徯夘偟偰偄傞偑丆巹偵偼擺摼偱偒側偄丅偍偭偪傚偙偪傚偄偺巹偑尰幚悽奅偱崲傜側偄傛偆偵丆枅斢柌偺拞偱乽徟傜偣偰乿僔儈儏儗乕僔儑儞偟偰偔傟偰偄傞偲偄偆偺側傜丆梋寁側屼悽榖偩丅乽柧濔柌乿偺愢柧偑偮偐側偄偲昅幰偼彂偄偰偄傞偑丆偱偒傟偽柌偼忢偵妝偟偄傕偺傪尒偨偄丅媣乆偺偍傕偟傠偄杮偱偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俁
亂杮暥偐傜亃
|
仧乽僸僩偲僠儞僷儞僕乕偺堚揱巕偑偦傟傎偳帡偰偄傞側傜丆恖娫偺抝惈偑僠儞僷儞僕乕偺帗傪擠怭偝偣傞偙偲傕壜擻側傫偠傖側偄偱偡偐丠丂儘僶偲僂儅傪偐偗崌傢偣傞傒偨偄偵乿 妛惗偺慱偄偳偍傝丆徫偄惡偑抝惈傪拞怱偵婲偙偭偨丆偲偼偄偊丆偙傟偼杮婥偺夞摎傪梫偡傞塻偄幙栤偩偲巚偭偨偺偱丆傢偨偟偼偙偆摎偊偨丅 乽僠儞僷儞僕乕偲僸僩偼愼怓懱偺柺偱旕忢偵帡捠偭偰偄傞偺偱丆壢妛幰偺戝晹暘偑丆偙偺擇庬岎攝偵傛傞巕偳傕偼惗懚壜擻偩偲峫偊偰偄傑偡乿(P.119) 仧偙偙偱傢偨偟偑乮擠怭拞斀懳榑幰偵乯堎媍傪彞偊偨偄偺偼丆偦偆偄偆乮泱偺)嵃傪慜採偲偡傞恄妛偱偼側偄丅傢偨偟偼扨偵丆偨傑偨傑堎側傞堄尒傪帩偭偰偄傞偵偡偓側偄丅堄媊傪彞偊傞偺偼傓偟傠丆帺暘偨偪偺尒夝偑怣嬄偵婎慴傪抲偄偰偄傞偙偲傪塀偟偰丆旕廆嫵揑棫応偵懳偡傞桪埵傪妋曐偡傞偨傔偵壢妛傪晄摉偵棙梡偡傞丆偦偺媆嵩揑側懺搙偩丅(P.150)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
僶僀僆僥僋僲儘僕乕偑偳傫偳傫恑曕偟偰偄傞尰嵼丆惗柦偵娭偡傞條乆側椣棟揑栤戣傪採婲偡傞杮偱偁傞丅椺偊偽丆懱偺忋晹偼乽擇恖乿偩偑丆壓敿恎偼乽堦恖乿偱偁傞婏宍帣偵暘棧庤弍傪巤偡応崌丆忋晹傪乽偳偪傜乿偵偡傞偐扤偑偳偺傛偆偵寛傔傞偺偐丆側偳偲偄偭偨嬶懱椺偑幚椺傪徯夘偟偮偮栤戣採婲偝傟傞丅傑偨丆帺暘偺棏巕偲僠儞僷儞僕乕偺惛巕傪庴惛偝偣偨偁偲丆帺暘偺巕媨偱堢偮偐傪娤嶡偟偰懖嬈榑暥偵偟偨偄偲怽偟弌偰偒偨彈巕戝惗偺僔儑僢僉儞僌側榖側偳傕徯夘偝傟偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俁
亂杮暥偐傜亃
|
仧偁傞偲偒儅僀働儖丒僼傽儔僨乕偑摨偠幙栤傪庴偗偨丅壢妛偼偄偭偨偄壗偵傗偔偩偭偰偄傞偺偐丆偲丅僼傽儔僨乕偼偙偆幙栤偟偐偊偟偨丅乽偱偼丆惗傑傟偨偽偐傝偺愒傫朧偼偄偭偨偄壗偵栶偩偭偰偄傑偡偐乿丅(P.21) 仧摑寁妛幰偼丆婾梲惈偺岆昑乮娫堘偭偨峬掕乯偲婾堿惈偺岆昑乮娫堘偭偨斲掕乯傪嬫暿偟偰埖偭偰偄傞丅偙傟偼丆偦傟偧傟乬僞僀僾侾偺岆傝乭丆乬僞僀僾俀偺岆傝乭偲傕屇偽傟傞丅僞僀僾俀偺岆傝丆偮傑傝婾堿惈偼丆幚嵺偼僷僞乕儞偑懚嵼偡傞偺偵丆偦傟傪専弌偱偒側偄応崌偺偙偲偱偁傞丅僞僀僾侾偺岆傝丆偮傑傝婾梲惈偼丆偦偺媡丆偡側傢偪丆幚嵺偵偼儔儞僟儉側尰徾埲奜偺側偵傕偺偱傕側偄偺偵丆壗傜偐偺僷僞乕儞偑偁傞偲寢榑偯偗偰偟傑偆偙偲偱偁傞丅(P.230)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
僯儏乕僩儞偑僾儕僘儉傪梡偄偰丆敀岝傪俈怓偺夝懱偟偨偲偒丆帊恖僉乕僣偼乽擑偺帩偮帊忣傪攋夡偟偨乿偲旕擄偟偨丅壢妛傪暥妛偺懳嬌偵偁傞傕偲偺峫偊偨傝丆媡偵壢妛偵幚棙揑側傕偺偺傒傪捛偄媮傔傞偙偲偼娫堘偄偱偁傞偲丆挊幰僪乕僉儞僗偼庡挘偡傞丅尨戣偼 "UNWEAVING THE RAINBOW" 丆偡側傢偪丆乽擑傪傎偳偔偙偲乿丅偩偄傇慜偵搑拞傑偱撉傫偱偍偄偨傕偺偩偑丆乽恄偼栂憐偱偁傞乿傪撉傫偩屻丆嵞傃庢傝弌偟偰撉傒廔偊偨丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧暷崙彫帣壢妛夛偼丆乽庒偄僒僢僇乕慖庤偑僿僨傿儞僌偺斀暅楙廗傪偡傞偙偲偵偮偄偰丆亀彮側偗傟偽彮側偄傎偳傛偄亁偲偄偆偺偑巹偨偪偺尒夝偱偁傞乿偲寈崘偟偨丅彫帣壢堛偨偪偼丆僒僢僇乕偺帋崌拞偵僿僨傿儞僌僾儗乕傛傝傕丆僼僅儚乕僪傗僨傿僼僃儞僗偺慖庤偨偪偑傗傞傛偆側丆摢傪儃乕儖偵偔傝偐偊偟懪偪偮偗傞僿僨傿儞僌偺楙廗偺傎偆傪怱攝偟偰偄傞丅摨偠傛偆側擭楊偲娐嫬偺恖偨偪傪廤傔丆僒僢僇乕傪偟偰偄偨惉恖偲偟偰偄側偐偭偨惉恖傪斾妑偟偨尋媶偑丆僲儖僂僃乕偲暷崙偱偦傟偧傟峴傢傟偨丅僲儖僂僃乕偺尋媶偱偼丆僒僢僇乕傪偟偰偄偨惉恖侾侽俇恖偺偆偪丆俉侾僷乕僙儞僩偵拲堄椡丆廤拞椡丆婰壇椡丆敾抐椡偵偍偄偰寉搙偐傜廳搙偵傢偨傞掅壓偑擣傔傜傟偨丅暷崙偺尋媶偱傕丆拲堄椡偲廤拞椡偺寚娮偑孮傪敳偄偰懡偔尒傜傟偨偺偼丆僿僨傿儞僌傪傕偭偲傕懡偔楙廗偟偨恖偨偪偩偭偨偲偄偆丅乮P.51)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
摢傪僐僣儞偲懪偭偨偩偗偱丆悢昐枩偺擼嵶朎偑巰柵偡傞丅偦傫側榖傪暦偄偨偙偲偑偁傞丅幚嵺偼偳傟傎偳偐偼傢偐傜側偄偑丆昅幰偺榖偱偼丆変乆偺擼傪庢傝姫偔娐嫬偼偁傑傝偄偄忬懺偱偼側偄傜偟偄丅擼偼擼悜塼偺拞偵晜梀偟偰偄傞偑丆摢奧崪偼撪晹偐傜尒傞偲偐側傝僑僣僑僣偟偰偄偰丆塻偄撍婲傕偁傞偺偱丆僿僨傿儞僌側偳傪偡傞偲丆擼偑偦傟傜偵傇偮偐偭偰偐側傝懝彎傪庴偗傞偲偄偆丅昅幰偼俽俹俤俠俿嶣塭偵傛傞擼夋憸傪帯椕偵惗偐偣傞擼壢妛幰偱偁傝惛恄壢堛偱傕偁傞丅偨偩丆姫枛偱擼偵椙偄僒僾儕儊儞僩偲偟偰乽憤崌價僞儈儞嵻丆價僞儈儞俠丆嫑桘丆傾僙僠儖俴僇儖僯僠儞丆兛儕億巁丆僐僄儞僓僀儉俻侾侽乿側偳傪姪傔偰偄傞偑丆偙偺傊傫偼偄傑堦偮怣梡偟偐偹傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃揱婰偺偨傔昡壙晄擻
亂杮暥偐傜亃
|
仧僴儞僞乕偼摉帪妋棫偝傟偰偄偨傗傝曽偡傋偰傪傑偢偼媈偭偰偐偐傝丆傛傝傛偄曽朄偺壖愢傪棫偰丆偦偺壖愢偑惓偟偄偐偳偆偐傪徻嵶側娤嶡偲挷嵏丆幚尡傪偲偍偟偰妋擣偟偨丅帺愢傪恖娫偵帋偡慜偵傑偢摦暔偱幚尡偡傞傛偆偵偟丆帺暘偑庤弍幒偱傎偳偙偟偨張抲偵偮偄偰偼丆姵幰偺偦偺屻偺宱夁偺娤嶡傪寚偐偝側偐偭偨丅姵幰偑巰傫偱偟傑偭偨偲偒偼丆専巰夝朥傪偟偰尨場傪捛媮偟偨丅偙偆偟偰妛傫偩偙偲傪傕偲偵丆傗傝曽傪彮偟偢偮曄偊偰偼寢壥傪妋偐傔丆偝傜偵尋媶偡傞偲偄偆丆擇昐擭屻偺尰戙偵旵揋偡傞壢妛尋媶偺巔惃偱椪傫偩丅掜巕偨偪偵傕偦偺尨懃傪扏偒偙傫偩丅僴儞僞乕偺垽掜巕偺堦恖偵丆偺偪偵揤慠摋儚僋僠儞傪奐敪偟偨僄僪儚乕僪丒僕僃儞僫乕偑偄傞丅乮P.21)
|
亂巹偺僐儊儞僩亃
僕儑儞丒僴儞僞乕偼丆拫偼孼僂傿儕傾儉傪庤揱偭偰夝朥嫵幒偱尒帠側昗杮傪嶌傝丆栭偼曟揇朹側偳偄偐偑傢偟偄儖乕僩偐傜巰懱傪庤偵擖傟傞偙偲偵庤榬傪敪婗偟偨丅壗愮懱偲偄偆朙晉側夝朥宱尡傪婎偵丆傗偑偰斵偼帪戙傪愭傫偠傞奜壢堛偲側偭偰偄偔丅尨戣偼乽The Knife Man乿丅朷傫偩巰懱偼昁偢庤偵擖傟傞偲偄偆抝丅擠晈偺懱偐傜傑偝偵抋惗悺慜偺戀帣偺夝朥恾偼寍弍揑側傑偱偵旤偟偄乮偨偩偟捈愙偙傟傪昤偄偨偺偼夋壠乯丅乽僪儕僩儖愭惗乿傗乽僕僉儖攷巑偲僴僀僪巵乿偺儌僨儖偵側偭偨抝偺婏憐揤奜側恖惗偱偁傞丅杻悓偺側偄摉帪偺奜壢偺條巕傗丆撪壢堛傛傝偢偭偲掅偔尒傜傟偰偄偨奜壢堛偺幮夛揑抧埵側偳傕昤偐傟偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏俁
亂杮暥偐傜亃
| 仧廆嫵忋偺怣擮偼丆偦傟偑廆嫵忋偺怣擮偱偁傞偲偄偆偩偗偺棟桼偱懜廳偝傟側偗傟偽側傜側偄偲偄偆尨懃傪庴偗擖傟偰偄傞偐偓傝丆巹偨偪偼僆僒儅丒價儞丒儔僨傿儞傗帺敋僥儘斊偑書偄偰偄傞怣擮傪懜廳偟側偄傢偗偵偼偄偐側偄丅偱偼偳偆偡傟偽偄偄偺偐丆偲偄偊偽丆偙偆偟偰椡愢偡傞昁梫傕側偄傎偳帺柧側偙偲偩偑丆廆嫵忋偺怣擮偲偄偆傕偺傪僼儕乕僷僗偱懜廳偡傞偲偄偆尨懃傪曻婞偡傞偙偱偁傞丅偦傟偙偦偑丆巹偑傕偰傞偐偓傝偺椡傪偮偔偟偰丆偄傢備傞乽夁寖庡媊揑側乿怣嬄偵懳偟偰偩偗偱側偔丆怣嬄偦偺傕偺偵懳偟偰恖乆偵寈崘傪敪偡傞棟桼偺堦偮側偺偱偁傞丅乮P.448) |
亂巹偺僐儊儞僩亃
僞僀僩儖偐傜偟偰夁寖偩丅偟偐偟丆尨戣偼 "The God Delusion"偩偐傜娫堘偄側偄丅僪乕僉儞僗傪偟偰偙偙傑偱尵傢偟傔傞傕偺偼壗偐丠
廆嫵偑偐傜傓偲偡傋偰偑僼儕乕僷僗偵側傞乗乗僪乕僉儞僗偼偦偆偟偨尰忬偵寈崘傪敪偡傞丅乽巹偼柍恄榑幰偱偁傞乿偲岞尵偡傞偙偲偑傾儊儕僇幮夛偱偼溳傜傟傞乗乗僪乕僉儞僗偼偦傟偼偍偐偟偔側偄偐偲寈崘傪敪偡傞丅尨棟庡媊幰偑墶峴偡傞僀僗儔儉傗傾儊儕僇傪尒傞偲偒丆帺敋僥儘偑懕敪偡傞尰嵼丆峫偊偝偣傜傟傞杮偱偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俁丏俀
亂杮暥偐傜亃
| 仧擏懱偲偄偆傕偺偵偮偄偰丆巹偨偪偼帺傜偺姶妎偲偟偰丆奜奅偲妘偰傜傟偨屄暔偲偟偰偺幚懱偑偁傞傛偆偵姶偠偰偄傞丅偟偐偟丆暘巕偺儗儀儖偱偼偦偺幚姶偼傑偭偨偔扴曐偝傟偰偄側偄丅巹偨偪惗柦懱偼丆偨傑偨傑偦偙偵枾搙偑崅傑偭偰偄傞暘巕偺備傞偄乽梽傒乿偱偟偐側偄丅偟偐傕丆偦傟偼崅懍偱擖傟懼傢偭偰偄傞丅偙偺棳傟帺懱偑乽惗偒偰偄傞乿偲偄偆偙偲偱偁傝丆忢偵暘巕傪奜晹偐傜梌偊側偄偲丆弌偰峴偔暘巕偲偺廂巟偑崌傢側偔側傞丅(P.163) |
亂巹偺僐儊儞僩亃
乽僥僙僂僗偺慏乿偲偄偆揘妛揑栤戣偑偁傞丅僊儕僔儍恄榖偵弌偰偔傞僥僙僂僗偼僋儗僞搰傊峴偭偰夦暔儈僲僞僂儖僗傪戅帯偡傞丅摉帪偺慏偼夡傟傗偡偔丆峲奀偺搑拞偱夡傟偨晹暘傪怴偟偄傕偺偵岎姺偟側偑傜恑傓偺偩偑丆僥僙僂僗偺慏偺応崌丆夦暔戅帯傪廔偊偰僊儕僔儍偺峘偵婣偭偨偲偒偵偼丆慏偺偡傋偰偺晹昳偑怴偟偄傕偺偵岎姺偝傟偰偄偨丅偝偰丆偙偺僥僙僂僗偺慏偼丆弌斂帪偺慏偲乽摨偠傕偺乿偩傠偆偐丠
変乆偺懱傕愨偊偢暘巕扨埵偱廋暅偑孞傝曉偝傟丆悢擭傕偡傟偽偡傋偰偺嵶朎偼怴偟偄傕偺偵擖傟懼傢傞丅偦傟偱偼崱偺巹偼悢擭慜偺巹偲乽摨偠傕偺乿側偺偩傠偆偐丠
杮彂偼丆儚僩僜儞偲僋儕僢僋偺乽僇儞僯儞僌蓚鎮閮m乕儀儖徿妉摼傗丆栰岥塸悽偺尰戙偺昡壙丆尋媶忋偺偡偝傑偠偄傑偱偺嫞憟側偳嫽枴怺偄榖偑惙傝偩偔偝傫偱偁傞丅忋婰偺乽巹偨偪惗柦懱偼丆崅懍偱擖傟懼傢偭偰偄傞丆備傞偄亀梽傒亁偱偟偐側偄乿偲偄偆巜揈傕偍傕偟傠偄丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏俉
亂杮暥偐傜亃
|
仧偳傫側偵寜暼徢偱傕丆偄偔傜昿斏偵偐傜偩傪愻偄棳偟偰偄偰傕丆恖娫偺旂晢忋偵偼嵶嬠偑廧傒偮偄偰偄偰丆柍嬠忬懺偱偄傞偙偲偼晄壜擻偱偁傞丅傢傟傢傟偵偱偒傞偺偼愻偭偨傝丆峈嬠嵻傪梡偄傞側偳偟偰丆偣偄偤偄偦偺斏怋傪梷偊傞偙偲偩偗偺傛偆偩丅(P.40)
仧阬崄偑偙傫側偵傕偰偼傗偝傟偰偒偨偺偼丆傾儞僪儘僗僥僲乕儖偺僼僃儘儌儞偲偟偰偺椡偑庛傑傝丆杮棃偺惈僼僃儘儌儞偲偟偰偺栶妱傪壥偨偝側偔側偭偨傕偺偺丆偦偺擋偄偵懳偡傞岲傒偲擼偵梌偊傞嶌梡偩偗偑巆傝丆傾儞僪儘僗僥僲乕儖偵帡偨擋偄傪偄偮偟偐岲傓傛偆偵側偭偨偨傔偲偼峫偊傜傟側偄偩傠偆偐丅尵傢偽丆僼僃儘儌儞偺戙梡昳偲偟偰偺儉僗僋偱偁傝丆儉僗僋偵傾儞僪儘僗僥僲乕儖偑帡偰偄傞偺偱偼側偔丆傾儞僪儘僗僥僲乕儖偵儉僗僋偑帡偰偄偨偐傜偙偦偺榖偱偁傞丅(P.136) |
亂巹偺僐儊儞僩亃
彈惈偺娋偵懡偔娷傑傟傞傾儞僪儘僗僥僲乕儖偼庛偄儉僗僋廘傪帩偭偰偄傞丅堦曽丆抝惈偺娋偵偼傾儞僪儘僗僥儘儞偑懡偔娷傑傟傞丅傾儞僪儘僗僥僲乕儖偼抝惈偵偼捔惷丆彈惈偵偼妎惲嶌梡偑偁傝丆媡偵傾儞僨儘僗僥儘儞偼抝惈偵偼妎惲丆彈惈偵偼捔惷嶌梡偑偁傞丅傕偭偲傕彈惈偵偼,抝惈偺擋偄偺傾儞僨儘僗僥儘儞偑丆乽晄夣側偵偍偄乿偲姶偠傜傟傞偙偲偑懡偄傜偟偄丅擋偄偲偄偆偺偼丆擹搙傗懠偺擋偄偲偺暋崌嶌梡偱戝偒偔報徾偑曄傢傞傕偺傜偟偄丅椺偊偽丆杮彂偺拞偱(P.96)丆偦偺傑傑偱偼摦暔墍偺烞偺拞偺傛偆側暢曋偵帡偨擋偄偺乽僔儀僢僩丒傾僽僜儕儏乕僩乿偲偄偆揤慠崄椏傕丆偦傟傪婓庍偟偰偄偔偲丆壴偺擋偄偵帡偨朏崄傪帩偮傛偆偵側傞偲偄偆偙偲偑徯夘偝傟偰偄傞丅偦傕偦傕丆崱偺傛偆偵悈愻偑晛媦偡傞埲慜丆偡側傢偪徍榓偺帪戙偱偼廃埻偼傕偭偲暢擜偺廘偄偵枮偪偰偄偨偟丆偦傟偑晛捠偱偁偭偨丅僩僀儗偼媯傒庢傝幃偱丆梡曋拞偼傾儞儌僯傾廘偺巋寖偱栚偑捝偔側偭偨偙偲傪巚偄弌偡丅偦偟偰崱傗僨僆僪儔儞僩偺帪戙丅擋偄偼暥壔偲嫟偵偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏俁
亂杮暥偐傜亃
|
仧偁傞崄傝傪偮偗偰偄傞彈惈傪丆偦偺崄傝偩偗傪棅傝偵歬妎偱捛偄側偑傜丆扵偟摉偰傞偙偲偑偱偒傞偩傠偆偐丅僷乕僸儏乕儅乕偵偲偭偰偼丆摎偊偼僀僄僗偱偁傞丅旲愭偵拲堄傪廤拞偟偰傒傞偲丆偳偺曽岦偐傜崄傝偑偔傞偐偑暘偐傞丅壗夞偐孞傝曉偟偰偄傞偆偪偵丆曽岦偑妋偐偵側偭偰偔傞丅僀僰偼丆僸僩偺昐枩乣侾愮枩攞傕晀姶偱丆偄偲傕娙扨偵傗偭偰偄傞偙偲側偺偩偑丆巹偨偪僷乕僸儏乕儅乕傕丆孭楙偵傛偭偰丆晛捠偺恖偺昐攞偔傜偄偼偐偓暘偗傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞丅(P.63)
仧崄悈傗崄椏傪堄枴偡傞塸岅偺 perfume 偼丆儔僥儞岅偺 per fumum乮墝傪捠偟偰乯傪岅尮偲偟偰偄傞丅崄傝偼丆恄偵愙嬤偡傞庤抜偲愢柧偝傟偰偒偨丅崄傝偑恖偺怱偵嶌梡偡傞岠壥傪峫偊傞偲丆屆戙崙壠偺惉棫偺偲偒丆惌帯乮傑偮傝偛偲乯傪峴側偆幰偼丆崄墝偵傛偭偰嵳抎偺慜偵傂傟暁偡恖乆偺怱傪榓傜偘丆崙壠摑堦傪梕堈偵偡傞偺偵栶棫偰偨丅崄椏偼惌帯偺彫摴嬶偩偭偨偲巹偼巚偆丅(P.86) |
亂巹偺僐儊儞僩亃
傕偲傕偲乽擋偄乿偵娭怱偑偁偭偨偑丆愭擔娤偨塮夋亀僷僸儏乕儉乗乗偁傞恖嶦偟偺暔岅亁偱偝傜偵娭怱偑崅傑偭偨乮傕偭偲傕丆偙偺塮夋帺懱偼扨側傞僼傿僋僔儑儞乯丅擋偄偵娭學偡傞偺偼丆擼偺拞偱傕嵟傕屆偄晹埵丅偦傟偩偗杮擻偵嬤偄偲偄偆偙偲偐丅擔杮偵傕乽崄摴乿偺揱摑偑偁偭偨偺偩偐傜丆傕偭偲擋偄偵娭怱傪帩偭偰傕偄偄偺偱偼側偄偐丅乽僸僩偺歬妎偼戅壔偟偰丆撦姶偵側偭偰偄傞偲巚偆恖偑偄傞偐傕偟傟側偄偑丆偦偆偱偼側偄丅僸僩偼帇妎偵棅傝偡偓傞偨傔偵歬妎偺巊偄曽傪偍傠偦偐偵偟偰偄偰丆偦偺擻椡傪廫暘偵堷偒弌偟偰偄側偄偺偱偁傞乿偲杮彂偵傕彂偐傟偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃係丏侽
亂杮暥偐傜亃
|
仧偙傟傑偱懕偗偰偒偨儀僢僪忋埨惷偺尋媶栚揑偼乽廳椡偺塭嬁傪愃乮偟傝偧乯偗偨忬懺偵偍偄偰丆塅拡旘峴巑偲儀僢僪忋埨惷偺寬峃側儃儔儞僥傿傾偼丆側偤埲忋偵憗偔嵨傪偲偭偰偟傑偆偺偐乿傪夝柧偡傞偙偲偱偟偨丅偟偐偟丆巹偼偙偺偲偒丆巹偑摎偊偨偄偲巚偭偰偄傞栤戣偼乽崅楊幰偺擏懱揑側曄壔偼丆偼偨偟偰擭楊傪廳偹偨寢壥偩偗側偺偩傠偆偐丅廳椡偲壗偐娭學偑偁傞偺偱偼側偄偩傠偆偐乿偱偁傞偙偲偵丆婥偯偒傑偟偨丅(P.26)
仧嵨傪偲傟偽壠懓傗桭恖偨偪傗恎偺夞傝偵偄傞恖偨偪偐傜偼丆備偭偔傝夁偛偡傛偆偵姪傔傜傟傞傛偆偵側傝傑偡丅偦偟偰丆偁傞擭楊偵払偡傞偲巇帠傪帿傔偰丆恎懱傪巊傢側偔側偭偰偟傑偄丆偦偺寢壥丆廳椡偺壎宐傪偁傑傝庴偗側偄惗妶偵擖偭偰偟傑偄傑偡丅偦偆偱偡丅廳椡偼偄偮傕偦偙偵偁傞偵傕偐偐傢傜偢丆偦傟傪妶梡偟側偄偐偓傝丆寬峃偵偲偭偰堄枴偑側偄偽偐傝偱側偔丆傓偟傠埆幰偵側偭偰偟傑偆偺偱偡丅尰戙偺惗妶廗姷偵恎懱傪姷傜偟偰偟傑偭偨恖偼丆廳椡偺壎宐傪旔偗偰惗妶偟偰偄傞傛偆側傕偺偱偡丅(P.27) |
亂巹偺僐儊儞僩亃
昅幰偼尦俶俙俽俙儔僀僼僒僀僄儞僗晹栧偺愑擟幰丅塅拡偐傜婣娨偡傞乮柍廳椡偐傜廳椡偺偁傞応強偵婣娨偡傞乯塅拡旘峴巑偺條巕偑丆榁壔偺徢忬偲偦偭偔傝偱偁傞偙偲偵婥偯偄偨挊幰偑丆廳椡偲榁壔偺娭學傪夝柧偟偰偄偔暔岅偱偁傞丅変乆抧媴忋偺惗暔偼偙偺抧媴偺廳椡偺拞偱恑壔偟偰偒偨偺偱偁傝丆廳椡偑変乆偺寬峃偵懡戝側塭嬁傪媦傏偟偰偄傞偙偲偼妋偐偩丅抧媴忋偱偼柍廳椡忬懺偼宱尡偟偵偔偄偑丆偟偐偟偦傟偵嬤偄忬懺偼嶌傟傞丅偦傟偼儀僢僪偵墶偵側傞偙偲偱偁傞丅榁恖偵偲偭偰怮偨偒傝偵側傞偙偲偑偄偐偵椙偔側偄偙偲偐偑偙偺杮傪撉傔偽傢偐傞丅寬峃偵偮偄偰怴偨側帇揰偐傜峫偊傞偙偲偑偱偒傞杮偱偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾係丏俁
亂杮暥偐傜亃
| 仧暘楐昦偁傞偄偼暘楐昦宆恖奿偺姵幰偺儕僗僩偼偒傢傔偰挿偄丅桳柤側柤慜傪彮悢偁偘傞偩偗偱偦偺撪梕偑悇應偱偒傞偩傠偆丅壒妝壠偱偼僪僯僛僢僥傿丆僔儏乕儅儞丆儀乕僩乕儀儞丆儀儖儕僆乕僘丆僔儏乕儀儖僩丆儚僌僫乕丅嶌壠偱偼儃乕僪儗乕儖丆僗僩儕儞僪儀儕丆僗僂傿僼僩丆僔僃儕乕丆僿儖僟乕儕儞丆僐儞僩丆億乕丆僕儑僀僗丆僑乕僑儕丆僴僀僱丆僥僯僜儞丆僇僼僇丆僾儖乕僗僩丆僴僋僗儗僀丅揘妛幰偱偼丆僇儞僩丆僂僀僩僎儞僗僞僀儞丆僷僗僇儖丅壢妛幰丆敪柧壠偱偼丆傾僀儞僔儏僞僀儞丆僼傽儔僨僀丆僐儁儖僯僋僗丆儕儞僱丆傾儞儁乕儖丆僄僕僜儞丆儊儞僨儖丆僟乕僂傿儞丅恖椶偵懳偟傕偭偲傕崅搙側峷專傪偟偨偵傕偐偐傢傜偢暘楐昦宆恖奿傪敪尰偟偨恖乆偺偛偔堦晹偱偁傞丅(P.182) |
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼乽惛恄暘楐昦乿偑乽摑崌幐挷徢乿偵曄峏偡傞捈慜偵弌斉偝傟偨傕偺偱偁傞丅摑崌幐挷徢偼俁乣係屄偺堚揱巕偑娭學偡傞昦婥偱偁傝丆偡傋偰偑偦傠偭偨応崌偱傕敪徢偼擇暘偺堦偱偁傞丅媡偵丆偄偔偮偐偺堚揱巕傪帩偪丆恖奿揑偵摑崌幐挷徢揑側恖暔偑偐偊偭偰憂憿揑側嬈愌傪巆偟偰偄傞丅偟偐傕偙偺昦婥偼抧堟傗恖庬偵慡偔曃傝偑側偔丆偳偺崙丆偳偺恖庬偱偁偭偰傕偦偺敪惗棪偼侾亾庛偱偁傞丅偙偺偙偲偐傜丆昅幰偼侾係枩擭慜偐傜俉枩擭慜偵変乆偺慶愭偑摑崌幐挷徢傪妉摼偟丆偦偺偙偲偑怴恖椶抋惗傪彽偄偨偺偱偼側偄偐偲悇應偡傞丅旕忢偵旕忢偵柺敀偄愢偱偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃係丏俆
亂杮暥偐傜亃
| 仧侾俈俋俀擭俇寧乗乗僼儔儞僗墹惌偺枛婜丆乽妚柦偵傛傞暯摍乿偲偄偆怴偟偄婓朷傪拞怱偵悽奅偑夞傝偼偠傔偨偙傠乗乗擇恖偺揤暥妛幰偑丆搑曽傕側偄巊柦傪懷傃偰惓斀懳偺曽岦傊偲椃棫偭偨丅乮棯乯斵傜偺巊柦偼悽奅偺戝偒偝傪應傞偙偲乮棯乯偱偁偭偨丅乮棯乯偦偟偰斵傜偺巇帠偼丆偙偺怴偟偄扨埵丆乽儊乕僩儖乿傪丆杒嬌偐傜愒摴傑偱偺嫍棧偺堦愮枩暘偺堦偺挿偝偲偟偰寛掕偡傞偙偲偱偁偭偨丅 |
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偼丆侾儊乕僩儖偡側傢偪抧媴偺巕屵慄偺係暘偺侾偺侾侽侽侽枩暘偺侾傪應傞傋偔惗奤傪偐偗偨擇恖偺抝偺暔岅偱偁傞丅偨偩丆偦偺帪婜偑埆偐偭偨丅弌敪偟偨偲偒墹惌偩偭偨偑丆搑拞偱妚柦偑偍偒偰偟傑偄丆斵傜偺屻傠弬偑側偔側偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅偨偩丆榖偑忕枱偡偓偰搑拞偱朞偒偰偔傞偐傕丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏係
亂杮暥偐傜亃
仧俀侽侽侾擭偵僗僩儔僗僽乕儖戝妛偺僄僪僁僶乕儖丒儊乕儖偑丆僜儖儂儞僰戝妛偱偺攷巑榑暥傪傕偲偵彂偄偨杮偺拞偱丆偦傟傑偱尋媶偝傟偰偙側偐偭偨悢懡偔偺堦師帒椏傪暘愅偟偨丅斵偺尋媶偐傜晜偐傃忋偑偭偨慡懱憸偵傛偭偰丆僨僇儖僩偑錕錘廫帤抍偺巚憐偵怺偔塭嬁傪庴偗偰偄偨偙偲偼傎傏媈偄傛偆偑側偔側偭偨丅(P.108)
仧側偤僨僇儖僩偼丆戝惃偺恖偑婹偊傗愴偄偱巰傫偱偄偔丆偙偺傛偆側嫲傠偟偄愴憟偺応偵傗偭偰偒偨偺偩傠偆偐丠乮棯乯僨僇儖僩偼丆忢偵孯戉慻怐傗孯帠巤愝偵枺椆偝傟偰偄偨丅乮棯乯僨僇儖僩偼嬻拞偱偺抏娵偺抏摴偵嫽枴傪帩偪丆廳椡壓偱偺暔懱偺棊壓傪尋媶偟偰偄偨丅乮棯乯僨僇儖僩偼恖惗偵娭偟偰偱偒傞尷傝偺偙偲傪妛傃偨偄偲巚偭偰偍傝丆儔丒儘僔僃儖偺曪埻愴偼偦偆偟偨妛廗偺堦娐偩偭偨偺偩丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
尨戣偼"Descartes' Secret Notebook"丅巹偼杮彂偺僞僀僩儖傪尒偰丆椺偺乽僟償傿儞僠側傫偲偐乿偺椶偺乽僩儞僨儌杮乿偺堦庬偲巚偭偰偄偨丅偟偐偟丆傛偔尒傞偲嶌幰偼傾僋僛儖偱偼側偄偐丅乽揤嵥悢妛幰偨偪偑挧傫偩嵟戝偺擄栤乿乽亀柍尷亁偵枺擖傜傟偨揤嵥悢妛幰偨偪乿乽検巕偺偐傜傒偁偆塅拡乿乽僼乕僐乕偺怳傝巕乿偺挊幰偱偁傞丅偙偺挊幰側傜崻嫆偺側偄榖偼愨懳彂偐側偄丅撉傫偱傒傞偲婜懸捠傝偺撪梕偱偁偭偨丅傾僋僛儖偼側傫偲偁偺儔僀僾僯僢僣帺恎偑彂偒幨偟偨僨僇儖僩偺乽旈枾偺僲乕僩乿傪捈愙撉傫偱偙偺杮傪挊偟偨丅側偤丆儔僀僾僯僢僣偑僨僇儖僩偺旈枾偺僲乕僩傪崕柧偵彂幨偟偨偺偐乗乗摉帪儔僀僾僯僢僣偺傾僀僨傾偼僨僇儖僩傪櫁愞偟偨傕偺偩偲偄偆偆傢偝偑棫偰傜傟偰偄偨丅斵偼偦偆偱側偄偙偲傪徹柧偡傞偨傔偵傕僨僇儖僩偺慡偰偺挊嶌傪僠僃僢僋偡傞昁梫偑偁偭偨偺偩丅
僠儑儉僗僉乕偼帺暘偺偙偲傪乽僇乕僥傿乕僕儍儞乮僨僇儖僩庡媊幰乯乿偲柧尵偟偨偑丆僨僇儖僩偺峫偊曽偵偼妋偐偵枺偐傟傞傕偺偑偁傞丅僨僇儖僩偑摉帪偺妛幰偨偪偺旈枾僌儖乕僾偱偁偭偨乽錕錘廫帤桭垽抍乿偺儊儞僶乕偱偁偭偨偙偲傪巚傢偣傞婰弎傕偁傞丅偲偭偰傕偍傕偟傠偄杮側偺偱堦撉偺壙抣偁傝丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃暔岅偺偨傔應掕晄壜
亂杮暥偐傜亃
仧僐儞僺儏乕僞乕僠僢僾偺墘嶼張棟擻椡偲擼偺偡偖傟偨壜慪惈偺偍偐偘偱嵞傃揹榖偑巊偊傞傛偆偵側偭偨偺偩丅揹榖偑偐偐偭偰偔傟偽丆傏偔偼憡庤偲偺夛榖傪妝偟傓丅実懷揹榖偲恖岺撪帹僔僗僥儉傪夘偟偰壒慺偑弌擖傝偡傞側偐偱丆傏偔傜偼忕択傪尵偭偰徫偭偨傝丆嬤嫷傪抦傜偣崌偭偨傝丆壗偐傪栺懇偟偨傝偡傞丅揹榖偱暦偔壒惡偼憡曄傢傜偢嬥懏揑偱偐傏偦偔丆嶨壒傕擖傞偑丆彮偟搘椡偡傟偽昁梫側尵梩偼偩偄偨偄暦偒庢傟傞丅傏偔偼丆乽帹偼巰傫偩偗偳丆偙偄偮偼巊偊傞乿偲峫偊側偑傜丆揹榖傪偒傞偙偲偑偁傞丅偦偺傛偆側偲偒丆帺暘偼偄偭偨傫朣楈偲側傝側偑傜傕丆僐儞僺儏乕僞乕偺偍偐偘偱僒僀儃乕僌偲偟偰暅妶偟偨偙偲傪偁傜偨傔偰幚姶偡傞丅(p.155-156)
亂巹偺僐儊儞僩亃
尨戣偼"How Becoming Part Computer Made Me More Human乮堦晹傪僐儞僺儏乕僞壔偡傞偙偲偱帺暘偑偄偐偵傛傝恖娫傜偟偔側偭偨偐)"偱偁傞丅
乽僒僀儃乕僌乿偲偼乽懱偺慡晹傑偨偼堦晹偑揹婥婡夿憰抲偱抲偒姺偊傜傟偨恖娫乿偺偙偲偱偁傝丆姶忣傪帩偨側偄婡夿偦偺傕偺偺乽儘儃僢僩乿偲偼堎側傞丅挊幰偼偦偆偟偨掕媊偱帺傜傪僒僀儃乕僌偲屇傇丅擖傟帟偼乽揹婥婡夿憰抲乿偱偼側偄偺偱丆擖傟帟傪偟偰偄傞恖偼乽僒僀儃乕僌乿偱偼側偄偑丆怱憻儁乕僗儊乕僇乕傪憰拝偟偰偄傞恖偼乽僒僀儃乕僌乿偱偁傞丅
杮彂偼丆幐挳偺偨傔恖岺撪帹偺杽傔崬傒庤弍傪庴偗偨恖偺懱尡択偱偁傞丅傾儊儕僇偱偼偡偱偵偐側傝懡偔偺恖偑偙偆偟偨庤弍傪庴偗偰偄傞傜偟偄丅恖岺撪帹偺棙揰偼僜僼僩傪姺偊傞偙偲偱僶乕僕儑儞傾僢僾偑偼偐傟傞偲偄偆偙偲偩丅
偐偺儀乕僩乕儀儞傪傕幐挳偵捛偄傗偭偨乽帹峝壔徢乿偲偄偆擄昦偵擸傓抦恖偑偄傞丅崱偼曗挳婍偱側傫偲偐傗偭偰偄傞偑丆傗偑偰姰慡偵幐挳偡傞偺偱偼側偄偐偲晄埨偵巚偭偰偄傞丅偱偒傟偽偙偺杮傪徯夘偟偨偄偺偩偑丆偨偩丆乽僒僀儃乕僌乿偲偄偆尵梩偺僀儊乕僕偑偁傑傝偵傕嫮楏偱偁傞偨傔丆憡庤偑彎偮偔偺偱側偄偐偲巚偄丆崱傂偲偮寛抐偱偒偢偵偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏侽
亂杮暥偐傜亃
仧侾俋俋俈擭偵僀僊儕僗偱敪姧偝傟偨俀億儞僪峝壿偵偼丆僊僓僊僓偺墢偺偲偙傠偵乽嫄恖偨偪偺尐偺忋偵棫偭偰乿偲偄偆尵梩偑崗傑傟偨丅偙偺尵梩偼僯儏乕僩儞偑摨椈偺壢妛幰儘僶乕僩丒僼僢僋偵埗偰偨庤巻偐傜嵦偭偨傕偺偱丆僯儏乕僩儞偼偦偙偱師偺傛偆偵彂偄偰偄傞丅乽傕偟傕巹偑傎偐偺恖偨偪傛傝傕墦偔傪尒偨偲偡傟偽丆偦傟偼嫄恖偨偪偺尐偺忋偵棫偭偨偍偐偘側偺偱偡乿偙傟偼僯儏乕僩儞偑丆帺暘偺傾僀僨傿傾偼僈儕儗僆傗僺儏僞僑儔僗側偳丆側偩偨傞愭恖偨偪偺傾僀僨傿傾偺忋偵抸偐傟偰偄傞偙偲傪擣傔偨尓嫊側尵梩偺傛偆偵尒偊傞丅偟偐偟幚嵺偼丆偙傟偼攚崪偑嬋偑偭偰傂偳偔孅傫偱偄偨僼僢僋偺恎懱傪偦傟偲側偔巜偟帵偡丆埆堄偵枮偪偨昞尰偩偭偨丅僯儏乕僩儞偼丆僼僢僋偼擏懱揑偵嫄恖偱偼側偄偙偲傪巚偄帄傜偣丆抦惈偵偍偄偰傕傑偨嫄恖偱偼側偄偙偲傪傎偺傔偐偟偨偺偱偁傞丅(忋 p.138乯
仧價僢僌僶儞丒儌僨儖偵傛傟偽丆乽嵟弶丆偡傋偰偺暔幙偲僄僱儖僊乕偼堦揰偵廤拞偟偰偄偨乿丂偦偺屻丆價僢僌僶儞偑婲偙偭偨丅乽價僢僌僶儞乿偲偄偆尵梩偼偲傕偐偔傕戝敋敪傪堄枴偟丆幚嵺丆敋敪傪巚偄晜偐傋傞偺偼偦傟傎偳揑偼偢傟偱偼側偄丅偟偐偟價僢僌僶儞偼丆嬻娫偺拞偱壗偐偑敋敪偟偨偺偱偼側偔丆嬻娫偑敋敪偟偨偺偱偁傞丅摨條偵丆價僢僌僶儞偼帪娫偺拞偱壗偐偑敋敪偟偨偺偱偼側偔丆帪娫偑敋敪偟偨偺偱偁傞丅嬻娫偲帪娫偼偳偪傜傕丆價僢僌僶儞偺弖娫偵嶌傜傟偨偺偩丅(壓 p.230)
亂巹偺僐儊儞僩亃
僒僀儌儞丒僔儞偺彂偔杮偼暥嬪側偔柺敀偔偦偟偰傢偐傝傗偡偄丅惵栘巵偺東栿傕棫攈偩丅巹偼偙偺僐儞價偺杮偼昁偢攦偆偙偲偵偟偰偄傞丅偙偺杮偼乽價僢僌僶儞棟榑乿偑偳偺傛偆偵偟偰擣傔傜傟偰偄偭偨偐傪傢偐傝傗偡偔愢柧偟偰偔傟傞丅價僢僌僶儞棟榑偑擣傔傜傟傞偒偭偐偗偲側偭偨乽塅拡儅僀僋儘攇攚宨曻幩乿偺敪尒偑丆偳偆偟偰傕彍嫀偱偒側偄乽嶨壒乿傪側傫偲偐偮偒偲傔傛偆偲偟偨擇恖偺揹攇揤暥妛幰偺夦変偺岟柤偱偁偭偨偲偄偆偔偩傝側偳傕柺敀偄丅
偦傟偵偟偰傕丆乽嫄恖偺尐偺忋乿偺敪尵偑僼僢僋傊偺業崪側嵎暿敪尵偩偭偨偲偼丅揤嵥僯儏乕僩儞偺帩偮曄幙嫸揑偄傗傜偟偝偑傛偔昞傟偰偄傞丅斵偼僼僢僋偺偁偲墹棫嫤夛夛挿偵側偭偨偲偒丆僼僢僋偺嵀愓傪揙掙揑偵攋夡偟偨偑丆傛傎偳僼僢僋偑寵偄偩偭偨偺偩傠偆丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俇
亂杮暥偐傜亃
仧慺悢棟夝偵峷專偟偨悢妛幰偵偼丆挿庻傪慡偆偟偨恖偑懡偄丅乮棯乯悢妛幰偨偪偼丆儕乕儅儞梊憐傪徹柧偟偨恖娫偼晄巰恎偵側傞偲忕択傪旘偽偟偰偄傞丅(P.470)
仧儕乕儅儞梊憐傪夝偗偽100枩僪儖偺朖旤偑傕傜偊傞偺偵丆偦傟偱傕嫲傟傪側偟偰偙偺柤偆偰偺擄栤戣傪宧墦偡傞悢妛幰偼懡偄丅儕乕儅儞丆僸儖儀儖僩丆僴乕僨傿乕丆僙儖僶乕僌丆僐儞僰丒丒丒偠偮偵懡偔偺執戝側恖乆偑丆儕乕儅儞梊憐傪夝偙偆偲偟偰嵙愜偟偨丅乮棯乯儕乕儅儞梊憐偑夝寛偝傟側偄傑傑200擭偑偡偓傞偩傠偆偲峫偊傞恖偼懡偄丅乮棯乯儕乕儅儞梊憐偼娫堘偭偰偄傞偲偄偆恖傕偄傞丅偝傜偵偼丆偡偱偵夝偐傟偰偄傞偺偵丆悢妛奅偺尃埿嬝偑旈枾偵偟偰偄傞偩偗偩偲偄偆恖傕偄傞丅偙偺梊憐傪夝偙偆偲偟偰婥偑傆傟偨恖傕偄傞丅(P.472)
亂巹偺僐儊儞僩亃
乽兡(x)=1/1偺x忔亄1/2偺x忔亄1/3偺x忔亄丒丒丒亄1/n偺x忔亄丒丒丒丒乿傪乽僛乕僞乮兡)娭悢乿偲偄偆偺偩偑丆偙偺 x 偺偲偙傠偑暋慺悢乮崅峑偱廗偭偨 a+bi 偲偄偆傗偮乯偵側偭偰偄傞傕偺傪乽儕乕儅儞偺僛乕僞娭悢乿偲偄偆乮僛乕僞娭悢偵偼懠偵傕亀僆僀儔乕偺僛乕僞娭悢亁側偳偄傠偄傠偁傞乯丅偙偺柍尷榓偲側偭偰偄傞娭悢偑 a 偲 b 偺抣偵傛偭偰偼屳偄偵懪偪徚偟偁偭偰嵟屻偵偼乽兡(x)=0乿偲側傞応崌偑偁傞丅偦偺偲偒偺暋慺悢乮a+bi)傪嫇偘偰偄偔偲乽1/2+14.135i丆1/2+21.022i丆1/2+25.011i丒丒丒乿偲側傞丅偦偙偱儕乕儅儞偼偙偺娭悢偑侽偵側傞応崌丆偦偺暋慺悢偺a偵偁偨傞晹暘乮偙傟傪乽幚晹乿偲偄偆乯偼昁偢1/2偱偁傞偲偄偆梊憐傪棫偰偨丅偙傟偑乽儕乕儅儞梊憐乿偱偁傞丅僐儞僺儏乕僞傪嬱巊偟偰尰嵼偺偲偙傠100壄屄傑偱偼儕乕儅儞偺梊憐捠傝偵側偭偰偄傞丅偟偐偟傕偟偐偡傞偲101壄屄栚偱1/2傪偼偢傟傞悢帤偑弌傞偐傕偟傟側偄丅崱媮傔傜傟偰偄傞偼乽偡傋偰偵悢偵偍偄偰儕乕儅儞梊憐偑惉傝棫偮乿偲偄偆乽徹柧乿側偺偱偁傞丅
杮彂偼幚偼悢妛揑抦幆傪慡偔帩偪崌傢偣偰偄側偔偰傕妝偟傔傞丅儕乕儅儞梊憐偲偼壗側偺偐偝偊棟夝偱偒側偔偰傕傛偄丅偦傫側傆偆偵偐偐傟偰偄傞偺偱暥宯恖娫傪帺擣偝傟偰偄傞曽偱傕廫暘偍傕偟傠偄丅
偪側傒偵崱側偤乽儕乕儅儞梊憐乿偑乽擬偄乿偺偐偲偄偆偲丆偙傟偑乽慺悢乿偲棈傫偱偄傞偐傜偩丅慺悢偲偼帺暘帺恎埲奜偱偼妱傝愗傞偙偲偺偱偒側偄悢帤偱偁傞丅83亊97亖8051偼揹戩偑偁傟偼悢昩偱偱偒傞丅偟偐偟丆8051傪83偲97偵暘夝偡傞乮慺場悢暘夝乯偡傞偙偲偼偐側傝帪娫偑偐偐傞丅100寘偺悢傪場悢暘夝偡傞偲側傞偲崱偺偲偙傠晄壜擻偲偄偭偰傛偄傎偳偺挿偄帪娫偑偐偐傞丅幚偼僀儞僞乕僱僢僩忋偺埫崋偼偙偺乽場悢暘夝乿偺擄偟偝傪棙梡偟偰嶌傜傟偰偄傞偺偩丅尰嵼偺偲偙傠崅搙側婡枾惈偑媮傔傜傟傞応崌偼600枩寘偺悢帤偑棙梡偝傟偰偄傞偲偄偆丅儕乕儅儞梊憐偺徹柧偼偙偺埫崋僔僗僥儉偑堐帩偱偒傞偐偲偄偆偙偲偵傕怺偔娭傢偭偰偔傞偺偩丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俇丏侽
亂杮暥偐傜亃
仧恑壔傪丆戝宆壔丆暋嶨壔傊偺摴乗乗尵偄姺偊傟偽丆傢偨偟偨偪恖娫傊偲峴偒偮偔廔傢傝側偒恑曕偺楢懕乗乗偲峫偊傞偺偼丆恖娫偺帺慠側徴摦偩傠偆丅偟偐偟丆偦傟偼帺崨傟偩丅恑壔偺恀偺懡條惈偼彫偝偄婯柾偱婲偙偭偰偄傞丅傢偨偟偨偪戝偒側幰偼丆嬼慠偺嶻暔丆傔偢傜偟偄暘攈側偺偩丅惗暔偺俀俁偺庡側晹栧偺偆偪丆擏娽偱尒傞偙偲偑偱偒傞偺偼偨偭偨嶰偮乗乗怉暔丆摦暔丆嬠椶乗乗偱丆偦偺側偐偵偝偊丆尠旝嬀傪巊傢側偗傟偽尒偊側偄傕偺偑偁傞丅偦傟偳偙傠偐丆僂僅乕僘偵傛傞偲丆抧媴忋偺惗暔検乗乗怉暔傕娷傓抧媴忋偺偡傋偰偺尰懚検偺崌寁乗乗偺俉侽僷乕僙儞僩丆偙偲偵傛傞偲偦傟埲忋偑丆旝惗暔偱愯傔傜傟偰偄傞偲偄偆丅悽奅偼旝彫側惗柦偨偪偺傕偺偱丆偦傟偼丆愄偐傜偢偭偲曄傢傜側偄偺偩丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
僀儞僷僋僩巜悢俀寘偺杮偵傆偝傢偟偄撪梕偱偁傞丅庤偵庢傞偲俇俁俆儁乕僕偺傗傗戝晹側杮偩偑丆傗偝偟偔彂偐傟偨壢妛巎側偺偱堦婥偵撉傔傞丅杮彂傪撉傔偽丆塅拡抋惗埲棃傢傟傢傟偑崱側偤偙偙偵偙偆偟偰偄傞偺偐偑傢偐傞偩傠偆丅
嵟嬤偺尋媶偱偼丆嵶嬠偼偙傟傑偱峫偊傜傟偰偄偨埲忋偵屆偔偐傜偡偱偵懚嵼偟偰偄偨壜擻惈偑偁傞偲偄傢傟偰偄傞丅壗廫壄擭傕偺偁偄偩柆乆偲柦傪僶僩儞僞僢僠偟偰偒偰偄傞偟偨偨偐側惗柦偩丅斵傜偺楌巎偵斾傋偨傜恖娫偺楌巎側傫偐斾妑偺懳徾偵偼側傜側偄丅偙傟傑偱偺楌巎偐傜峫偊傟偽恖椶偑柵朣偟偨屻傕斵傜偼壗帠傕側偐偭偨偐偺傛偆偵埶慠偲偟偰柦偺僶僩儞僞僢僠傪懕偗偰偄偔偙偲偩傠偆丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏侾
亂杮暥偐傜亃
仧俀侽侽俁擭丆偙偺乮巜椫暔岅偺乯儂價僢僩偲傎傏摨偠戝偒偝偺彫偝側僸僩偺壔愇偑僀儞僪僱僔傾偺搰偱尒偮偐傝傑偟偨丅彈惈偱恎挿偼侾儊乕僩儖傎偳丆摢偺戝偒偝傕僌儗乕僾僼儖乕僣掱搙丆巹偨偪偺俁暘偺侾埲壓偺梕検偺擼偟偐傕偨側偄偲偄偆彫偝偝偱偡丅惗偒偰偄偨帪戙傪抦偭偰嬃偒傑偟偨丅侾枩俉侽侽侽擭慜偲偄偄傑偡偐傜丆傕偆巹偨偪偺儂儌丒僒僺僄儞僗偼偲偭偔偵搊応偟偰偄偰丆暥壔傪偮偔傝巒傔偰偄偨偙傠偱偡丅巹偨偪偼摨偠帪娫丆嬻娫傪偙偺彫偝側恖偨偪偲嫟桳偟偰偄偨偼偢側偺偱偡丅丂(P.4)
仧儂儌懏恑壔偺弶婜偵擏偺枴傪妎偊偰偄側偐偭偨傜丆僱傾儞僨儖僞乕儖恖傕傢傟傢傟傕崱丆懚嵼偟偰偄側偐偭偨壜擻惈偑戝偒偄偺偱偡丅偦偺傛偆側偙偲偱壗昐枩擭傕偺偁偲偺僗僥僀僞僗偑寛傑傞側傫偰丆恑壔偲偼柺敀偄傕偺偱偡丅(P.186)
亂巹偺僐儊儞僩亃
尰嵼丆僸僩偲偄偆庬偵懏偡偲峫偊傜傟偰偄傞傕偺偼慡晹偱侾俋庬傕偁傞偲偄偆丅拞偱傕俀侽侽俁擭丆僀儞僪僱僔傾偱尒偮偐偭偨崪偼儂儌丒僒僺僄儞僗偲椬傝崌偭偰嫟懚偟偰偄偨乽傢傟傜埲奜偺恖椶乿偱偁偭偨偲偄偆偐傜丆偙傟偼偨偄傊傫側僯儏乕僗偱偁傞丅杮彂偼墡恖偐傜僱傾儞僨儖僞乕儖恖偵帄傞傑偱丆傢傟傜偲偼暿偺恖椶偵偮偄偰傢偐傝傗偡偔夝愢偟偰偔傟傞丅杮彂偺拞偱摿偵巹偑柺敀偄偲巚偭偨偺偼丆僗僩儕儞僈乕偲偄偆妛惗偑乽帺暘偺庤傪墭偟偰敪孈傪偡傞乿偺偱偼側偔丆儓乕儘僢僷拞偺帺慠巎攷暔娰偵揥帵偝傟偰偄傞乽偡偱偵扤偐偑敪孈偟偰偔傟偨乿僱傾儞僨儖僞乕儖恖偲僋儘儅僯儓儞恖偺崪傪偮傇偝偵挷傋丆偦傟傜傪懡曄検夝愅偱斾妑尋媶偡傞偲偄偆丆偦傟傑偱扤傕傗偭偨偙偲偺側偄庤朄傪梡偄丆乽僱傾儞僨儖僞乕儖恖偼僋儘儅僯儓儞恖偵傛偭偰抲偒姺傢偭偨乿偲偄偆尋媶榑暥傪敪昞偟偨偲偄偆帠幚偩丅曽朄榑偺撈憂惈偑傕偺傪尵偆榖偱偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侾丏侽
亂杮暥偐傜亃
仧偁側偨偺廃埻偵偼丆墦偔偺嬊偐傜曻憲偝傟偰偄傞壗昐傕偺揹攇偑旘傃岎偭偰偄傞丅乮棯乯偲偙傠偑丆儔僕僆傪偮偗傞偲丆堦搙偵傂偲偮偺廃攇悢偺揹攇偟偐暦偙偊側偄丅懠偺廃攇悢偼姳徛惈傪幐偄丆埵憡偑堦抳偟側偔側偭偰偄傞丅乮棯乯摨偠傛偆偵丆偙偺塅拡偱傢傟傢傟偼丆暔棟揑側尰幚偵懳墳偡傞廃攇悢傪乽庴怣乿偟偰偄傞丅偲偙傠偑丆幚偼丆摨偠晹壆偺拞偱傢傟傢傟偲嫟懚偟偰恑峴偟偰偄傞尰幚偑柍悢偵偁傞丅偨偩偟丆傢傟傢傟偵偼偦傫側尰幚偑乽庴怣乿偱偒側偄丅(P.206)
仧尰嵼丆懡偔偺暔棟妛幰偼丆枩暔偺攚屻偵偼扨弮偐偮僄儗僈儞僩偱桳柍傪尵傢偣偸棟榑偑偁傞偑丆偦傟偼廫暘偵婏憐揤奜偱旕忢幆偱偁偭偰偙偦惓偟偄偲峫偊偰偄傞丅(P.226)
仧巹帺恎偼丆塅拡偺偁傑傝偺戝偒偝偵婥偑柵擖傞偳偙傠偑丆偙偺悽奅偺偦偽偵傑偭偨偔暿偺悽奅偑偁傞偲偄偆峫偊偵傢偔傢偔偝偣傜傟傞丅(P.427)
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偼偄傢備傞乽僩儞僨儌杮乿偱偼側偄丅擔宯偺挊幰偼僯儏乕儓乕僋巗棫戝妛棟榑暔棟妛嫵庼偱挻傂傕棟榑偺尃埿偱偁傞丅杮彂偵偼悢幃偼堦愗弌偰偙側偄丅偙傟傎偳擄偟偄棟榑傪偙傟傎偳傢偐傝傗偡偔岅傞挊幰偵椡検偵偼姶扱偡傞丅偲偼偄偭偰傕巹偼偙偺杮偺偡傋偰傪棟夝偟偨偲偄偆傢偗偱偼側偄丅偨偩丆攷棗嫮婰偺挊幰偑條乆側暥妛嶌昳傪椺偵偁偘偰忋庤偵愢柧偡傞偺偱偲偰傕妝偟偔撉傔傞杮偱偁傞丅僀儞僷僋僩巜悢俀寘偺杮偵媣乆弌夛偭偨丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丒俇
亂杮暥偐傜亃
仧僗僲乕乮嵢僄儅偺柮乯偑僟僀僯儞僌偵偄傞偲丆僠儍乕儖僘偑乽搨撍偵乿斵彈偵嬤偯偄偰偒偨偲偄偆丅偦偟偰丆乽傑傞偱偢偭偲偦偺偙偲傪峫偊偰偄偨偐偺傛偆偵丆壗偺慜抲偒傕側偔榖偟巒傔偨偺偱偡丅亀恖偼傒側丆惗傑傟側偑傜偵偟偰恄偺懚嵼傪怣偠偨偄偲巚偆傕偺偩偗傟偳丆傏偔偼丆恖娫偺偁傜備傞姶忣偼偦偺朑夎傪摦暔偺拞偵尒偮偗傜傟傞偲偄偆偙偲傪挷傋偰偒偨偺偱丆偦偆偄偆峫偊傪庴偗擖傟傞偙偲偑偱偒側偄偺偩傛亁偲乿丅(P.546)
仧僠儍乕儖僘偼丆恄傗挻帺慠揑側楈偺懚嵼偵偮偄偰媍榑偡傞偺偼帪娫偺楺旓偱偁傞偲傕岅偭偨丅乽恖偵嫋偝傟偰偄傞帪娫偼尷傜傟偰偄傞偺偩偐傜丆桳岠偵巊偭偨傎偆偑偄偄乿丅偙偺悽偲恖椶偺偨傔偵偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偑偁傝丆帺慠偑傑偩傑偩懡偔偺撲傪巆偟偰偄傞偆偪偼丆帺慠尰徾埲奜偺栚揑偵妱偔帪娫偼桳岠偵巊偆傋偒偩偲偄偆偺偱偁傞丅(P.548)
亂巹偺僐儊儞僩亃
價乕僌儖崋偵忔傝崬傓偲偒丆僠儍乕儖僘丒僟乕僂傿儞偼杚巘偵側傞偙偲傪峫偊偰偄偨丅偦偟偰價乕僌儖崋傪崀傝傞偲偒丆斵偺峫偊偼慡偔曄傢偭偰偄偨丅斵偼壠懓偲擔梛擔偵嫵夛偵峴偭偰傕丆斵堦恖偼嫵夛偵擖傜偢偵奜偱懸偭偰偄偨偲偄偆丅偦偺揰偱宧錳側僉儕僗僩嫵搆偱偁偭偨嵢僄儅偲偺娫偵偼乽恏偄峚乿偑偁偭偨丅偨偩尗柧偱壏岤側僟乕僂傿儞偼帺暘偑桞暔榑幰偱偁傞偙偲傪柧妋偵偡傞偙偲偺婋尟傪廫暘棟夝偟偰偄偨丅偨偩丆僟乕僂傿儞偼椪廔偱壗搙傕乽偁偁恄條乿偲嫨傫偩偲柡偺僄僥傿偑弎傋偰偄傞偺偩偑乧丅
杮彂偺挊幰偼僟乕僂傿儞偺尯懛乮懛偺懛乯偵偁偨傞丅僠儍乕儖僘偺垽柡傾僯乕偑帩偭偰偄偨暥敔傪幚壠偺暔抲偱敪尒偟丆偙偺傾僯乕偺巰偙偦僟乕僂傿儞偵恑壔榑傪幚姶偝偣偨偺偱偼側偄偐偲峫偊傞丅傾僯乕偼棙敪偱偐傢偄偄彮彈偱丆寛偟偰恄偺敱傪庴偗傞傛偆側巕偱偼側偐偭偨丅傾僯乕偺巰偼乽帺慠偺偒傑偖傟乮帺慠搼懣乯乿偲僟乕僂傿儞偼峫偊偰帺暘傪擺摼偝偣傛偆偲偡傞丅杮彂偼僟乕僂傿儞偵嬤偟偄恖偵傛偭偰彂偐傟偨杮偱偁傝丆惗恎偺僟乕僂傿儞偑昤偐傟偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏係
亂杮暥偐傜亃
仧1979擭丆僀儞僪撿晹偺僶儞僈儘乕儖偱奐偐傟偨妛夛偱丆擔杮偺楈挿椶妛幰偱偁傞悪嶳岾娵偑丆徴寕揑側曬崘傪峴側偭偨丅偦傟偼儔儞僌乕儖偺僆僗偑丆偦傟傑偱偺儕乕僟乕傪嬱拃偟偰儊僗偺僴乕儗儉傪偺偭偲傞偲丆偐側傜偢愒傫朧傪奆嶦偟偵偡傞偲偄偆帠幚偩偭偨丅乮棯乯偩偑妛夛偺弌惾幰偼扤傂偲傝偲偟偰丆偦傟偑怴偟偄楌巎偺侾儁乕僕偱偁傞偙偲偵婥偑偮偐側偐偭偨丅悪嶳偺曬崘偵丆夛応偼嫲傠偟偄傎偳惷傑傝偐偊傞丅(P.134)
仧僉僪僑偼怱憻傪埆偔偟偰偄偨偣偄偱懱椡偑棊偪丆偍偲側偺僆僗傜偟偄僗僞儈僫傕帺怣傕幐偭偰偄偨丅儈儖僂僅乕僉乕摦暔墍偺儃僲儃僐儘僯乕偵楢傟偰偙傜傟偨摉弶丆僉僪僑偼姷傟側偄寶暔偺側偐偱偡偭偐傝崿棎偟偰偄偨丅僩儞僱儖偺偁偪傜偐傜偙偪傜偵堏摦偡傞傛偆偵帞堢學偑巜帵偟偰傕丆偲傑偳偆偽偐傝偩丅偟偽傜偔偡傞偲丆傎偐偺悢摢偺儃僲儃偑僉僪僑偵嬤偯偒丆斵偺庤傪庢偭偰峴偒愭傪埬撪偟偨丅偮傑傝儃僲儃偨偪偼丆帞堢學偺堄恾偲丆僉僪僑偺媷忬傪偳偪傜傕棟夝偟偰偄偨偙偲偵側傞丅(P.221)
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偺懷偵偼乽働儞僇偭憗偔偰椻崜側僠儞僷儞僕乕丆側傫偱傕俫偱夝寛偡傞儃僲儃丆偁側偨偼偳偭偪婑傝丂摎偊仺偳偭偪傕両乿偲偁傞丅偮傑傝変乆恖娫偼僠儞僷儞僕乕偺朶椡惈偲儃僲儃偺暯榓庡媊傪暪偣帩偭偰偄傞偲偄偆偺偩丅偙偺杮偺撪梕傪堦尵偱偄偆偲偦偆偄偆偙偲偵側傞丅変乆偼偲傕偡傞偲丆恖娫偩偗偑懠偺摦暔傛傝傕偼傞偐偵桪傟偨傕偺偲姩堘偄偟偰偄傞丅偟偐偟偙偺杮傪撉傔偽丆偡偱偵懠幰傊偺嫟姶傗丆嬀傪尒偰帺屓擣幆偑偱偒傞椶恖墡偲変乆偑偄偐偵嬤偄偐偑傛偔傢偐傞偩傠偆丅忋婰偺悪嶳偩偑丆偦偺屻侾侽擭娫妛夛偐傜柍帇偝傟偮偯偗偨丅偟偐偟傗偑偰巕嶦偟偑楈挿椶偼傕偲傛傝丆僋儅丆僀儖僇丆僾儗乕儕乕僪僢僋丆捁椶側偳偱傕師乆偺帠椺偑敪尒偝傟丆斵偺惓偟偝偑擣傔傜傟傞傛偆偵側傞丅傕偭偲傕儃僲儃偵偼巕嶦偟偼尒傜傟側偄丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃係丏俈
亂杮暥偐傜亃
仧侾俉悽婭僼儔儞僗偺婱懓幮夛傎偳丆乽晄昳峴乿偑戝庤傪怳偭偰偁傞偄偰偄偨幮夛偺椺偼丆楌巎忋丆偍偦傜偔丆偦傟傎偳懡偔側偄偩傠偆丅偳傫側暥壔寳偺丆偳傫側尩偟偄夲棩偺傕偲偱傕丆晄椣偺垽偼懚嵼偟偨丅偄偮偺帪戙偱傕丆抝偑嵢埲奜偵垽恖傪傕偮偙偲傪丆幮夛偼栙擣偟偰偒偨丅偩偑丆婛崶偺彈偺楒垽偑偙傟傎偳帺桼偩偭偨偙偲偼丆偨傇傫捒偟偄偩傠偆丅(P.76)
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偼慜乆偐傜晄巚媍偵巚偭偰偄偨偙偲偑偁傞丅侾俉悽婭偺儓乕儘僢僷忋棳幮夛偱偼側偤婛崶彈惈偱偁傞仜仜岒庉晇恖偑晇埲奜偺垽恖傪偁傟傎偳偍偍偭傄傜偵帩偰偨偺偐偲偄偆偙偲偩丅晇偼嵢偺晜婥偵壗傕姶偠側偐偭偨偺偩傠偆偐丅幚偼偙偺帪婜偼傑傟偵尒傞帺桼楒垽偺帪戙偱偁偭偨偺偩丅傕偪傠傫儖乕儖偼偁傞丅晇偺懱柺傪彎偮偗傞傛偆側偍偍偭傄傜側偙偲偼傗偭偰偼偄偗側偄乮偨偲偊偽垽恖偺巕偳傕傪嶻傓側偳乯偲偄偆儖乕儖偩丅偙傟偝偊傢偒傑偊偰偍偗偽丆偳偆偣晇傕摨偠偙偲傪偟偰偄傞傢偗側偺偩丅僔儍僩儗岒庉晇恖偼悢妛偲儔僥儞岅偵偨偗丆偁偺擄夝側僯儏乕僩儞偺乽僾儕儞僉僺傾乿傪拲庍擖傝偺僼儔儞僗岅偵栿偟偨偲偄偆偺偩丅偟偐傕偙偺栿彂偼崱偱傕攧傜傟偰偄傞偺偩偲偄偆丅杮彂偼丆償僅儖僥乕儖偲偺岎嵺傪婎斦偵丆僔儍僩儗岒庉晇恖偺抝惈曊楌偑岅傜傟偰偄傞丅偪側傒偵丆乽壩偺彈乿偲偼抝傪垽偟偨傜偲偙偲傫傑偱偄偐偹偽偡傑側偄斵彈偺惈奿偲丆斵彈帺恎偑昞偟偨乽壩乿偵娭偡傞榑暥傪偐偗偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俇
亂杮暥偐傜亃
仧偙偺杮偼丆巹偨偪偼傒側惎孄偺巕嫙偱偁傞偲偄偆擣幆偐傜惗傑傟偨丅巹偨偪偺懱傪宍偯偔傞尨巕偼偦傟偧傟丆偐偮偰丆偁傞峆惎偺撪晹偵偁偭偨丅偦偺峆惎偼丆偄偮偺擔偐巹偨偪偑惗傑傟傞傛偆惗偒丆偦偟偰巰傫偩偺偩丅偟偐偟丆摨帪偵巹偨偪偼抧媴偺巕嫙偱傕偁傞偲偄偆帠幚傪尒幐偄偐偹側偄丅巹偨偪偺懱傪宍偯偔傞尨巕偺傂偲偮傂偲偮偑懱撪偵偲偳傑偭偰偄傞偺偼丆偦偺埵抲偵傛偭偰悢暘偩偭偨傝悢擭偩偭偨傝偡傞偑丆偲傕偐偔偄偭偲偒偵偡偓側偄丅乮p.272)
仧塅拡傪栰媴儃乕儖偺僒僀僘偵傑偱埑弅偡傞偲丆憤僄僱儖僊乕偺偆偪丆崱擔偺偡傋偰偺嬧壨傪宍偯偔傞暔幙偺偡傋偰偺幙検偲寢傃偮偄偰偄傞晹暘偺妱崌偼丆偍傛偦侾侽亅俀俁丆偮傑傝偍傛偦侾侽挍暘偺堦偺侾挍暘偺堦偩両乮偙偺曻幩偼崅埑偱丆朿挘偡傞塅拡偵摥偒偐偗丆悢愮擭偱偦偺僄僱儖僊乕偼徚偊嫀傝丆庢傞偵懌傜側偔側偭偰丆崱擔偺塅拡偱偼暔幙偑桪埵傪愯傔偰偄傞丅乯偮傑傝丆崱擔晛捠堦屄偺尨巕偑愯傔偰偄傞嬻娫偵摉帪丆媗傔崬傑傟偰偄偨暔幙偺惷巭幙検偼抧媴偺幙検掱搙偩偭偨偑丆曻幩僄僱儖僊乕傪娷傔傞偲丆偙偺嬻娫偑書偊偰偄偨僄僱儖僊乕偼丆偙傟傛傝傕偢偭偲戝偒偐偭偨偙偲偵側傞丅幚偼丆偙傟偼尰嵼尒偊傞塅拡慡懱偺僄僱儖僊乕偵憡摉偡傞僄僱儖僊乕偩丅
堦屄偺尨巕偵媗傔崬傑傟偨塅拡両(p.20)
亂巹偺僐儊儞僩亃
尨戣偼"An Odyssey from the Big Bang to Life on earth...and Beyond"偱偁傞丅乽價僢僌僶儞偐傜抧媴偺惗柦丒丒丒偦偟偰枹棃傊偺僆僨傿僢僙僀乿偲偄偆堄枴偩丅摪乆弰傝偵側傞偑丆傕偟杮摉偵塅拡偑價僢僌僶儞偱抋惗偟偨偺側傜丆偦偺慜偼壗偩偭偨偺偩偲偄偆偙偲偑婥偵側傞丅傑偨丆塅拡偑栰媴偺儃乕儖偔傜偄偺戝偒偝偩偭偨偲偄偆偺側傜丆偳偆偟偰抧媴傪巒傔偲偡傞塅拡偺朿戝側暔幙偑偦偺傛偆側彫偝側嬻娫偵媗傔崬傔傞偲偄偆偺偐丅
偙偺杮偱偼丆壗偲栰媴偺儃乕儖偳偙傠偐丆彫偝側尨巕堦屄偺嬻娫偵慡塅拡傪媗傔崬傓偙偲傕壜擻偩偲偄偆偺偩丅偦偺応崌丆傕偼傗乽暔幙乿偼懚嵼偟側偄丅傎偲傫偳偑曻幩僄僱儖僊乕偲偄偆宍偱懚嵼偡傞偲偄偆丅偙偺庤偺榖偼偁傑傝偵傕悢帤偑朿戝偡偓偰偳偆傕姶妎偑偮偐傔側偄丅偟偐偟偍傕偟傠偄丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俈丏俈
亂杮暥偐傜亃
仧柊傝偼僸僩偺愱攧摿嫋偱偼側偄丅乮棯乯懡嵶朎惗暔偵嫟捠偺摿挜偩丅崺拵丆擃懱摦暔丆嫑丆椉惗椶丆捁丆歁擕椶傪偼偠傔丆偁傜備傞庬椶偺摦暔偵柊傝偑娤嶡偝傟偰偄傞丅
仧悋柊攳扗偑嬌尷偵払偡傞偲側偵偑婲偒傞偺偩傠偆丅乮棯乯偨偩偺塡榖偺偨偖偄傪傋偮偵偡傟偽丆僸僩偐傜嫮惂揑偵悋柊傪扗偆偲巰偵偄偨傞偐傪壢妛揑偵専徹偟偨椺偼柍偄丅偨偲偊壢妛幰偐傜偦偺傛偆側幚尡偺怽惪偑偁偭偰傕丆椣棟埾堳夛偑擄怓傪帵偡偩傠偆丅偩偑僸僩埲奜偺庬偱偁傟偽丆偼偭偒傝偟偨徹嫆偑偁傞丅摦暔偼幚尡偱悋柊傪扗傢傟偮偯偗傞偲丆嵟屻偵偼昁偢巰偸丅偦偟偰丆僸僩偑偦傟偲偼崻杮揑偵堘偆偲偄偆崻嫆偼偳偙偵傕柍偄丅
仧傢傟傢傟偼傒側柊偭偰偄傞偁偄偩偵杣婲偡傞乗乗偁側偨傕丆傢偨偟傕乮偊偊丆偦偆偱偡偲傕乯丆傾儊儕僇戝摑椞傕丆偍椬偝傫傕丅乮棯乯悋柊拞偺儁僯僗偺杣婲偼偁傜備傞擭楊偺寬慡側抝惈偵丆巕媨撪偺戀帣偵偝偊婲偙傞丅乮棯乯栭娫杣婲偼寬慡偐偮偁傝傆傟偨尰徾偩丅栭娫偺儁僯僗偺杣婲偼拫娫偺偦傟偲偼堘偄丆擭傪偲偭偰傕昿搙傗廃宎偑偝傎偳掅壓偟側偄丅偟偨偑偭偰偙偺揰偵偐傫偟偰丆拞擭屻婜偺抝惈偺杣婲擻椡偼俀侽戙慜敿偺偦傟偲曄傢傜側偄丅乮棯乯捠忢丆拞擭抝惈偵偼堦斢偵俁乣係夞偺栭娫杣婲偑偁傝丆侾夞偺杣婲偼偍傛偦俁侽暘懕偔丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
媣偟傇傝偵丆傕偺偡偛偔柺敀偄杮偵弌偔傢偟偨丅偙偺傛偆側杮偼俀侽嶜攦偭偰侾嶜偁傞偐側偄偐偩丅偙偺杮偼悋柊傪尋媶偡傞壢妛幰偑彂偄偨杮偱偁傞丅尨戣偼 Counting Sheep 偩偑丆朚戣偑偙傟傑偨偍傕偟傠偄丅栿傕偙側傟偰偄偰撉傒傗偡偄丅悋柊偲偄偆傕偺偑扨側傞媥懅側偳偲偄偆惗堈偟偄傕偺偱偼側偔丆変乆偺惗巰傪嵍塃偡傞傕偺偱偁傞偙偲偼棟夝偟偰偍偄偰偄偄偩傠偆丅僸僩傪揹婥傕側偔丆擔偑曢傟傞偲埫偔側傞忬懺偵抲偔偲丆偨偄偰偄俉帪娫偺悋柊偵棊偪拝偔偲偄偆丅偁側偨偼俉帪娫怮偰傑偡偐丠
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏侽
亂杮暥偐傜亃
仧帪娫偵娭偡傞巚峫幚尡偱嵟傕桳柤側傕偺偼丆1921擭丆僶乕僩儔儞僪丒儔僢僙儖偑峫偊偨傕偺偱偁傞丅悽奅偑5暘慜偵偱偒偨偲偟傛偆丅婰壇傗乽埲慜偺乿弌棃帠偺嵀愓傕丆憿暔庡偺偄偨偢傜偲偟偰5暘慜偵嶌傜傟偨偺偱偁傞丅偦偆偱側偄偙偲傪丆偳偆傗偭偰徹柧偡傞偺偩傠偆丅偦傟偼偱偒側偄偲儔僢僙儖偼尵偆丅儔僢僙儖偲榑憟偟傛偆偲偄偆恖偼彮側偄偩傠偆丅摨偠榑朄偱丆偳傫側斀榑傕懪偪嵱偗偰偟傑偆偐傜偩
仧嵒嶳傪巚偄晜偐傋丆偦偙偐傜嵒傪堦棻庢傝嫀傠偆丅夁嫀偺宱尡偵婎偯偄偰丆嵒棻傪堦偮庢傝彍偗偽嵒嶳偱側偄偼側偄傕偺偑巆傞傛偆側偙偲偑偁傝偆傞偐丅傕偪傠傫側偄丅偡傞偲嵒嶳偐傜巒傔偰丆堦棻偢偮嵒傪庢傝彍偄偰偄偙偆丅偄偢傟嶳偼彫偝偔側偭偰堦屄偺嵒棻偵側傞偩傠偆丅偦傟偱傕嵒嶳偱側偗傟偽側傜側偄丅嵟屻偺棻傪庢傟偽壗傕巆傜側偄丅偦偺壗傕側偄偲偙傠傕傗偼傝嵒嶳偱側偗傟偽側傜側偄丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
僛僲儞偄傢偔丆埦棻傪堦棻棊偲偟偰傕壒偼偟側偄丅偟偐偟瀍偄偭傁偄偺埦棻傪棊偲偡偲壒偑偡傞偺偼側偤偐丅偙偺庤偺榖傪乽愊傒廳偹偺媡愢乿偲偄偆傜偟偄丅忋婰偺擇偮栚偺榖傕偦傟偵偁偨傞丅嵒嶳偐傜嵒傪堦棻偲偭偰傕丆傗偼傝嵒嶳偱偁傞丅偟偐偟丆偦傟傪墑乆偲懕偗傞偲丆嵟屻偵偼嵒棻偑堦偮偩偗偺偙傞丅偦傟傕乽嵒嶳乿偲偄偆偺偐丅傕偟偦偆偱側偄偲偡傟偽丆乽嵒嶳偼偄偮嵒嶳偱偁傞偙偲傪傗傔偨偺偐乿丅杮彂偼乽僥僙僂僗偺慏乿乽僩儉僜儞偺儔儞僾乿乽敳偒懪偪僥僗僩乿乽廁恖偺僕儗儞儅乿側偳屆崱搶惣偺偝傑偞傑側媡愢傪夝愢偡傞丅嵟弶偺乽墘銏偲婣擺乿偺榖偼偨傔偵側傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俁丏俋
亂杮暥偐傜亃
仧崱擔丆僴僢僩儞偑拝憐偟丆儔僀僄儖偑懱宯偩偰偨抧媴娤偼乽惸堦愢乿偲屇偽傟偰偍傝,偦偺屻偺抧幙妛傗惗暔恑壔榑偵懡戝側塭嬁傪梌偊偰偒偨丅偟偐偟側偑傜丆偦偺塭嬁椡偺戝偒偝偵傕偐偐傢傜偢丆嵟弶偵惸堦愢偺崪巕傪惗傒偩偟偨僕僃僀儉僘丒僴僢僩儞偲偄偆恖暔偲丆斵偑壗傪峫偊偨偺偐偼丆傑偭偨偔偲尵偭偰偄偄傎偳丆惓偟偔偼棟夝偝傟偰偄側偄丅
仧僕僃僀儉僘丒僴僢僩儞偼,側偤抧幙妛幰埲奜偵傎偲傫偳抦傜傟偰偄側偄偺偩傠偆偐丠乮棯乯僕僃僀儉僘丒僴僢僩儞偼丆堄巚傪揱偊傞岻傒側嵥傪傕偨側偐偭偨偲偄偆帠幚偑偁傞丅乮棯乯寚娮偺懡偄彂偒曽偼丆僴僢僩儞偑杮偺幏昅偵偁偨偭偰偄偨偲偒偵恎懱偺晄挷偵嬯偟傫偱偄偨偙偲偲憡傑偭偰丆愘懍偵憱傜偣傞尨場偲側偭偨丅扨偵挿戝偩偲偄偆偩偗偱側偔丆亀抧媴偺棟榑亁偵偼丆傎偐偺尵岅偱彂偐傟偨懠恖偺嶌昳偐傜偺嬄乆偟偄売強偑娷傑傟偰偄傞丅庤偵晧偊側偄杮偲偄偆偩偗偱崱擔偱偼撉傫偱傕傜偊側偄偩傠偆偟丆摉帪傕峀偔撉傑傟偨傢偗偱偼側偐偭偨丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼丆揤抧憂憿偵傛偭偰抧媴偑嶌傜傟偰偐傜6000擭偱偁傞偲峀偔怣偠傜傟偰偄偨帪戙偵丆抧媴偼朿戝側帪娫偺拞偱彊乆偵曄壔偟偰偒偨偲庡挘偟偨抧幙妛偺晝僕僃僀儉僘丒僴僢僩儞偵偮偄偰彂偐傟偨傕偺偱偁傞丅斵偼僄僨傿儞僶儔傪拞怱偵妶摦偟丆儔僀僄儖傗僟乕僂傿儞偵塭嬁傪梌偊偨丅乽惸堦愢乿偲乽恑壔榑乿偺愙揰傪峫偊傞忋偱傕杮彂偼帵嵈偵晉傓丅
偨偩丆巹偼杮彂傪撉傫偱師偺傛偆側儊乕儖傪弔廐幮偵憲偭偨偺偩偑丆壗偺墳摎傕側偄丅偡偽傜偟偄杮偱偁傞偺偵丆惤堄偺側偝偑婥偵側傞丅
---------憲晅偟偨儊乕儖 2004.11.3-----------
弔廐幮丂曇廤晹丂揳 乮偁偰愭偑堘偆傛偆偱偟偨傜丆偍庤悢偱偡偑丆曇廤晹偺曽傊 偛揮憲偄偨偩偗傟偽偲懚偠傑偡乯
崱丆乽僕僃僀儉僘丒僴僢僩儞乿乮僕儍僢僋丒儗僾僠僃僢僋挊丆暯栰榓巕栿丆弔廐幮丆2004乯傪撉傒廔偊傑偟偨丅僒僀儌儞丒僂傿儞僠僃僗僞乕偺乽悽奅傪曄偊偨抧恾乿傗乽僋儔僇僩傾偺戝暚壩乿傪撉傫偩偲偙傠偩偭偨偺偱丆偲偰傕嫽枴怺偔撉傒傑偟偨丅儔僀僄儖偼桳柤側偺偵乽惸堦愢乿偺杮壠杮尦偱偁傞僕僃僀儉僘丒僴僢僩儞偺抦柤搙偑崱傂偲偮偱偁傞偺偼晄岞暯偵巚偊傑偡丅
偲偙傠偱丆杮暥偺拞偱偄偔偮偐婥偵側偭偨揰偑偁傝傑偟偨丅
嘆p.53 乽儂儕乕儖僢僪媨揳乿
Holyrood 傪乽儂儕乕儖僢僪乿偲昞尰偝傟偰偄傑偡偑丆傗偼傝堦斒偵尵傢傟偰偄傞傛偆偵乽儂儕乕儖乕僪乿偱偼側偄偱偟傚偆偐丅嶰徣摪偺乽屌桳柤帉塸岅敪壒帿揟乿 偵偼乽Holyrood (in Scotland) holiru丗d乿偲偁傝傑偡偟丆Longman Dictionary of English丂Language and Culture偵傕乽Holyrood Palace /holiru丗d 乣乿偲偟偰偄傑偡丅嘇摨暸
嵟屻偺峴偵乽偄傑偱偼偙偺忛偼孯帠栚揑偵巊梡偝傟偰偄傞丅乿偲偁傝傑偡偑丆偙偺乽偄傑偱偼乿偼21悽婭偺偙偲偱偟傚偆偐丅偲偰傕乽孯帠栚揑乿偵巊梡偝傟偰偄傞傛偆偵偼巚偊傑偣傫偑丒丒丒丅偦傟偲傕偙偺乽偄傑偱偼乿偼18悽婭偺偙偲傪偄偭偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅嘊p.74丂2乣4峴栚
僴僢僩儞偺巜摫偵偁偨偭偰偄偨巘偼丆朄棩偑斵偵岦偄偰偄側偄偙偲傪偡偖偝傑屽傝丆乽斵偵傕偭偲揔偟偨傎偐偺巇帠傪峫偊偨傎偆偑傛偄乿偲傾僪僶僀僗偟偨偲偁傝傑偡偑丆乽扤偵乿傾僪僶僀僗偟偨偺偱偟傚偆偐丅栚揑岅偑尒偊傑偣傫丅暥柆偐傜偡傞偲丆乗乗僴僢僩儞偺巜摫偵偁偨偭偰偄偨巘偼丆朄棩偑斵偵岦偄偰偄側偄偙偲傪偡偖偝傑屽傝丆斵偵乽傕偭偲揔偟偨傎偐偺巇帠傪峫偊偨傎偆偑傛偄乿偲傾僪僶僀僗偟偨乗乗偲側傞偺偱偼偲巚傢傟傑偡偑丅
埲忋丆媈栤偵巚偭偨師戞偱偡丅
-----------------儊乕儖廔椆---------------
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏俋
亂杮暥偐傜亃
仧斵偼恖偲堘偭偰偄偨丅帇揰偑恖偲偼堘偭偰偄偨偺偩丅斵偩偗偑傗偑偰丆塣壨偺儖乕僩偵増偭偨揷墍抧懷偺旤偟偄宨怓偑曄杄偟偰偄偔偙偲偵偼堄枴偑偁傞偲婥偯偒丆偦傟偑僒儅僙僢僩偺抧壓悽奅傪抦傞偺偵廳梫側忣曬偩偲妋怣偡傞偵偄偨偭偨丅揤暘乗傠偔側嫵堢傕庴偗偰偄側偄擾壠偺懅巕偵偟偰偼巚偄偑偗側偄揤暘偩偭偨乗乗偵宐傑傟偨斵偼丆偨偩偙偺曄壔偵栚傪偲傔偨偩偗偱偼側偐偭偨丅斵偼傑偭偝偒偵丆偙偺曄壔偺尨場傪偮偒偲傔傜傟傞偐傕偟傟側偄乗乗偤傂丆偮偒偲傔偨偄丆偨傇傫廳梫側偙偲偑傜偩偐傜乗乗偲峫偊偨偺偩丅(p.107)
仧斵傜乮僀僊儕僗抧幙妛夛弶戙夛挿僌儕乕僲僂傜傪巜偡乯偼偁傞寁夋偵拝庤偟丆偦傟偑傗偑偰僗儈僗傪攋柵偵捛偄傗偭偨丅斵傜偼帺暘偨偪偱怴偟偄戝婯柾側抧幙恾傪嶌傞傋偒偩偲寛傔偨偺偩丅(棯)偁偮偐傑偟偔傕愭庤傪庢傠偆偲偟偨柍抦側揷幧幰乮僂傿儕傾儉丒僗儈僗傪巜偡乯傪偙傟埲忋巚偄忋偑傜偣側偄傛偆丆巭傔偺堦寕傪壛偊側偗傟偽偄偗側偄丅(p.260)
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼丆OED抋惗偺榖傪昤偄偨乽攷巑偲嫸恖乿偺挊幰偑彂偄偨椡嶌偱偁傞丅奒媺幮夛偺拞偱偦偺嵥擻偑擣傔傜傟側偐偭偨偽偐傝偐丆弌棃偨偽偐傝偺抧幙妛夛偐傜偦偺嬈愌傪搻傑傟偝偊偟偨抝丆僂傿儕傾儉丒僗儈僗偺榖偱偁傞丅斵偼丆偙傟傎偳宐傑傟側偄抝偼偁傞偺偩傠偆偐偲巚偊傞恖惗傪曕傓偑丆榁嫬偵擖偭偰偐傜傗偭偲偦偺柤梍偑夞暅偝傟傞丅働儞僽儕僢僕戝妛偺僂僢僪儚乕僪婰擮島嵗嫵庼傾僟儉丒僙僕償傿僢僋偑僗儈僗偵憲偭偨僗僺乕僠偼姶摦揑偱丆偮偄巹偼栚摢偑擬偔側偭偰偟傑偭偨^^;丂報嶞壆偺挌抰偐傜妛幰偵側偭偨儅僀働儖丒僼傽儔僨乕丆揤嵥帪寁怑恖僕儑儞丒僴儕僜儞丆壔愇彈偲屇偽傟偨儊傾儕乕丒傾僯儞僌丆偦偟偰偙偺僂傿儕傾儉丒僗儈僗丒丒丒巹偼偙偆偟偨丆奒媺幮夛偺僀僊儕僗偱嵎暿偵孅偣偢偵偑傫偽偭偨嵥擻偁傞恖偨偪偺偙偲偵側傞偲偳偆偄偆傢偗偐擬偔側傞偺偩丅
摉妛夛偺嵟弶偺庴徿幰偲偟偰僀僊儕僗抧幙妛夛偺晝偵儊僟儖傪憽傞偙偲偼丆巕偲偟偰偺巹偨偪偺媊柋偱偁傝傑偡丒丒丒乮傾僟儉丒僙僕償傿僢僋乯
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俁.俁
亂杮暥偐傜亃
仧偳偆偵偐撉幰傪愢摼偟偰丆惗柦偑暋嶨側壔妛宯偺杮棃偺惈幙偱偁傞偙偲傪丆傢偐偭偨傕傜偄偨偄偲峫偊偰偄傞丅壔妛僗乕僾偺拞偱暘巕偺庬椶偺悢偑偁傞鑷抣傪挻偊傞偲丆帺屓傪堐帩偡傞斀墳偺僱僢僩儚乕僋乗帺屓怗攠揑側暔幙戙幱乗偑丆撍慠惗偢傞偱偁傠偆偙偲傪偤傂偲傕擺摼偟偰傎偟偄偺偱偁傞丅
仧堦枩屄偺儃僞儞偑丆栘偱偱偒偨彴偺忋偵偽傜傑偐偰偄傞偲偙傠傪憐憸偟偰傒傛偆丅儔儞僟儉偵擇偮偺儃僞儞傪慖傫偱丆偦傟傜傪巺偱偮側偖丅偙傫偳偼偙偺儁傾傪彴偵抲偒丆偝傜偵擇偮偺儃僞儞傪儔儞僟儉偵慖傇丅偦偟偰丆偦傟傪庢傝忋偘巺偱偮側偖丅乮棯乯堦懳偺儃僞儞傪儔儞僟儉偵慖傫偱巺偱偮側偖嶌嬈傪懕偗偰偄傞偲丆偟偽傜偔偟偰丆儃僞儞偼傛傝戝偒側偐偨傑傝丆偮傑傝僋儔僗僞乕傊偲憡屳偵楢寢偝傟傞傛偆偵側傞丅乮棯乯巺偲儃僞儞偺斾偑侽丏俆傪挻偊傞偲丆憡揮堏偑惗偢傞丅偙偺揰偵偍偄偰丆乽嫄戝僋儔僗僞乕乿偑撍慠宍惉偝傟傞偺偱偁傞丅乮棯乯巺偲儃僞儞偲偺斾偑侽丏俆傪挻偊傞偲丆撍慠丆傎偲傫偳偺僋儔僗僞乕偑岎嵎揑偵楢寢偝傟傞傛偆偵側傝丆堦偮偺嫄戝側僋儔僗僞乕偑宍惉偝傟傞偺偱偁傞丅乮棯乯堦枩屄偺儃僞儞傪梡偄偨偲偡傟偽丆嫄戝側惉暘偼丆巺偑偍傛偦俆侽侽侽杮偵側偭偨偲偒弌尰偡傞偱偁傠偆丅
仧偙偺嫄戝側僋儔僗僞乕偼晄壜巚媍側傕偺偱偼側偄丅偦傟偑弌尰偡傞偺偼摉慠側偙偲偱偁傞丅儔儞僟儉僌儔僼偵娭偟偰梊憐偝傟偰偄傞惈幙偱偁傞丅偙傟偲椶帡偟偨埲壓偺傛偆側尰徾偑丆惗柦偺婲尮偵偮偄偰偺棟榑偺拞偵尰傟傞丅壔妛斀墳宯偵偍偄偰丆廫暘懡偔偺斀墳偑怗攠嶌梡傪庴偗傞偲丆怗攠偝傟偨斀墳偺旕忢偵戝偒側怐暔偑撍慠乽寢徎壔乿偡傞丅偙偆偟偨怐暔偼丆傎傏妋幚偵帺屓怗攠揑偱偁傞偙偲偑傢偐傞丅偦偟偰丆傎傏妋幚偵帺屓堐帩揑偱偁傞丅惗偒偰偄傞偺偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
俆俁侽儁乕僕偵傕側傞杮彂偼寛偟偰撉傒傗偡偄傕偺偱偼側偄丅偟偐偟丆偠偭偔傝撉傔偽摼傞偲偙傠偺戝偒側杮偱偁傞丅拞偱傕丆偙偺儃僞儞偲巺偺榖偼丆僌儔僼棟榑偵婎偯偔傕偺偱偁傞偑丆旕忢偵帵嵈揑偱偁傞丅擬椡妛戞俀朄懃偵傛傟偽丆僄儞僩儘僺乕偼憹戝偺曽岦傊偲忢偵岦偐偄丆拋彉偐傜柍拋彉傊偲岦偐偆偲偄偆丅偟偐偟丆偦傟偱偼偳偆偟偰惗柦偺傛偆側拋彉偑惗偠偨偐偑愢柧偱偒側偄丅偦偙偵偙偺帺屓慻怐壔偺棟榑偱偁傞丅堦掕偺鑷乮偟偒偄乯抣傪挻偊偨偲偒丆偦偙偵撍慠偦傟傑偱偵側偐偭偨拋彉偑惗偠傞偲偄偆偺偩丅偟偐傕丆偦傟偼僌儔僼偱昞偡偲丆帺摦幵嫵廗強撪偺乽僋儔儞僋摴楬乿偺傛偆偵傎傏俋侽搙偱嬋偑傞僌儔僼偲側傞丅乽彊乆偵乿偱偼側偔丆偁傞揰傪嫬偵乽撍慠乿栚偺慜偵尰傟傞偺偩丅僇僂僼儅儞偼乽恑壔偵偍偄偰偼丆帺屓慻怐壔偲僟乕僂傿儞揑側帺慠搼懣偲偺椉曽偺栶妱傪擣傔側偗傟偽側傜側偄乿偲弎傋偰偄傞丅杮彂偺僀儞僷僋僩巜悢偼傗傗掅偄偑丆偙傟偼杮彂偑偨偄偔偮側傕偺偱偁傞偲偄偆偺偱偼側偔丆巹偑屻敿偺撪梕傪廫暘撉傒偒傟偰偄側偄偣偄偱偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俀
亂杮暥偐傜亃
仧巹偑堚揱巕偵柌拞偵側偭偨偺偼丆僔僇僑戝妛偺嶰擭惗偺偲偒偩偭偨丅偦傟傑偱偼丆彨棃偼攷暔妛幰偵側傠偆偲巚偄丆帺暘偺堢偭偨僔僇僑偺壓挰丆僒僂僗僒僀僪偺寲憶偲偼傑偭偨偔堘偭偨娐嫬偱尋媶偡傞偙偲傪妝偟傒偵偟偰偄偨丅偦傫側巹偑怱曄傢傝傪偟偨偺偼丆朰傟偑偨偄嫵巘偑偄偨偐傜偲偄偆傢偗偱偼側偔丆侾俋係係擭偵弌偨亀惗柦偲偼壗偐亁偲偄偆彫偝側杮偵姶摦偟偨偐傜偩丅挊幰偼丆僆乕僗僩儕傾惗傑傟偱丆攇摦椡妛偺晝偲尵傢傟傞僄儖償僃僀儞丒僔儏儗乕僨傿儞僈乕偱偁傞丅
仧俢俶俙暘巕偺杮幙偼丆斵傜乮壔妛幰乯偱偼側偔丆戝妛惗儗儀儖偺抦幆偡傜傕偨側偄惗暔妛幰偲暔棟妛幰偺擇恖慻偵傛偭偰敪尒偝傟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅偟偐偟媡愢揑偱偼偁傞偑丆彮側偔偲傕晹暘揑偵偼丆柍抦偼惉岟偺尞偩偭偨丅嵟弶偵擇廳傜偣傫偵偨偳傝偮偄偨偺偑僋儕僢僋偲傢偨偟偩偭偨偺偼丆摉帪偺戝懡悢偺壔妛幰偑丆俢俶俙暘巕偼戝偒偡偓傞偨傔壔妛揑暘愅偱偼棟夝偱偒側偄偲峫偊偰偄偨偐傜側偺偩丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼僋儕僢僋偲偲傕偵俢俶俙偺峔憿傪敪尒偟偨僕僃乕儉僗丒儚僩僜儞偵傛偭偰彂偐傟偨傕偺偱偁傞丅俢俶俙峔憿敪尒偐傜僸僩僎僲儉夝愅傑偱丆斵偺娭傢偭偨條乆側懱尡偑帺愢傪傑偠偊偰岅傜傟偰偄傞丅斵偼惡崅偵堚揱巕慻傒懼偊怘昳傊偺寈崘傪嫨傇娐嫬榑幰偵偼斸敾揑偱偁傞丅傑偨丆亀儀儖丒僇乕僽亁偵懳偟偰傕俰丒僌乕儖僪偲堎側傝丆堦掕偺昡壙傪梌偊偰偄傞丅偦偆偟偨揰偱丆巹偵偼偳偪傜偐偲偄偆偲曐庣揑偲偄偆報徾傪庴偗傞偑丆幚嵺偼壗偑恀棟偱偁傞偐傪姶忣傪岎偊偢偵尒偰偄偙偆偡傞壢妛幰偺巔惃側偺偐傕偟傟側偄丅偨偩丆偪傚偭偲婥偵側傞偺偼丆姫枛偺拲偵乽巹偺俬俻偼侾俀俀偲偄偆側偐側偐棫攈側抣偩偑丆偲偔偵桪廏偲偄偆傢偗偱偼側偄丅巹偼侾侾嵨偺偲偒丆愭惗偺婘偺忋偵偁偭偨儕僗僩傪搻傒尒偟偰偙傟傪抦偭偨乿偲偁傞丅抦擻僥僗僩偵傛傞俬俻偼惗奤晄曄偺傕偺偱偼側偄丅偦偺揰偱偼俰丒僌乕儖僪偺亀恖娫偺應傝傑偪偑偄亁偺曽偑惓偟偄丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏俋
亂杮暥偐傜亃
仧傕偺偛偲傪悢検揑偵峫偊傞挍偟偑尰傟偨偺偼丆惣儓乕儘僢僷偺恖岥偲宱嵪惉挿偑嵟弶偺僺乕僋偵払偟偨侾俁侽侽擭慜屻偺偙偲偩偭偨丅偙偺挍偟偼丆惣儓乕儘僢僷幮夛偑憡師偖嫲晐偵尒晳傢傟偨侾係悽婭傪捠偠偰丆徚偊傞偙偲偼側偐偭偨丅偙偺侾侽侽擭偺娫偵恖岥偼寖尭偟丆愴憟偼峆忢壔偟偨丅
仧侾俁悽婭屻敿偐傜侾俇悽婭偵偐偗偰惣儓乕儘僢僷偺暥壔偼抦妎偵崿棎傪偒偨偟偨忬懺偵偁傝丆棊抇偺徖偱傕偑偄偰偄偨丅尰幚悽奅傪擣抦偟丆愢柧偡傞偨傔偵揱摑揑偵梡偄偰偒偨巚峫條幃偼丆偟偩偄偵偦偺庡梫側婡擻傪壥偨偝側偔側偭偰偄偨丅乮棯乯惣儓乕儘僢僷恖偼偒傢傔偰備偭偔傝偲丆偨傔傜偄偑偪偵亅亅偟偽偟偽彜嬈偵娭楢偟偨亅亅帠幚偵婎偯偄偰丆尰幚悽奅傪怴偟偄尒曽偱尒傞傛偆偵側傝偼偠傔偨丅偙偆偟偰宍惉偝傟偨悽奅憸傪乽怴偟偄儌僨儖乿偲柤偯偗傛偆丅乽怴偟偄儌僨儖乿偺偒傢偩偭偨摿挜偼丆惓妋偝偲暔棟揑尰徾偺悢検揑攃埇丆偦偟偰悢妛傪丆偼傞偐偵廳帇偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
乽儓乕儘僢僷掗崙庡媊乿偑偐偔傕惉岟偟偨尨場偼壗偱偁偭偨偐丅偦偺捛媮傪儔僀僼儚乕僋偲偟偰偄傞挊幰偑偄偒偮偄偨夝摎偺堦偮偑丆乽悢検壔乿偱偁傞丅係戝暥柧偺偐偘偰僷僢偲偟側偐偭偨惣儓乕儘僢僷偑侾俁悽婭偁偨傝偐傜椡傪偮偗偰偮偄偵偼悽奅傪惾姫偡傞偵偄偨偭偨偺偼側偤偐丅挊幰偼偦傟傪僥僋僲儘僕乕偺敪払偲偲曅偯偗傞偺偱偼側偔丆偦偺崻杮揑尨場偲偟偰乽悢検乿偵婎偯偔擣抦妚柦偵偁偭偨偺偱偼側偄偐偲愢偔丅偍傕偟傠偄敪憐偱偁傞丅偨偩丆屻敿偼巹偵偼偪傚偭偲朞偒傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏俇
亂杮暥偐傜亃
仧僇儕僼僅儖僯傾戝妛僶乕僋儗乕峑偺抧幙妛幰儗僀儌儞僪丒僕乕儞儘僗偼丆師偺傛偆側曽朄偱朿戝側悢偺椡傪妛惗偵帵偟丆偁偭偲偄傢偣傞偺偑摼堄偩丅傑偢僠儑乕僋偱崟斅偺抂偐傜抂傑偱堦杮偺慄傪傂偒丆偙偭偪偺抂傪僛儘丆岦偙偆偺抂傪侾挍偲偡傞丅師偄偱妛惗偵侾侽壄偑偳偺偁偨傝偵側傞偐丆慄傪堷偐偣偰傒傞偲丆偨偄偰偄偺幰偼僛儘偲侾挍偲偺偁偄偩偺嶰暘偺堦偁偨傝偵報傪偮偗傞丅偲偙傠偑侾侽壄側偳幚偼僛儘偺報偲偨偄偟偰偼側傟偰偄側偄偺偩丅p.33
仧乽暍傝揰乿偼丆彮悢偺傕偺偑懡悢偵埑搢偝傟偰偄傞傛偆側傕偺傕偺偺忬嫷偵傕尰傟傞傜偟偄丅偨偲偊偽暔棟妛嫵幒偺彈巕妛惗偼丆偦偺悢偑僋儔僗偺乮偁傞偄偼妛晹偺乯侾俆僷乕僙儞僩掱搙偵憹偊傞傑偱偼丆屒棫偟偰側傫偲側偔嫃怱抧偑埆偄丅偲偙傠偑侾俆僷乕僙儞僩偺帪揰偱暤埻婥偑偑傜傝偲曄傢傝丆暔棟妛偼傛偦傛偦偟偔椻偨偄撽挘傝偐傜堦揮偟偰乮昁偢偟傕抔偐偔側偄傑偱傕乯廧傒怱抧偺傛偄娐嫬偵側傞偲偄偆丅p.97
仧晝傗曣偺尐幵偵偺偭偰僷儗乕僪傪尒暔偟偨偙偲偺偁傞恖偼丆娤揰傪曄偊傞偲偄偆偙偲偑丆偳傫側偵嫮椡側偙偲偐傛偔抦偭偰偄傞偼偢偩丅戞嶰偺師尦傊偲侾俉侽僙儞僠儊乕僩儖偽偐傝忋偵傛偠搊偭偰傒傞偲丆偳偆偩傠偆丅怴偟偄帇奅偑奐偗丆傎傫偺偪傚偭偲慜傑偱尒偊側偐偭偨椞堟偑丆偵傢偐偵偼偭偒傝尒偊偰偔傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼悢帤傪僥乕儅偵埖偭偨傕偺偱偼偁傞偑丆悢幃偺傛偆側傕偺偼傎偲傫偳弌偰偙側偄丅悢帤偲偄偆傕偺偼堦尒丆乽壢妛揑偱榑棟揑乿偺傛偆側婄傪偟偰偄傞偺偱丆巹偨偪偼偮偄偮偄悢帤偱偄傢傟傞偲乽惓偟偄傕偺乿偲姩堘偄偟偰偟傑偆丅乽巹偺廧傓捠傝偺幵偼偡傋偰俛俵倂偩乿偲偄偆偺傪暦偄偰丆嬃偄偰偼偄偗側偄丅偦偺捠傝偵偁傞幵偺戜悢偼偨偭偨侾戜偲偄偆偙偲傕偁傝偆傞偐傜偩丅暥宯棟宯傪栤傢偢乮偲偄偆傛傝丆傢偨偟偼偙偺傛偆側暘偗曽偼岆傝偩偲巚偆偺偩偑乯丆杮彂偼偨傔偵側傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏係
亂杮暥偐傜亃
仧堄幆偼偦偺帩偪庡偵丆悽奅憸偲丆偦偺悽奅偵偍偗傞擻摦揑庡懱偲偟偺帺屓憸傪採帵偡傞丅偟偐偟丆偄偢傟偺憸傕揙掙揑偵曇廤偝傟偰偄傞丅姶妎憸偼戝暆偵曇廤偝傟偰偄傞偨傔丆堄幆偑惗偠傞栺侽丏俆昩慜偐傜丆懱偺傎偐偺晹暘偑偦偺姶妎偺塭嬁傪庴偗偰偄傞偙偲傪丆堄幆偼抦傜側偄丅堄幆偼丆鑷壓抦妎傕偦傟偵懳偡傞斀墳傕丆偡傋偰塀偡丅摨條偵丆帺傜偺峴堊偵偮偄偰書偔僀儊乕僕傕榗傔傜傟偰偄傞丅堄幆偼丆峴堊傪巒傔偰偄傞偺偑帺暘偱偁傞傛偆側婄傪偡傞偑丆幚嵺偼堘偆丅尰幚偵偼丆堄幆偑惗偠傞慜偵偡偱偵暔帠偼巒傑偭偰偄傞丅p.295
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偼僨儞儅乕僋偱侾俁枩晹攧傟偨偲偄偆丅擔杮偺恖岥斾偱姺嶼偡傞偲俀俆侽枩晹偺儀僗僩僙儔乕偩丅擔杮偱偼偮傑傜側偄楒垽杮偑儀僗僩僙儔乕偲側偭偰偄傞偲偄偆偺偵丅偙偺杮偼丆懡偔偺壢妛揑嬈愌偑悢懡偔堷梡偝傟偰偍傝丆寛偟偰撉傒傗偡偄杮偱偼側偄丅偦傟偑俀俆侽枩晹偵旵揋偡傞攧傟峴偒傪尒偣傞僨儞儅乕僋偲偄偆崙偑幚偵偆傜傗傑偟偄丅
偙偺杮偑徯夘偡傞悢乆偺帠幚偼嬃偒偵尒偨傕偺偽偐傝偩丅偨偲偊偽,乽巹偼帺暘偺幵偱偒傑偟偨乿偲偄偆偲偒丆偦偺幵偑敀偺係僪傾僙僟儞偺僇儘乕儔偱嶐擭攦偭偨拞屆偱偁傞偲偄偆傛偆側愢柧偼偟側偄丅偦傟傜傪乽帺暘偺幵乿偲偄偆尵梩偵乽埑弅乿偟偰憡庤偵揱偊傞丅巹傪傛偔抦偭偰偄傞憡庤偼乽帺暘偺幵乿偲偄偆尵梩傪庴偗庢傞偲偦傟傪摢偺拞偱乽夝搥乿偟偰丆惓偟偄僀儊乕僕傪昤偔丅僐儈儏僯働乕僔儑儞偲偄偆偺偼敪榖偟偰偄傞尵梩偦偺傕偺傛傝傕丆偦傟傪嶌傝弌偡偨傔偵愗傝庢傜傟偨乽奜忣曬乿偑傓偟傠廳梫偩偲偄偆偺偩丅
拞偱傕嬃偔傋偒帠幚偼丆巋寖偑擼偵揱傢傝擼偑妶摦傪巒傔偰偐傜丆乽堄幆乿偑棫偪忋偑傞傑偱偵乽侽丏俆昩乿偐偐傞偲偄偆偙偲偩丅偙偺偙偲偼偁傜備傞幚尡偵傛偭偰徹柧偝傟偰偄傞丅巹偨偪偼擔忢偺峴摦偼偡傋偰帺暘偺堄巙偱峴偭偰偄傞偲屌偔怣偠偰偄傞丅偟偐偟丆巹偨偪偑壗偐峴摦傪婲偙偡偲偒丆傑偢擼偑妶摦偟丆偦偺乽侽丏俆昩屻乿偵堄幆偑惗傑傟傞偺偩丅乽偦傫側偙偲偼側偄丆帺暘偼巚偭偨弖娫偵峴摦偟偰偄傞乿偲庡挘偡傞恖傕偄傞偩傠偆丅幚偼丆偙偺侽丏俆昩傪杽傔崌傢偣偡傞偨傔偵丆堄幆偼侽丏俆昩偝偐偺傏偭偰乽挔怟傪崌傢偣偰偄傞乿偲偄偆偺偩丅壗偐傪偟傛偆偲偡傞偲偒丆傑偢柍堄幆壓偱妶摦偑偼偠傑傝丆偦偺侽丏俆昩屻偵堄幆偑惗傑傟丆堄幆偼偁偨偐傕偦傟埲慜偐傜帺暘偱峫偊偰偄偨偐偺傛偆偵侽丏俆昩孞傝忋偘傞偲偄偆偺偩丅
僷僜僐儞忋偺晄梫側僼傽僀儖偼僨僗僋僩僢僾偵偁傞偛傒敔偺傾僀僐儞偵僪儘乕仌僪儘僢僾偡傞丅偟偐偟丆偙偺乽偛傒敔乿偼偨偩儐乕僓乕偺曋媂偺偨傔偵嶌傜傟偨尪憐偵偡偓側偄丅僐儞僺儏乕僞偺幚懺偼偍偦傠偟偄検偺侽偲侾偺梾楍偱偁傞丅偟偐偟丆変乆偼偦偙偵偁偨偐傕偛傒敔偑偁傞偐偺傛偆偵晄梫側僼傽僀儖傪幪偰傞丅変乆傪偲傝傑偔悽奅偼丆変乆帺恎偺乽堄幆乿傕娷傔偰丆偡傋偰幚懺偼乽尪憐乿側偺偩丅杮彂偺僞僀僩儖乽儐乕僓乕僀儕儏乕僕儑儞乿偼偙偙偐傜偒偰偄傞丅偝傜偵嫽枴偺偁傞曽偼丆偙偺僐乕僫乕偵偁傞亀恖偼側偤姶偠傞偺偐亁偺彂昡傪偛傜傫偄偨偩偒偨偄丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俀丏俀
亂杮暥偐傜亃
仧She selles sea shells sitting on the sea shore. 乮斵彈偼奀娸偵嵗偭偰奓妅傪攧傞乯
偙傟偼傛偔儊傾儕乕偺偙偲傪壧偭偨偲偄傢傟傞丅傕偪傠傫扨側傞偙偲偽梀傃偵偡偓側偄偑丆傕偟儌僨儖偑偄傞偲偟偨傜斵彈傎偳傆偝傢偟偄恖暔傕偄側偄丅
仧儊傾儕乕偼偄偮偛傠偐傜偐乽僼僅僢僔儖丒僂乕儅儞乿偲偄偆堎柤偱屇偽傟傞傛偆偵側偭偨丅壔愇晈恖偁傞偄偼壔愇彈丅娙寜偵偟偰捈滲偦偟偰儐乕儌儔僗偩丅偦傟偑垽徧偱偁傟暿徧偱偁傟丆斵彈偵偙傟傎偳傆偝傢偟偄傕偺傕偁傞傑偄丅偄偢傟偺偟傠儊傾儕乕偼暯慠偲庴偗梕傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
崱側偍尩慠偲懚嵼偡傞僀僊儕僗偺奒媺幮夛丅侾俉俁侽擭戙丆僀僊儕僗撿晹偺僪乕僙僢僩奀娸偵廧傓柍妛偱昻朢側壔愇攧傝偺彈偲側傟偽丆妛夛偐傜偼偼傞偐棧傟偨懚嵼偲峫偊傜傟偰偄偨偙偲偩傠偆丅偙偺彈惈偑摉帪偲偟偰偼嵟愭抂偺妛栤偱偁偭偨抧幙妛傪撈妛偱儅僗僞乕偟丆摪乆偲戝妛嫵庼偺榑暥偵偮偄偰偺岆傝傪巜揈偟偰偄偨偲偄偆偺偩丅
偙偺杮偼嫑棾僀僋僠僆僒僂儖僗偺壔愇偺敪尒幰儊傾儕乕丒傾乕僯儞僌偵偮偄偰偺弶傔偰偺揱婰偱偁傞丅挊幰偑偐偮偰偺拵僾儘偺傾僯儊乕僞乕偲屆惗暔妛幰偲偄偆庢傝崌傢偣傕偍傕偟傠偄丅
巹偼偙偺杮偵怗敪偝傟丆偙偺搤(俀侽侽係擭侾寧乯偵儘儞僪儞偺帺慠巎攷暔娰傊峴偭偰丆偙偺栚偱斵彈偺敪孈偟偨僀僋僠僆僒僂儖僗傪尒偰偒偨丅搤偺儘儞僪儞偼屵屻巐帪偵偼偡偱偵埫偔丆揥帵応強偺徠柧傕崱傂偲偮偱丆懠偺僐乕僫乕傛傝傕娤媞偑彮側偐偭偨丅偟偐偟丆斵彈偺惉偟悑偘偨嬈愌傪朖傔徧偊傞偐偺傛偆偵偦偺徰憸夋偲愢柧偑戝偒偔挘傝弌偝傟偰偄傞偺傪傒偰側偤偐傎偭偲偟偨丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃係丏俆
亂杮暥偐傜亃
仧栚偵擖偭偰偔傞憸偦傟帺懱偼丆崅偝偲暆偟偐側偄擇師尦偺傕偺偱偁傞丅偲偄偆偙偲偼丆梌偊傜傟偨憸偐傜偼丆偦傟偧傟堎側傞柍悢偺嶰師尦悽奅傪峔抸偡傞偙偲偑壜擻偱偁傝丆巕嫙偨偪偼偦傟偧傟暿屄偺嶰師尦悽奅傪峔抸偟偰傕丆側傫偺晄巚媍傕側偄傢偗偩丅乮棯乯巕嫙偼偳偆傗偭偰丆峔抸壜擻側柍悢偺帇妎悽奅偐傜丆懠偺巕嫙偨偪偲摨偠傛偆側帇妎悽奅傪慖傃弌偟偰偄傞偺偩傠偆偐丠乮棯乯慖傇傋偒帇妎悽奅傪寛掕偡傞朄懃傪丆惗傑傟側偑傜偵偟偰偡偱偵傕偭偰偄偨偲偟偨傜丆峔抸偼壜擻偩丅乮棯乯惗屻侾擭偺偆偪偵巕嫙傪帇妎偺揤嵥偵偟丆栚偵擖偭偰偔傞憸偺柍尷偺偁偄傑偄偝偵傕偐偐傢傜偢丆寬忢側戝恖偲摨偠帇妎峔抸傪偍偙側偊傞傛偆偵偡傞丆偙偆偟偨惗棃偺朄懃偺偙偲傪丆巹偼乭晛曊揑帇妎偺朄懃乭偲屇傫偱偄傞丅偙偺晛曊揑帇妎偺朄懃偼丆尵岅妛幰僲乕儉丒僠儑儉僗僉乕偵傛偭偰採彞偝傟偨丆偐偺桳柤側晛曊揑暥朄偺朄懃偲摨偠傛偆側傕偺偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偨偪偑暔傪尒傞偲偒丆栚偵擖偭偨憸偑偦偺傑傑價僨僆偺傛偆偵擼偵憲傜傟偰擼撪偱儕傾儖僞僀儉偱塮幨偝傟偰偄傞偲側傫偲側偔巚偭偰偄傞丅幚嵺偼偦偆偱偼側偔丆栐枌偵忋壓偝偐偝傑偵塮偟弌偝傟偨憸偼懡偔偺晹暘偵暘夝偝傟丆擼偺偝傑偞傑側晹暘偵憲傜傟丆偦偙偱乽堦掕偺朄懃乿偵婎偄偰嵞峔抸偝傟傞丅杮棃偼擇師尦偺憸偑乽堦掕偺朄懃乿偵婎偒丆嶰師尦偺傕偺偲偟偰乽夝庍乿偝傟傞丅偦傟偱偼偳偆偟偰丆巹偑峔抸偡傞憸偲偁側偨偑峔抸偡傞憸偑摨偠偱偁傞偺偐丆偡側傢偪丆巹偺尒偰偄傞傕偺偲偁側偨偑尒偰偄傞傕偺偑偳偆偟偰摨偠傕偺偱偁傞偺偐丅偦傟偼傢偨偟偨偪偑乽摨偠朄懃乿傪梡偄偰夝庍偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅挊幰偼偙偺乽朄懃乿傪乽暥朄乿偲屇傃,偦傟偼僠儑儉僗僉乕偺晛曊暥朄偺傛偆偵丆惗傑傟側偑傜偵帩偭偰偄傞傕偺偱偁傞偲偄偆丅偦偟偰丆帇妎偵尷傜偢丆挳妎丆怗妎側偳偡傋偰偺姶妎傕丆偦傟偧傟偺乽暥朄乿偵婎偄偰擼撪偱嵞峔抸偝傟偰偄傞偺偩偲偄偆丅杮彂偱偼偙偺乽暥朄乿偲偟偰偺俁俆偺朄懃偵偮偄偰丆條乆側恾偲偲傕偵丆愢摼椡偺偁傞夝愢傪峴偭偰偄傞丅擼偑恖椶嫟捠偺晛曊朄懃傪帩偭偰偄偰丆偦傟偵傕偲偯偄偰姶妎婍姱偐傜擖傞忣曬傪張棟偟偰偄傞偲偄偆偺偼幚偵嫽枴怺偄偙偲偩丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏俋
亂杮暥偐傜亃
仧怴偟偄敪尒偺偨傔偵偼丆抧掙怺偔愽偭偰傒傞偵偼媦偽側偄丅偨偲偊偽偪傚偭偲棤掚偵弌偰丆嶨憪偺崻偺偁偨傝偺搚傪擇杮偺巜偱偮傑傒忋偘偰傒傛偆丅侾侽壄偵嬤偄惗暔屄懱丆偙偲偵傛傞偲堦枩庬傎偳偺旝惗暔傪庤偵偟偰偄傞偙偲偵側傞偩傠偆丅乮棯乯堦偮傑傒偺搚偱偙傟偩偗側偺偩丅昗弨揑偵寬慡側搚傪偰偺傂傜偄偭傁偄偡偔偊偽丆偦偙偵偼慡抧媴偺恖岥傛傝懡偄惗暔偑偄偰丆壗昐儅僀儖偺嬠巺偑墑傃偰偄傞丅(p.10)
仧悈慺偼塅拡偺慡暔幙偺俋侽僷乕僙儞僩埲忋丆恖懱偺尨巕悢偺俇侽僷乕僙儞僩埲忋傪愯傔傞丅悈慺偼偡傋偰丆侾俆侽壄擭慜偵婲偒偨乽價僢僌僶儞乿偺寖偟偄敋敪偵傛偭偰宍惉偝傟偨丅乮棯乯侾俋俉俁擭偵尦慺偺婲尮偵娭偡傞尋媶偱僲乕儀儖徿傪庴徿偟偨僂傿儕傾儉丗僼傽僂儔乕偼師偺傛偆偵尵偆丅乽変乆偼傒側丆暥帤捠傝惎孄偺彫偝側偐偗傜偵偡偓側偄乿丅(p.35)
仧抧媴偵偍偗傞惗柦偺婲尮傪扵偟媮傔傞変乆偼丆嵟嬤堦楢偺枺椡揑側敪尒傪偟偨丅抧拞壗愮僼傿乕僩偲偄偆怺偝偱巁慺傕岝傕側偄崅壏崅埑偺応強偵斏塰偡傞旝惗暔偺幮夛偑偁偭偨偺偩丅乮棯乯崱偱偼乽埫崟怘暔楢嵔乿偺崻掙偱晄巚媍側戙幱傪峴偆旝惗暔偙偦丆抧媴嵟弶偺惗柦宍懺偺捈宯偺巕懛偐傕偟傟側偄偲峫偊傞壢妛幰傕偄傞丅(p.54)
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偼丆偙偺壓偵偁傞亀昦尨嬠偼僸僩傛傝嬑曌偱尗偄亁偲偄偆杮偲娭楢偑偁傞丅偙傟傑偱変乆偼惗柦偼懢梲偺宐傒偺偍偐偘偱偁傞偲嫵偊傜傟偰偒偨丅偟偐偟丆抧壓悢昐儅僀儖偺巁慺傕岝傕側偄娾斦偺娫偱惗懅偡傞嵶嬠偑尒偮偐偭偨偺偩丅偙偆偟偰抧壓偵惗懅偡傞惗暔偺検偼丆抧忋偱惗懅偡傞惗暔偺検傪偼傞偐偵偟偺偖偲偄偆寁嶼傕偁傞丅偙傟傑偱埫崟偺悽奅偩偭偨墿愹偺悽奅偑丆惗柦偵枮偪偨悽奅偱偁傞偙偲偑傢偐偭偰偒偨偺偩丅傗偭傁傝嵶嬠偼偨偩傕偺偱偼側偄丅偙偺杮偵傛傝丆巹偺嵶嬠偵懳偡傞堌宧偺擮偑偝傜偵怺傑偭偨丅岝傕巁慺傕昁梫偲偟側偄惗柦懱偺懚嵼偼丆壩惎偵傕惗柦偑偁傞壜擻惈傪帵嵈偟偰偄傞傛偆偵傕巚傢傟傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏侽
亂杮暥偐傜亃
仧戝帠側偙偲偼丆帺慠奅偵偄傞傎偲傫偳偡傋偰偺嵶嬠偼丆僸僩偵昦婥傪婲偙偡偙偲偑側偄"旕昦尨惈嬠"偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅僸僩偑柤慜傪晅偗偨嵶嬠偺偆偪偺俋俋僷乕僙儞僩偼丆旕昦尨惈嬠偱偁傞偲偄傢傟偰偄傞丅(p.71)
仧巹偨偪偺懱偺偙偲傪傑偢峫偊偰傒傞偲丆奜奅偵偮側偑傞憻婍丆偨偲偊偽旂晢偼傕偪傠傫偺偙偲丆旲丆岥丆婥摴丆徚壔娗丆斿擜宯側偳偝傑偞傑側奜奅偵奐偄偨憻婍偱偼丆偦傟偧傟偺晹埵偵摿桳側旝惗暔丆摿偵嵶嬠偑偡傒偮偄偰丆僼儘乕儔乮嵶嬠憄乯傪宍惉偟偰偄傞丅偙偺忢嵼嵶嬠憄偲屇偽傟傞旝惗暔孮乮堦恖偺恖娫偺懱傪嶌偭偰偄傞慡嵶朎悢傛傝懡偔丆侾侽偺侾係忔屄偵媦傇旝惗暔偑堦恖偺恖娫偵廧傒偮偄偰偄傞乯偼丆巹偨偪偺惗偒偰偄傞尷傝丆巹偨偪偺懱偲嫟偵惗偒丆偝傑偞傑側塭嬁傪媦傏偡丅(p.81)
仧堓捵釃偺敪惗偼丆僗僩儗僗偲堓巁偱愢柧偝傟偰偒偨丅乮棯乯偟偐偟丆嵟嬤偱偼偙傟偑尒帠丆僂僜偱偁偭偨偙偲偑傢偐傝丆湵慠偲偟偰偄傞丅偦傟偱偼丆堓捵釃偺杮摉偺尨場偼丆壗偩偲偄偆偺偐丅偦傟偼丆僸儕僐僶僋僞乕丒僺儘儕偲偄傢傟傞嵶嬠偱偁傞丅堓捵釃偼姶愼徢偩偭偨偲偄偆偙偲偵側傞丅(p.120)
仧昦尨嬠偼丆帺暘帺恎偺巕懛傪憹傗偡偨傔丆偁傞偄偼堐帩偡傞偨傔偲偄偆惗暔偲偟偰偺摉慠偺峴堊傪偟偨寢壥偩傞偐丆偁傞偄偼嬼慠偵恖娫偺懱撪偺拞偵柍棟傗傝庢傝崬傑傟偨偨傔偵丆傕偑偒嬯偟傫偱乮丠乯憗偔扙弌偟傛偆偲偡傞偙偲偑丆姶愼徢偲偄偆昦婥偱偁傞偐傕偟傟側偄丆偲昅幰偼峫偊偰偄傞丅(p.149)
亂巹偺僐儊儞僩亃
恖娫偺慡嵶朎俇侽挍屄傪偼傞偐偵墇偊傞俇侽侽挍傕偺嵶嬠偑偨偭偨堦恖偺懱撪偵懚嵼偡傞丅旂晢侾僙儞僠儊乕僩儖巐曽偩偗偱傕悢枩乣悢廫枩偺嵶嬠偑廧傒偮偄偰偄傞丅偝傜偵尵偊偽丆変乆偑擔乆攔煏偡傞曋偺敿暘偼嵶嬠偱偁傞丅偙偆偟偨帠幚傪抦傞偲丆傕偼傗乵峈嬠乿傪攧傝暔偵偟偰偄傞條乆側惢昳偑柍懯側搘椡偺傛偆偵巚偊偰偒偨丅梫偡傞偵丆巹偨偪偼嵶嬠偩傜偗偺悽奅偵偄傞偺偩丅恖椶偑弌尰偡傞偼傞偐埲慜偐傜抧媴偵懚嵼偟丆偍偦傜偔恖椶柵朣屻傕抧媴偺廧柉偱偁傝偮偯偗傞偱偁傠偆丆偙偺戝愭攜偱偁傞嵶嬠傪揋偲傒側偡偙偲帺懱偑岆傝側偺偩丅帺慠偺娐嫬傗帺暘偺寬峃偺僶儔儞僗傪偲傝側偑傜丆偙偺乽戝愭攜乿偲偄偐偵偆傑偔偮偒偁偭偰偄偔偐偑戝愗側偺偩傠偆丅巹偼偙傟傑偱丆乽恖娫偼懠偺摦暔偲偄偐偵堘偆偐乮尗偄偐乯乿傪嫮挷偡傞橖枬側尵偄曽偵偆偝傫偔偝偄傕偺傪忢乆姶偠偰偒偨丅偦偆偟偨堄枴偱杮彂偺僞僀僩儖偑偲偰傕婥偵擖偭偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏俀
亂杮暥偐傜亃
仧怱棟僥僗僩偺傕偮偙偺恖岺惈傪巜揈偡傞偩偗偱丆婼偺庱傪庢偭偨傛偆偵怱棟僥僗僩偵偐偐傢傞媍榑慡懱傪柍堄枴側傕偺偲寛傔偮偗傞榑媞偑偟偽偟偽偄傞丅恑壔惗暔妛幰偲偟偰挊柤側僗僥傿乕償儞丒俰丒僌乕儖僪側偳偼偦偺堦恖偩丅斵偼俬俻専嵏偑應偭偰偄傞抦擻側傞傕偺偑丆摑寁妛揑偵峔惉偝傟偨傕偺偱偁傝丆偄偐側傞幚懱偲偟偰偺堄枴傕側偄偙偲傪嫮挷偟偰丆偦偙偐傜抦擻堚揱榑傪斸敾偡傞偲偄偆庤朄傪偲偭偰偄傞丅偙偺庬偺榑朄偼丆恖娫偺怱棟揑宍幙偺堚揱偺栤戣傪僀僨僆儘僊乕榑憟偺拞偵埵抲偯偗傛偆偲偡傞恖偺偲傞忢搮庤抜偱偁傝丆偄傑偩偵懡偔偺恖偵愢摼椡傪帩偭偰庴偗擖傟傜傟偰偄傞傜偟偄丅
仧堚揱偺岠壥偵懳偡傞娐嫬偺岠壥偼丆壛嶼揑丆偁傞偄偼憡屳嶌梡揑偩偲峫偊傟偽傛偄丅壛嶼揑偱偁傞偲偼丆堚揱偺帒幙偵娭學側偔梌偊傜傟偨嫵堢娐嫬偺岠壥偑壛嶼偝傟傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅堚揱揑偵楎偭偨恖偱傕嫵堢娐嫬偑廫暘偵傛偔梌偊傜傟傟偽丆妛廗惉愌傪忋偘傞壜擻惈傕偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
峴摦堚揱妛幰偵傛傞偍傕偟傠偄杮偱偁傞丅"nature vs. nurture乮惗傑傟偐堢偪偐乯"偼屆偔偰怴偟偄栤戣偲偟偰丆僞僀儉帍乮傾僕傾斉丆俀侽侽俁擭俇寧俀擔崋乯偵傕庢傝忋偘傜傟偨丅乽惗傑傟乿攈偲偟偰丆僇儞僩丆僑乕僩儞丆儘乕儗儞僣丆僠儑儉僗僉乕丆乽堢偪乿攈偲偟偰儘僢僋丆僷僽儘僼丆僼儘僀僩丆儃傾僘偑嫇偘傜傟偰偄偨丅杮彂偺婰弎偺傎偲傫偳偑巹偵偲偭偰擺摼偺偄偔傕偺偱偁偭偨丅変乆偺峴摦傗姶忣丆偦偟偰條乆側擻椡偑堚揱巕偺惂栺傪庴偗偰偄傞偙偲偼娫堘偄側偄丅偨偩杮彂偱傕庢傝忋偘傜傟偰偄傞偑丆堚揱妛偑偲傕偡傞偲桪惗妛偺傛偆偵嵎暿怱偵崻偞偟偨棟榑偺摴嬶偲偟偰梡偄傜傟偨夁嫀偑偁傞丅偦傟偼摑寁妛偺楌巎偲廳側傞丅俬俻偵偍偄偰傕娫堘偭偨棙梡偑懡乆側偝傟偰偒偨丅僌乕儖僪偑斸敾偟偰偄傞偺傕偦偆偄偆偙偲偩偲巚偆乮偪側傒偵丆巹傕僗僺傾儅儞偺倗偺懚嵼偼怣梡偟偰偄側偄乯丅偙偺傛偆偵堚揱偺榖偼偳偆偟偰傕姶忣揑偵側傝傗偡偄偑丆忢偵恀棟傪媮傔偰偄偙偆偲偡傞挊幰偺懺搙偵偼岲姶偑傕偰偄傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏侾
亂杮暥偐傜亃
仧乽俁侽擭埲忋偵傢偨偭偰尋媶傪懕偗偰偒偨偑丆朿戝側僨乕僞偐傜堷偒弌偣傞寢榑偼師偺堦揰偵恠偒傞丅怱棟椕朄偵傛偭偰傛偔側傞恖傕偄傞偑丆偐偊偭偰埆偔側傞応崌傕懡偄丅懡偔偺徢椺偵偮偄偰挷嵏偡傞偲丆偙偺憡斀偡傞岠壥偑憡嶦偝傟偰嵎偟堷偒僛儘偲側傞乿偲傾儊儕僇偺怱棟妛幰僥儗儞僗丒倂丒僉儍儞儀儖
偼弎傋偰偄傞丅(p.23)
仧梷埑偝傟偨僪儔僂儅偑傕偲偱惛恄忈奞偑堷偒婲偙偝傟傞---僒僀僐僗儕儔乕側偳偱偼傛偔偁傞偙偲偩偑---側偳偲偄偆偙偲偼丆傑偢愨懳偵側偄偲尵偭偰娫堘偄側偄丅(p.79)
仧偁傞柸枾側暘愅寢壥偵傛傟偽丆帺暘偑庴偗偨媠懸偺崷傒傪傢偑巕偱乽惏傜偡乿恖偼嶰暘偺堦偟偐偄側偄丆偁偲偺嶰暘偺僯偼壠掚偺巆崜側乽揱摑乿傪堷偒宲偑側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅(p.103)
仧乽懡廳恖奿側偳偲偄偆傕偺偼懚嵼偟側偄乿偲傾儊儕僇偺怱棟妛幰偱壢妛僕儍乕僫儕僗僩偺儘僶乕僩丒A丒儀乕僇乕偼弎傋偰偄傞丅乽徻偟偔暘愅偝傟偨徢椺偼偡傋偰丆帯椕幰偺傗傜偣偩偭偨偲敾柧偟偰偄傞乿
亂巹偺僐儊儞僩亃
俀侽悽婭偺俀戝尪憐偼乽儅儖僋僗庡媊乿偲乽僼儘僀僩偺惛恄暘愅乿偱偁傞偲偄偆丅嵟嬤丆惛恄暘愅偺婙怓偑埆偄丅傾儊儕僇偺堛妛奅偱偼乽恄宱徢乿偲偄偆尵梩偑巊傢傟側偔側偭偨偲暦偔丅惛恄暘愅傗怱棟椕朄偱偼側偐側偐帯傜側偐偭偨姵幰偑丆僾儘僓僢僋傪張曽偡傞偲傑偨偨偔傑偵帯偭偨側偳偲偄偆偙偲偑懕弌偟偰丆惛恄暘愅傊偺怣棅偑敄傜偄偱偄傞偲偄偆丅偦傕偦傕尰嵼偁傞惛恄偺堎忢偑丆梷埑偝傟偨夁嫀偵尨場偑偁傞偲偡傞偺偼偁偔傑偱堦偮偺棟榑偱偁傝丆廫暘側専徹偑昁梫偱偁偭偨偼偢偩丅巹傕尰幚偼傕偭偲 physical 側傕偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄偨丅偙偺杮偼丆変乆偺帩偭偰偄傞條乆側乽忢幆乿傪師乆偲偔偮偑偊偡丅椪巰懱尡偡傜丆偦偺偡傋偰偑懁摢梩傊偺巋寖偱嵞尰偱偒傞偲偄偆丅偄偢傟偵偣傛丆偳傫側棟榑偱偁傠偆偲傕乽斀徹壜擻惈乿偺側偄棟榑偼媈偭偰偐偐傟偲偄偆偙偲偩傠偆丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏侽
亂杮暥偐傜亃
仧夅偵巋偝傟傞偲偐備偄偺偼丆扨偵崺拵偺偄傗傜偟偝偲偄偆偩偗側偺偩傠偆偐丅偦傟偼丆巹偨偪偺寣塼偑妋幚偵棳傟懕偗傞傛偆偵偡傞偨傔偵夅偑巊偭偰偄傞壔妛暔幙偺嬼慠偺寢壥偱偁傞偩偗側偺偐傕偟傟側偄偑丆偦傟偼丆傑偨丆彨棃丆傑偨夅偵巋偝傟側偄傛偆偡傞偨傔偺巹偨偪偺揔墳側偺偐傕偟傟側偄丅夅偵巋偝傟傞偺傪傑偭偨偔婥偵偐偗側偄恖偑偄偨傜偳偆側傞偐丆憐憸偟偰傎偟偄丅偦偟偰丆夅偵巋偝傟偨偙偲偵婥偯偐側偄傛偆偩偭偨側傜丆夅偑偳傟傎偳惉岟偡傞偐丆憐憸偟偰傎偟偄両(p.50)
仧巆擮側偑傜丆恖乆偺婥暘傪傛偔偝偣傞偙偲偼丆昁偢偟傕寬峃傪岦忋偝偣丆懠偺挿婜揑側棙塿傪妋曐偡傞傕偺偱偼側偄丅乮棯乯帺慠搼懣偵偼丆恖娫傪岾偣偵偟傛偆偲偡傞偮傕傝偼側偔丆挿婜偵尒偨巹偨偪偺棙塿偵丆寵側宱尡偑栶棫偭偰偄傞偙偲偑傛偔偁傞丅徢忬偑弌傞偺傪梷偊傞慜偵丆偦偺婲尮偲偳傫側婡擻偑偁傞偺偐傪傑偢棟夝偡傞傛偆偵帋傒傞傋偒偩丅
仧傕偟恑壔偑尗柧側寁夋傪傕偲偵恑傫偱偄偔傕偺偩偭偨側傜偽丆怴偟偄屇媧僔僗僥儉偼弶傔偐傜愝寁偟捈偝傟偨丆尗柧側僔僗僥儉偵側偭偨偱偁傠偆丅偟偐偟丆恑壔偼尗柧側寁夋傪棫偰側偄丅偦傟偼忢偵丆偡偱偵偁傞傕偺傪傢偢偐偽偐傝偵廋惓偟偰恑傓偺偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偼嵟嬤惗傑傟偨偽偐傝偺乽僟乕僂傿儞堛妛乮恑壔堛妛乯乿偵偮偄偰彂偐傟偨弶傔偰偺奣愢彂偱偁傞丅偙傟傑偱偺堛妛傪恑壔榑偺棫応偐傜尒捈偦偆偲偄偆怴偟偄敪憐偱偁傞丅尦棃寵側傕偺丆梷偊傞傋偒傕偺偲峫偊傜傟偰偒偨敪擬傗偔偟傖傒側偳偑丆幚偼変乆偑恑壔偺拞偱妉摼偟偰偒偨杊塹愴棯偱偁傞偙偲偑傢偐偭偰偒偨丅偦傕偦傕乽昦婥偼側偤丆偁傞偺偐(尨戣偼"Why We Get Sick")乿丅屄懱傪巰偵捛偄傗傞傛偆側昦婥偼丆摉慠丆恑壔偺夁掱偱搼懣偝偣傞偼偢偱偼側偐偭偨偺偐丠偄傗媡偵丆恑壔偺嫞憟傪彑偪敳偄偰偒偨偐傜偵偼偳傫側婖傓傋偒昦婥偵傕壗傜偐偺懚嵼堄媊乮恑壔忋偺棙揰乯偑偁偭偨偺偱偼側偄偐丅偙偺杮偼昦婥偲偄偆傕偺傪壗壄擭偲偄偆恑壔偺夁掱偺拞偐傜尒捈偦偆偲偄偆旕忢偵嫽枴怺偄峫偊曽偐傜彂偐傟偰偄傞丅
偨偩傆偲巚偭偨偺偩偑丆偙偺杮偺朚戣偼乽扤偑偨傔偵忇偼柭傞乿揑岆傝傪斊偟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅僿儈儞僌僂僃僀偺"For Whom The Bell Tolls"偺Whom偼媈栤帉偱偼側偔娭學戙柤帉偱偁傝丆暥帤捠傝偵栿偣偽乽忇偑柭傝傢偨傞恖乿偱偁傞丅偙偺杮偺尨戣偺"Why We Get Sick"傕媈栤暥偱偼側偄丅媈栤暥側傜"Why Do We Get Sick?"偲側傞偐傜偩丅偙偺Why偼娭學戙柤帉偱丆the reason why 偺抁弅宍偲峫偊傜傟傞丅偩偐傜乽巹偨偪偑昦婥偵側傞棟桼乿偲偄偆偺偑傛傝尨戣偵懄偟偨傕偺偩傠偆丅傕偭偲傕丆撉幰偺拲堄傪堷偔偐偲偄偆尒塰偊偺揰偐傜尵偊偽丆僿儈儞僌僂僃僀偺応崌傕偙偺杮偺応崌傕崱偺傑傑偺曽偑偄偄偺偐傕偟傟側偄丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾俀丏俀
亂杮暥偐傜亃
仧僷僂儘偺搘椡偼側偤幚偭偨偺偩傠偆偐丠(棯)僷僂儘偑偦偺屻廫擇擭娫偵曕偄偨嫍棧偼擇枩僉儘偵媦傫偩丅偟偐偟斵偼儔儞僟儉偵曕偒夞偭偨傢偗偱偼側偄丅僉儕僗僩嫵偑傕偭偲傕岠棪傛偔夎惗偊丆峀偑傞傛偆側丆恖暔丆応強丆戝偒側僐儈儏僯僥傿乕傪朘傟偨偺偱偁傞丅恄妛偲幮夛揑僱僢僩儚乕僋偺椉曽傪岠壥揑偵妶梡偟偨僷僂儘偼丆僉儕僗僩嫵偺嵟弶偵偟偰嵟戝偺僙乕儖僗儅儞偩偭偨丅
仧廂塿偺俉侽僷乕僙儞僩偼廬嬈堳偺俀侽僷乕僙儞僩偑偁偘偰偄傞丅乮棯乯斊嵾偺俉侽僷乕僙儞僩偼丆斊嵾幰偺俀侽僷乕僙儞僩偑斊偟偰偄傞丆側偳偲丅俉侽懳俀侽偺朄懃偼丆傒側摨偠偙偲傪弎傋偰偄傞偵偡偓側偄丅梫偡傞偵丆傢傟傢傟偑傗傞偙偲偺屲暘偺巐偵偼堄枴偑側偄偲偄偆偙偲偩丅
仧僴僽偼丆儅乕働僥傿儞僌偺悽奅偱偼乽僆僺僯僆儞丒儕乕僟乕乿丆乽僷儚僼儖儐乕僓乕乿丆乽僀儞僼儖僄儞僒乕乿側偳偲屇偽傟丆暯嬒揑側恖偨偪偵斾傋偰惢昳偵偮偄偰偺忣曬岎姺傪妶敪偵峴偭偰偄傞丅偙偆偄偆恖偨偪偼丆柍悢偺幮夛揑儕儞僋傪棙梡偟偰妚怴幰偺峴摦偵偄偪憗偔栚傪偮偗丆帺暘傪偦傟傪嵦梡偡傞丅僴僽帺恎偑妚怴幰偱偁傞昁梫偼側偄偗傟偳傕丆斵傜偵嵦梡偟偰傕傜偊傞偐偳偆偐偼丆傾僀僨傿傾傗怴婡幉偑晛媦偡傞偐偳偆偐偺戝偒側尞偵側傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
僱僢僩儚乕僋棟榑偼僆僀儔乕偵巒傑傞丅僄儖僨僔儏亖儗乕僯僀偨偪偑偦傟傪敪揥偝偣偨偑丆斵傜偺棟榑偱偼僱僢僩儚乕僋偺悽奅偼暯嬒揑偱儔儞僟儉偱偁傞偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅傎偲傫偳偺僲乕僪偑暯嬒揑側悢偺儕儞僋傪挘偭偰偄傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅挊幰偼僀儞僞乕僱僢僩偺悽奅偱偼彮悢偺乽僴僽乮旕忢偵懡偔偺儕儞僋傪偼偭偰偄傞傕偺乯乿偲戝懡悢偺僲乕僪乮偁傑傝懠偐傜偺傾僋僙僗偑側偄儂乕儉儁乕僕乯偐傜惉傝棫偭偰偍傝丆偙傟偼僀儞僞乕僱僢僩偵尷傜偢丆幮夛偵偍偗傞僸儏乕儅儞僱僢僩儚乕僋側偳偵傕尵偊傞偲榑偠偰偄傞丅抧曽偺嬻峘偑暵嵔偝傟偰傕慡懱偵戝偒側曄壔偼梌偊側偄偑丆娭惣嬻峘傗惉揷嬻峘偑暵嵔偝傟傞偲擔杮慡懱偺嬻偺曋偑杻醿偡傞丅娭嬻傗惉揷偼堦斒偺嬻峘偵斾傋偰偼傞偐偵懡偔偺儕儞僋傪帩偭偰偄傞偐傜偱偁傞丅摉偨傝慜偺偙偲偱偼偁傞偑丆夵傔偰偄傢傟傞偲擺摼偟偰偟傑偆丅偙偺杮偼條乆側峫偊曽偵墳梡偱偒偦偆偩丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俋
亂杮暥偐傜亃
仧婭尦慜俆俈侽擭偺愄丆僋僙僲僼傽僱僗偑儂儊儘僗偺彇帠帊傪旕擄偟偨偺傕丆恄乆傪恖娫偺傛偆偵埖偭偰偄傞偲偄偆棟桼偩偭偨丅傕偟攏偵奊怱偑偁傟偽丆斵傜偺昤偔恄偼攏偦偭偔傝偩傠偆丆偲僋僙僲僼傽僱僗偼潏潐偟偨丅(p.37)
仧恑壔偵娭偡傞(僐儞儔乕僩丒乯儘乕儗儞僣偺奣擮偵偼偄傠偄傠側儗僢僥儖偑揬傜傟偰偄傞偑丆偦傟埲忋偵巹偑偮傜偄偺偼丆斵偑彂偄偨柉懓嵎暿揑側暥復偱偁傞丅偁傟傎偳摦暔偵垽忣傪拲偄偩恖偑丆側偤偦偺垽傪恖娫偵岦偗傜傟側偐偭偨偺偐丠丂儘乕儗儞僣偼丆壠抺壔偲摨偠偔暥柧傕帺慠偺懧棊偲峫偊偨丅偦偺寢壥丆暥柧偵懳偡傞嵟戝婯柾偺堦寕偑峴傢傟傛偆偲偟偰偄傞偲偒丆壩偵桘傪拲偄偱偟傑偭偨丅恖娫儘乕儗儞僣偲壢妛幰儘乕儗儞僣傪暘偗傞偙偲偼晄壜擻側偺偱丆巹帺恎偑斵偵書偔暋嶨側姶忣傕怳傝暐偆偙偲偼偱偒側偄丅(p.108)
仧偦傟偵偟偰傕丆儂乕儖僗僥僢僪偼側偤偙偙傑偱柍楃側怳傞傑偄偵偱偨偺偐丠側偤帺暘偺崙偵婣偭偰偡偖丆崱惣偺尒夝偺傒側傜偢擔杮暥壔慡懱傪偙偒偍傠偡榑暥傪彂偄偨偺偐丠偁偘偔偵亀僱僀僠儍乕亁傑偱偑偦偺榑暥傪宖嵹偟丆乽崱惣嬔巌偺挊嶌偑擔杮偱崅偄恖婥傪屩偭偰偄傞帠幚偼丆擔杮幮夛傊偺嫽枴怺偄摯嶡偲側傞偺偐丠乿偲偄偆懢屰帩偪揑側尒弌偟傪偮偗偨偺偼側偤偐丠堦楢偺偱偒偛偲偑摯嶡傪梌偊偰偔傟傞偲偟偨傜丆偦傟偼儂乕儖僗僥僢僪偺惈奿偵偮偄偰偩傠偆丅
仧崱惣嬔巌偼丆挿庻偺摦暔傪僼傿乕儖僪偱娤嶡偡傞偡傋偰偺尋媶幰偐傜丆恠偒偣偸姶幱偺擮傪曺偘傜傟偰偟偐傞傋偒偩丅側偤側傜斵偼娤嶡偵桳岠側偨偭偨傂偲偮偺傾僾儘乕僠偺庬傪傑偄偨恖暔偩偐傜偩丅偦偺攚宨偵偼丆搶梞揑側廤抍廳帇偺峫偊曽偲丆屄懱偺傾僀僨儞僥傿僥傿傪懜廳偡傞巔惃偑偁偭偨丅偟偐偟偄偭傐偆偱丆崱惣偼僟乕僂傿儞恑壔榑偺榞慻傒偑帩偮椡傪寉帇偡傞偐丆岆夝偟偰偍傝丆偦傟備偊昁梫偲偝傟偰偄偨曄壔傪朩偘偰偟傑偭偨丅(p.122)
亂巹偺僐儊儞僩亃
挊幰偼僆儔儞僟恖偺摦暔峴摦妛幰丅崱惣嬔巌偵偮偄偰偼偦偺棟榑偵偮偄偰偼摨堄偱偒側偄偑側傜傕丆僒儖偺屄懱偵柤慜傪偮偗偰偦偺峴摦傪娤嶡偡傞偲偄偆庤朄偼崱惣偵偼偠傑傞偲偟偰惓偟偔昡壙偟偰偄傞丅
1985擭儊僉僔僐戝抧恔偺嵺丆姠釯偺壓偐傜惗懚幰傪敪尒偡傞偨傔偵摥偄偰偄偨僕儍乕儅儞丒僔僃僷乕僪偨偪偑丆偔傞擔傕偔傞擔傕巰懱偽偐傝偑偱偰偔傞偺偱丆傒傞傒傞傗傞婥傪幐偄丆偮偄偵偼怘帠傕怘傋側偔側偭偰偟傑偭偨丅偦偙偱媬彆戉偺堦恖偑堦寁傪埬偠偰丆乽惗懚幰乿傪憰偄姠釯偺壓偵塀傟偨丅偦傟傪媬彆將偑乽敪尒乿偡傞偲丆斵傜偼慡恎偱婌傃傪昞尰偟丆偦偺屻夆慠傗傞婥偑弌偰偒偨偲偄偆丅晛捠丆摦暔偼乽偛傎偆傃乿傪栚揑偵寍傪墘偠傞偺偱偁傝丆帺暘偺傗偭偰偄傞峴摦偑偳偆偄偆堄枴傪帩偮偐偼棟夝偟偰偄側偄丅偟偐偟丆偙偺將偨偪偼丆乽惗偒偨恖娫傪彆偗傞乿偲偄偆帺傜偺栚揑傪柧傜偐偵棟夝偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟偨丅杮彂偵偼偙偺傛偆側嫽枴怺偄僄僺僜乕僪傕惙傝崬傑傟偰偄傞丅嫵偊傜傟傞偲偙傠偺懡偄杮偱偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侾丏係
亂杮暥偐傜亃
仧悢昐慻偺憃巕偵偮偄偰尋媶偟偨僩儅僗丒J丒僽僠儍乕僪丒僕儏僯傾偲拠娫偺尋媶幰偼丆暿乆偵堢偰傜傟偨堦棏惈憃惗帣偼偲傕偵堢偭偨堦棏惈憃惗帣偲摨偠偔傜偄傛偔帡偰偄傞偲偄偆寢榑傪弌偟偨丅偙偺尋媶偺徴寕偼戝偒偔丆侾俋俉俉擭偵敪昞偝傟偨偲偒偵偼丆怣偠傜傟側偄偲抐尵偟偨恖乆傕偄偨丅堦搙傕夛偭偨偙偲偑側偄偺偵丆摨偠壠掚偱堢偭偨孼掜巓枀偺傛偆偵傛偔帡偰傞側傫偰偁傝偊側偄丆偲巚傢傟偨偐傜偩丅偩偑丆帠幚偼嫮椡偩偭偨丅堚揱巕偼恖偺恎懱偮偒傗梕杄傪寛傔傞偺偵椡偑偁傞偩偗偱側偔丆偳偆峴摦偟丆姶偠丆偳傫側恖惗宱尡傪偡傞偐傑偱塭嬁傪媦傏偡偙偲偑帵偝傟偨偺偱偁傞丅尋媶幰偼丆惗傑傟偑堢偪傪椊夗偟偰偄傞働乕僗傪偮偓偮偓偵敪尒偟偨丅
仧償傽乕僕僯傾戝妛偱俈嵨偺憃巕俁俆侽慻傪挷傋偨尋媶偱偼丆撪婥丆壈昦丆梷惂揑側峴摦偺俆侽僷乕僙儞僩偼堚揱偩偲悇寁偝傟偰偄傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
僇僢僐僂偵偼戯棏偲偄偆峴摦偑偁傞丅懠偺捁偺憙偵帺暘偺棏傪嶻傒偮偗偰堢偰偝偣傞偺偩丅偟偐傕丆嬃偔傋偒偙偲偵偙偺棏偼杮棃偺捁偺棏傛傝悢擔偼傗偔偐偊偭偰丆傑偩栚傕奐偄偰偄側偄僇僢僐僂偺悧偑偦偽偵偁傞偡傋偰偺棏傪憙偐傜棊偲偟偰偟傑偆偺偩丅偙偆偟偨峴堊偼悧偑扤偐傜傕妛傫偩傕偺偱偼側偔丆堚揱揑偵僾儘僌儔儉偝傟偰偄傞傕偺偱偁傞丅偦偆偱偁傞側傜丆恖娫偲偰傕帺暘偺敾抐偱峴偭偰偄傞偲巚偭偰偄傞峴堊偑幚偼堚揱揑偵僾儘僌儔儉偝傟偰偄傞傕偺傪扨偵幚峴偟偰偄傞偵夁偓側偄偙偲傕偁傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偦傟偑偙偺杮傪撉傫偱傑偡傑偡妋怣偡傞傛偆偵側偭偨丅
挊幰偺堦恖僿僀儅乕偼暘巕堚揱妛偺僷僀僆僯傾丅侾俋俁俁擭偵乽僎僀堚揱巕乿傪敪尒偟榖戣偲側偭偨丅乽巵偐堢偪偐乿偲偄偆偙偲偵偮偄偰偺挊幰偺夞摎偼乽偳偪傜傕乿偲偄偆堦斒揑側寢榑側偺偱偼偁傞偑丆偳偪傜偐偲偄偆偲乽巵乮堚揱乯乿偺曽偵傗傗僶僀傾僗偑偐偐偭偰偄傞丅偨偩堦偮婥偵側偭偨偺偼丆僗僥傿乕僽儞丒俰丒僌乕儖僪偑偁傟傎偳斸敾偟偨乽僗僺傾儅儞偺g (恖娫偵偼憤崌揑側擻椡偺傕偺偝偟偱偁傞g 場巕偑偁傞偲偄偆愢乯乿偺懚嵼傪峬掕偟偰偄傞偲偄偆揰偱偁傞丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俋
亂杮暥偐傜亃
丂
仧廵偺怱憻晹偱偁傞敪壩憰抲傪峔惉偡傞俆侽屄偺晹昳丆偦傟傜偲宍忬悺朄偑悺暘堘傢偢摨堦偱偁傞傛偆偵傕偆侾僙僢僩惢嶌偡傞丅偦偆偡傟偽丆嵟弶偺僙僢僩偲傕偆堦偮偺僙僢僩偲懳墳偡傞晹昳傪帺桼偵岎姺偟偰傕丆敪壩憰抲傪摨偠傛偆偵慻傒棫偰傞偙偲偑偱偒傞丅偙傟偑屳姺惈晹昳偺堄枴偱偁傞丅侾俉悽婭枛偵惗偒偰偄傞乮僩乕儅僗丒乯僕僃僼傽乕僜儞偵偲偭偰丆偙傫側摿挜傪傕偮廵側偳尒偨偙偲傕暦偄偨偙偲傕側偐偭偨丅偙傟偱廋棟偑旕忢偵梕堈偵側傞丅斵偼偦偆捈娤偟偨丅
仧庬巕搰斔庡偺庬巕搰帪嬆(僩僉僞僇)偼抌栬怑恖偺敧嶁嬥暫塹偵丆億儖僩僈儖恖偐傜憽傜傟偨壩撽廵偺柾憿傪柦偠偨丅嬥暫塹偼摏側偳偼嶌傞偙偲偑偱偒偨偑丆廵旜偺旜愷偲傛偽傟傞僱僕偺嶌傝曽偑傢偐傜側偄丅儃儖僩偺栶妱傪壥偨偡梇僱僕偵偮偄偰偼側傫偲偐嶌傟偰傕丆僫僢僩偺栶妱傪壥偨偡廵旜偺帗僱僕偺嶌傝曽偼尒摉傕偮偐側偐偭偨丅
仧乮僉乕儃乕僪偺乯俻倂俤俼俿倄攝楍偼丆揟宆揑側僨僼傽僋僩丒僗僞儞僟乕僪偱偁傞丅乮棯乯儗儈儞僩儞幮偵傛偭偰屳姺惈媄弍偵婎偄偰惢憿偝傟偨俻倂俤俼俿倄幃僞僀僾儔僀僞乕偼丆懡偔攧傟傞偙偲偵傛偭偰偝傜偵埨偔側偭偰偄偔丅偙偆偟偰俻倂俤俼俿倄幃偺僞僀僾儔僀僞乕偑晛媦偟丆偦偺傛偆側僞僀僾儔僀僞乕傪桳偡傞婇嬈偺悢偑憹偊傞偲丆偦偺僉乕攝楍偺懪偪曽偵姷傟傛偆偲偡傞僞僀僺僗僩偺悢傕憹偊偰偄偔丅弶婜偵偼懠偺攝楍傕偁偭偨偑丆儗儈儞僩儞幮偺僞僀僾偑巗応傪巟攝偟丆俻倂俤俼俿倄攝楍傪慖傇僞僀僺僗僩偑憹偊偨偙偲偱搼懣偝傟偰偟傑偭偨丅偙偆偟偰俻倂俤俼俿倄幃偼乽帠幚忋偺昗弨乿偵偺偟忋偑偭偨傢偗偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
崱擭(2002擭)偮偄偵僜僯乕偼儀乕僞偺價僨僆僥乕僾偺惢憿傪拞巭偟偨偲偄偆僯儏乕僗傪暦偄偨帪丆偊偭傑偩嶌偭偰偄偨偺丠偲巚偭偨丅
巗応偵兝偲倁俫俽偺椉曽偑暲傫偱偄偨摉帪丆巹偼柪傢偢兝傪慖傫偩丅摉帪偲偟偰偼寢峔側抣抜偱兝儅僢僋僗偺價僨僆婡婍傪攦偭偨偺偱偁傞丅僆乕僾儞儕乕儖偐傜僇僙僢僩僥乕僾傊偺堏峴偑帵偟偰偄傞傛偆偵丆悽偺拞偼傛傝彫偝偄傕偺傊偲摦偄偰偄傞丅兝偼倁俫俽傛傝彫偝偄丅偦傟偵壗偟傠僜僯乕偱偁傞丅壒幙傕傛偄丅偙傟偑攧傟側偄傢偗偼側偄偲巚偭偨偺偩丅偲偙傠偑偁偵偼偐傜傫傗丆倁俫俽偺彑棙偲側偭偨偺偼偛傜傫偺捠傝偩丅倁俫俽偑帠幚忋偺昗弨乮僨僼傽僋僩丒僗僞儞僟乕僪乯偲側偭偨偺偩丅嵟弶偼傎傫偺偝偝偄側嵎偱偁偭偨傕偺偑丆傗偑偰偼傂偭偔傝曉偡偙偲偺偱偒側偄嵎偵側偭偰偟傑偆丅偙傟偑僨僼傽僋僩丒僗僞儞僟乕僪偺晐偄偲偙傠偩丅俻倂俤俼俿倄偼傢偞偲僞僀僾偺僗僺乕僪傪棊偲偡傛偆側攝楍偱偁傝丆僪儃儔僋幃偺曽偑擇攞埲忋偺僗僺乕僪偱懪偰傞偙偲偑傢偐偭偰偄傞丅偟偐偟丆偦傟偑晛媦偟側偄丅偄偭偨傫恎偵晅偗偰偟傑偆偲恖偼偝傜偵暿偺僉乕攝楍傪妎偊傞婥偑偟側偔側傞傕偺偱偁傞丅堦懢榊攈偑偄偮傑偱傕堦懢榊僼傽儞偱偁傞偺傕摨偠偩丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏俉
亂杮暥偐傜亃
丂
仧乽媡曽岦峴偒偺僶僗偽偐傝懡偔棃傞乿偲偄偆傛偆偵姶偠傞偙偲偼丆惓偺偱偒偛偲偲晧偺偱偒偛偲偺旕懳徧惈偲偄偆娤揰偐傜偼丆摿偵嫽枴怺偄丅晧偺偱偒偛偲偼丆惓偺偱偒偛偲偲堘偭偰丆拁愊偝傟堈偄偲偄偆惈幙偑偁傞丅媡曽岦峴偒偺僶僗偺曽偑懡偄傛偆偵姶偠偰偟傑偆偺偼丆尰偵丆帺暘偺峴偒偨偄曽岦傊峴偔僶僗偑侾戜棃傞傑偱偺娫偵丆媡曽岦峴偒偺僶僗偑偨偔偝傫棃傞偺傪尒傞偙偲偑懡偄偐傜偱偁傞丅偙偺媡偼寛偟偰婲偙傜側偄丅媡曽岦峴偒偺僶僗偑侾戜棃傞娫偵丆帺暘偺峴偒偨偄曽岦偺僶僗偑壗戜傕棃傞偺傪尒傞偙偲偼偁傝偊側偄丅側偤側傜丆帺暘偺峴偒偨偄曽岦峴偒偺僶僗偑侾戜棃傟偽丆偦傟偵忔偭偰偟傑偆偐傜偱偁傞丅偙偆偟偨旕懳徧惈偺偨傔偵丆巹偨偪偼乽埆偄偙偲偺楢懕乿傪偟偽偟偽宱尡偡傞偙偲偼偁偭偰傕丆椙偄偙偲傪摨偠傛偆偵楢懕偟偰宱尡偡傞偙偲偼側偄丅偲偙傠偑丆偙偺帠幚偵婥偯偐側偄偱偄傞偲丆傑傞偱悽偺拞偼帺暘偵椻崜偵偱偒偰偄傞偐偺傛偆偵姶偠傜傟偰偟傑偆偺偱偁傞丅乮p.111)
仧僥儗價側偳偺僯儏乕僗丒儊僨傿傾偼丆庢傝忋偘偨栤戣偺廳戝偝傪傾僺乕儖偡傞偨傔偵丆偦偺栤戣偵嬯偟傓恖乆偺惗乆偟偄徹尵傪棙梡偡傞丅偙偆偟偨庤朄偼丆帇挳幰偵丆帺暘偑摨偠傛偆側嫬嬾偵抲偐傟偨傜偳偆側傞偐傪憐憸偝偣傞偨傔偵偒傢傔偰桳岠偱偁傞丅偦偆偟偨嫬嬾偵嬯偟傓恖乆傊偺摨忣怱傕桸偒傗偡偄丅偟偐偟側偑傜丆偦偆偟偨栤戣偑偳偺掱搙恖乆偺娫偵峀偑偭偰偄傞偐傪抦傞忋偱丆斵傜傊偺摨忣偼娭學側偄偼偢偱偁傞丅乮棯乯偳傫側偵姶摦揑側徹尵偱偁偭偰傕丆偦傟偼丆偦偺恖傂偲傝偺宱尡傪弎傋偨傕偺偵偡偓側偄丅乮p.183)
仧偁傞傾儅僠儏傾攐桪偑偨傑偨傑椃峴拞偵儘儞僪儞偺寑応偵擖偭偰丆崅峑帪戙偺墘寑晹偺屭栤偺愭惗偵偽偭偨傝弌夛偭偨偲偡傞丅側傫偲傕晄巚媍側嬼慠偺弌夛偄偱偁傞丅偩偑丆寑応偱弌夛偭偨偺偑崅峑帪戙偺墘寑偺嫟墘幰偱偁偭偨偲偟偰傕摨條偵晄巚媍側嬼慠偲姶偠傜傟傞偱偁傠偆偟丆戙栶幰偱偁偭偨偲偟偰傕摨條偱偁傞丅傑偨丆弌夛偭偨搒巗偑丆儘儞僪儞偱側偔丆傾僥僱偱偁偭偰傕丆僷儕偱偁偭偰傕丆儘乕儅偱偁偭偰傕摨偠偙偲偱偁傞丅偝傜偵偼丆弌夛偭偨応強傕丆寑応偱偼側偔丆僆儁儔僴僂僗偱傕丆攷暔娰偱傕丆堸傒壆偱傕丆摨偠傛偆偵晄巚媍側嬼慠偺弌夛偄偲姶偠傜傟偨偵堘偄側偄丅
偙偺傛偆偵彮偟椻惷偵峫偊偰傒傟偽丆偦傟偧傟偺嬼慠偑惗偠傞妋棪偼妋偐偵彫偝偄偐傕抦傟側偄偑丆偦傟偧傟偺妋棪偺榓廤崌偼偐側傝崅偄傕偺偱偁傞偙偲偑傢偐傞偼偢偱偁傞丅偦傟偵傕偐偐傢傜偢丆晄巚媍側嬼慠偑廳側偭偨偲偒偵丆摨條偺偱偒偛偲偺偡傋偰偺榓廤崌偱偼側偔丆偦偺愊廤崌偺曽傪昡壙偟偰偟傑偆捈娤揑孹岦偑偁傞偨傔偵丆巹偨偪偼傃偭偔傝偟偰偟傑偆偺偱偁傞丅(p.300)
亂巹偺僐儊儞僩亃
椺偊偽巹偑偁傞擔偺屵屻丆嫵幒偱惗搆偵嫵壢彂偵弌偰偒偨儌儞僔儘僠儑僂偺榖傪偟偰偄偨偲偡傞丅偡傞偲丆撍慠憢偐傜儌儞僔儘僠儑僂偑僸儔僸儔偲旘傫偱偒偰巹偑庤偵偟偰偄傞嫵壢彂偺愭偵巭傑偭偨偲偡傞丅偙偺嬼慠傪堦懱偳偆愢柧偡傟偽傛偄偺偐丅儐儞僌偼偙偆偟偨嬼慠傪乽嫟帪惈乿偲屇傃丆慡偔偺嬼慠偲偼峫偊側偐偭偨丅偙偺擇偮偺弌棃帠偵偼側傫傜偐偺娭楢傪姶偠偰偄偨偺偱偁傞丅
杮彂偼偙偆偟偨懺搙偲偼慡偔暿偺棫応偵棫偮丅昅幰偼乽嫟帪惈乿側偳偼擣傔側偄丅堦尒丆偨偄傊傫側嬼慠偲巚偊傞傕偺偑丆幚偼偐側傝婲偙傞妋棪偺崅偄傕偺偱偁偭偨傝丆柍堄幆偵帺暘偺搒崌偺偄偄傛偆偵夝庍偟偰偟傑偆孹岦傪懡悢偺椺傪偁偑偰巜揈偡傞丅尨戣偼 How We Know What Isn't So. ---The Fallibility of Human Reason in Everyday Life. 乽偦偆偱側偄偙偲傪偳偺傛偆偵偟偰抦傞偐---恖娫偺棟惈偺婋偆偝乿偱偁傞丅偦偆偄偊偽乽壗偲偐偺備傜偓乿側傫偰杮偑偁偭偨丅巹傕堦帪朢偟偄棟惈偑彮偟偱偼偁傞偑備傜偓偦偆偵側偭偨偑丆俽偲偄偆恖暔偑幚偼僀儞僠僉杺弍巘偱偁傝丆戝曄偄偐偑傢偟偄抝偱偁傞偙偲傪暿偺杮偱抦傝丆乽愻擼乿偐傜媬傢傟偨丅偁傇側偄丆偁傇側偄丅
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏俋
亂杮暥偐傜亃
丂
仧傕偟傕丆晠偭偨棏偑寵側擋偄傪敪偟丆慻怐偑彎偮偔偲捝傒偑偐偠傜傟丆嵒摐偼娒偄偺偩偲偡傞偲丆偦傟偼棸壔悈慺僈僗偑寵側擋偄傪帩偭偰偄傞偐傜偱偼側偔丆旂晢偵恓偑撍偒巋偝偭偨偲偒丆偦偙偐傜捝傒偑夝偒曻偨傟傞偐傜偱偼側偔丆嵒摐暘巕偺懏惈偑娒偄偐傜側偺偱偼側偄丅偦偆偱偼側偔偰丆恖娫偺擼偑丆堚揱巕偺懚懕偵偲偭偰桳棙偱偁偭偨傝晄棙偱偁偭偨傝偡傞偙偺悽偺弌棃帠偵偮偄偰丆堦斒揑側夣姶傗晄夣姶傪宍惉偱偒傞傛偆側恄宱慻怐傪恑壔偝偣偰偒偨偐傜側偺偩丅(P.26)
仧娒偝偼嵒摐暘巕偺惈幙側偺偱偼側偄丅偦傟偼丆恑壔偱惗偠偨擼偺憂敪揑惈幙側偺偩丅偙傫側姶妎偑婲偙傞偲丆偦傟偑惗暔妛揑偵偳傟傎偳廳梫偐棟夝偟偰偄側偔偰傕丆偦偺恑壔揑側婲尮傪抦傜側偔偰傕丆偙偺姶妎傪惗偠偝偣偨弌棃帠傪偨偩偪偵昡壙偡傞偙偲偵側傞丅(P.27)
仧偨偄偰偄偺恖偼丆悽奅偼岝傗怓傗壒傗娒偄枴傗寵側擋偄傗廥偄傕偺傗旤偟偄傕偺偵枮偪偁傆傟偰偄傞偲巚偭偰偄傞偑丆偦傟偼娫堘偄側偔丆戝偄側傞尪憐偱偁傞丅妋偐偵偙偺悽奅偼丆揹帴攇傗嬻婥偺埑椡傗丆悈傗嬻婥偵夝偗偨壔妛暔幙偵枮偪偁傆傟偰偄傞偑丆惗暔偺偄側偄悽奅偼丆恀偭埫偱壒傕側偔丆枴傕側偔丆擋偄傕側偄丅偡傋偰偺堄幆揑宱尡偼丆惗暔妛揑側擼偺憂敪揑惈幙偱偁傝丆偙偺擼偺奜晹偵偼懚嵼偟側偄丅(P.269)
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偼嵒摐偑娒偄偐傜娒偔姶偠丆儅儕儕儞丒儌儞儘乕偼僫僀僗儃僨傿偩偐傜僙僋僔乕側偺偩偲巚偭偰偄偨丅偟偐偟丆偦傟偼偡傋偰尪憐偩偲偄偆偺偩丅偙傟偼壗傕斾歡揑側堄枴偱尵偭偰偄傞偺偱偼側偔丆暥帤捠傝偺堄枴偱偄偭偰偄傞偺偩丅変乆偼摿掕偺揹帴攇傪愒傗椢偵姶偠偰偄傞偑丆幚偼偙偺椉幰偺嵎偼侾俆侽侽壄暘偺侾儊乕僩儖偲偄偆攇挿偺堘偄偵懠側傜側偄丅偙傟偼傎偲傫偳摨偠偲偄偭偰偄偄丅偟偐偟丆恖娫偼偦偺嵎傪嬫暿偡傞傛偆偵恑壔偟偰偒偨偺偩丅変乆偼惗懚偵桳棙側傕偺傪乽慖戰揑乿偵怓丒擋偄丒壒偲偟偰乽姶偠偰乿偄傞偺偩丅幚嵺偺悽奅偼偨偩埮偱偁傝丆枴傕擋偄傕側偄丅偡傋偰偑恑壔偺夁掱偱妉摼偝傟丆変乆偺擼偺拞偱偺傒姶偠傞傕偺偱偁傞丅
巹偼埲忋偺帠幚傪抦傝丆湵慠偲偟偨丅摉偨傝慜偱偁偭偨偙偲偑幚偼摉偨傝慜偱偼側偐偭偨丅偍傕傢偢丆懅傪偺傓傛偆側尰幚偱偁傞丅傗傗戝偘偝偵尵偊偽悽奅娤偑曄傢傞杮偱偁傞丅
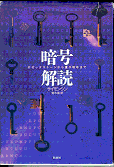 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏係
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏係
亂杮暥偐傜亃
丂
仧僶僗儔丆僋乕僼傽丆僶僌僟乕僪偵偼戝婯柾側恄妛偺妛栤強偑愝棫偝傟丆僐乕儔儞偵弎傋傜傟偨儉僴儞儅僪偺孾帵偑巕嵶偵嬦枴偝傟偨丅恄妛幰偨偪偼孾帵傪擭戙弴偵暲傋傞偙偲偵娭怱傪帩偪丆偦偺偨傔偵丆偦傟偧傟偺孾帵偵娷傑傟傞扨岅偺弌尰昿搙傪挷傋偨丅偲偄偆偺偼丆扨岅偵偼屆偄傕偺傕偁傟偽怴偟偄傕偺傕偁傝丆怴偟偄扨岅傪懡偔娷傓孾帵偼擭戙揑偵怴偟偄偼偢偩偐傜偱偁傞丅(P.37)
仧壗恖偐偺埫崋夝撉幰偲夛偭偨僠儍乕僠儖偼丆偐偔傕壙抣偁傞忣曬傪採嫙偟偰偔傟偰偄傞偺偑丆側傫偲傕堎條側柺乆偱偁傞偙偲偵嬃偐偝傟偨丅偦偙偺偼悢妛幰傗尵岅妛幰偺傒側傜偢丆從偒暔偺柤恖丆尦僾儔僴旤弍娰偺妛寍堳丆慡塸僠僃僗戝夛偺僠儍儞僺僆儞丆僩儔儞僾偺僽儕僢僕偺柤恖側偳偑偄偨偐傜偱偁傞丅僠儍乕僠儖偼丆旈枾専嶡嬊偺嬊挿偱偁偭偨僒乕丒僗僠儏儚乕僩丒儊儞僕乕僘偵岦偭偰偮傇傗偔傛偆偵偙偆尵偭偨丅乽敧曽庤傪偮偔偣偲偼尵偭偨偑丆偙偙傑偱暥帤捠傝偵傗傞偲偼側乿(P.244)
仧奜晹偺恖娫偵偲偭偰僫償傽儂岅偑偳傟偩偗擄夝偐傪弉抦偟偰偄偨僕儑儞僗僩儞偼丆僫償傽儂岅偑乮懠偺偳偺傾儊儕僇愭廧柉偺尵梩偱傕傛偄偑乯夝撉晄擻偺埫崋偵側傞偙偲偵婥偯偄偨偺偱偁傞丅傕偟傕懢暯梞愴慄偺奺晹戉偑丆柍慄僆儁儗乕僞乕偲偟偰擇柤偢偮偺傾儊儕僇愭廧柉傪嵦梡偡傟偽丆捠怣偺埨慡偑曐徹偝傟傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丠(P.263)
仧偨偐偑慺場悢傪媮傔傞偖傜偄丆偦傫側偵帪娫偑偐偐傞偼偢偑側偄偲巚偆撉幰傕偄傞偩傠偆丅偦傫側撉幰偺偨傔偵師偺栤戣傪弌偟偰偍偙偆丅傢偨偟偼廫昩傎偳偱1709023偲偄偆悢帤傪嶌偭偨丅撉幰偼揹戩傪巊偭偰偙偺悢偺慺場悢傪媮傔偰傒偰傎偟偄丅偍偦傜偔摎偊偑弌傞傑偱偵偼屵屻偄偭傁偄偐偐傞偩傠偆丅(P.367)
仧PGP偱埫崋壔偝傟偨偨偭偨堦偮偺儊僢僙乕僕傪夝撉偡傞偨傔偵丆悽奅拞偵偁傞偍傛偦僯壄榋愮枩戜偺僷乕僜僫儖丒僐儞僺儏乕僞乕傪搳擖偟偨偲偟偰傕丆夝撉偵偼暯嬒偟偰塅拡偺擭楊偺堦愮擇昐枩攞偺帪娫偑偐偐傞偲悇掕偝傟偰偄傞丅(P.420)
亂巹偺僐儊儞僩亃
僒僀儌儞丒僔儞偺彂偔杮偼幚偵傢偐傝傗偡偄丅擄偟偄偙偲傪偐偔傕傢偐傝傗偡偔昞尰偱偒傞偺偼傛傎偳摢偺傛偄恖側傫偩傠偆丅偳傫側偵岻傒偵塀偟偰傕暥帤偲偄偆傕偺偼偦偺尵岅偺拞偱弌尰昿搙傗懠偺暥帤偲偺娭學乮偙傟傪乽楢愙摿挜乿偲偄偆乯偱撈摿偺嵀愓傪巆偡丅偙傟偑埫崋夝撉偺庤偑偐傝偲側傞偺偩丅僐乕僷僗偵娭怱傪帩偮巹偼丆僀僗儔儉嫵恄妛幰偨偪偑丆僐乕儔儞偺尋媶夁掱偱扨岅偺弌尰昿搙傪挷傋偰偄傞偙偲偵偨偄傊傫嫽枴傪書偄偨丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃係丏侾
亂僀儞僷僋僩巜悢亃係丏侾
亂杮暥偐傜亃
仧抧幙妛幰偵偲偭偰丆瑕愇徴撍愢偼丆戝棨堏摦愢傛傝傕堸傒崬傓偺偑偼傞偐偵擄偟偄丆偲偄偆偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅偲偄偆偺偼丆偙偺妛愢偼僨僂僗丒僄僋僗丒儅僉僫乵屆戙僊儕僔儍墘寑偱媫応偺夝寛偵搊応偡傞拡忔傝偺恄乶偵慽偊偰偄傞偐傜偱偁傝丆抧幙妛幰偨偪偑捠忢尋媶偟峫偊傞傗傝曽偲偼傑偝偵惓斀懳偱偁偭偨偐傜偱偁傞丅(P.25)
仧 徴撍愢偼丆恑壔偺嬱摦椡偑嵟揔幰偺惗懚偱偼側偔偰嵟岾塣幰偺惗懚偱偁傞偐傕偟傟側偄壜擻惈傪丆惗暔妛幰偨偪偑峫椂偡傞傛偆梫媮偟偰偄傞偺偱偁傞丅(P.25)
仧戝曄摦偵慽偊傞偲偄偆偙偲偼偦偆偟偨抧幙妛偺廳梫側惉岟傪棤愗傞偙偲偱偁傞丆偡側傢偪丆抧幙妛揑帪娫偺峀戝側挿偝側偐偱偼偡傋偰偺偙偲偑払惉壜擻偱偁傞偲偄偆擣幆傪棤愗傞偙偲偱偁傞丅(P.67)
仧傾儖償傽儗僗愢偑桪傟偰偄偨揰偼丆傑偨偦傟偑旕忢偵桳岠偱偁傞偲敾柧偟偨傢偗偼丆戝検愨柵偵娭偡傞懡偔偺懠偺彅愢偲偼懳徠揑偵丆偦傟偑帋尡偝傟偆傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅傕偟傾儖償傽儗僗晝巕偑岆偭偰偄偰斵傜偺妛愢偑娫堘偭偰偄傞側傜丆徹嫆偑偦偺偙偲傪帵偡偼偢偱偁傞丅(P.108)
仧傾儖償傽儗僗愢偑傕偨傜偟偨嵟傕桳塿側暃嶻暔偺傂偲偮偼丆慜椺偺側偄傎偳偵偝傑偞傑側暘栰偺壢妛幰偨偪傪堦摪偵廤傔偨偦偺傗傝曽偱偁偭偨丅偨偲偊偽壴暡愱栧壠偼丆嫲棾愱栧壠傗壔妛幰傗暔棟妛幰傗揤暥妛幰偲摨偠晹壆偺側偐偱丆挻怴惎傗婱嬥懏傗徴撍敋敪傗戝検愨柵傪媍榑偟偰偄傞帺暘偵弶傔偰婥偯偄偨丅(P.255)
仧儖僀僗丒傾儖償傽儗僗偼愴偄傪岲傫偩偺偱丆傗傜傟偨傜偦偺暘傑偨傗傝偐偊偟偨丅乮棯乯乽巹偼屆惗暔妛幰偵偮偄偰埆岥偼尵偄偨偔側偄偑丆斵傜偼幚嵺偵偦傟傎偳椙偄壢妛幰偱偼側偄丅斵傜偼偳偪傜偐偲尵偊偽愗庤廂廤壠偵嬤偄偺偩乿丅(P.278)
仧壢妛幰側傜扤傛傝傕傛偔抦偭偰偄傞傛偆偵丆傕偟偁側偨偺榑揰傪徹柧偡傞偨傔偺桞堦偺曽朄偑摑寁偺巊梡偱偁傞側傜偽丆偁側偨偼媷抧偵娮傞偐傜偱偁傞亅偲偔偵傕偟偁側偨偑摑寁妛幰偱側偗傟偽側偍偝傜偱偁傞丅摑寁偵傛偭偰惗偒傞偙偲偼丆摑寁偵傛偭偰巰偸婋尟傪朻偡偙偲偱偁傞丅(P.338)
亂巹偺僐儊儞僩亃
偄傑偱偙偦忢幆偵側偭偰偄傞瑕愇偵傛傞嫲棾愨柵愢傕丆抧幙妛幰偵偲偭偰偼暚斞暔偺愢偱偁偭偨丅偙偺杮偼傾儖償傽儗僗晝巕偺壢妛幰偑傂傚傫側偙偲偐傜俇俆侽侽枩擭慜偺瑕愇徴撍偲偦傟偵傛傞嫲棾愨柵偺僔僫儕僆傪尒弌偟偰偄偔丅偲偒偵偼朶尵傪揻偒側偑傜偡偝傑偠偄揇帋崌傪墘偠傞壢妛幰偨偪丅斵傜傕傗偼傝恖娫側偺偱偁傞丅偙偺杮偼杮暥傕戝曄偍傕偟傠偄偺偩偑丆巹偑嵟傕嫽枴傪堷偐傟偨偺偼丆東栿幰偵傛傞乽偁偲偑偒乿偱偁偭偨丅東栿幰偺堦恖帥搱巵偼傾儖償傽儗僗愢偑幚偼尨敋懱尡偵捈愙偺娭傢傝傪帩偮偺偱偼側偄偐偲挷傋偰偄偔夁掱偱杮彂偵弌夛偭偨偲偄偆丅幚偼儖僀僗丒傾儖償傽儗僗偼戞擇師悽奅戝愴偱峀搰偵尨敋偑搳壓偝傟偨偲偒丆僄僲儔丒僎僀偲偲傕偵旘傫偱偄偨娤應婡偐傜丆偦傟傪尒撏偗偨壢妛幰偱傕偁偭偨偺偩両
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俀丏俋
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俀丏俋
亂杮暥偐傜亃
仧僠儏乕儕儞僌偼媡廝偟偨丅乽偁側偨曽偼埫偵丆恖娫偑懠偺偳傫側憂憿暔傛傝傑偝偭偰偄傞丆偲怣偠偨偑偭偰偄傞傛偆偱偡偹丅(棯)偟偐偟巹偑抦傞尷傝丆恖娫偺曽偑偡偖傟偰偄傞偲偄偆徹嫆偼側偄偺偱偡丅乿(P.95)
仧乽尵梩偼丆巕偳傕偑曣崙岅偵怗傟傞偙偲偱惗偠傞丅曣崙岅偺拻宆偩偗偑妶敪壔偟丆懠偺拻宆偼偦偺傑傑丆偲偄偆偙偲偱偟傚偆偐乿偲儂乕儖僨僀儞偑恞偹偨丅乽傑偁偦偆偄偆偙偲偱偡乿偲僠儏乕儕儞僌偼摨堄偟偨丅(P.149)
仧乽偱偼惗暔偲柍惗暔偺婡擻偺堘偄偼怴捖戙幱丆帺屓廋暅椡丆暋惢擻椡偺嶰偮偵偁傞偲偍偭偟傖傞偺偱偡偹乿偲儂乕儖僨儞偼恞偹偨丅乽偦偆偱偡乿偲僔儏儗乕僨傿儞僈乕偑擣傔偨丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
侾俋係俋擭塸崙働儞僽儕僢僕偵俆恖偺抦偺嫄恖偑廤傑偭偨丅C丒P丒僗僲僂丆償傿僩僎儞僔儏僞僀儞丆儂乕儖僨儞丆僔儏儗乕僨傿儞僈乕偦偟偰僠儏乕儕儞僌丅怘戩傪埻傒側偑傜斵傜偼媍榑傪愴傢偣傞丅偦傟偧傟偺嫄恖偵偮偄偰偺怺偄尒幆偑側偗傟偽彂偗側偄僼傿僋僔儑儞偱偁傞丅挊幰偼亀僷儔僟僀儉偺柪媨亁傪彂偄偨僕儑儞丒L丒僉儍僗僥傿丆栿偼亀怱偼屒撈側悢妛幰亁偺摗尨惓旻偲摗尨旤巕巵偱偱偁傞丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俈
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俈
亂杮暥偐傜亃
仧崌廜崙寷朄偵丆儖僀儞僗僉乕丒僙僢僋僗丒僗僉儍儞僟儖偺梊尵偑埫崋壔偝傟偰偄傞偲偄偆偺偩丅偍偦傜偔崌廜崙偺巒慶偨偪偑擖傟偨傕偺偱丆偙偺尃埿偁傞楌巎暥彂偺拞偵偼丆價儖(Bill)偲儌僯僇(Monica)偲偄偆岅偵偁傞侾侽帤偑丆婯懃惓偟偄娫妘偱暲傫偱偄傞丅(棯)寷朄偺偁傞摿掕偺偲偙傠偱丆倐偺俈俇暥帤屻傠偵倝偑偁傝丆偦偺俈俇帤屻傠偵倢偑偁傝丒丒丒偲偄偆傆偆偵懕偒丆嵟屻偵們偺俈俇帤屻傠偵Monica偺倎偵払偡傞丅(P.80)
仧傗偼傝廫暘昡壙偝傟偰偄側偄帠幚偼丆柍嶌堊偵慖傫偩擇偮偺検偺娫偵摑寁揑憡娭傪扵偣偽丆偳傫側検偱偁偭偰傕丆昁偢壗傜偐偺桳堄側娭學偑尒偮偐傞偲偄偆帠幚偱偁傞丅怣偠偰偄傞廆嫵偲庱夞傝偺娭學偱傕偄偄偟丆儐乕儌傾偺僙儞僗偲巇帠忋偺抧埵偱傕偄偄偟丆傕偟偐偡傞偲堦擭偵徚旓偝傟傞僗僀乕僩丒僐乕儞偺検偲丆妛楌偱傕偄偄偐傕偟傟側偄丅(P.197)
仧巹偵巚偄晜偐傇僒儈儏僄儖丒儀働僢僩偑彂偄偨傕偺偼丆巹偺栚偵偼偄偮傕偳偙偲側偔悢妛揑側傕偺偵尒偊傞丅儀働僢僩偺亀儚僢僩亁偼丆僸儏乕丒働僫乕偑僐儞僺儏乕僞尵岅偺僷僗僇儖偵堏偟偨傎偳偱偁傞丅(P.205)
仧暔岅偵偁傞寑揑側偲偙傠傗恖娫惈偑壢妛傗摑寁偺尋媶傪嫮壔偟丆媡偵壢妛傗摑寁偺尩枾偱扺乆偲偟偨帇揰偑丆暔岅偑姶彎揑側嵄帠傗偍偍偘偝側徿巀偵娮傜側偄傛偆偵偟偰偔傟傞丅尒棫偰傗椶悇偼丆悢妛傗壢妛偺棟夝傪暥帤捠傝偵夝庍偟偨偲偒偺嫹偝傪峀偘偰偔傟傞偟丆悢妛偺寁嶼傗惂栺偼丆暥妛揑側憐憸椡傪抧偵懌偺偮偄偨傕偺偵偟偰偔傟傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙傟偼僀儞僠僉壢妛偺僩儞僨儌杮偱偼側偄丅傓偟傠媡偱偁傞丅崌廜崙寷朄偵Bill偲Monica偺暥帤偑敪尒偱偒傞偲偄偆偺偼帠幚偩偑丆偦偺恖偑乽偁傞堄恾乿傪帩偭偰扵偣偽丆惞彂傪偼偠傔偳傫側杮偺拞偵偱傕乽栚揑偺岅乿傪敪尒偡傞妋棪偼戝曄崅偄偙偲傪杮彂偼偒偪傫偲愢柧偟偰偄傞丅嵟屻偺堷梡偵傕偁傞傛偆偵丆杮彂偼乽暥宯乿偲乽棟宯乿偑庤傪慻傔偽偄偐偵枺椡揑側傕偺偵側傞偐傪嫵偊偰偔傟傞丅側偍丆杮彂偼悢妛偵娭偡傞杮偱偼偁傝側偑傜丆悢幃偼弌偰偙側偄偙偲傪怽偟揧偊偰偍偒偨偄丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃 侾侾丏俀
亂僀儞僷僋僩巜悢亃 侾侾丏俀
亂杮暥偐傜亃
仧僂僅儗僗偼夁忚搼懣庡媊幰偱丆帺慠搼懣偺嶌梡傪惗暔宍懺偺偁傜備傞旝柇側偁傗偺偆偪偵擣傔偨偑傜側偄僟乕僂傿儞傪愑傔偨偰偰偄偨偑丆僸僩偺擼傪慜偵偟偨偲偒丆媫偵棫偪巭傑偭偨偺偱偁傞丅僂僅儗僗偺庡挘偵傛傞偲丆傢傟傢傟偺抦惈傗摽惈偼帺慠搼懣偺嶻暔偱偁傞偼偢偑側偄丅偦偟偰丆帺慠搼懣偑恑壔偺桞堦偺摴偱偁傞偐傜偵偼丆側傫傜偐偺傛傝崅師偺椡亅亅偼偭偒傝尵偊偽恄亅亅偑惗暔夵椙偺偆偪偱傕偙偺嵟傕怴偟偔執戝側傕偺傪偮偔傝偁偘傞偨傔偵偼夘嵼偟偰偄傞偵偪偑偄側偄丅乮棯乯僟乕僂傿儞偼丆僂僅儗僗偑廔拝抧揰傑偱棃偰媫偵曽岦揮姺傪偟偨偙偲偵傑偝偟偔垹慠偲偟偨丅(忋丂P.72)
仧恑壔惗暔妛偺嵟崅偺惞幰偱偁傞僠儍乕儖僘_乕僂傿儞偼丆婣擺庡媊幰偲儐儕僀僇庡媊幰偺椉曽偺岲椺偲偟偰嫇偘傜傟傞偙偲偑偁傞丅巹偼埲壓偵丆偙傟傜偺夝庍偼偳偪傜傕揑偼偢傟偱偁傞偙偲傪弎傋丆帺慠搼懣愢偵岦偭偨僟乕僂傿儞帺恎偺挿偄挿偄朻尟椃峴乮僆僨儏僢僙僀傾乯偵偮偄偰嬤擭摼傜傟偨抦尒偑丆僟乕僂傿儞偺拞娫揑側峴偒曽傪棫徹偟偰偄傞偙偲傪榑偠偰傒偨偄丅(忋丂P.86)
仧帺慠搼懣偼價乕僌儖崋偺彅帠幚傪偨偩夝庍偟偨偩偗偱偼弌偰偙側偄丅偦偺屻丆俀擭偵傢偨傞巚嶕偲嬯摤偺側偐偐傜尰傢傟偰偔傞丅偦偺愓偼夁嫀俀侽擭娫偵敪尒偝傟偰弌斉偝傟偨堦楢偺僲乕僩僽僢僋偵偵偠傒弌偰偄傞丅偙傟傜偺僲乕僩傪撉傓偲丆僟乕僂傿儞偼偄偔偮傕偺棟榑傪専徹偟偨傝丆抐擮偟偨傝丆懡偔偺夦偟偘側庤偑偐傝傪媮傔偨傝偟偰偄偨偙偲偑傢偐傞亅亅屻擭偵側偭偰丆僟乕僂傿儞偑嫊怱偵懡悢偺帠幚傪婰榐偟偰偄偨偲庡挘偟偨偺偼偦偆偄偆偙偲偩丅僟乕僂傿儞偼偄偮傕堄枴偲摯嶡傪扵傝側偑傜丆揘妛幰傗帊恖傗宱嵪妛幰偺挊嶌傪撉傫偱偄偨丅(忋丂P.90)
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偙偟偽傜偔僌乕儖僪偺嶌昳偑尰傢傟傞偙偲傪偛偐傫傋傫婅偄偨偄丅斵偺杮偼偨偄傊傫巋寖揑偱丆傕偺偺峫偊曽偵懳偡傞帵嵈偵晉傓婰弎偑懡偄偺偩丅
僂僅儗僗偼嵟屻偺偲偙傠偱乽僸僩乿傪摿暿帇偡傞巚憐偐傜敳偗弌偣偢丆扙棊偟偰偟傑偭偨丅忋偺堷梡偵傕偁傞傛偆偵丆僟乕僂傿儞偼帺慠搼懣偺拝憐傪摼傞傑偱偵偼愱栧奜偺偝傑偞傑側杮傪撉傒丆偄傢偽僽儗乕儞僗僩乕儈儞僌傪偟偰偄偨偺偱偁傞丅恑壔偼彊乆偵婲偙傞偺偱偼側偄丅梈揰偵払偟偨偲偒揝偑撍慠塼壔偡傞傛偆偵丆恑壔傕挿偄懸婡偺帪娫偺偁偲乽検偐傜幙傊偺揮姺乿偑撍慠偵婲偙傞傕偺偩(壓 P.18)偲偄偆偺偑僌乕儖僪偺庡挘偱偁傞丅
偙偺杮偵偼懠偵傕丆乽戝偒偝偺擛壗偵偐偐傢傜偢乮僸僩傪偺偧偔乯歁擕椶偼偡傋偰堦惗偺娫偵栺俀壄夞丆懅傪偡傞偙偲偑傢偐傞丅怱憻偼偍傛偦俉壄夞攺摦偡傞偙偲偵側傞丅彫宆歁擕椶偼懍偔懅傪偡傞偗傟偳傕抁婜娫偟偐惗偒側偄(壓丂P.191)乿側偳偺偍傕偟傠偄僄僺僜乕僪傕偁傞丅乮偨偩偟丆僸僩偩偗偼側偤偐偦偺俁攞惗偒傞乯
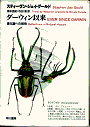 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏俉
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俆丏俉
亂杮暥偐傜亃
仧側偤斵乮僟乕僂傿儞乯偼帺暘偺棟榑傪敪昞偡傞偺傪俀侽擭埲忋傕偍偔傜偣偨偺偩傠偆偐丅乮棯乯嫲晐怱偲偄偆徚嬌揑側梫慺偑戝偒側栶妱傪壥偨偟偨偵偪偑偄側偄丅乮棯乯僟乕僂傿儞偼偄偭偨偄壗傪嫲傟偨偺偩傠偆偐丅乮棯乯偙傟傜偺僲乕僩偵偼丆恑壔偦傟帺懱傛傝傕偼傞偐偵堎抂揑偱偁傞偲斵偑姶偠偨偁傞傕偺偵偮偄偰丆偦傟傪斵偼怣偠側偑傜傕怣偠偰偄傞偙偲傪恖偵抦傜傟傞偙偲傪嫲傟偰偄偨丆偲偄偆偙偲傪帵偡懡偔偺婰弎偑娷傑傟偰偄傞丅偦偺偁傞傕偺偲偼丆揘妛偲偟偰偺桞暔榑偱偁傝丆暔幙偑偁傜備傞懚嵼偺慺嵽偱偁偭偰丆偡傋偰偺怱揑丒惛恄揑尰徾偼暔幙偺暃嶻暔偱偁傞偲偄偆壖掕偱偁傞丅惛恄偑偨偲偊偳傟傎偳暋嶨偱椡偑偁傠偆偲傕偦傟偼扨偵擼偺嶻暔偵偡偓側偄丆偲偄偆庡挘埲忋偵惣墷巚憐偺嵟傕怺偄揱摑偵偲偭偰徴寕揑側傕偺偼側偐偭偨丅(P.30)
仧儅儖僋僗偼偺偪偵亀帒杮榑亁戞擇姫偵僟乕僂傿儞偵曺偘傞專帿傪偮偗偨偄丆偲怽偟擖傟偨偑丆僟乕僂傿儞偼丆帺暘偑撉傫偱偄側偄挊嶌偵巀堄傪昞偟偰偄傞傛偆側報徾傪梌偊傞偙偲偼朷傑側偄偲偄偭偰丆挌廳偵偙偲傢偭偰偄傞丅乮P.35)
仧偙偺埆柤崅偄棟榑乮幮夛僟乕僂傿僯僘儉乯偼丆偝傑偞傑側恖庬傗暥壔傪丆恑壔忋偺摓払搙偲偄偆壦嬻偺悈弨偱奿晅偗偟丆嬃偔傎偳偺偙偲偱偼側偄偑丆儓乕儘僢僷偺敀恖偵嵟崅埵偵悩偊丆斵傜偑惇暈偟偨怉柉抧偵廧傓恖乆傪嵟壓埵偵抲偄偨丅崱擔偱傕偙偺峫偊偼丆乽傢傟傢傟恖娫偼丆偙偺抧媴偲偄偆榝惎偵廧傫偱偄傞侾侽侽枩庬埲忋偵偺傏傞懠偺惗暔偲摨偠拠娫側偺偱偼側偔偰丆偦傟傜傪巟攝偟偰偄傞偺偩乿偲偄偆傢傟傢傟偺怣擮丆抧媴揑婯柾偵偍偗傞傢傟傢傟偺巚偄忋偑傝丆傪惗傒弌偟偰偄傞壗傛傝偺梫慺偲側偭偰旜傪堷偄偰偄傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙傟傑偨丆偍傕偟傠偄杮偱偁傞丅僟乕僂傿儞偑嵟傕抦傜傟傞偙偲傪嫲傟偰偄偨傕偺偑乽恑壔榑乿偱偼側偔丆乽桞暔榑乿偱偁偭偨偲偼徴寕揑偱偁偭偨丅傑偟偰儅儖僋僗偵塭嬁傪梌偊偰偄偨偙偲偼抦傜側偐偭偨丅僌乕儖僪偼帺恎偑儐僟儎恖偱偁傞偲偄偆偙偲偐傜丆嵎暿偵偮偄偰忢偵晀姶偵斀墳偡傞丅偦偟偰挊彂偺偄偨傞偲偙傠偱側傫偳傕乽恑壔乿偼乽恑曕乿偱偼側偄偙偲傪嫮挷偡傞丅偼傞偐愄偵惗傑傟偨扨嵶朎惗暔偑傗偑偰懡嵶朎惗暔偲側傝丆偦偟偰歁擕椶丆恖椶傊偲乽恑壔乮恑曕乯乿偟偰偒偨偲懡偔偺恖偑峫偊傞丅僌乕儖僪偼偦傟偑娫堘偄偩偲偄偆丅偦傟偱偼尰懚偡傞嵶嬠偼偳偆側偺偐丅斵傜傕傑偨恑壔偺帋楙傪惗偒墑傃偰偒偨偺偱偼側偄偺偐偲僌乕儖僪偼偄偆偺偩丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俀
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俉丏俀
亂杮暥偐傜亃
仧R丒M丒儎乕僉乕僘偼戞1師戝愴偺帪,棨孯傪愢摼偟偰侾俈俆枩恖偺孯恖傪僥僗僩偟丆堚揱寛掕榑幰偺庡挘傪惓摉壔偟偨偑丆侾俋俀係擭偵偼偦傟偑楎摍側堚揱巕傪帩偮崙偐傜偺堏柉偺悢傪掅偔偍偝偊傞偲堏柉惂尷朄傪摫偔偙偲偵側偭偨丅IQ偺堚揱寛掕榑偼傾儊儕僇偑帺傜峫偊弌偟偨傕偺偱偁傞丅乮P.227)
仧戝抇偵傕僞乕儅儞偨偪偼夁嫀偺挊柤恖偺IQ偺暅尦傪帋傒丆堦嶜偺傇岤偄杮傪弌斉偟偨丅偦傟偼丆夁嫀偵偮偄偰偺偽偐偘偨尋媶偺拞偱傕嵟傕捒婏側傕偺偱偁傞丅乮棯乯儅僀働儖丒僼傽儔僨乕偼丆偐傠偆偠偰侾侽俆傪梌偊傜傟偨丅巊偄憱傝彮擭偲偟偰偺怣梡偲丆壗帠偵傕媈栤傪帩偮偲偄偆惈奿偑傢偢偐偵峫椂偝傟丆椉恊偺晄棙側抧埵傪曗偭偨偺偱偁傞丅(棯乯斱嫠偺惗傑傟偱偁傝丆巕偳傕帪戙偵偮偄偰奆栚抦傜傟偰偄側偄僔僃乕僋僗僺傾偺摼揰偼丆摉慠侾侽侽埲壓偵側偭偰偟傑偆丅偦偙偱僐僢僋僗偼(棯乯僔僃乕僋僗僺傾偺応崌偵偼彍奜偣偞傞傪摼側偐偭偨丅乮P.268)
仧傢傟傢傟偼亀儀儖丒僇乕僽亁偺妛愢偲愴傢偹偽側傜側偄丅側偤側傜偽丆偦傟偑岆傝偱偁傝丆傕偟忦椺壔偝傟傟偽偁傜備傞恖乆偺抦擻傪惓偟偔堢傓偡傋偰偺婡夛傪揈傒庢偭偰偟傑偆偩傠偆偐傜丅(P.474)
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺壞乮俀侽侽侽擭乯偵撉傫偩嵟傕姶柫傪庴偗偨彂暔偱偁傞丅係俋侽侽墌偼妋偐偵崅偄偑偦偺撪梕偼侾枩墌偩偟偰傕惿偟偔側偄傕偺偩偭偨丅乽恖偺抦擻偼惗摼偺傕偺偱偁傝丆偦偺堦斒揑抦擻偼扨堦偺悢抣乮椺偊偽僗僺傾儅儞偺g乯偱寁傞偙偲偑偱偒丆偦偺悢抣偵婎偯偄偰恖娫傪彉楍壔偱偒傞丅偦偟偰偦偺悢抣偼堦惗晄曄偱偁傞乿偙偆偟偨怣擮偺傕偲偵抦擻僥僗僩傗場巕暘愅偼奐敪偝傟偰偄偭偨丅偦偟偰堦扷偼攋抅偟偨偼偢偺偙偆偟偨愢偑侾俋俋係擭亀儀儖丒僇乕僽亁乮俼丒僿乕儞僔儏僞僀儞丆俠丒儅儕乕乯偲偟偰傛傒偑偊偭偨偲偄偆偺偩丅偦傟偵懳偡傞僌乕儖僪偺尵梩偑忋婰偺嵟屻偺堷梡暥偱偁傞丅僌乕儖僪偑偙偺傛偆偵偄偆偺偵偼栿偑偁傞丅椺偊偽丆僔儞僈億乕儖偺儕乕丒僋傾儞丒儐乕偼弌惗棪傪傛傝崅傔傞偨傔偵丆崅妛楌偺彈惈偵曬彏傪梌偊傞桪惗妛揑僾儘僌儔儉偺惂搙壔傪峫偊傞側偳丆尰嵼偱傕桪惗妛偺朣楈偼偼偄偐偄偟偰偄傞偺偱偁傞丅
乽敀恖乿偲偄偆尵梩偑丆偳偆偟偰塸岅偱偼Caucasian(僐乕僇僒僗恖乯偲偄偆偺偐丆偮傑傝側偤儘僔傾偺嶳柆偺柤慜偑偮偗傜傟偰偄傞偺偐慜乆偐傜晄巚媍偵巚偭偰偄偨丅偟偐偟偙偺杮偺嵟屻傪撉傫偱偦傟偑傢偐偭偨丅偦傟偼偙偺嶳柆偺傆傕偲偵嵟傕旤偟偄恖庬偑惗傑傟丆偦偙偑恖椶敪徦偺抧偲峫偊傞僪僀僣偺僫僠儏儔儕僗僩丆僽儖乕儊儞僶僢僴偑柦柤偟偨傕偺偱偁偭偨丅斵偼儕儞僱偺掜巕偱偁偭偨偑丆摢奧崪偺宍偐傜恖庬偵彉楍傪偮偗偰丆傕偭偲傕宍偑旤偟偔抦揑摴摽揑偵偡偖傟偨乮偲峫偊傞乯傕偺傪乽僐乕僇僒僗恖乿偦偟偰俀儔儞僋栚偵乽傾儊儕僇儞丒僀儞僨傿傾儞乿偲乽儅儗僀恖乿丆俁儔儞僋栚偵乽搶梞恖乿偲乽傾僼儕僇恖乿偲偟偨丅偄傗偼傗偙偺傛偆偵恖庬傪偝傑偞傑側傕偺偵傛偭偰儔儞僋晅偗偟傛偆偲偡傞敀恖偺擬堄偵偼偁偒傟傞偽偐傝偩丅杮彂偵偼偙偆偟偨乽崪憡妛乿側偳偵偮偄偰傕徻偟偔弎傋傜傟偰偄傞丅
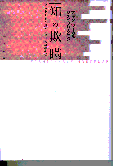 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏俇
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俋丏俇
亂杮暥偐傜亃
仧夝愅妛傗検巕椡妛偵偮偄偰柍抦側偺偼側傫傜抪偢偐偟偄偙偲偱偼側偄偲嫮挷偟偰偍偙偆丅傢傟傢傟偑斸敾偟偰偄傞偺偼丆堦晹偺挊柤側抦幆恖偑丆幚嵺偵偼堦斒岦偗偺夝愢彂偱巇擖傟偨掱搙偺抦幆偟偐帩偪崌傢偣偰偄側偄偺偵丆擄偟偄僥乕儅偵偮偄偰怺墦側巚憐傪揥奐偟偰偄傞偐偺傛偆偵傒偣偐偗偰偄傞偙偲側偺偩丅(俹丏俉乯
仧乽偦偙偱丆偦偺寢壥偲偟偰丆傢傟傢傟偺梡偄偰偄傞戙悢偵偟偨偑偭偰丆偙偺堄枴嶌梡傪寁嶼偡傞偲丆S(婰崋昞尰)/s(婰崋撪梕)=s(尵昞偝傟偨傕偺), S=(-1)偵傛偭偰,s=併-1偑摼傜傟傞乿乮儔僇儞1960擭僙儈僫乕偐傜乯
偙偆側傞偲丆儔僇儞偼撉幰傪偐傜偐偭偰偄傞偲偟偐巚偊側偄丅偨偲偊斵偺乽戙悢乿偵側傫傜偐偺堄枴偑偁傞偲偟偰傕丆幃偺拞偺乽婰崋撪梕乿丆乽婰崋昞尰乿乽尵昞偝傟偨傕偺乿偼悢偱偼側偄偟丆幃偺拞偺乮彑庤偵慖傫偩婰崋偲偟偐傒側偟傛偆偑側偄乯悈暯側慄偑暘悢傪昞尰偟偰偄傞傢偗偱傕側偄丅儔僇儞偺乽寁嶼乿偼丆偨偩偺嬻憐偺嶻暔偵夁偓側偄丅(俹丏俁俈乯
仧埖偭偰偄傞撪梕帺懱偺惈幙偺偨傔偵擄偟偔側偭偨尵愢偲丆傢偞偲傢偐傝偵偔偄彂偒曽傪偟偰丆拞恎偑側偄偙偲傗杴梖側偙偲傪梡怱怺偔塀偦偆偲偟偰偄傞尵愢偵偼丆塤揇偺嵎偑偁傞丅
仧偙偺傛偆側僥僋僗僩偼丆撉傒曽偵墳偠偰丆惓偟偄偑偐側傝摉偨傝慜偺庡挘偐丆夁寖偩偑柧傜偐偵岆偭偨庡挘偐偺偄偢傟偐偵偁傞丅偦偟偰懡偔偺応崌丆偙偺傛偆側濨枂偝偼挊幰偑堄恾偟偰帩偪崬傫偩偲峫偊偞傞傪偊側偄丅幚嵺丆偙偆偄偆彂偒曽傪偟偰偍偔偲妛栤揑側榑憟偺嵺戝偄偵桳棙偱偁傞丅夁寖側夝庍偺曽偼丆斾妑揑宱尡偺愺偄挳廜傗撉幰偺婥傪傂偔偺偵栶棫偮丅偦偟偰丆偙偺夝庍偑偽偐偘偰偄傞偙偲偑業尒偟偨傜丆偡偖偵丆帺暘偼岆夝偝傟偨偲曎夝偟偰柍奞側曽偺夝庍偵揚戅偡傞偙偲偑偱偒傞偺偩丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
儔僇儞丆僋儕僗僥償傽丆儔僩僁乕儖側偳億僗僩儌僟儞偺恖偨偪偺彂偄偨傕偺偼擄偟偄丅乽変乆偺暋嶨偱丆挻惷揑偱丆僂僀儖僗揑側宯偼傕偭偭傁傜巜悢揑師尦乮偦傟偑巜悢娭悢揑晄埨掕惈偱偁傝埨掕惈偱偁傟乯偵丆曃怱惈傕偟偔偼棧怱惈偵丆晄掑偺僼儔僋僞儖側丒丒丒乿乮儃乕僪儕儎乕儖乯側偳偲偄偆暥復偑棟夝偱偒側偄帺暘偼傂傚偭偲偡傞偲攏幁偱偼側偄偐偲巚偭偰偟傑偆丅偱傕埨怱偟偰梸偟偄丅偙偆偟偨暥復偼丆悢棟暔棟妛偺愱栧壠偑撉傫偱傕丆乽傑偭偨偔堄枴偺側偄暥復偺拞偵丆壢妛梡岅傗媅帡壢妛梡岅偑崅擹搙偵偮傔偙傑傟偰偄傞乿偩偗偲偄偆偺偩丅
嬸偐側恖娫偵偼尒偊側偄偲偄偆暈傪墹條偑拝偰偄偨丅扤傕偑帺暘偑攏幁偲巚傢傟偨偔側偄偺偱尒偊傞傆傝傪偟偰偄偨丅偟偐偟巕嫙偑乽墹條偼棁偩両乿偲偄偭偨弖娫丆扤傕偑乽側乕傫偩丆懠偺恖偵傕尒偊側偐偭偨偺偐乿偲屽偭偨丅偙偺杮偼丆偦傟傪屽傜偣偰偔傟傞杮偱偁傝丆偙偗偍偳偟偺彂暔偵偩傑偝傟傞側偲偄偆寈忇偱傕偁傞丅僜乕僇儖帠審乮偙傟偵偮偄偰偼搶杒戝偺崟栘巵偺僒僀僩偑徻偟偄乯偺僜乕僇儖偺傗傝曽偼墭偄偲偄偆惡傕偁傞偑丆彂偄偰偄傞杮恖偡傜傢偐傜側偄暥復傪悅傟棳偟偟偰偒偨楢拞偺曽偑傕偭偲墭偄偺偱偼側偐傠偆偐丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俉
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俉
亂杮暥偐傜亃
仧嵒嶳偐傜堦棻偺嵒傪庢傝嫀偭偰傕丆偦偙偵偼嵒嶳偑偁傞丅傕偆堦棻庢傝嫀偭偰傕丆偦偙偼嵒嶳偱偁傞丅偦傟傪懕偗偰偄偗偽丆偄偮偐偼堦棻偺嵒偑巆傞丅偦傟偼傑偩嵒嶳偐丅嵟屻偺堦棻傪庢傝嫀傟偽丆偦偙偵偼壗傕側偔側傞丅偦偆側偭偰傕嵒嶳偐丅嵒嶳偱側偄偲偡傟偽丆偄偮丆偦傟偼嵒嶳偱偁傞偙偲傪傗傔偨偐丅(P.32)
仧僓僨乕偼暋嶨側暘栰偺偄偨傞偲偙傠偵偁偄傑偄側奣擮偑偁傆傟偰偄傞偙偲偵婥偯偄偨丅偨偲偊偽丆朄棩偺偍偗傞辔弼傗惛恄堎忢丆堛妛偵偍偗傞娭愡墛傗摦柆峝壔傗惛恄暘楐徢丆宱嵪妛偵偍偗傞宨婥屻戅傗壙抣傗岠梡丆尵岅妛偺偍偗傞暥朄傗堄枴丆僔僗僥儉棟榑偵偍偗傞埨掕惈傗揔墳惈丆揘妛偵偍偗傞抦惈傗憐憸椡丆偳傟傕偑偁偄傑偄側奣擮偱偁傞丅僼傽僕傿廤崌偼丆偦傟傜偡傋偰傪婰弎偡傞偙偲偑偱偒傞丅(P.60)
仧悢擭慜丆昅幰偺堦恖偑偨傑偨傑丆價僶儕乕僸儖僘偺儗僗僩儔儞偱儊儖丒僽儖僢僋僗偺偦偽偵嵗偭偨丅僂僃僀僩儗僗偑棃偰丆斵偵偦偺斢偺摿暿儊僯儏乕傪崘偘偨丅僆乕僪僽儖偵偼丆曅柺傪從偒曅柺偼惗偺僴儅僠偑梡堄偱偒傑偡偑丆偲斵彈偼尵偭偨丅偦傟傪暦偄偰斵偼嫨傫偩丅乽偍偄偍偄丆偦傟偼側傫偩丅亀僗僔亁偐亀僗僔偠傖側偄亁偺偐丆偼偭偒傝偟傠傛乿丅傾儕僗僩僥儗僗埲棃俀俁侽侽擭丆巹偨偪偑柆乆偲庴偗宲偄偱偒偨乽僋儔僗暘偗乿偺巚憐偑儊儖丒僼儖僢僋僗偵偦偆嫨偽偣偨偺偩丅(P.72)
仧擔杮偱嵟弶偵僼傽僕傿惢昳傪攧傝弌偟偨偲偒丆儊乕僇乕偼偦偺彜昳柤偵乽fuzzy乿偺擔杮岅栿偱偁傞乽偁偄傑偄乿傪巊偭偨丅徚旓幰偺斀墳偼偼偐偽偐偟偔側偐偭偨丅偦偙偱夛幮偼柤慜傪乽僼傽僕傿乿偵曄偊偨丅乽僼傽僕傿乿偼塸岅偺壒傪偦偺傑傑彂偒昞偟偨傕偺偱丆戝敿偺擔杮恖偵偲偭偰偼撻愼傒偺側偄堄枴晄柧偺偙偲偽偩偭偨丅偡傞偲彜昳偼旘傇傛偆偵攧傟弌偟偨丅(P.211)
亂巹偺僐儊儞僩亃
侾俋俇係擭儘僩僼傿丒僓僨乕偑弶傔偰僼傽僕傿棟榑偺榑暥傪彂偄偨偲偒丆傾儊儕僇偺妛夛偼慡偔憡庤偵偟側偐偭偨丅乽僼傽僕傿乿偲偄偆尵梩偑傾儕僗僩僥儗僗埲棃榑棟惈丒柧濔惈傪廳帇偡傞乽壢妛揑乿巚峫偵斀偡傞傕偺偩偭偨偐傜偱偁傞丅偦偟偰俁侽擭丅寢嬊偦偺壙抣傪擣傔丆偦傟傪墳梡偟偰抧壓揝傗揹壔惢昳傪嶌傝弌偟偨偺偼擔杮恖偩偭偨丅僗僷僗僷偲擇尦榑偱愗傝幪偰偰偄偔偺偼妋偐偵婥帩偪偺偄偄傕偺偱偼偁傞偑丆峫偊偰傒傞偲変乆偺廃埻偺傎偲傫偳偺尰徾偼乽僼傽僕傿乿側傕偺偽偐傝偱偁傞丅弔偑楢懕偟偰偄偔偆偪偵偄偮偺傑偵偐壞偵側偭偰偄傞丅偙偺杮偼乽僼傽僕傿棟榑乿偺擖栧彂偱偼側偄丅乽僼傽僕傿棟榑乿偑偳偺傛偆偵昡壙偝傟偰偒偨偐傪岅傞乽僼傽僕傿棟榑乿偺嬯擄偺楌巎偱偁傞丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俇
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俇
亂杮暥偐傜亃
仧係俉俆恖偺嫟挊幰傪帩偮僄儖僨僔儏偼丆悢妛幰偲偟偰巎忋嵟傕嫟挊偑懡偄丅偙偺岾塣側係俉俆恖偼丆悢妛奅偺嫄彔僄儖僨僔儏偲偄偭偟傚偵榑暥傪彂偄偨偲偄偆堄枴偱丆僄儖僨僔儏斣崋侾傪梌偊傜傟偰偄傞丅僄儖僨僔儏斣崋俀偼丆僄儖僨僔儏斣崋侾傪帩偮悢妛幰偲嫟挊傪敪昞偟偨恖偵偮偗傜傟丆僄儖僨僔儏斣崋俁偼僄儖僨僔儏斣崋俀傪帩偮恖偲嫟挊偑偁傞恖傪巜偡丅傾僀儞僔儏僞僀儞偼僄儖僨僔儏斣崋俀偱偁傝丆僄儖僨僔儏斣崋偺嵟戝悢偼偙傟傑偱偺偲偙傠俈偱偁傞丅(p.18)
仧僄儖僨僔儏岅偵偼摿暿側岅渂偑偁偭偨丅乽俽俥乮拲丗supreme fascist=僄儖僨僔儏傪嬯偟傔傞恄偺偙偲)乿乽僄僾僔儘儞乮拲丗巕嫙偺偙偲乯乿偩偗偱偼側偔丆乽儃僗乮彈惈乯乿乽搝楆乮抝惈乯乿乽曔妉偝傟偨乮寢崶偟偨乯乿乽夝曻偝傟偨乮棧崶偟偨乯乿乽嵞曔妉偝傟偨乮嵞崶偟偨乯乿乽嶨壒乮壒妝乯乿乽撆乮傾儖僐乕儖乯乿乽愢嫵偡傞乮悢妛偺島媊傪偡傞乯乿乽僒儉乮暷崙乯乿乽僕儑乕乮僜楢乯乿側偳偱偁傞丅偩傟偐偑乽巰傫偩乿偲僄儖僨僔儏偑尵偆偲偒偵偼丆偦偺偩傟偐偑悢妛傪傗傔偨偙偲傪堄枴偟偨丅恖偑巰傫偩偲偒偵偼乽嫀偭偨乿偲尵偭偨丅(p.12)
仧僄儖僨僔儏偼傂偲傝偱偙偭偦傝偲尋媶傪懕偗偨儚僀儖僘偺懺搙傪嫋偝側偐偭偨丅儚僀儖僘偑悢妛奅慡懱傪姫偒偙傫偱尋媶偟偰偄偨傜丆掕棟偼傕偭偲憗偔徹柧偱偒偰偄偨偐傕偟傟側偄偲僄儖僨僔儏偼巚偭偰偄偨丅(p.200)
仧僼僃儖儅乕偺擄栤傪係侾嵨偱憭偭偨儚僀儖僘偼丆偡偖傟偨悢妛傪徹柧偱偒傞偺偼庒幰偩偗偩偲偄偆朄懃偺娊寎偡傋偒椺奜偲偟偰偄偭偦偆傕偰偼傗偝傟偨丅乮棯乯乽偐傟偑擭婑傝偩偲偄偆側傜丆傢偟偼偳偆側傞偹丠壔愇偐丠乿僄儖僨僔儏偼棾傪戅帯偟偨偙偲偵娭偟偰儚僀儖僘傪徿巀偟偨偑丆徹柧傪棟夝偟偨傆傝傪偟傛偆偲偼偟側偐偭偨丅偦偟偰栤戣傪夝偔俈擭偺偁偄偩丆儚僀儖僘偑堦搙偲偟偰僐儞僺儏乕僞傪巊傢側偐偭偨偲抦偭偰婌傫偩丅(p.218)
[巹偺僐儊儞僩]
僄儖僨僔儏偵偮偄偰偼偐偮偰俶俫俲偱曻塮偝傟偨偙偲偑偁傞丅偦偺拞偱僺乕僞乕丒僼儔儞僋儖偑乽僄儖僨僔儏斣崋乿偺偙偲傪榖偟偰偄偨丅僄儖僨僔儏偑僼僃儖儅乕偺嵟廔掕棟傪徹柧偟偨儚僀儖僘偲堎側傞揰偼,斵偼忢偵悢妛偺媈栤傪懠偺悢妛幰偲嫟桳偟傛偆偲偟偨偙偲偱偁傞丅係俉俆恖偺悢妛幰偲侾侽侽侽杮埲忋偺榑暥傪敪昞偟偨偑丆偁傞堄枴偱偼偙偆偟偰斵偼懡偔偺屻恑傪堢偰偰偄偨偲偄偊傞偩傠偆丅僄儖僨僔儏偼帺暘偺孋偺傂傕偝偊枮懌偵寢傋側偄恖偱偼偁偭偨偑丆悢妛偵娭偟偰偼執戝側嫵巘偱偁偭偨丅俈侽嵨傪墇偊偰偐傜傕侾廡娫偵侾杮偼榑暥傪彂偄偨偲偄傢傟偰偄傞丅侾俋俋俇擭俉俁嵨偺僄儖僨僔儏偼儚儖僔儍儚偱奐偐傟偨僙儈僫乕偱島媊拞丆怱憻敪嶌偱搢傟朣偔側偭偨丅偙傟偙偦偼斵偺朷傫偱偄偨巰偵曽偩偭偨丅
側偍丆僄儖僨僔儏丒僫儞僶乕偵偮偄偰嫽枴偺偁傞曽偼僆乕僋儔儞僪戝妛僌儘僗儅儞嫵庼偺
僄儖僨僔儏丒僫儞僶丒僾儘僕僃僋僩丒僒僀僩
傪偛棗壓偝偄丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俉
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俉
亂杮暥偐傜亃
仧僆僀儔乕偼挳廜偺慜偵棫偪丆傕偭偨偄傇偭偨傛偆偡偱偙偆弎傋偨丅
乽妕壓丆(a+b^n)/n=x丆備偊偵恄偼懚嵼偟傑偡丅偄偐偑偐両乿
戙悢妛偺慺梴偺側偄僨傿僪儘皞獌垇[儘僢僷悘堦偺悢妛幰偵斀榑偱偒傞偼偢傕側偔丆斵偼柍尵偱偦偺応傪棫偪嫀偭偨丅(p.112)
仧揤暥妛幰偲暔棟妛幰偲悢妛幰偑僗僐僢僩儔儞僪偱媥壣傪夁偛偟偰偄偨偲偒偺偙偲丆楍幵偺憢偐傜傆偲尨偭傁傪挱傔傞偲丆堦摢偺崟偄梤偑栚偵偲傑偭偨丅揤暥妛幰偑偙偆尵偭偨丅乽偙傟偼偍傕偟傠偄丅僗僐僢僩儔儞僪偺梤偼崟偄偺偩乿暔棟妛幰偑偙偆墳偠偨丅乽壗傪尵偆偐丅僗僐僢僩儔儞僪偺梤偺拞偵偼崟偄傕偺偑偄傞偲偄偆偙偲偠傖側偄偐乿悢妛幰偼揤傪嬄偖偲丆壧偆傛偆偵偙偆尵偭偨丅乽僗僐僢僩儔儞僪偵偼彮側偔偲傕堦偮偺尨偭傁偑懚嵼偟丆偦偺尨偭傁偵偼彮側偔偲傕堦摢偺梤偑娷傑傟丆偦偺梤偺彮側偔偲傕堦曽偺柺偼崟偄偲偄偆偙偲偝乿(p.174)
仧扟嶳亖巙懞梊憐偼枹徹柧偺梊憐偩偭偨偵傕偐偐傢傜偢丆傕偟傕偦傟偑徹柧偝傟偨傜壗偑尵偊傞偐丆偲偄偆悇應偺偐偨偪偱丆壗昐傕偺榑暥偑搊応偟偰偄偨丅偦偆偟偨榑暥偱偼乽扟嶳亅巙懞梊憐偑惉傝棫偮偲壖掕偡傞偲丒丒丒乿偲偄偆尵梩偵懕偄偰丆枹夝寛偺栤戣偺夝偒曽偑弎傋傜傟偰備偔丅乮棯乯扟嶳亖巙懞偲偄偆堦偮偺梊憐傪搚戜偲偟偰丆傑傞傑傞堦偮偺怴偟偄峔憿暔偑偱偒偁偑偭偰偄偭偨偺偱偁傞丅偟偐偟偙偺梊憐偑徹柧偝傟側偄偆偪偼丆偄偮側傫偳偒丆偦偺偡傋偰偑曵夡偟偰傕偍偐偟偔偼側偐偭偨丅(p.244)
仧壢妛僕儍乕僫儕僗僩偑儚僀儖僘偺徹柧傪愨巀偡傞堦曽偱丆偦傟偲晄壜暘偺娭學偵偁傞扟嶳亖巙懞梊憐偑徹柧偝傟偨偙偲偵怗傟傞婰帠偼傎偲傫偳側偐偭偨丅侾俋俆侽擭戙偵儚僀儖僘偺尋媶偺庬傪帾偄偨俀恖偺擔杮恖悢妛幰丆扟嶳朙偲巙懞屲榊偺峷專傪岅傠偆偲偡傞幰偼偄側偐偭偨偺偱偁傞丅扟嶳偼俁俈擭慜偵帺嶦偟偰偄偨偑丆巙懞偼崱傕寬嵼偱丆偦偺梊憐偑徹柧偝傟傞帪戙偵嫃崌傢偣偨丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼傾儞僪儕儏乕丒儚僀儖僘偑僼僃儖儅乕偺嵟廔掕棟傪偄偐偵偟偰夝偄偨偐偲偄偆偙偲傪岅偭偰偄傞偺偩偑丆偦傟偵晅悘偡傞偝傑偞傑側悢妛忋偺僄僺僜乕僪偑悘強偵偪傝偽傔傜傟撉幰偺嫽枴傪堷偒晅偗傞丅岾偄側偙偲偵擄偟偄悢幃偼傎偲傫偳搊応偟側偄(^^乁丅丂恻梋嬋愜傪宱側偑傜傕寢嬊儚僀儖僘偼丆侾俋侽俉擭僪僀僣偺帒嶻壠償僅儖僼僗働乕儖偑僼僃儖儅乕偺嵟廔掕棟傪嵟弶偵徹柧偟偨傕偺偵侾侽枩儅儖僋乮尰嵼偺壙抣偵姺嶼偡傞偲侾俆壄墌傪墇偊傞乯傪梌偊傞偲偟偨乽償僅儖僼僗働乕儖徿乿傪妉摼偟偨丅傕偭偲傕儚僀儖僘偑庤偵偟偨帪偺嬥妟偼壿暭壙抣偺壓棊偺偨傔偵俆侽侽枩墌掱搙偵側偭偰偄偨丅偟偐偟丆偙偺徿傪摼偨偲偄偆偙偲偼丆儚僀儖僘偑尩偟偄専嵏傪宱偨忋偱偺恀偺僼僃儖儅乕偺嵟廔掕棟偺徹柧幰偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅
儚僀儖僘偑掕棟傪徹柧偡傞戝偒側婎慴偲側偭偨偺偼扟嶳亖巙懞梊憐偱偁偭偨偑丆偙偺擔杮恖偵偮偄偰偼傎偲傫偳怗傟傜傟偰偄側偄偲挊幰偼暜奡偡傞丅挊幰偑僀儞僪宯僀僊儕僗恖偱偁傞偙偲偵傕娭學偡傞偺偐傕偟傟側偄偑丆側傫偲杮彂偱偼扟嶳丆巙懞偺俀恖偺擔杮恖悢妛幰偺偨傔偵傢偞傢偞侾復暘傪妱偄偰偄傞丅偦偆偟偨堄枴偱傕岲姶偺帩偰傞堦嶜偱偁傞丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俉
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俇丏俉
亂杮暥偐傜亃
仧斢擭丆僴乕儀僀偼偙偆弎傋偰偄傞丅乽巹偼僼傽僽儕僉僂僗偲嫟偵傛偔偙偆尵偭偨傕偺偩丅亀宱尡偵傛偭偰寢榑偑斲掕偝傟傞側傜偽丆偦偺寢榑偼偦偭偔傝捑栙偝偣傞傋偒偩亁偲丅偄傑偺帪戙偵偲傝傢偗暆傪偒偐偣偰偄傞埆暰偼丆榑棟揑側徹嫆偑傑偭偨偔側偄傑傑偵丆壇應偁傞偄偼偆傢傋偩偗偺榑棟偵傕偲偯偄偨扨側傞尪憐傪丆柧傜偐側恀幚偱偁傞偐偺傛偆偵墴偟偮偗傞偙偲偱偁傞乿
仧愴憟偑廔傢偭偰偐傜丆僪僀僣偺儘働僢僩愱栧壠偨偪偼丆傾儊儕僇偵楢傟偰偙傜傟偨偑丆儘働僢僩岺妛偵偮偄偰幙栤偝傟偨偲偒丆斵傜偼丆嬃偄偰栚傪尒挘偭偨丅側偤傾儊儕僇恖偨偪偼丆偦偺傛偆側幙栤傪乮傾儊儕僇恖偱偁傞乯僑僟乕僪偵偟側偐偭偨偺偐丆傓偟傠丆斵傜偺傎偆偑偦偺棟桼傪抦傝偨偑偭偨丅偦偺偲偒偼丆傕傗偼抶偡偓偨丅僑僟乕僪偼丆侾俋係俆擭俉寧侾侽擔丆尨巕椡偺栭柧偗偺偙傠偵巰傫偱偄偨丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼丆傾儖僉儊僨僗偐傜傾僀儞僔儏僞僀儞傑偱壢妛幰偺偍傕偟傠偄僄僺僜乕僪傪徯夘偡傞丅傑偠傔偵偙偮偙偮偲儘働僢僩偺尋媶傪懕偗傞儘僶乕僩丒僑僟乕僪傪傾儊儕僇偼攏幁偵偟懕偗丆堦曽斵偺挊彂偐傜懡偔傪妛傫偩僪僀僣偱偼儘働僢僩岺妛偑偝偐傫偵側偭偨偲偄偆僄僺僜乕僪偼恎偵偮傑偝傟傞榖偩丅丂
悘強偵嫴傑傟偰偄傞媑塱椙惓巵偺僐儔儉傕偍傕偟傠偄丅
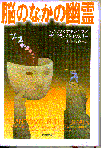 亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏俈
亂僀儞僷僋僩巜悢亃侾侽丏俈
亂杮暥偐傜亃
仧傾儕僗僩僥儗僗偼帺慠尰徾偺塻偄娤嶡幰偩偭偨偑丆幚尡傪偡傞丆偡側傢偪悇應偟偰偦傟傪宯摑揑偵専徹偡傞偲偄偆敪憐傪傕偭偰偄側偐偭偨丅偨偲偊偽斵偼丆彈惈偼抝惈傛傝傕帟偺悢偑彮側偄偲怣偠偰偄偨丅偙偺愢偑惓偟偄偙偲傪幚徹偡傞丆偁傞偄偼斀徹傪偁偘傞偮傕傝偑偁傟偽丆偁傞掱搙偺悢偺抝彈偵岥傪奐偗偰傕傜偭偰帟偺悢傪悢偊傞偩偗偱偱偒偨偼偢偩丅嬤戙揑側幚尡壢妛偼僈儕儗僆偲偲傕偵偼偠傑偭偨丅乮棯乯僈儕儗僆埲慜偼丆廳偄暔懱偺曽偑寉偄暔懱傛傝傕懍偔棊偪傞偲偩傟傕偑怣偠偰偄偨丅偦偟偰偨偭偨俆暘偺幚尡偱丆偦偺岆傝偑棫徹偝傟偨丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
帠屘側偳偱庤傗懌傪愗抐偟偨恖偑丆埶慠偲偟偰丆側偄偼偢偺庤傗懌傪姶偠丆捝傒偵擸傓偙偲偑偁傞丅擼偺拞偵偁傞婰壇偑徚偝傟偰偄側偄偨傔偩丅挊幰偼嬀傪梡偄偨娙扨側憰抲偱姵幰偺擸傒傪夝寛偡傞丅杮彂偺僞僀僩儖偼偙偆偟偨帠幚偐傜偮偗傜傟偨丅杮彂偼曽朄榑傪柾嶕偡傞巹偵偲偭偰戝偒側帵嵈傪梌偊偰偔傟偨丅幚尡偵傛傞専徹偲偄偆偙偲偺戝愗偝傪丆傑偨丆壗傕崅壙側憰抲側偔偰傕傾僀僨傾偵傛偭偰夋婜揑側専徹偑偱偒傞偙偲傪杮彂偼嫵偊偰偔傟偨丅
 亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俆
亂僀儞僷僋僩巜悢亃俈丏俆
亂杮暥偐傜亃
仧帺慠搼懣偑丆揔墳傪惗傒偩偡傛偆偵乽栚揑傪傕偭偰乿摥偄偰偄傞偲偄偆岆夝偱偡丅乮棯乯偦傕偦傕惗偒暔偺娫偵懚嵼偡傞曄堎偼丆娐嫬偲偼柍娭學偵惗偠偰偔傞傕偺偱偡丅曄堎偼堚揱巕偺攝楍偵惗偠傞傕偺偱偡偑丆堚揱巕偼丆傑傢傝偺娐嫬偑偳偆側偭偰偄傞偐側偳抦傞傛偟傕偁傝傑偣傫丅
仧柍惈惗怋偱偼丆堦旵偺恊偐傜偳傫偳傫巕偑惗傑傟傞偺偵懳偟丆桳惈惗怋偱偼丆擇旵偺恊偑偄偭偟傚偵側偭偰丆傗偭偲堦旵偺巕傪嶌傞偺偱偡偐傜丆偙偙偵偼丆杮幙揑偵擇攞偺庤娫偑偐偐偭偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅偙傟傪丆桳惈惗怋偺擇攞偺僐僗僩偲屇傃傑偡丅乮P.170)
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偼崅峑惗懳徾偲偟偰彂偐傟偨傕偺偱偁傞偑丆戝恖偑撉傫偱傕廫暘偍傕偟傠偄丅擇攞偺僐僗僩偑偐偐傞偵傕偐偐傢傜偢偳偆偟偰抧忋偵偼桳惈惗怋惗暔偑斏塰偟偰偄傞偺偐丅偦傟偼堚揱巕偵慻懼偊偵傛偭偰丆巕偑恊偲偼彮偟偢偮偪偑偭偨堚揱巕傪庴偗庢傞偙偲偵偁傞丅偦傟偱偼巕偑恊偲彮偟偢偮堘偆偙偲偵偳傫側棙揰偑偁傞偺偐丅乽偙傟偙偦丆崱偱傕傑偩夝偐傟偰偄側偄丆尰戙惗暔妛偺嵟戝偺撲偺堦偮側偺偱偡乿偲挊幰偼偄偆丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧愭擔丆傢偑戝妛偺朄妛晹妛惗偵丆乽悈椡敪揹偱偼偳偺傛偆偵偟偰揹婥傪敪惗偝偣傞偐乿偲偄偆幙栤傪偟偨偲偙傠丆乽悈傪悈慺偲巁慺偵暘偗傞偲偒偵弌傞擬傪棙梡偡傞乿側偳偲偄偆撍攺巕傕側偄摎偊偑懕弌偟偨偑丆拞偵丆乽偦傫側偙偲偼抦傜側偔偰傕傛偄乿偲偄偆摎偊偑偁偭偨丅偙傟偼栤戣偱偁傞丅(p.57)
仧庤懌傗婄偺傛偆側嵍塃懳徧偺峔憿偼丆杮棃丆堚揱妛揑偵偼偒偭偪傝懳徧偵側傞傛偆偵愝寁偝傟偰偄傞偼偢偩偑丆敪惗偺搑拞偺偝傑偞傑側埆忦審傗帠屘丆幘昦側偳偵傛偭偰丆杮棃偺姰慡側懳徧偼払惉偝傟側偄偙偲偑懡偄丅偦偙偱丆偙傟傜偺峔憿偵娭偟偰丆偒偪傫偲懳徧偵側偭偰偄傞屄懱偑偄偨偲偟偨傜丆偦偺懳徧惈偼丆敪惗搑忋偺尩偟偄忦審偵傕娭傢傜偢払惉偝傟偨偺偩偐傜丆偦偺屄懱偑堚揱揑偵旕忢偵嫮偄偙偲傪暔岅偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅偦偆偩偲偡傞偲丆帗偼丆攝嬼幰偺慖傝岲傒傪偡傞偲偒偵丆梇偺宍幙偺懳徧惈偺備傜偓偵拝栚偟偰偄傞偐傕偟傟側偄偺偱偁傞丅(p.24)
亂巹偺僐儊儞僩亃
媣偟傇傝偵偲偰傕偍傕偟傠偄杮偵弌偔傢偟偨丅巹偼撉彂拞偵偍傕偟傠偄売強偵弌夛偭偨傜昁偢偦偺儁乕僕偺抂傪愜傝嬋偘偰偍偔偙偲偵偟偰偄傞丅偩偐傜偙偺愜嬋偑傝偑懡偄傎偳巹偵偲偭偰偍傕偟傠偄杮偲偄偆偙偲偵側傞丅杮彂偼208儁乕僕拞18儢強傕偺乽愜傝嬋偑傝乿偑偁偭偨丅忋偵嫇偘偨俁偮偺帠崁傕偦偺拞偺堦晹偱偁傞丅彈惈偑僴儞僒儉側抝惈傪媮傔傞偺傕柍堄幆偺偆偪偵堚揱揑偵嫮偄抝惈傪媮傔偰偄傞偐傜側偺偩傠偆偐丠
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧揹嬌(delctrode),揹婥暘夝(electrolysis),僀僆儞(ion),亙棯亜偲偄偭偨梡岅偼偡傋偰丆偙偺偲偒僼傽儔僨乕偵傛偭偰採彞偝傟偰傕偺偱偁傞丅亙棯亜壢妛偵怴偟偄尵梩傪摫擖偡傞偲偒偼丆僊儕僔傾岅偑傛偔棙梡偝傟偨丅亙棯亜偟偐偟丆崅摍嫵堢傪庴偗側偐偭偨僼傽儔僨乕偵偼丆偦偆偟偨屆揟偵娭偡傞抦幆偼朢偟偐偭偨丅偦偙偱丆僼傽儔僨乕偼丆働儞僽儕僢僕偺揘妛幰僸儏乕僂僃儖偵嫵偊傪惪偄丆斵偺彆尵傪擖傟偰丆偝偒傎偳徯夘偟偨梡岅傪採埬偟偨偺偱偁傞丅(pp.116-118)
亂巹偺僐儊儞僩亃
尋媶偼懳徾傪柦柤偟丆懠偲偺屄暿壔傪偼偐傞偙偲偐傜巒傑傞丅妋偐偵僼傽儔僨乕偼悢幃傪梡偄側偐偭偨偑丆偦偺戙傢傝偵尵梩傪尩奿偵掕媊偟丆悢妛偺傛偆偵榑棟揑偵榑暥傪彂偄偰偄偭偨偺偱偁傞丅斵偺榑暥偺嶌傝曽傕儐僯乕僋偩丅斵偼崕柧偵幚尡擔帍傪偮偗丆嵟屻偵偦傟傜傪傑偲傔偰榑暥偵偟偨偺偱偁傞丅偩偐傜斵偑壗傪媈栤偵巚偄丆偦傟傪偳偆傗偭偰夝寛偟偰偄偭偨偺偐偲偄偆巚峫夁掱偑傛偔傢偐傞偺偱偁傞丅儅僀働儖丒僼傽儔僨乕偵偮偄偰偼懠偵傕揱婰偑偱偰偄傞偑丆杮彂偼僐儞僷僋僩偵傛偔傑偲傑偭偰昤偐傟偰偄傞丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
亂巹偺僐儊儞僩亃
儐儞僌偵偮偄偰慡偔抦幆傪帩偨側偄恖偑嵟弶偵撉傓偺偵偼嵟揔偺杮偱偁傞丅 偙偺儅儞僈偱慡懱偺僀儊乕僕傪攃埇偡傞偙偲偼旕忢偵桳堄媊偩偲巚偆丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
亂巹偺僐儊儞僩亃
峔憿恖椶妛幰偺儗償傿丒僗僩儘乕僗傗尵岅妛幰偺僠儑儉僗僉乕側偳丆偙傟傑偱懡偔偺暘栰偺妛栤偑丆忋婰偺尦宆偺壖愢偲帡偨傛偆側奣擮傪採彞偟偰 偒偨丅偟偐偟丆偦偺嵺偵儐儞僌偺柤偑尵媦偝傟傞偙偲偼傑偢側偄偲挊幰偼 偄偆丅挊嶌偼擄夝偩偲偄傢傟傞儐儞僌偩偑丆偙偺杮偼乮侾乯傪撉傫偩恖偵惀旕偡偡傔偨偄丅旕忢偵傢偐傝傗偡偔帵嵈偵晉傓丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧怘椘惂尷偵傛傞寁夋揑側乮惛恄忈奞幰偺乯夓巰偼丆枙嶦巤愝偵尷傜偢懡悢偺惛恄昦堾偱峀偔峴傢傟偰偄偨丅偦偺偨傔偵丆偡傋偰偺怘帠偐傜揙掙揑偵帀朾暘偩偗傪庢傝彍偄偨摿暿偺專棫偑丆埨妝巰慻怐埾堳偺堦恖僾僼傽儞丒儈儏乕儔乕偺庤偱峫埬偝傟偨丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙傟偼僫僠僗偑峴偭偨惛恄忈奞幰傊偺敆奞偲偦傟偵壸扴偟偨堛幰傗抦幆恖偺楌巎偱偁傞丅愊嬌揑偱偼側偐偭偨偲偼偄偊丆堦帪偼僫僠僗偲愙嬤偟偨偲偄傢傟傞儐儞僌偵偮偄偰傕怗傟傜傟偰偄傞丅傕偭偲傕丆乮俀乯偺杮偱偼偦傟偑斲掕偝傟偰偄傞偺偱撉傒崌傢偣偰傒傞偺傕偍傕偟傠偄丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧偨偭偨俁俆侽枩傎偳丆惷壀導傎偳偺恖岥偺彫崙乮傾僀儖儔儞僪乯偑丆偙傟偩偗寙弌偟偨暥恖傪攜弌偟偨偲偄偆偙偲偼恞忢偱偼側偄丅偝傜偵偙傟傜暥恖偑傒側丆恖岥俆侽枩傎偳偺僟僽儕儞偱惗傑傟偨偙偲傪峫偊傞偲丆僀僊儕僗恖偑壗偲尵偍偆偲丆僟僽儕儞偼傑偝偵暥妛巎忋偺摿堎揰側偺偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
枩桳堷椡偺僯儏乕僩儞丆巐尦悢偺僯儏乕僩儞偦偟偰朿戝側撲偺岞幃傪巆偟偰俁俀嵨偱巰傫偩儔儅僰僕儍儞丅挊幰偼偙偺嶰恖偺揤嵥悢妛幰偺惗抧偵晪偒丆偦傟偧傟偺執嬈傪夞憐偡傞丅巹偼偲傝傢偗儔儅僰僕儍儞偵嫽枴傪帩偭偨丅昻朢側僀儞僪恖偺庒幰偑働儞僽儕僢僕戝妛偵彽偐傟傞丅傾僀儞僔儏僞
僀儞偑偄側偔偰傕摿庩憡懳惈棟榑偼俀擭埲撪偵敪尒偝傟偨偩傠偆偲偄傢傟偰偄傞偑丆儔儅僰僕儍儞偑偄側偐偭偨傜斵偺岞幃孮偵旵揋偡傞傕偺偼侾侽侽擭嬤偔偨偭偨崱擔偱傕敪尒偝傟偰偄側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偍傕偟傠偄偺偼偦偆偟偨岞幃偼帺暘偺怣偠偰偄傞僫乕儅僊儕彈恄偐傜庼偐偭偨偲斵
帺恎偑弎傋偰偄傞揰偱偁傞丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧乽斵偲榖偟偰傕丆傕偆榁恖偵側傝偐偗偱柺敀偔側偐偭偨丅斵偑壗傪尵偭偰偄偨偐偼偭偒傝妎偊偰偄側偄丅傛偄報徾傪梌偊傛偆偲偑傫偽偭偰偄偨傛偆偩偑丆偡偛偔戅孅偱栵夘偩偭偨乿乮乽恖岺惗柦乿乯
亂巹偺僐儊儞僩亃
乽暋嶨宯乿偲偄偆棳峴岅偺偨傔丆傊偦嬋偑傝側巹偼偙偆偄偆僞僀僩儖偺杮傪嬌椡旔偗偰偒偨偑丆偙偺杮偼暥嬪側偟偵偍傕偟傠偐偭偨丅摦暔偺孮傟偺帺慠側摦偒傪傾僯儊乕僔儑儞偱昤偔僾儘僌儔儉傪嶌傞偨傔丆曟応偺僇儔僗傕孮傟傪壗擔傕娤嶡偟偮偯偗偨僋儗僀僌丒儗僀僲儖僘偺榖側偳柺敀偄
僄僺僜乕僪偑枮嵹偱偁傞丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧孨偑庤偵傆傞傞悈偼夁偓偟悈偺嵟屻偺傕偺偵偟偰丆棃傞傋偒悈偺嵟弶偺傕偺偱偁傞丅尰嵼偲偄偆帪傕傑偨偐偔偺偛偲偟丅
仧偳偺傛偆偵楈嵃偑偦偺擏懱偺拞偵廧傫偱偄傞偐尒偨偔偍傕偆傂偲偼丆偳偺傛偆偵偦偺擏懱偑偦偺擔忢偺廧嫃傪巊梡偟偰偄傞偐 傪娤嶡偡傞偑傛偄丅偮傑傝丆廧嫃偵拋彉偑側偔棎嶨偱偁傞応崌偵偼,偦偺楈嵃偺巟攝偡傞擏懱傕柍拋彉偱棎嶨偱偁傞偩傠偆丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
忋婰偺嵟屻偺傕偺側偳偼丆妛峑偱憒彍傪偝傏傞惗搆偵梌偊傞偺偵揔偟偰偄傞丅偙偺杮偼僷僗僇儖偺僷儞僙偺傛偆偵尗恖偺抦宐偺
尵梩偵枮偪偰偄傞丅柊傝偺慜偵揔摉側儁乕僕傪撉傫偱傒傞偺傕偄偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧柤梍傗拠娫偺懜宧傪偐偪摼偨偄偲偄偆婅朷偼丆壢妛偺弶婜偺崰偐傜懚嵼偡傞傕偺偱偁傝丆壢妛幰傜偼丆堦偮偺棟榑傪 晛媦偝偣傞偨傔偵丆庢傝慤偭偰傒傛偆偲偐丆帠幚柍崻偺僨乕僞偝偊傕漵憿偟偨偄丆偲偄偆桿榝偵偐傜傟偰偒偨丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
杮彂偑僈儕儗僀丆僯儏乕僩儞丆儊儞僨儖偐傜尰戙偵偄偨傞傑偱偺條乆側壢妛幰偺漵憿僨乕僞傗櫁愞榑暥偑庢傝忋偘傜傟偰偄傞丅
偲傝傢偗桳柤側傾儖僒僽僥傿帠審偵僗儁乕僗偑妱偐傟偰偄傞偺偼傢偐傞偑丆堦曽偱栰岥塸悽偵偮偄偰傕尵媦偑側偝傟偰偄傞
偙偲偵懳偟偰堄奜偵巚傢傟傞曽傕偄傞偐傕偟傟側偄丅栰岥偼傾儖僒僽僥傿偺傛偆偵櫁愞傪偟偨傢偗偱偼側偄偑丆儘僢僋僼僃
儔乕尋媶強偲偄偆尃埿傪攚宨偵榑暥偑僼儕乕僷僗傪偟偰偟傑偭偨椺偲偟偰嫇偘傜傟偰偄傞丅乽僷僗僣乕儖傗僐僢儂偺尋媶偼帪
偺帋楙偵懴偊偨偑丆栰岥偺尋媶偼偦偆偱偼側偐偭偨丒丒丒斵偺巰偐傜栺俆侽擭屻丆斵偺嬈愌偺憤妵揑側昡壙偑峴傢傟偨偑丆傎
偲傫偳偺尋媶偑偦偺壙抣傪幐偭偰偄偨乿丅栰岥偺偄偨儁儞僔儖僶僯傾戝妛偵斵偺嵀愓偑慡偔尒傜傟側偐偭偨乮1990擭巹偺懱尡乯偙偲偐
傜傕傢偐傞傛偆偵丆斵偺昡壙偼奀奜偱偼嬃偔傎偳掅偄丅乽尋媶幰偑偄偐偵桪廏偱偁偭偰傕丆壢妛忋偺曬崘偵懳偟偰偼廩暘側専
摙偑側偝傟側偗傟偽側傜側偄偲尵偊傞偐傕抦傟側偄乿偲栰岥偺嬈愌挷嵏偵偁偨偭偨昡榑壠偑弎傋偨偲偄偆丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧(i)墘銏偺寢壥偑丆偦偺偲偒傑偱偵峴傢傟偨偳偺幚尡偵傕柕弬偟側偄偙偲丅傑偨丆堷偒弌偣傞偐偓傝偺梊尵偑怴偟偄幚尡偵傛傝偡傋偰妋偐傔傜傟傞偙偲丅
(ii)尨棟偺拞偵柕弬偑娷傑傟偰偄側偄偙偲丅
偙偺傛偆側庤弴偺尋媶偵梡偄傜傟傞尨棟傪乽壖愢乿偲傛傇丅乮棯乯尋媶偺偙偆偄偆恑傔曽傪乽壖愢偲幚尡偺曽朄乿偲傛傇丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偼乽暔偼壗偐傜偱偒偰偄傞偺偐乿偵偮偄偰悢愮擭偵傢偨傞恖椶偺條乆側峫偊曽傪徯夘偟偮偮師戞偵杮幙偵敆偭偰峴偔夁掱傪傢偐傝傗偡偔愢柧偟偰偄傞丅拞崅惗岦偗偵彂偐傟偨杮偱偁傞偑戝恖偑撉傫偱傕廫暘曌嫮偵側傞丅偲傝傢偗僼儔儞僔僗丒儀乕僐儞偺婣擺朄偲僨僇儖僩偺墘銏朄偺偲偙傠偑柺敀偄丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧僀儞僷僋僩僼傽僋僞乕偲偼丆偦偺僕儍乕僫儖偵宖嵹偝傟偨堦曇偺榑暥偑丆師偺擭偵暯嬒偟偰偳偺偔傜偄懠偺榑暥偵堷梡偝傟偨偐傪帵偡丅偨偲偊偽Science偺僀儞僷僋僩僼傽僋僞乕偼21.9(1995擭搙乯丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
偙偺杮偼僴僂丒僣乕傕偺偱偁傞丅尋媶僥乕儅偺慖傃曽丆儃僗偺慖傃曽摍乆丆幚偵嵶偐偔愢柧偟偰偔傟傞丅偙傟傑偱偙偺庬偺杮偼乽寶慜榑乿偑懡偐偭偨丅偙偺杮偼偳偺儁乕僕傕幚懱尡偵婎偯偄偨傕偺偱丆柍懯傗寶慜偼堦愗側偄丅僕儍乕僫儖偑僀儞僷僋僩僼傽僋僞乕偲偄偆悢抣偱昡壙偝傟偰偄傞揰傕丆偙偺杮偱偼偠傔偰抦偭偨丅乽棟宯偺偨傔偺乿偲偁傞偑丆暥宯偱傕廫暘偨傔偵側傞丅傓偟傠暥宯偺恖乆偵撉傫偱梸偟偄丅
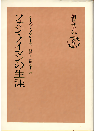 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧尵梩傗悢妛婰崋偵偼敳孮偺僙儞僗偑偁偭偨偺偵丆恖偺婄傪妎偊傞偺偼壓庤偩偭偨丅帺暘傪抦偭偰偄傞恖傪帺暘偺傎偆偼抦傜側偄丆偦傫側帠懺偵惗奤擸傑偝傟傞丅
仧乽偄偪偽傫偍偟偄偲偙傠傪偲傞恖乿偲偄偆旕擄傕偁傞偑丆偦傟偼桪傟偨惛恄偵傆偝傢偟偄峴堊偩傠偆丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
巹偼僼傿儔僨儖僼傿傾偺儁儞僔儖僶僯傾戝妛偱悽奅弶偺僐儞僺儏乕僞乽僄僯傾僢僋乿傪尒偨丅偙偺僐儞僺儏乕僞偼傕偲傕偲儁儞僔儖僶僯傾戝妛偺儌乕僋儕乕仌僄僢僇乕僩払偑奐敪傪巒傔偨傕偺偩偑丆搑拞偱僲僀儅儞偑壛傢偭偨丅偦偟偰尰嵼偺僐儞僺儏乕僞偼乽僲僀儅儞宆乿僐儞僺儏乕僞偲屇偽傟丆僄僢僇乕僩払偺柤慜偼側偄丅恖偺傾僀僨傾傪偝傜偭偰偼丆偁偭偲偄偆娫偵偦傟傪敪揥偝偣偰偟傑偆抝偲偄傢傟偨丅偨偩丆傕偟斵偑偄側偗傟偽崱擔偺僐儞僺儏乕僞偼懚嵼偟偨偐偼媈傢偟偄偲杮彂偼偄偆丅
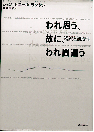 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧偙偆偟偰侾侽侽枩擭慜偺傢傟傜偺慶愭偑尒偮偐偭偨丅偱偼恖娫偺梙庹偺抧偼傾僕傾偩偭偨偺偩傠偆偐丠偙傟偼帺暘偨偪偺暥柧偵旕忢側屩傝傪傕偭偰偄偨儓乕儘僢僷恖偵偼壗偐偆偭偲偆偟偄偲偙傠偑偁傞丅儓乕儘僢僷偱丆傕偭偲屆偄慶愭傪尒偮偗偨偄両擬嫸揑垽崙怱偺塭嬁椡偼偁傑傝偵傕嫮偡偓丆偦偺柌偼偁傑傝偵傕枺榝揑偱偁傞丅偩偐傜偙偺柌偼丆壢妛巎偺拞偱傕傕偭偲傕桳柤側儁僥儞偵傛偭偰尰幚偲側傞丅僺儖僩僟僂儞恖偱偁傞丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
僺僞僑儔僗丆僐儁儖僯僋僗丆僟乕僂傿儞丆僉儏儕乕丆僷僗僣乕儖丆傾僀儞僔儏僞僀儞丅揤嵥偨偪偼師乆偲岆傝傪偍偐偟偨丅杮彂偼偙偆偟偨岆傝偺悢乆傪儐乕儌傾傪傕偭偰夝愢偟偰偔傟傞丅偟偐偟丆壢妛偑恑曕偟丆抦偺懱宯偑峔抸偱偒傞偺偼偦偆偟偨岆傝偺偍偐偘偱偁傞偙偲傕朰傟偰偼側傜側偄丅
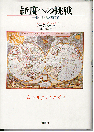 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
仧壢妛奅偺僄儕乕僩偨偪偼丆僴儕僜儞偺杺朄偺敔傪憡庤偵偟側偐偭偨丅乮棯乯乽婡夿怑恖乿傛傝傕揤暥妛幰傪桪嬾偡傞偨傔偵丆偨傃偨傃婯懃傪曄峏偟偨丅
亂巹偺僐儊儞僩亃
抧媴媀傪巚偄晜偐傋偰傒偰梸偟偄丅乽堒搙乿偼愒摴偵暯峴偵偄傢偽抧媴傪摍娫妘偱墶偵僗儔僀僗偟偰偄傞丅偟偐偟乽宱搙乿偼抧媴傪廲偵僗儔僀僗偟偰偍傝丆愒摴偺偁偨傝偑嵟傕挿偔丆嬌偵嬤偯偔傎偳抁偔側傞丅偮傑傝丆堦掕偱偼側偄丅偲傝傢偗栚報偺側偄戝奀尨偱帺暘偺埵抲傪抦傞偙偲偼暲戝掞偺偙偲偱偼側偄丅僀僊儕僗偼1741擭丆惓妋偵宱搙傪應掕偡傞曽朄傪敪尒偟偨傕偺偵擇枩億儞僪偺徿嬥傪梌偊傞偲敪昞偟偨丅偦偟偰柍柤偺僕儑儞丒僴儕僜儞偼摉帪偳傫側偵惛岻側帪寁偱傕堦擔悢暘抶傟偨傝恑傫偩傝偡傞偺偑摉偨傝慜偩偭偨偵傕偐偐傢傜偢丆堦儢寧偱偨偭偨堦昩偺岆嵎偟偐惗傑側偄嬃堎揑帪寁傪奐敪偟偨丅偙偺帪寁傪巊偊偽宱搙偺應掕偼壜擻偵側傞偺偩偑丆宱搙埾堳夛偼妛楌偺側偄僴儕僜儞傪擣傔傛偆偲偼偟側偐偭偨丅偄偭偨偄丆妛栤偲偼壗偐丅壢妛偲偼壗偐丅偨偩妛楌偩偗偟偐側偄柍擻側妛幰偲丆宱尡偲岺晇偲抦惈偐傜桪傟偨傕偺傪惗傒弌偟偰偄傞怑恖偲偳偪傜偑乽恀偺壢妛幰乿側偺偐丆乽恖椶偵峷專偟偰偄傞傕偺乿偱偁傞偐傪峫偊偝偣傜傟傞杮偱偁傞丅
 亂杮暥偐傜亃
亂杮暥偐傜亃
乽尋媶偺丆愭偑尒偊偨傜丆晹壆戄偟偰丆柤慜傪偮偗偰丆僲乕儀儖徿乿
亂巹偺僐儊儞僩亃
僲乕儀儖徿偼挊偟偔恖椶偺峷專偵恠偔偟偨壢妛幰偵梌偊傜傟傞徿偱偁傞丅偟偐偟丆幚嵺偼搘椡偩偗偱偼側偔丆塣傕昁梫偱偁傞偙偲偑傢偐傞丅杮彂偼丆俋俋恖偺壢妛幰偑偳偺傛偆偵偟偰僲乕儀儖徿傪庤偵偟偨偐傪偍傕偟傠偍偐偟偔岅偭偰偔傟傞丅偦傟偧傟偺榖偺廔傢傝偵偮偗傜傟偰偄傞愳桍偑偍傕偟傠偄丅寉柇側僞僢僠偱彂偐傟偰偼偄傞偑丆傓傠傫娙扨偵扤偱傕偲傟傞徿偱偼側偄丅忢偵偦偺偙偲偵娭怱傪傕偪丆僙儗儞僨傿僺僥傿乮晛捠偺恖側傜尒夁偟偰偟傑偄偦偆側偙偲偱傕丆偦偺廳梫惈偵婥偯偔偙偲偺偱偒傞弨旛偝傟偨怱乯傪帩偭偰偄側偗傟偽偳傫側偙偲偱傕惉岟偵寢傃偮偐側偄偱偁傠偆丅