 《作者》
《作者》
慈円
私が選んだ心に残る詩歌
昨日見し人はいかにと驚けど
|
 《作者》
《作者》
慈円
《出典》
新古今集
《感想》
知り合いの訃報を聞くと,「この前会ったときは元気だったのにどうして」と思うことがよくある。医療の発達していない当時はなおさらだったことだろう。慈円は関白藤原忠通の子。法然を批判したが,その弾圧には反対し,法然やその弟子親鸞を庇護している。
我が背子は物な思ひそ事しあらば
|
 《作者》
《作者》
安部女郎(あべのいらつめ)
《出典》
万葉集4-506
《感想》
You don't have to worry, worry, 守ってあげたい あなたを苦しめるすべてのことから。私はこの和歌を見るといつもユーミンの「守ってあげたい」を連想する。好きな男性を守ってあげたい――時代を越えて共通する女性の心だ。原文は「吾背子波 物莫念 事之有者 火尓毛水尓<母> 吾莫七國」。安部女郎(あべのいらつめ)は奈良時代の女性。和銅-宝亀(ほうき)(708-780)のころの人。中臣東人(なかとみの-あずまひと)との贈答歌など5首が「万葉集」巻3,4におさめられている。巻8には安倍女郎の名による大伴家持(やかもち)との贈答歌もあるが,これは別人らしい。情熱の人であるがこれ以上のことは不詳。
世の中を思へばなべて散る花の
|
 《作者》
《作者》
西行
《出典》
新古今和歌集 1470
《感想》
西行から批評を頼まれていた20歳代の定家は,大先輩の和歌に対しての批評を2年以上も躊躇していた。しかし西行が1189年に弘川寺で病の床に伏したと聞き,急いで批評を送った。西行はこの歌の本質を鋭く見抜いた定家の次の批評をとても喜んだという。「その初句から結句まで,すべての句に思いが深くこもっており,作者が心深く悩んでいるところがある。そのような作者の深く思い悩める心が出ている」。
うち日さす 宮に行く児を まがなしみ
|
 《作者》
《作者》
大伴宿奈麿(すくなまろ)
《出典》
万葉集巻4 532
《感想》
原文は「打日指宮尓行兒乎真悲見留者苦聴去者為便無」。大伴宿奈麿は大伴旅人の弟で,坂上郎女の夫。当時は備後の国に国守として赴任していた。采女として上京する乙女を歌った歌だが,この采女は宿奈麿の恋人ではない。国守であった宿奈麿が当地の容姿端麗な娘を選出し,都に送りだしたのだ。しかし,今,目の前で親と別れを惜しみ,行く末に不安を抱いて泣いている若い娘を見ると,果たしてこれでよかったのかと思ってしまうのだ。国守としての役目を果たしたが,一方では自責の感にかられる宿奈麿の優しさが見える。
さらぬだに 打ちぬる程も 夏の夜の
|
 《作者》
《作者》
お市の方
《出典》
辞世の歌
《感想》
この歌の本歌は藤原俊成の「さらぬだにふす程も無き夏の夜を待たれても鳴く時鳥(ほととぎす)哉 (新勅撰和歌集159)」。お市の方は「
さらぬだに打ちぬる程も夏の夜の 夢路を誘ふほととぎすかな」と歌ったという説もある。秀吉に攻められ,二度目の夫の柴田勝家とともに自害する寸前の歌なのだが,妙に諦観しているところがなおさら哀れだ。享年37歳。
春は萌え夏は緑に紅(くれない)の
|
《作者》
読み人知らず
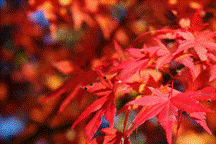
《出典》
万葉集 巻10-210
《感想》
春夏秋の山の変化をうまく歌った歌。春には雪が溶けて若葉が萌える。夏は緑一面に。そして秋は紅葉がまだらになって,錦を織りなす。もう一つがんばって冬景色を詠みこめれば最高なのだが。どうです,皆さん,チャレンジしてみませんか。
をしこめて秋の哀(あはれ)にしづむかな
|
 《作者》
《作者》
式子内親王(しょくしないしんのう)
《感想》
不思議な歌である。山麓の村が夕霧の底に沈んでいる。深く悲しい心象風景でもあるのだろう。この歌は哲学的な和歌だといわれる。
作者は後白河天皇の第3皇女の式子内親王(1149〜1201)。和歌は藤原俊成に学んだが,その子の定家とも交流があった。和歌の名手で三十六歌仙の一人。10歳から21歳まで,賀茂神社の斎院を務めた。生涯独身。53歳で没した。
ぼんやりとした悲しみが夜(よ)となれば
|
《作者》
石川啄木
《出典》
歌集「悲しき玩具」

《感想》
先の見えない不安をよく表した歌。この歌は肺結核で入院中に書かれた。結局27歳で妻,父,友人の若山牧水に看取られて死去。「たわむれに母を背負いて・・・」の母カツはその前月に死去していたが,嫁と姑の中は非常に悪かった。歌集「悲しき玩具」は友人で歌人の土岐善麿がタイトルをつけ,死後出版された。
石川は22歳で東京に出た。盛岡中学で1年先輩だった金田一京助から金銭的援助を受けるが,芸者遊びが尋常ではなかったという。啄木自身がそのことを「ローマ字日記」に赤裸々に書いている。金田一京助の息子の春彦は,その様子を見て「石川啄木は石川五右衛門の子孫ではないか」と子どもながら疑ったという。
なお,啄木は大逆事件に尋常ならぬ関心を抱き,膨大な公判記録を部分ではあるが読み込み,裁判全体は政府によるでっち上げだったと確信していた。
瀧の水は空のくぼみにあらはれて
|
《作者》
上田三四二(うえだ みよじ)

《出典》
歌集「遊行」
《感想》
上田はアララギ派の歌人で医者。結腸癌,そして膀胱癌を病み平成元年65歳で死去。私はこの歌を知ったとき,ナイヤガラの滝を思い出した。何キロも先からまるで山火事のような噴煙が上がっているのがタクシーから見えた。膨大な水量の水が流れ落ちたときに出る水蒸気だった。あの滝の落下の様子をこれほどまで言語で見事に表現できるものなのか。絶句したのを覚えている。なお,この歌は我が故郷串本近くの那智の滝(落差133m)を歌ったものだという。
ちなみに,上田は昭和61年9月7日のNHK教育テレビ「こころの時代」で自分の死生観を次のように語っている。
「電波,赤外線,可視光線,紫外線,X線,γ線,宇宙線というのは同じ性質の電磁波なんですね。その可視光線の部分だけが見えるわけなんです。見えるというのは人間の目で見える,感覚として見えるというわけなんですけどね。自分の生ということを考えると,その見える世界がまあ生きている命の世界で,生まれてくる以前というのは,なんか変な言い方だけど,赤外線のほうから送られてきていましてね,それで見える世界に入って,また見えない紫外線のほうの世界に消えていく,と。そして,ウンと長い波長とウンと短い波長というのは,単なる妄想ですけど,どこかで一つひっくり返って結び付くんじゃないんじゃないかという,そういうふうに考えたいわけなんですけどね。」
あなたは勝つものと思つてゐましたかと
|
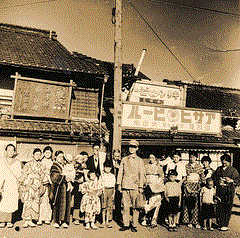 《作者》
《作者》
土岐善麿(とき ぜんまろ)
《出典》
歌集「夏草」(1946年)
《感想》
この歌集の発行が終戦の翌年になっていることに注目。全体主義の日本。「畏れ多くも・・・」という言葉を聞くと,無意識のうちに姿勢を正す条件反射。密告がまかり通る社会では,戦争を云々することはたとえ夫婦の間でも触れるべき話題ではなかった。この歌はそれを示している。作者の土岐善麿は啄木と交流のあった歌人。読売新聞社会部長だった1917年(大正6年),東京遷都50年の記念博覧会協賛事業として東京〜京都間のリレー競走「東海道駅伝」を企画し大成功を収め,これが現在の「駅伝」につながった。のちに自由主義者として批判され,退職。戦争中は隠遁生活を送ったが,戦後,母校の早稲田大学教授となった。
昨日見し人はいかにとおどろけど
|
 《作者》
《作者》
慈円
《出典》
新古今和歌集
《感想》
慈円は鎌倉時代の天台宗の僧侶。38歳で天台座主。異端視されていた専修念仏の法然の教義を批判しつつも,その弾圧には反対で法然や弟子の親鸞を庇護した。
年たけてまた越ゆべしと思ひきや
|
 《作者》
《作者》
西行
《出典》
新古今和歌集
《感想》
「小夜の中山」は静岡県掛川市佐夜鹿(さよしか)に位置する峠で,箱根峠や鈴鹿峠と列んで、東海道の三大難所とされていた。このとき西行は69歳(1186年)。東大寺大仏建立の勧進のため奥州に向けて旅をしていたのだった。この「命なりけり」の表現はその後,いろいろな和歌に使われるようになった。後に芭蕉もこの中山にて「命なりわづかの笠の下涼ミ」の句を作った。西行は72歳で死んだが,当時としては長寿だった。
愛(かな)し妹(いも)を いづち行かめと山菅(やますげ)の
|
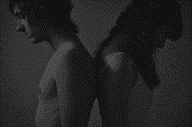 《作者》
《作者》
読人知らず
《出典》
万葉集 第14巻 東歌
《感想》
「今となっては」ということは,「妻があの世に旅立ってしまった今では」ということである。単に離婚したのではないのか――
そうではないことは確かだ。というのもこの歌の前書きには「挽歌」とあるからだ。作者はよほど妻を愛していたのであろう。私はこの歌がなぜか好きだ。
蟻と蟻うなづきあひて何か事
|
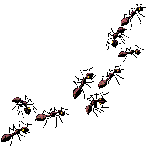 《作者》
《作者》
橘曙覧(あけみ)
《出典》
志濃夫廼舎(しのぶのや)歌集
《感想》
まるで現代短歌のように思えるが,これは幕末に生きた福井藩士,橘曙覧(1812-1868)の作。彼は家督を弟に譲り,赤貧の中を国学と和歌に専念した。平易な日常語と自由な発想の歌を多く読んだ。正岡子規の先輩ともいえる。例えば,
たのしみは空(あ)き米櫃に米いでき今一月はよしといふとき
などの歌もある。
大方(おほかた)に過ぐる月日をながめしは
|
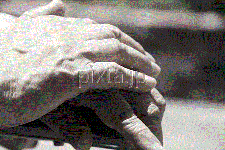 《作者》
《作者》
慈覚大師
《出典》
新古今和歌集 雑歌上 1587
《感想》
息子が生まれた日のことはよく覚えている。予定日を大幅に超えてしまい,大きくなりすぎてしまっていた。出産には10時間以上かかり四苦八苦の上,吸引分娩で生まれた。出産直後,分娩室からストレッチャーに乗せられて出てきた妻の唇は,高熱のためひび割れて出血していた。難儀して生んだその子も,高1のときにインフルエンザ脳炎で死にかけた。幸い今は健康でやっている。息子はすでに青年期を越えたが,私たち夫婦はそれだけ年をとったということなのだ。子どもは成長し,親は老ける。この歌の作者も,その事実にハッとしたのであった。
難波人(なにはひと)葦火(あしひ)焚く屋の煤(す)してあれど
|
 《作者》
《作者》
詠み人知らず
《出典》
万葉集 巻11 2651
《感想》
万葉集の中でも私のお気に入りの一つ。妻を「すすけてしまっている」と言いながら「それでもやっぱりかわいいもんです」と持ち上げる。私は作者は苦笑しつつ半分冗談,半分本気でこの歌を作ったのではないかと思う。でもやはり妻を愛しているのだろう。この歌を知ったとき,私は家内に「煤(す)してあれど」をことさら強調しながら披露した。
秋来(き)ぬと目にはさやかに見えねども
|
 《作者》
《作者》
藤原敏行
《出典》
古今和歌集 巻第4 秋歌上
《感想》
立秋に読んだ歌。まだ夏の暑さが残っているのに,すでにもう秋は来ている。作者はその「小さい秋」を風の音の中に見つけたのだ。一葉落ちて天下の秋を知るということだ。ファジー理論ではないが,物事はぱっぱっとデジタルに変化するのではない。ある事柄の真っ最中にすでにもう別の事柄が始まっているのだ。我われは日頃その変化に気づかないだけである。磨ぎ澄まされた感覚を持つ詩人の感性がそれを感知する。この今の時代の中ですでにどのような変化が起きているのだろうか?
世の中を憂しと恥(やさ)しと思へども
|
 《作者》
《作者》
山上憶良
《出典》
万葉集(巻5-893)
《感想》
山上憶良といえば,マイホーム・パパというイメージを私は勝手に抱いていた。中西進の『悲しみは憶良に聞け』によれば,幼年のころ父と共に百済から日本に渡来してきたのではないかという。そして朝廷に仕えたものの常に部外者という気持ちをぬぐえなかったのではないか。それが彼を日本初の社会派歌人にしたのかもしれない。彼は太宰府にいるころ,大伴旅人と親交を結び,その子家持の家庭教師もしていた。
わがやどのいささ群竹
|
《作者》
大伴家持
 《出典》
《出典》
万葉集(巻19-4291)
《感想》
この歌はさびしい。こんなさびしい心象風景を歌った大伴家持なる男のことを私はもっと知りたいと思った。大伴家持は陰謀術数渦巻く朝廷近くにありながら,常に注意深く一歩退くスタンスをとっていた。そして様々なクーデターの誘いにも乗らなかった。しかし大和朝廷以来の武門を誇る大伴氏の嫡男であることが災いして,常に政敵からは疑いの目で見られ続けた。九州,伊勢,陸奥など地方に出向くことが多かったのも,はっきりいえば左遷である。陸奥で死んだ後も,藤原種継暗殺事件に関与したとして埋葬が許されぬまま除名され,庶民となった。(しかし天変地異が続いたため祟りを恐れた朝廷によって従三位に名誉回復された)
さくら花ちりぬる風のなごりには
|
 《作者》
《作者》
紀貫之
《出典》
古今集89
《感想》
貫之が屏風に書いた歌という。空気は透明でふだんはその動きを我われは見ることはできない。しかし,雲や煙,桜の花などが空中を漂うときに,その流れや動きを目に見ることができる。さっと風が吹き,おびただしい桜の花が空中舞った。まるで大波が起こったかのように花びらが一定の統一のとれた動きをしている。貫之はその一瞬を歌った。言葉が視覚に訴える歌だ。
A Memory
Four ducks on a pond,
むこうには芝生の岸 春の青空には 白い雲が漂う 何てささいなことだろう 何年も忘れずに思い出すには 涙とともに思い出すには |
 《作者》
《作者》
アイルランドの詩人 William Allinngham(1824-1889)
《出典》
Poems(1850)
《感想》
確かこの詩は高校の英語の教科書で習った(と思う)。断定はできないが,おそらくラフカディオ・ハーンの著作『詩論』からの抜粋ではなかったか。当時は高校の英語の教科書に英詩の鑑賞があったのだ。教養主義の復活ではないが,実学いってんばりの時代はもう終わりだと思う。人間を人間たらしめるのはやはり文学ではないか。我われはこの大切な事実をなおざなりにしてきたように思う。
人はだれしも心象風景のようなものを持っている。どういうわけかしばしば夢に登場するような風景。一見どうってことがないのになぜか忘れられない場面。きっとそれは何か我われの心をとらえるものがあったのだろう。ウィリアムはそれをやさしい言葉にした。
手にむすぶ水にやどれる月かげの あるかなきかの世にこそありけれ「両手に掬った水に映るこの月のように,有ったのか無かったのかわからないほどはかない人生だったなあ」
|
 《作者》
《作者》
紀貫之
《出典》
和漢朗詠集・巻下 無常
《感想》
紀貫之の辞世の歌という。幼名は阿古屎(あこくそ)。異様な名だが,幼児にこうした忌避すべき名をわざと与えるのは魔除けの意味があったからだという。貫之は日本文学史上初めての仮名による随筆「土佐日記」を女になりかわって書き,後の女流文学の道を開いた。かつての名門紀氏も,もはや文学の道で生きるしかなかった。この辞世の言葉は素直に心に響く。
人の親の心は闇にあらねども 子を思ふ道にまどひぬるかな「子を持つ親として別に心の中は闇というのではないが,そうはいっても子の行く末を考えるとあれこれと迷ってしまうものだ」
|
 《作者》
《作者》
藤原兼輔(ふじわらのかねすけ)
《出典》
後選集和歌集・雑一
《感想》
この歌は藤原兼輔(ふじわらのかねすけ)が,醍醐天皇の更衣となった娘の桑子を案じて歌ったものといわれている。天皇家に入るということは名誉とはいうものの,親としてはやはり心配だったのだろう。これは現代も同じと思われる。作者の兼輔は紫式部の曽祖父。桑子は後に章明(ふみあきら)親王を産み,下級官吏だった兼輔も最後には中納言兼右衛門督にまでのぼりつめる。
最近のコンピュータ解析により,この歌には元歌があり,それは清少納言の曽祖父,清原深養父(きよはらのふかやぶ)が作った「人を思ふ心は雁にあらねども雲居にのみもなきわたるかな」(古今集所収)だという。紫式部と清少納言の因縁はすでに曽祖父の時代にさかのぼるのか。いずれにせよ,この歌は子どもの将来を案ずる親の気持ちが出ている。私も,就職浪人を続ける30歳の息子の行く末を案じる親として,共感できる歌だ。
そこらは青くしんしんとしてどうも間もなく死にさうです
|
《作者》
宮沢賢治
《出典》
詩集「疾中」
《感想》
宮沢賢治の歌。詩のタイトルは「眼にて云う」。すでに最期が近づいている患者が,もはや言葉を発して目の前に医師に告げることはできないので,目で今の気持ちを伝えている内容が詩で表わされている。詩の全体は以下のとおり。
だめでせう
とまりませんな
がぶがぶ湧いてゐるですからな
 ゆふべからねむらず血も出つづけなもんですから
ゆふべからねむらず血も出つづけなもんですから
そこらは青くしんしんとして
どうも間もなく死にさうです
けれどもなんといゝ風でせう
もう清明が近いので
あんなに青ぞらからもりあがって湧くやうに
きれいな風が来るですな
もみぢの嫩芽と毛のやうな花に
秋草のやうな波をたて
焼痕のある藺草のむしろも青いです
あなたは医学会のお帰りか何かは知りませんが
黒いフロックコートを召して
こんなに本気にいろいろ手あてもしていたゞけば
これで死んでもまづは文句もありません
血がでてゐるにかゝはらず
こんなにのんきで苦しくないのは
魂魄なかばからだをはなれたのですかな
たゞどうも血のために
それを云へないがひどいです
あなたの方からみたらずゐぶんさんたんたるけしきでせうが
わたくしから見えるのは
やっぱりきれいな青ぞらと
すきとほった風ばかりです。
不思議なのは,外から見れば,出血が止まらず死に瀕している重篤の患者であるのに,患者の方からは見ると「きれいな青空とすきとおった風が吹いている」というのだ。死ぬってことは傍から見るほど苦しいものではないのかもしれない。臨死体験者は皆異口同音にそのようなことを言う。
2007年にやっと賢治をたずねて花巻へ行ってみた。イギリス海岸もながめた。どうってことのない川であり,どうってことのない牧場であるが,賢治の眼から見ればどんどんとイメージの膨らむ光景であったのだろう。心の持ち方で,見えるものには見えるのだろう。トトロやアスラン王のように。
散ればこそいとど桜はめでたけれ 憂き世になにか久しかるべき「散ってこそ,桜はその短い一生を精一杯生きたと言えるのです。そもそもこの世に永遠なものなどあるものですか」
|
《作者》
紀有常
 《出典》
《出典》
伊勢物語(第八十二段)
《感想》
惟喬(これたか)の親王が交野(かたの)の渚の院(現在の大阪府枚方市)で馬から降り,桜の枝を折って髪に差した時,右の馬頭(うまのかみ)(在原業平)が
世の中に絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし
と歌ったのに返歌して,「別の人」が標記の歌を歌ったという。この「別の人」とは紀有常らしい。私の祖母は,私がうっかりと茶碗を落として割ったりすると,叱る母を制して「いいよいいよ,形あるものは壊れるのだから」といったものです。「散ればこそ」の歌も,無常観をうまく言い表しています。この二つの歌では,どうみたって業平より有常の勝ち。なお,業平は有常の娘を妻にしているので,有常は義理の父になる。
終(つい)に行く道とはかねて聞きしかど 昨日今日とは思はざりしを「人間最後はこうなるとは聞いていたけど,まさか昨日今日とは思ってもみなかったよ」
|
 《作者》
《作者》
在原業平
《出典》
古今集861, 伊勢物語125段
《感想》
古今集には「やまひして弱くなりにける時よめる」とある。誰もが最後には死ぬことはわかっている。わかってはいるが,その死が来るのは突然である。まさか,今日ここで死ぬとは…。業平の無念が伝わってくる。この歌は正直で,上の「世の中に絶えて」という技巧的な歌より私は好きだ。
ながむべき残りの春をかぞふれば 花とともにも散る涙かな「あと何年こうした春を眺めることができるのかと数えてみると,ほとんどないことに愕然として桜の花のようにはらはらと涙が止まらない」
|
 《作者》
《作者》
俊恵(しゅんえ)法師
《出典》
新古今和歌集第百四十二
《感想》
この「花とともにも散る涙かな」という表現は,ついて行けないほど大袈裟だという人もいる。しかし,間もなく定年を迎える年齢になった私には身につまされるものがある。若いころはまったく思いもしなかった「死」というものを自覚する年齢になってきたのだ。先日,妻が息子から誕生祝いにもらったサザンやユーミンなどのオールディーズの曲の入ったCDを車で聞きながら帰っていたら,思わず涙が出て止まらなくなったといった。「青春時代の思い出がよみがえったのか」と聞いたら,そうではないという。そうではなくて,この歌を聞いたのがつい昨日のように思えるのに,その頃赤ん坊だった息子は今や30になっている。30年があっという間だ。ましては自分はあと30年も生きられるわけはない。おそらく「その日」が来るまで,「あっという間」だろう。そう思うと涙が出て止まらなくなったのだという。この俊恵や業平の気持ちになったのだろう。
こころこそいくさする身の命なれ 揃ふればいき揃はねば死す「心こそが戦う者にとって最も大切なものである。味方が心を一つにして協力すれば戦場を生き抜くことができるが,さもなければ死あるのみだ」
|
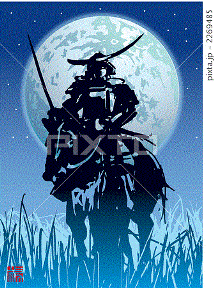 《作者》
《作者》
島津忠良(しまづ ただよし)
《出典》
日新公いろは歌
《感想》
島津忠良は苦労の人で,子どもや孫たちの教育にも熱心だった。このいろは歌もその教材である。まさに命のやり取りをする戦いの場においてこそ,人の和の大切さを忠良は痛感したであろう。たった一人の野心,わがまま,裏切りが,全員の死につながることもあるのだ。
孫の義弘(よしひろ)は,関ヶ原の戦いで1500人を率いて西軍についたが,敵中に孤立してしまった。このとき、島津軍は捨て奸(すてがまり)という方法を用いて敵中突破を図った。それは,何人かがそこに留まって敵を足止めをし,それが全滅するとまた何人かが次の足止め役をつとめるという方法である。その結果,1500人のうち最後は80数名となったが,それでもこの多くの犠牲のおかげで義弘は生還できたのであった。進んで足止め役を買って出る者がいたからこそできたことである。私はこの話をNHKの「その時歴史が動いた」で知った。
一将(いっしょう)功(こう)成って万骨枯る「一人将兵の手柄の陰には無数の兵士が死がある」
|
 《作者》
《作者》
曹松(そうしょう)
《出典》
詩題 己亥(きがい)の歳(とし)
《感想》
作者は70歳を過ぎてやっと科挙に合格するが,まもなく死んだ。一生を赤貧の中で暮らした。この詩は唐末期の混乱を表している。英雄を誉めたたえるのはやめてくれ。その男を英雄にしたのは戦場に散った何万という戦死した兵隊たちなのだから――立場を変えれば確かにそうなのだ。この詩は徹底した反戦の詩である。全体の詩は以下の通り。
沢国江山入戦図(たくこくのこうざん せんとにいる)
【豊かな地域の川も山も戦場となり】
生民何計楽樵蘇(せいみんなんのけいあってか しょうそをたのしまん)
【民衆は普段の生活を楽しむ術さえ失っている】
憑君莫話封侯事(きみにねがう かたるなかれほうこうのこと)
【たのむから手柄を立てて王侯になった奴のことなど話さないでくれ】
一将功成万骨枯(いっしょうこうなって ばんこつかる)
【一人の将兵が手柄を立てたということは,無数の兵士が死んだということなのだから】
有ろじより 無ろじへ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け「私は煩悩の世界(この世)から悟りの世界(あの世)へと帰る途中で一休みをしているのだ,何が起ころうとどうってことはない」
|
 《作者》
《作者》
一休宗純
《出典》
『洞山三頓の棒』という公案への回答
《感想》
この歌により,師から「一休」の道号を受けた。僧侶でありながら女犯を行い,晩年には盲目の美女「森待者(しんじしゃ)」と同棲した。実子の弟子まで持っている。この風狂の僧がなぜあれほどまで社会から許されたのか。本人の性格もあるのだろうが,やはり後小松天皇の落胤といううわさが世間に信じられていたからだろう。一休の奇行は仏教の形骸化を批判し,伝統の風化に警鐘を鳴らす意味もあった。彼はものごとをありのままにとらえること,嘘や偽善を排することを常に意識していた。1420年のある夜,カラスの鳴き声を聞いて,一休は突然悟る。師の華叟は印可状を与えようとしたが,彼は辞退する。それを見て師は馬鹿者と苦笑いしながら見送ったという。一休は当時としては尋常でない88歳の長寿を全うしたが,死ぬまぎわに「死にとうない」と言ったとか。最後まで「ありのまま」の男だった。
Copyright (C) 1998 Hiroshi Suga All Rights Reserved.