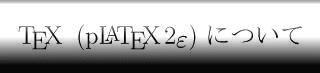
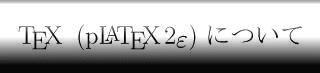
旧 パソコン通信「ニフティサーブ」で、友人とメールのやりとりをしていたところ、「インターネット」を勧められて接続することになり、それから20数年になります。
ここ18年間は、Windows のコンピュータはもっぱら「TeX 」に関することが中心です。
TeX はアメリカ・スタンフォード大学のコンピュータ学者/数学者の D.Knuth教授によって開発された無償の「組版ソフト(=印刷などの版下で使用される)」であり,
「MS-DOS」,「UNIX」,「Windows」,「Macintosh」など,あらゆるプラットフォームの上で動くソフトウエアです。
通常の文書は,もちろんですが,特に数式を含む文章については,市販のワープロソフトや,他の「数式エディタ」では表現できないような非常に美しい出力を得ることができます。
現在の主流は,「LaTeX2e(ラテフ・ツーイー)」と呼ばれるもので,日本語版はアスキー(株)による,「pLaTeX2e(ピー・ラテフ・ツーイー)」です。
「AMS=米国数学協会」の「標準」になっており,「TeX」で書いた論文は優先的に扱われるということです。
私の場合はSOFT BANK から出版されている「pLaTeX2e for Windows Another Manual Vol.1 BasicKit 1999(乙部厳己・江口庄英著)」を,
Windowsのコンピュータにインストールしていましたが、のちに、基本OSを「Windows 98」から「Windows 2000」に入れ換えた際に,
「角藤版アスキーpTeX 3.05 Win32 Web2C-7.3.11」,さらに,「pTeX 3.1.3 Win32 Web2C-7.5.2 (2003.11.10)」へとアップグレードしました。(旧版はアスキーpTeX 2.1.8 Web2C-7.2.7でした。最新版は,角藤版 pTeX W32 TeX Live 2017 (2018.2月 現在)です。)
なお,現在使用しているコンピュータのOSは 「Windows XP」と「Windows7」ですが,個人的には「Windows 2000」がもっとも気に入っており,また「TeX」にも相性がいいと思っています.
定年退職後,2012年3月まで非常勤講師として公立高校と私立高校に勤務。2013年4月から再び非常勤講師として公立高校で教壇に立ち、2016年3月をもって退職。非常勤講師のとき、教材作成の際はLANで接続されたコンピュータにTeXのファイルを持ち込んで,最終的にはネットワークプリンタに出力していました。ただし,ネットワークに接続されているコンピューターのうち,「TeX」のプログラムをインストールしている機械はありませんから,他の人が使用しているときは,後述の「秀丸+祝鳥(のりてふ)」をUSBメモリから起動して,ネットワークに接続されている他のコンピュータを使用して出力します。
「TeX」による出力の美しさを体験した現在,通常の「ワープロ」やワープロソフト付属の「数式エディタ」などを使う気にはとてもなれません。以下私の場合は
前述の「秀丸+祝鳥」を使用することによって,(TeXのソースファイル->dvi->pdf)がほとんど自動的に実行されます。
また,他のソフト(
従来,「dvi->ps->pdf 」の変換には,「dvipsk」やAdobeSystems の「distiller」を使っての作業ということでしたが、TeX の最新版に同梱されている「dvipdfm(x)」というツールを使用して,dvi ファイルを直接 PDF に変換できることになりました。
また,上越教育大学の中川仁先生の「Easy TeX」という統合環境ソフトによって,入力〜dvi〜pdf の作業が驚くほど簡単になり、初心者にとってもTeX に対しての障壁が軽減されたと思います。(Thanks;Mr.Nakagawa)
「TeX」の学習にあたっては,「schlmath」という素晴らしいマクロを提供していただいた新潟県のM.K先生,さらには岡山県のK.I先生には個人的にお世話になりました。この場をお借りして御礼を申し上げます。
なお,「TeX」関係のリンク先を下にあげておきます。